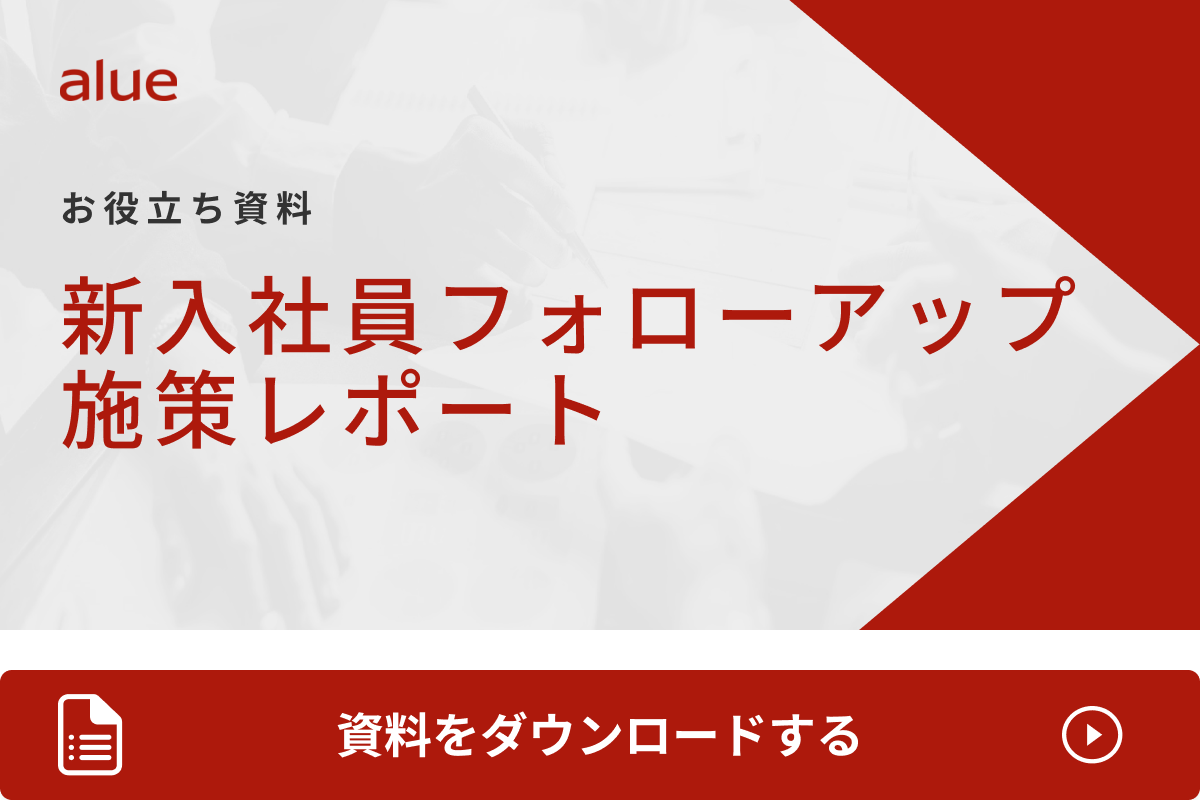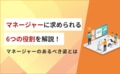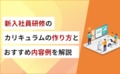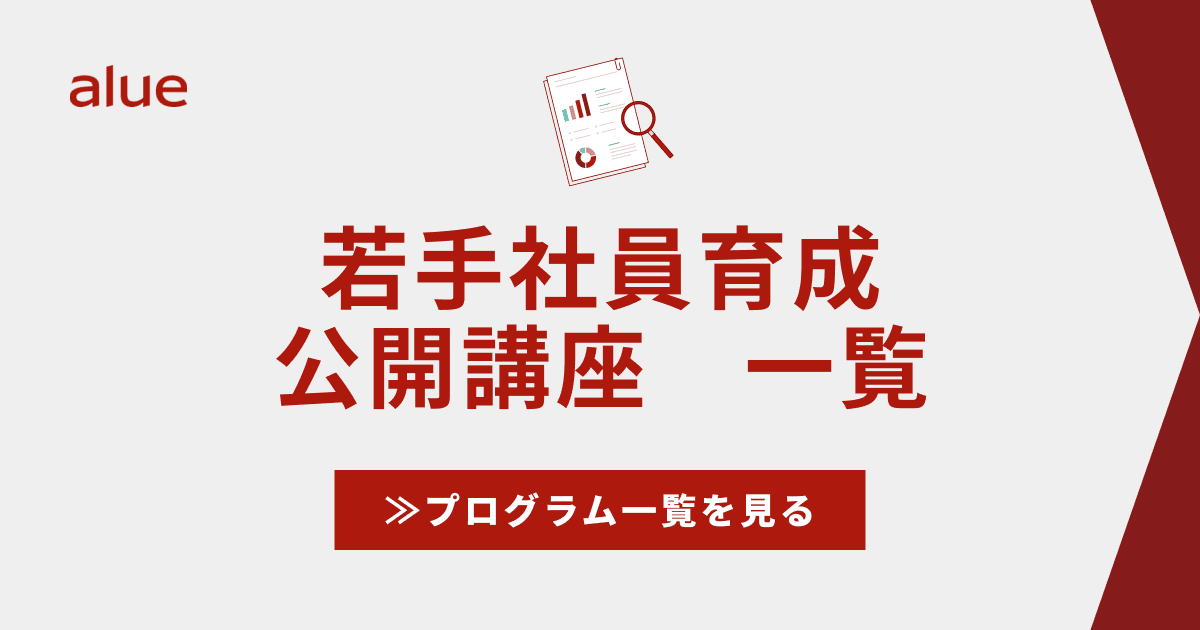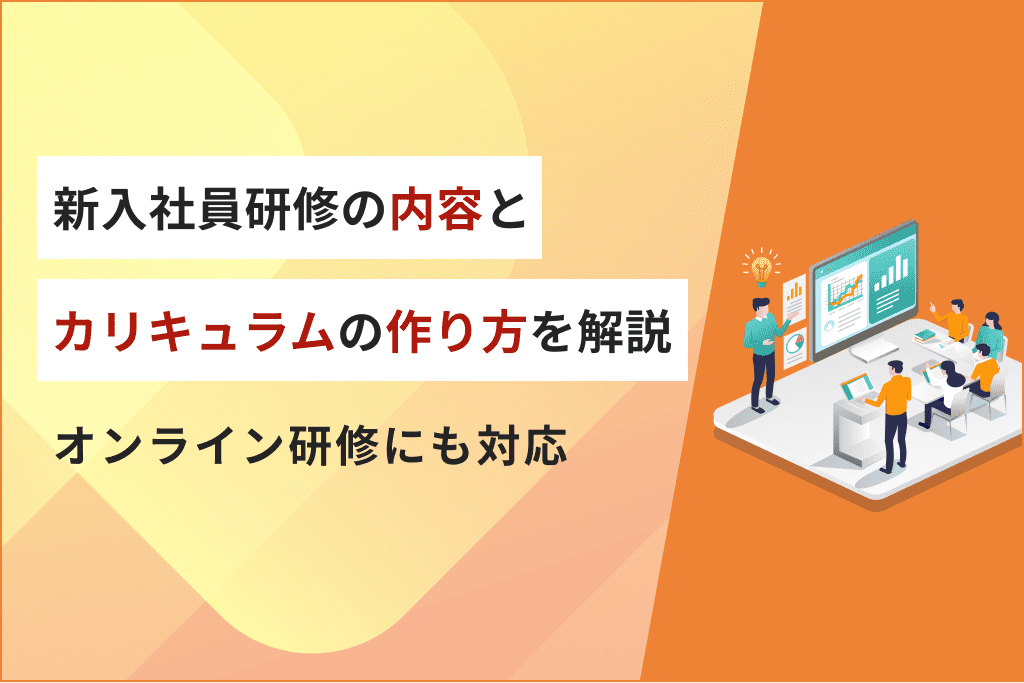
新入社員研修の内容とカリキュラムの作り方を解説。オンライン研修にも対応
企業が業績を伸ばしていくためには、業務を円滑に進められる人材を早い段階で教育していく必要があります。そのためには新入社員研修が欠かせません。新入社員研修と一言で言っても実施すべき内容は数多くあり、目的が達成できる研修の実施方法を研修前にしっかりと考えていく必要があります。
この記事では、新入社員研修を初めて担当する人事担当者や、今までの新入社員研修を改めたいと考えている方に向けて、研修カリキュラムの決め方と研修の種類をまとめました。新入社員研修の基礎的な知識を学べるようにポイントをまとめておりますので、最後までぜひ目を通してみてください。
2024年度新入社員研修の企画担当者の方必見! |
より深く知るための『オススメ』お役立ち資料
目次[非表示]
【テンプレートプレゼント!】新人教育育成計画書
アルーでは、年間100社以上の企業、2.3万人の受講者へ新人研修を提供しております。新人教育に役立つチェックシートを下記ページにて無料で配布しています。
テンプレートのサンプル
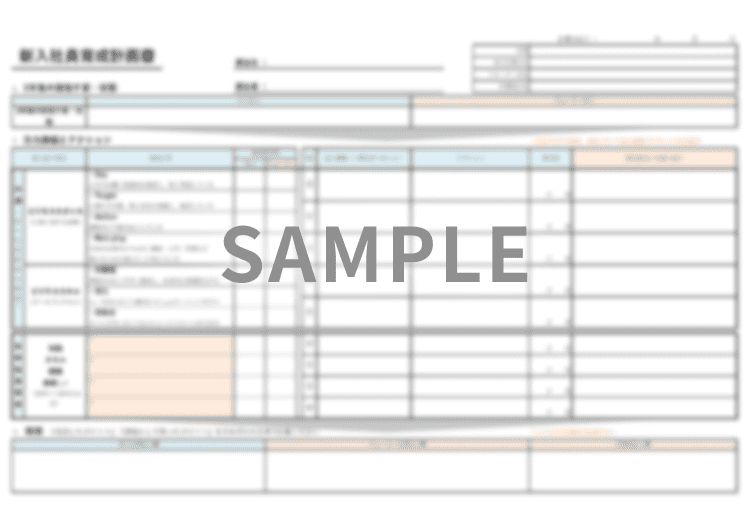
新人とOJTトレーナーが目標をすり合わせ、進捗を確認するために使用できます。自社の目標に合わせて項目を修正し、すぐに使えるExcel形式の資料です。ぜひダウンロードし、新人教育にお役立てください。
新入社員研修の目的
新入社員研修には主に以下の6つの目的があります。
- 学生から社会人としての意識改革
- ビジネスマナーや基本スキルの習得
- 企業についての理解を深める
- 報連相の徹底
- 社内コミュニケーションの活性化
- 業務に必要なスキルを身につける
▼新入社員研修の目的の決め方について詳しくは、以下のページをご参照ください。
『新入社員研修の目的とは?目標の決め方や必要なカリキュラムを紹介』
新入社員研修の内容
新入社員研修の目的は理解したものの、「具体的にどのような内容で研修を提供すればよいか分からない」と悩む人事担当者も多いでしょう。そこで、ここでは代表的な5つの目的それぞれに対して、どのような内容の研修を提供するべきかをご紹介します。
研修の内容やテーマに悩む人事担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
ビジネスマナー研修
ビジネスマナー研修は、社会人としてふさわしいマナーを理解し、職場やお客様先で実践できるようになることを目的としています。新入社員は、相手に失礼のない対応を心がけたいと思っていても、何が正解かわからず自信を持てないことが多くあります。そのため、基本的な型を学び、適切な対応ができるようにすることが重要です。
ビジネスマナーは、「信頼できるパートナー」になるための手段であり、相手の「心地よさ」を作り出すことがポイントです。研修では、第一印象を良くする顔合わせの方法、丁寧な受け答え、適切な立ち居振る舞いを学びます。これにより、多様な人と円滑に仕事を進めるための基礎を身につけることができます。
研修を通じて、新入社員はマナーの重要性を理解し、安心感・信頼感を与えられる振る舞いを実践できるようになることが期待されます。
▼ビジネスマナー研修について、以下のページで詳しく解説しています。
『ビジネスマナー研修の目的は?研修内容・厳しい研修を行う理由・背景を解説』
企業理念浸透研修
企業理念浸透研修は、企業のミッション・ビジョン・バリューを理解し、日々実践できるようになることを目的としています。ただ理念を知るだけではなく、自分ごととして捉え、行動に落とし込む力を養うことが重要です。
企業理念は、組織の一体感を生み、意思決定の指針となる要素ですが、一方的に伝えるだけでは浸透しにくく、押しつけに感じられることもあります。そのため、ワークショップやディスカッションなどの参加型の手法を取り入れ、自ら考え、言語化する機会を設けることが効果的です。
研修では、ワークショップを活用して理念を深く理解し、自身の業務との関連を考えながら実践につなげることを重視します。また、一度の研修で終わらせるのではなく、継続的な対話やフィードバックを行い、理念の定着を図ることが重要です。企業理念を行動に移せる社員を育成するため、主体的に学べる環境を整えることが求められます。
▼企業理念浸透研修について、以下のページで詳しく解説しています。
『理念浸透のためのワークショップ・ゲーム実例5選。押しつけにならないコツ』
学生から社会人への意識転換研修
学生から社会人へと立場が変わることで、求められる役割や責任が大きく変化します。この研修では、社会人としての心構えと基本行動を学び、自信を持って社会人生活をスタートできるようになることを目的としています。
学生のうちは受け身で学ぶことが多かったものの、社会人になると「与えられる側」から「価値を提供する側」へと意識を変える必要があります。また、モラルを守る責任感や、チームの一員として相手を尊重する姿勢が重要になります。そのため、主体的に行動し、成果を生み出すための考え方を身につけることが求められます。
研修では、指示待ちではなく主体的に動くこと、社会のルールや倫理を守ること、相手の視点を意識することを学びます。これにより、新入社員は会社の一員としての自覚を持ち、責任感を持って行動できるようになることが期待されます。
▼学生から社会人への意識転換について、以下のページで詳しく解説しています。
学生から社会人への意識転換プログラム
経験学習サイクル研修
経験学習サイクル研修は、自らの成長を自ら導く力を育てることを目的としています。新入社員が「やったら終わり」ではなく、経験から学びを得て、それを次の行動に活かす力を身につけることが、この研修の大きな狙いです。
この研修では、まず自分を動かす原動力を自覚することから始まり、「経験→振り返り→気づき→行動」という経験学習のサイクルを理解し、実践できるようにします。特に、経験の質を高めるための振り返りや、他者からのフィードバックを積極的に取り入れる姿勢も重視します。
研修を通じて、新入社員は自分の経験から教訓を得て、それを次の行動に結びつける方法を学びます。自分のモチベーションを意識的にコントロールし、行動量を増やすことの大切さを理解し、成長を自走できる力を養うことが期待されます。
▼経験学習サイクルの詳細について、以下のページで詳しく解説しています。
『経験学習サイクルとは?実践のコツや具体的な施策例』
業務の進め方研修
業務の進め方研修は、仕事の進め方の基本を体系的に理解し、確実に成果を出すためのスキルを身につけることを目的としています。ゴールから逆算して仕事を構造的に捉え、抜け・モレなく計画を立てる力を養うことがこの研修の中心です。
研修では、まず仕事のゴールを確認することの重要性を学びます。ゴールを曖昧なまま進めると、手戻りやミスが発生しやすいため、自らゴールを確認し、アウトプットイメージをすり合わせる力を養います。その上で、やるべきことを洗い出し、細かい作業へと分解し、作業時間の見積もりや順序の整理、計画立案までを学びます。
また、「わかったつもり」を防ぐために、相手の話を聞いた後で自分の理解を確認する習慣も重視されます。自分の思い込みで仕事を進めるのではなく、都度確認・すり合わせを行うことで、手戻りを減らし、仕事を前に進める力を身につけることができます。
この研修を通じて、新入社員は仕事の進め方を論理的に理解し、自律的に業務を計画・実行できる力を育むことが期待されます。
報連相研修
報連相(報告・連絡・相談)は、職場における信頼関係の構築と業務の円滑な遂行に欠かせない基本的なビジネススキルです。この研修では、チームの成功を第一に考えたコミュニケーションのあり方と、実践的なスキルを学ぶことを目的とします。
新入社員は「忙しそうな上司に声をかけづらい」「何を伝えればよいか整理できない」といった不安を抱えがちです。研修では、報連相の必要性やタイミング、伝え方の工夫を具体的に学ぶことで、そうした不安を解消し、自信を持ってコミュニケーションが取れるようになることを目指します。
ポイントは、報連相を単なる義務ではなく、チームの成果を支える行動として捉える意識を持つことです。また、「場のすり合わせ」や「エレベータートーク」、「BAD NEWS FIRST」など、すぐに使える実践的な7つのスキルを習得し、短時間で要点を伝える力や、相手の理解を確認する力を育てます。
この研修を通じて、新入社員は相手に配慮した報連相ができるようになり、職場での信頼関係と成果につながるコミュニケーションを実践できるようになることが期待されます。
▼報連相研修のポイントについて、以下のページで詳しく解説しています。
『【事例あり】報連相研修を成功させるポイントとおすすめのワークを紹介』
コミュニケーション研修
コミュニケーション研修では、ビジネスパーソンとして良好な人間関係を築くための基本的な考え方とスキルを学びます。円滑な人間関係は仕事の成果にも直結するため、相手との関係性をより良くするためのコツを新入社員には学んでもらう必要があります。
研修では、まず「ストロークを与える」ことの重要性を学びます。これは、相手の存在や行動を認め、反応することで、信頼関係を築くコミュニケーションの基本です。また、「人と事を切り分ける」ことで、問題が起きた際にも感情的にならず、冷静に対応できる力を養います。さらに、「I’m OK, You’re OK.(自分も相手も大切にする)」という心構えを持つことが、良好な関係を築く前提となります。
この研修を通じて、新入社員はコミュニケーションの取り方を見直し、相手との信頼関係を築く力を高めることができます。特に、「どう関わればよいかわからない」と悩む場面でも、相手と自分を尊重しながら対話する術を身につけることが期待されます。
▼コミュニケーション研修の詳細について、以下のページで詳しく解説しています。
『新入社員向けコミュニケーション研修の内容|事例や成功させるコツを紹介』
コンプライアンス研修
新入社員を対象としたコンプライアンス研修では、社会人としての基本的なルールやマナーを理解し、トラブルを未然に防ぐ意識を身につけることが目的です。SNS利用・情報管理・ハラスメント・ビジネスマナー・著作権の理解といった、新入社員が特に直面しやすいテーマを中心に扱います。
研修ではまず、コンプライアンス違反が企業や本人にどのような影響を与えるかを理解させることが大切です。SNSでの軽率な投稿や個人情報・社外秘の取り扱いミスなど、新入社員にとって身近なリスクについて具体的に解説します。また、ハラスメントやビジネスマナーについても、加害者や被害者にならないための予防と対応の基本を学びます。
さらに、著作権や肖像権のように、意図せず違反してしまう可能性のあるテーマについても正しい知識を身につけます。「知らなかった」では済まされないリスクへの感度を高めることが重要です。
この研修を通じて、新入社員は社会人として信頼される行動が取れるようになり、自らコンプライアンスを意識して行動できる姿勢を身につけることが期待されます。
▼コンプライアンス研修のポイントについて、以下のページで詳しく解説しています。
『新入社員研修でコンプライアンスを扱う重要性|テーマや効果的に行うポイント』
新入社員研修のカリキュラムの作り方
ここからは、カリキュラムを作る方法をお伝えしていきます。
企業としてどんな風に成長をしてほしいか、働くうえであるべき人物像を設定し、そのための目標を定めるところからスタートしましょう。以下で具体的に解説しますので、参考にしてください。
あるべき人材像を設定する
まずは、企業側がどんな風に育ってほしいかといった「あるべき人材像」を設定するところから始まります。人事制度で等級基準や必要なコンピテンシーを定めている場合には、その枠組みを参考にしながら、新入社員レベルではどのような行動が求められるかを定義し、社内で共有を行いましょう。
具体的に決まっていない場合は、経営者やリーダーといった責任者から意見を募ることがおすすめです。他には、SPIテストの結果や社内の理想的なハイパフォーマーの行動を観察し、行動特性を拾い上げるといった方法もあります。両方を組み合わせて、あるべき人材像を設定するとよいでしょう。
内容を決める前に目的を明確にする
新入社員研修で学ぶ内容を決める前に、まずは新入社員研修の目的を明確にしましょう。
自社が求める人材を定義し、新入社員研修ではどのレベルを目指すのか、言語化しておくことが重要です。
たとえば、下記のような例が挙げられるでしょう。
- 名刺交換などのビジネスマナーを現場で実践できるレベルで習得する
- 企業理念を理解し、自分の言葉で説明できるようになる
- ロジカルシンキングを習得し、相手に伝わりやすい日報を書けるようになる
▼新入社員研修の目的の決め方について詳しくは、以下のページをご参照ください。
『新入社員研修の目的とは?目標の決め方や必要なカリキュラムを紹介』
新入社員の傾向とスキルレベルを把握する
効果的な新入社員研修を行うためには、今の新入社員の傾向を把握して、カリキュラムや研修の進め方を工夫する必要があります。
例えば、近年の新入社員は自身が周囲からどのように見られているか、「見られ方」に意識が及ばない傾向にあると言えます。そのため、新入社員研修において、どう見えているのかを細かくフィードバックするセクションを入れるなどの工夫をすると良いでしょう。
▼最新の新入社員の傾向レポートはこちら
また、新入社員のスキルレベルがどの程度なのかも事前に把握しておきましょう。内定者研修の一環として、ビジネスマナーやコンプライアンスなどへの理解度テストを実施するのがおすすめです。
現場にヒアリングする
せっかく研修担当者がカリキュラムを決めたところで、配属予定の部署に必要のないカリキュラムが多くなってしまっては研修を行う意味がありません。お互いの齟齬をなくすためには、新入社員が配属予定の部署にどのようなスキルを身につけてほしいかヒアリングを行いましょう。指揮命令者である上司の意見はもちろんですが、直属となる先輩や同僚の意見も取り入れると、求めるスキルが更に鮮明になります。
研修期間を設定する
新入社員研修で実施できる研修内容は、研修を実施できる期間によって異なってきます。
その為、研修内容を決める際は、どのくらいの期間を使って研修を行うことが可能なのかを確認する必要があります。
平均的な新人研修期間は約3ヶ月と言われていますが、企業によって設定している研修期間は異なりますので、その期間内で実施できる研修内容にしましょう。
研修の方法を決定する
研修には、場所を準備し直接開催するパターンと、WEB会議ツールやeラーニングを活用してオンラインで実施する2つのパターンがあります。
直接開催する「実地研修」は、対面で研修ができるため学習に集中させやすく、ロールプレイング形式の研修にも対応できるというメリットがあります。一方で、業務の状況によっては参加できない社員が出てしまう、研修場所の確保にコストがかかるといったデメリットもあります。
オンライン研修やeラーニングは会場の準備が不要で、まとまった時間がなくても実施できます。オンラインで配信される教材なら各自で何度も復習できる点もメリットといえるでしょう。しかし、研修の進み具合が受講者ごとの主体性に左右されてしまうという点では実地研修の方が優れています。
このように、研修方法ごとにメリット・デメリットがあるため、目的に応じて方法を使い分けるのが良いでしょう。
内容とスケジュールを決定する
ここまで準備が整ったら、あとはスケジュールを組んで研修の内容を決めていきます。
新入社員研修のスケジュールと内容を決める際には、以下のポイントを押さえましょう。
-
配属前に自社や業界について学ぶ機会を取り入れる
- 新入社員が各部署に配属される前に、自社や業界についての知識をあらかじめ身につけられる研修内容を入れましょう。
- 自身が配属された部署で行う業務がどのような役割を担っているのか、全体のイメージを理解した上で実務に取り組ませることができます。
-
フォローアップの場を設ける
- 新入社員研修のスケジュールには、必ずフォローアップの時間も組み込みましょう
- 新入社員研修は受けたら終わりの場ではありません。研修の知識や身につけたスキルを定着させ、今後につなげていく必要があります。研修担当者やメンターとの定期的な面談を行い、どのようなスキルが身についたか、研修において不安や不満を感じる点はないかを聞き取ります。
- このようなフォローアップは、企業としての新入社員研修カリキュラムの改善にも活かせるでしょう。
アルーでは新入社員研修と併せて新人フォローアップ研修もご提供しています。
▼それぞれ詳しくはこちらのページをご覧ください。
新入社員研修のスケジュールの決め方について詳しくは、以下のページをご参照ください。
『新入社員研修のスケジュールの作り方|事例や表テンプレートをご紹介 』
監修者からひとこと |
新入社員研修の形式にはどんなものがある?

ここまで新入社員研修のカリキュラムとその組み方について詳しく解説をしてきました。
ここからは、新入社員研修におすすめの研修方法を8つご紹介していきます。どれか一つのみを取り入れるのではなく、いくつも組み合わせて使うことがおすすめです。いくつもの形式を組み合わせることで研修にメリハリが生まれ、新入社員も最後まで集中力を切らさずに主体的に参加しようという意識をもってくれるでしょう。
講義形式
講義形式は、研修の参加者が多い場合によく使われる手法です。業界の知識や企業の経営理念・今後のビジョンについて、一対多数で説明することができます。多くの知識をまとめて伝えることができるので、進行のコントロールがしやすい点もメリットといえるでしょう。
一方で発信者側と受信者側に分かれてしまうため、受講者が積極的に参加しづらいというデメリットもあります。受講者が研修内容を理解できていないまま進んでしまう可能性があるため、理解度の確認をこまめに行いましょう。おすすめの方法はグループワークの場を設けることです。講義で学んだ内容を踏まえたグループワークを設定することで、受講者の主体的な学びを促進できるでしょう。
ケーススタディ形式
ケーススタディとは、過去の事例やよくある事例を元にテーマを決めて学ぶ手法です。
過去に起きた事例を使うことで、似たようなシーンに出くわした際に適切な対応ができるようになります。一般的にはスライドに過去の事例を表示し、そのことについて10分程度の時間を取り数人で意見を交換し、結論を発表することが多いです。
事例の考察を通じて、問題解決に役立つポイントを受講者が見つけ出すことができるので、同様のケースが出てきた場合にも瞬時に判断できるようになります。
ロールプレイング形式
ロールプレイング形式とは、受講者に役割を与え、場面を想定して疑似練習をする形式の研修です。新入社員研修だけでなく、若手社員研修や中堅社員研修などでもよく実施されます。電話対応や営業のテレアポ、商品紹介の練習など、模擬体験をしながらスキルを習得していきます。
初めに講師や先輩社員がロールプレイングの見本をみせてから実践させることで、実務に役立つスキルを身につけさせることができます。
シミュレーション形式
実際にビジネスの現場で起こるシチュエーションの一場面を想定し、業務の一連の流れをシミュレーションする形式の研修です。
新入社員研修の中に組み込むのであれば、研修の後半の日程で組み込むことをおすすめします。これまで学んだビジネスマナー・電話応対・報連相をはじめとしたコミュニケーションの復習にもなります。
ワークショップ形式
ワークショップ形式とは、一般的にグループワークとも呼ばれる形式の研修を指します。
与えられた課題に対し、参加者それぞれが意見を出し合い、共有して結論を出していく手法のひとつです。コミュニケーション能力も磨くことができるため、企業では研修スタイルのひとつとして定着しつつあります。結論を出す際には全員の同意を得る、発言を否定するような言葉は使わないなど、基本的な決まり事を最初に決めておくとスムーズに意見を交換できるでしょう。
全員の同意を取るには、なぜこう思ったか、こうは思えないかと議題に大してひとつひとつ紐といて説明をしていく必要があります。相手の理解度に合わせて話す必要が出てきますので、伝える練習にもなるのです。
実技&フィードバック形式
研修カリキュラム内で実演を行い、身につけるべき観点が実践できているかを確認するのが「実技&フィードバック形式」です。
例としては、ビジネスマナー研修の名刺交換や電話応対、プレゼンテーションなどの判定試験が挙げられます。実技をさせるだけではなく、必ずフィードバックまで実施することが重要です。
テスト形式
テスト形式は、新しい知識を学ぶ際に、○×テストや穴埋めテストを実施し受講者の理解度を確認する形式です。
受講者が理解できている点といない点を洗い出し、フィードバックを行います。研修で理解できなかった部分は改めてOJTを通して教えていくことが重要です。
eラーニング
eラーニングはコンピューターとインターネットを活用した学習形態です。研修実施者が動画教材などを用意し、受講者は都合のよいタイミングで教材を視聴し、学習します。学ぶべき内容の多い新入社員にとって、自身の都合のよいタイミングで学べ、自由に復習できるeラーニングは非常に有益です。
新入社員研修でのeラーニングの活用方法について詳しくは以下の記事をご参照ください。
『新入社員研修でeラーニングを活用するメリットとデメリットと対策をわかりやすく解説』
新入社員が楽しめる研修にするには
新入社員が主体的に参加できるようなカリキュラムがあれば、新入社員も楽しく学習ができ、知識やスキルの定着につながります。
そのためには、先ほどご紹介した形式の中から以下の3つの形式を取り入れると効果的です。
- ロールプレイング形式
- シミュレーション形式
- 実技&フィードバック形式
- ゲーム形式
早く他の人の意見を聞きたい、もっと多くの事例を知りたいというように、自発的に動きたくなるカリキュラムを用意することも重要となるでしょう。
ロールプレイング形式
お辞儀、電話応対、名刺交換の仕方などのビジネスマナーなど、実際にやってみることを通して新入社員に身につけて欲しいテーマを取り扱う場合には、ロールプレイング形式で行うとよいでしょう。一人でのイメージトレーニングでは、新入社員は今の言動で大丈夫だったのか客観的に判断ができません。ロールプレイングを取り入れることで、実際の場面を想定した演習を通じて、実践力を高めることができます。また、一度身につけた内容を定着させ、忘れにくくする効果も期待できます。
ロールプレイングには下記の4種類がありますので、研修内容に応じて、最も適した形式を選ぶとよいでしょう。
ケース型ロールプレイング
グループ型ロールプレイング
問題解決型ロールプレイング
モデリング型ロールプレイング
▼ロールプレイングに関しては、以下で詳しく解説しています。
『【事例あり】ロールプレイング研修の進め方や効果、成功させるコツ』
シミュレーション形式
シミュレーション形式の研修では、実際の業務フローの流れを体験するとよいでしょう。たとえば、顧客へのヒアリング→提案書作成→プレゼンといった一連の営業フローを経験する研修が考えられます。
時間制限を設けることで、締め切りを厳守することへの意識や業務の効率的な進め方について学ぶことができます。
実技&フィードバック形式
実技&フィードバック形式で楽しく研修を実施するには、グループごとに実技を発表し、他のグループからフィードバックをもらうといったグループワークスタイルで行うとよいでしょう。もちろん、最終的なフィードバックは研修担当者が行います。
研修を通して新入社員同士がお互いの良い面を見つけたり、改善すべき面を伝え合うことで、「どのように見えているのか」をより意識させることができます。
ゲーム形式
新入社員が楽しめる研修とするために、ゲーム形式での研修を行うのもおすすめです。特にチームビルディングやコミュニケーション向けの研修との相性がよいでしょう。研修によく導入されるゲームとしては、下記のようなものがあります:
室内でできるゲーム
- コンビニ経営ゲーム
- NASAゲーム
- ペーパータワー
- レゴ®シリアスプレイ
- バースデーライン
短時間でできるゲーム
- ペア探しゲーム
- 質問ゲーム
- ジェスチャーゲーム
オンラインでできるゲーム
- 日本文化体験チームビルディング
- 願いの共有
- クエスチョンバースト
- Talking in the Park
少人数でできるゲーム
- メイク10
- 背中合わせでお絵描き
- ひとことゲーム
上記のゲームに関しては、下記で遊び方やルールなどを詳しく解説しています。ぜひご活用ください。
監修者からひとこと |
新入社員研修を成功させるポイント

会社が設定した目標を達成し、研修で教えた知識やスキル、マインドが身についていなければ、研修が成功したとはいえません。
設定した目標を達成し、かつ新入社員には主体的な参加を促し、学びを定着させるにはどのようにしたらよいかよく理解した上でカリキュラムを考えることが重要です。
研修の場では、教える知識やスキルが今後仕事にどう関わってくるのか、背景や必要性を伝えていくべきでしょう。正しく理解ができていないと、その場では覚えることができても短期的な記憶としていずれ忘れてしまいます。
以下では、新入社員研修を成功させるためのポイントを解説します。
最新の新入社員の傾向やトレンドを押さえる
昨今の新入社員は、周囲からどう見られるか、どういう行動が適切かを知らない傾向にあります。具体的には、講義中や休憩中におけるオン・オフの行動の使い分けの認識の甘さなどが見られるようです。新入社員の傾向やトレンドをつかむためには、人材会社が発行している新入社員の傾向調査レポートなどを入手するとよいでしょう。研修現場でみられるポジティブやネガティブな傾向がわかりやすく一覧化されていることが多いので、新入社員の傾向を踏まえて研修を設計する際の参考資料として活用できます。
最新の新入社員の傾向については、以下のページをご参照ください。
『【2024最新】最近の若者の特徴を企業112社のデータから読み解く』
研修後にフォローアップを行う
配属されたばかりの新入社員は業務の進行にあたり、「わからないことがわからない状態」に陥ることがあります。
また、「本人ができていると思っていても、本当はできていないこと」を教えてあげるのも人事部や先輩社員の役割です。
そのため、研修終了後にフォローアップを行い、できていることとできていないことを伝えてあげる必要があるでしょう。
振り返りを行うことで、PDCAサイクルをスムーズに回すことができるようになり、振り返りを通じて成長と課題を明確化することができるようになります。
新入社員研修を行った後は3ヶ月、6ヶ月、1年など一定の期間で、フォローアップの機会を設けるようにすることが理想です。
上司やOJTトレーナーの意識・行動変容も促す
新入社員が早期に活躍していくためには、「オンボーディング=組織になじむこと」から始めていく必要があります。そのためには、新入社員からの働きかけだけでなく、組織からの働きかけも大切です。
特に上司やOJTトレーナーは、新入社員が「チームに受け入れられている」、「チームの一員として貢献できている」という実感をもてるようにサポートしていく必要があります。
上司やOJTトレーナーが、組織全体で新入社員をサポートしていく意識や組織風土を作っていくことが、新入社員の早期戦力化のポイントとなります。
監修者からひとこと |
新入社員研修はアウトソーシングするべき?
新入社員研修は、カリキュラムによって内製と外注を使い分けていくとよいでしょう。
たとえば、ビジネスマナー研修は外部委託したいが、経営者が経営理念や今後のビジョンを伝える場は内製で設けたいというように内製化と外部委託が混在するパターンもよく見られます。
「初日は企業について学び、グループワークを中心にコミュニケーションを図る場」「2日目は社外セミナーで学ぶ場」など、内製化する部分と外部委託する部分で日程を分けておくと進行がスムーズになるはずです。
内製で新入社員研修を行うメリット・デメリット
内製で新入社員研修を行うメリットは主にコスト面や自社にあった研修を行うことができる点です。デメリットは、研修担当の負担が大きい、教育内容に差が出る、といった点です。
以下で詳しくお伝えしていきます。
メリット①コストが抑えられる
外注しない場合、自社の社員が研修を担当するため、あまりコストはかかりません。ただし、研修担当になったことで残業が発生し、残業代がかさむケースはよく聞きます。
メリット②ノウハウが蓄積される
研修後に人事部と講師の間で振り返りを行うことで、研修の内容は年々よくなっていきます。研修の講師を担当する社員の意識向上にもつながるでしょう。
メリット③自社の行動指針や組織風土に合った教育を行うことができる
自社の行動指針や組織風土に沿った研修を行うことができるので、自由度が非常に高いことも内製で新入社員研修を行うことのメリットのひとつです。
デメリット①人によって教え方に差が出る
研修担当が毎年同じ社員とは限らないため、年によって教える内容や分かりやすさが変わってしまう可能性があります。そのような場合には、研修担当用のマニュアルが必要です。
新入社員の成長度合いも、研修担当によって左右されるところが大きくなるためです。
デメリット②研修準備や運営に手間がかかる
これまでもご紹介してきたように、新入社員研修を行う際はカリキュラムの作り方や社員に適した研修方法など、さまざまなポイントを意識して準備しなければなりません。新入社員研修を内製で行う場合には、なにより研修準備の手間がかかるという点もデメリットのひとつです。
また、自社の会議室で行えない規模の場合、会場をレンタルする必要があります。開催規模によっては、直前の予約だと会場が空いていないなどのリスクもあるでしょう。
外注で新入社員研修を実施することのメリット・デメリット
外注の人材育成会社の提供するサービスには、オンラインを活用して実施できるものもあります。テレワーク導入企業や新入社員が遠方にいる企業の場合は、無理に遠方からきてもらう必要がなくなるので上手に活用していきたいところです。
メリット①最適な研修資料や講師を準備してもらえる
研修専門の外注であれば、蓄積されたノウハウに基づく研修資料やプロの講師に担当してもらうことができます。内製ではフォローできない部分まで教えてもらえるので、新入社員の学びも大きくなるでしょう。
例えば、ロジカルシンキングや問題解決のような思考スキルを実践できるレベルまで引き上げるには、実践演習での反復と個別フィードバックを繰り返す必要があります。このために必要な演習の用意や講師からのフィードバックの観点、研修の設計方法のノウハウは研修専門の会社だからこそ持っている知見です。学びの定着が早くなる手法や受講者間の学びの質のばらつきを少なくするための手法など、研修効果を上げるためのノウハウを持っているのも研修会社の特徴です。
また、講師の受講生への関わり方も社内講師と専門の講師では変わってくるでしょう。研修講師には、多くの心構えと研修を進める技術が求められます。例えば、以下のような技術が必要となります。
- 現場を意識した姿勢をアドバイスする
- 実践者として自身の体験や学びを伝える
- 受講者の将来のために耳の痛いことも伝える
- 研修の目的に沿って学習内容の意義付けをする
- 受講者を受容し、尊重する
上記のようなスタンスや技術を持っている講師から教えてもらうことで、受講者の理解度や納得度、現場で実践してみようと思う度合いも高まるでしょう。研修専門の会社に依頼すると、先述したような心構えや技術を持ち合わせたプロの講師から学ぶことができ、高い成果を発揮することが期待できます。
メリット②自分たちでは気づかない課題や解決法を提示してもらえる
研修を内製で毎年行っていると、毎年同じようなカリキュラムになりがちです。また、自分たちだけではそのカリキュラムの良しあしが分からず、効果の薄い研修を続けてしまう可能性もあります。
そこで、第三者視点として研修のプロの意見を取り入れることが有用です。研修会社は様々な業界、従業員規模の企業の研修を企画・運営してきているため、多くの知見を蓄積しています。外注の研修会社に相談すれば、これらの知見や人材育成の最新理論を活用した解決策を提案してもらえるでしょう。
デメリット①コストがかかる
内製に比べて外注はコストがかかります。しかし、会場や講師を自分たちで用意したり、研修講師として現場社員の時間を割いたりする必要はなくなります。内製することによる負担も考慮し、新入社員研修を外注させることは必要なコストであるかどうか検討する必要があるでしょう。
デメリット②講師や研修の雰囲気を自社の社風と合わせる必要がある
外注する会社によっては、自社の雰囲気と合わない可能性があります。たとえば、冷静にてきぱき仕事をこなす社風の会社に熱血指導の講師が派遣されてしまうと、研修の雰囲気と実際の職場の雰囲気の違いに新入社員は戸惑ってしまうことでしょう。
新入社員や現場の混乱を招かないためにも、外注先の研修会社には自社の社風や企業理念などをしっかりと伝えることをおすすめします。
監修者からひとこと |
オンライン研修を成功させるには

近年は、新型コロナウイルスの影響もあり、オンライン研修を導入する企業が多くなりました。
初めてオンライン研修を取り入れるという企業は、以下のことに注意しましょう。
操作方法を事前に予習・人材育成会社を吟味
WEB会議ツールなどの使い方が分からないと、そもそも実施することができません。事前に研修担当者が試して操作が難しくないかどうかチェックし、難しい点があれば補足資料を配布するとよいでしょう。
また、人材育成会社によってはオンライン研修の実績が少ない可能性があります。その場合、講師の教え方がオンライン研修に最適化されていなかったり、トラブルが起こり満足に受講できない受講者が出てしまったりする可能性があります。
人材育成会社を選ぶ際には、オンラインでの研修をどれくらい実施しているか確認した方がよいでしょう。また、当日の運営スタッフ体制や講師との質疑応答の方法なども事前に確認し、きちんと対応してもらえるかをチェックすることがおすすめです。
監修者からひとこと |
オンライン研修のメリット
ここではオンライン研修のメリットについて解説していきます。
なお、ここにあげた項目以外にも、自宅から参加ができるので交通費など会社が負担する費用が減るといったメリットもあります。
録画できるのでいつでも見返すことができる
オンライン研修の内容を録画しておけば、いつでも見直すことができます。また、事情があって参加できなかった受講者への共有も簡単です。
社員間の教育格差が生まれない
オンライン研修には、社員ごとの勤務地や雇用形態による教育の格差が生まれないというメリットがあります。
研修といえば集合研修のみであった時代は、地方の支社に勤めている社員は研修のたびに本社へ出張しなくてはなりませんでした。業務との兼ね合いから、研修の受けにくさを感じ教育に格差が生まれてしまっていたのです。オンラインで研修を開催すれば、全ての社員に学びの機会が拡がります。
受講者の意見を集めやすい
チャットや投票機能などを活用することで、受講者の意見やアイデアを集約しやすいのもオンラインならではの機能です。受講終了後のアンケートもその場で回答して送ってもらえれば、容易に回収ができます。
人材育成会社に外注するのもおすすめ
オンライン研修は、専用の資料の準備や受講者向けのWeb会議システムの使い方説明などに手間がかかります。また、ITリテラシーの高い社員やファシリテーション能力が高い講師が必要になるでしょう。したがって、社内でまかなうには事前準備と研修前教育に時間が取られてしまいがちです。
そこで、効率的に研修を実施したい場合は人材育成会社に外注するのもひとつの手です。
監修者からひとこと |
アルー株式会社の人材育成
アルー株式会社では、新入社員研修や新人フォローアップ研修、若手研修、中堅・リーダー研修、管理職研修と階層別に分かれた研修を行っています。
自律的に学び行動するプロフェッショナル人材の育成に力を入れているため、今までの研修では期待したほどの効果が出てこなかった企業には特におすすめです。
eラーニングシステムでのオンライン研修から集合研修まで取り揃えているため、学ばせたい学習内容に合わせて柔軟にプログラムを選択することができるでしょう。
▼アルーの新入社員研修の概要資料をダウンロードいただけます。
▼アルーの新入社員研修について詳しくはこちらのページもご覧ください。
監修者からひとこと |
新入社員研修の成功例
アルーがご提供し、成果を収めた新入社員研修の例を紹介します。
A社では、入社から3年間で一人前の社員となることを目的に新入社員を育成しています。その最初のステップとして、基本動作の定着を重要視した新入社員研修を実施していました。ところが、現場から「新入社員研修を受けても、社会人としての基礎の習得にバラつきがある」という不満がでてしまったのです。
実際、社会人としての基礎やビジネスマナーについては研修を行っていたものの、職場に出た後に行動ができているか、という点については人ごとにバラつきがある状況でした。そこで、「フィードバックされた内容の吸収力が高い」「協調性が高い」という近年の新入社員の強みを活かした新入社員研修を実施しました。
研修のゴールとして、新入社員全員が、社会人としての基本行動が「定着」し、自信を持って配属先で働けることを目指しました。
ゴール達成のポイントに向けた工夫は次の3つです。
- 研修期間の途中で基本行動に対する個別フィードバックを実施。受講者の改善点を明確にする
- 実践ドリルによる自主練の時間を設け、自ら練習に取り組む機会を設ける
- 中間試験、最終試験を設け、「最後は全員合格する」という目的を定め、新入社員が協力しながらも、主体的に練習に取り組む環境を作る
結果として、最終的に全員が最終試験をクリアし、社会人としての基本行動が定着した状態で現場への配属を迎えました。
長い時間を使い、練習時間の確保と最終試験合格という目的を置いたことで、新入社員が主体的に基本動作の習得に励むことができました。また、研修期間を通して同じ講師が担当したことにより、受講者の変化を見逃さずフィードバックすることができ、受講者のモチベーション維持、基本動作の習得促進につなげることができました。
まとめ
新入社員研修と一口で言っても、内容や形式が多岐にわたるため、内製だけで行うと効果が出づらい時代に変わってきています。社員研修を効率的・効果的に行うなら、自社の説明や専門的な分野の知識伝達は自社で行い、その他の研修は簡単に高品質な研修が実施できる外部の人材育成会社に依頼するのがおすすめです。
アルー株式会社では、『自己変容』『業務・課題への取り組み』『人や組織へのかかわり』『ビジネススキル』の4つの観点から研修を提供しています。また、毎年実施する新入社員研修を通して新入社員の傾向を分析し、新入社員の強みや弱みを把握した上でカリキュラムを組むことで、効果の高い研修が可能です。
どれも新入社員の成長を促すために重要なものですので、興味のある方は、ぜひ一度お問い合わせください。
▼アルーの新入社員研修の概要資料をダウンロードいただけます。
▼アルーの新入社員研修について詳しくはこちらのページもご覧ください。