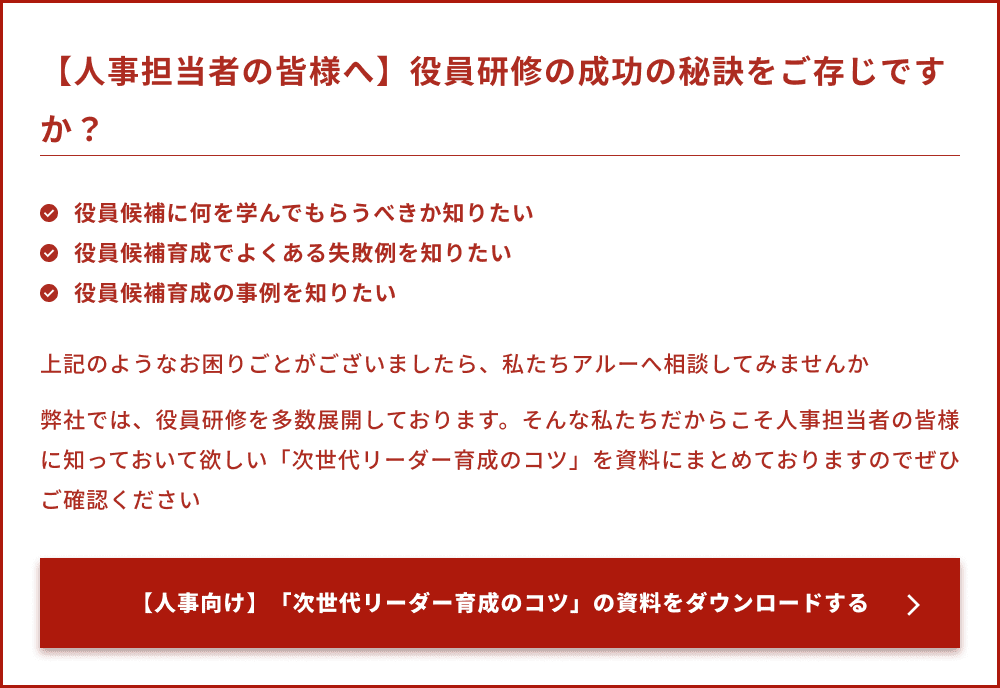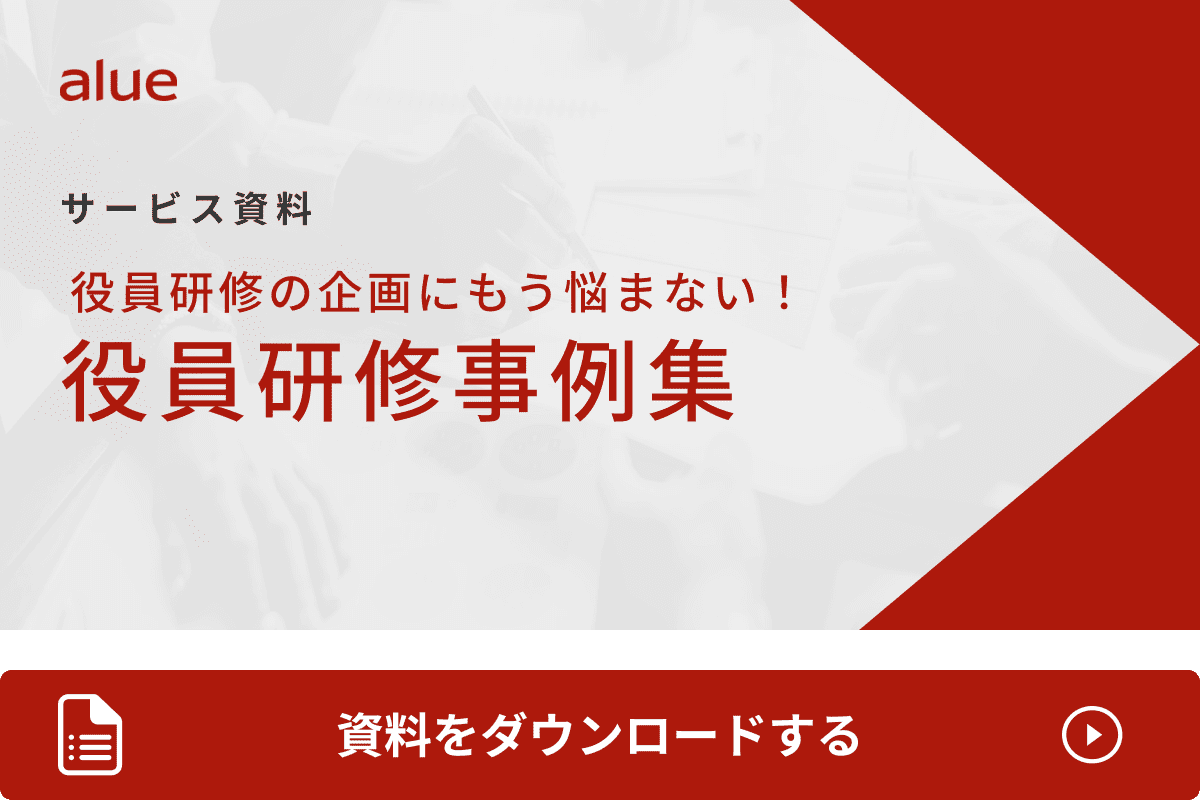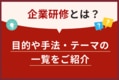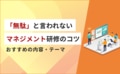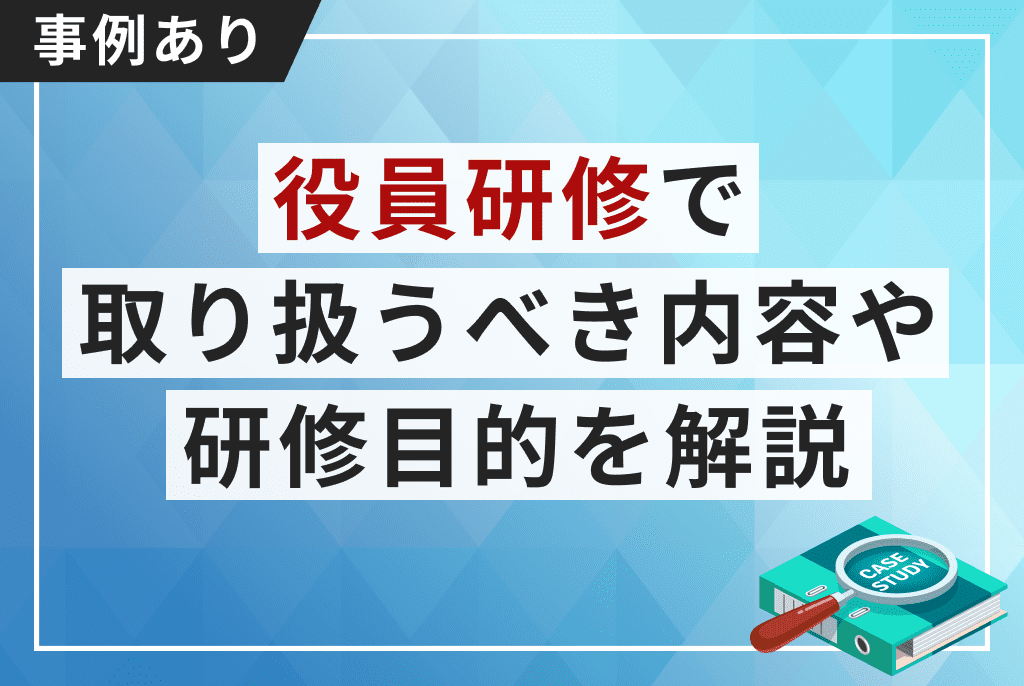
【事例あり】役員研修で取り扱うべき内容や研修目的を解説
現代における企業経営は困難を極めており、企業を維持するためには役員研修を実施し、役員を成長させることが必要不可欠です。
しかし、役員研修といっても「どのような研修を実施すれば良いか分からない」といった不安を抱える企業も少なくありません。
この記事では、役員研修の目的や取り扱うべき内容、研修効果を高めるポイントなどを解説します。
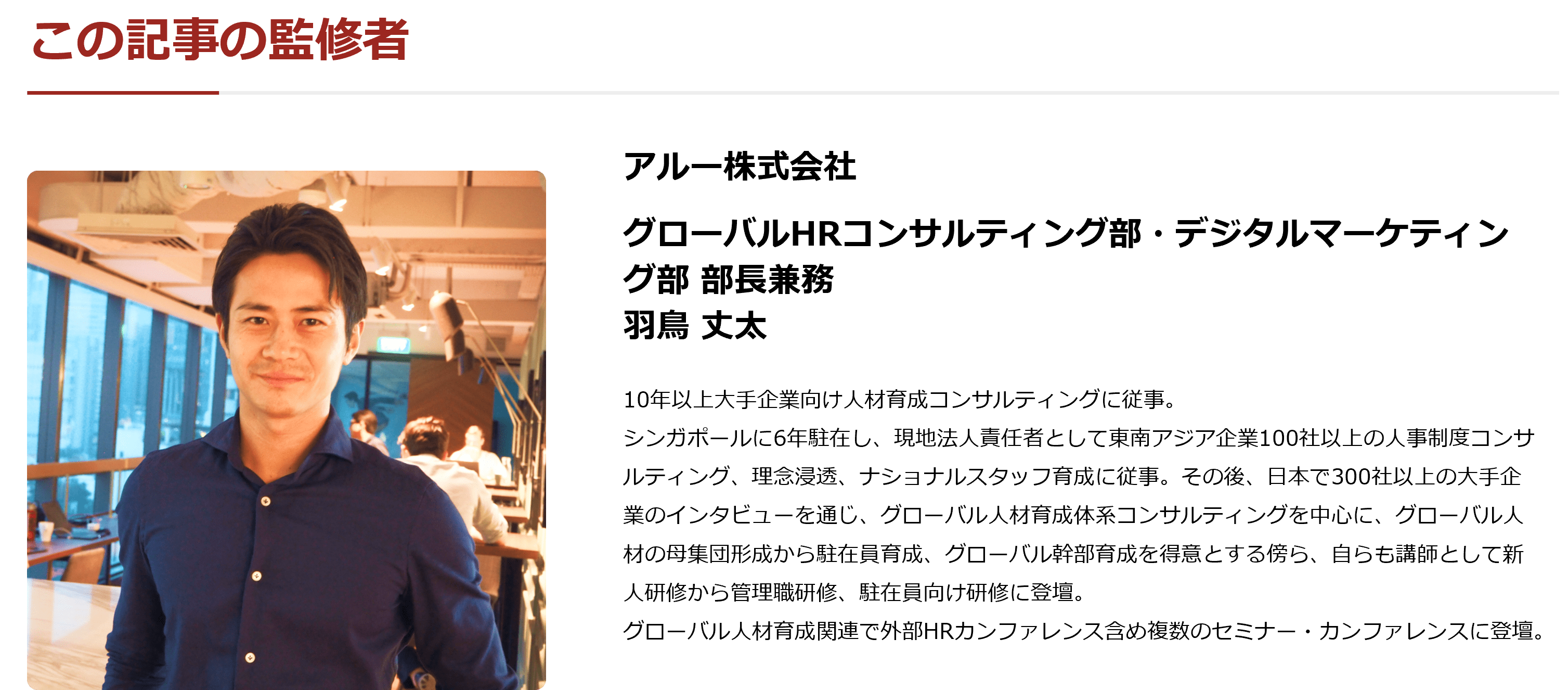
目次[非表示]
- 1.役員研修とは
- 2.役員研修の対象
- 3.役員研修の目的
- 4.役員研修で取り上げるべき内容
- 5.新任役員研修のプログラム例
- 6.役員研修の種類・方法
- 7.役員研修の設計方法
- 8.役員研修の効果を高めるポイント
- 9.アルーが行っている役員研修事例
- 10.役員研修ならアルーにお任せください
役員研修とは
役員研修とは、企業の経営に関わる人材として必要なマネジメントスキルをはじめ、「リーダーシップ」や「変化に対応できる能力」などを身につけるための研修です。
新入社員や中堅社員に向けた研修とは異なり、高いレベルのスキルを学ぶ研修内容となっている傾向があります。
役員は責任感と的確に判断できる能力が必要であり、経営に関わる人材として意思決定にも参加するため、変化の激しい現代のなかで柔軟に対応しながら企業を成長させるためにも必要不可欠な人材です。
そのため、近年では研修を通じて役員が求められている能力を身につけ、企業を成長させていくという考えが広まっています。
役員研修の対象
会社法上では、役員とは取締役・監査役・会計参与のことです。これらに執行役と会計監査人を加えると、「役員等」と呼ばれます。
役員研修を行う際の「役員」は、「取締役」や「執行役員」のことを指すことが多いです。
取締役は会社の業務執行に関する最終的な意思決定を行う役目を持っています。一方、執行役員は取締役の代わりに会社の業務を執行する役員であり、取締役の決定に従う立場です。
役員研修の目的
役員研修の具体的な目的として、以下の4つが挙げられます。
- 企業の経営理念・ミッション・ビジョンを実現するため
- 業績を高めるため
- 経営者の負担を軽減するため
- 役員に必要なスキルを高めるため
下記では、それぞれに分けて具体的に解説します。
企業の経営理念・ミッション・ビジョンを実現するため
まず、企業の経営理念や、ミッション・ビジョンを確認し、「組織のビジョンを実現するために自身は何をするべきか」を知り、社員に向かってどのように発信するべきかを学ぶ目的があります。
役員は社員と接する機会が少ないため、心理的な距離もあり、コミュニケーションが取りづらいですが、そのような中で役員としてどう振る舞うべきか、ビジョンの実現のために必要なスキルを取得します。
業績を高めるため
役員研修には、企業の業績を高める目的が含まれています。
上述したように役員は経営に関わる幹部の一人であり、意思決定も行うため、事業運営に大きな影響を与える人材です。
そのため、研修を通じて得た知識やスキルは企業経営に直結することが多くあり、役員の能力が企業の業績を左右するといっても過言ではありません。
確実な業績向上を狙いたい場合は高度な役員研修を実施し、的確な判断と円滑に業務が進められる人材を育てることが大切です。
経営者の負担を軽減するため
役員の経営に関わる幹部としての能力が十分であれば、経営者の負担を軽減することができます。
しかし、一方で役員の能力が足りてなければ最終的な意思決定やマネジメントなどは経営者が行わなければならず、企業経営の妨げにつながってしまうかもしれません。
そのため、役員研修を通じて役員の知識やスキルを向上させ、経営者の負担を軽減することで円滑な企業経営ができるようになるでしょう。
役員に必要なスキルを高めるため
役員は経営に関わる人材であるため、役員として必要不可欠なスキルを高めることや、求められる能力を身につけることは非常に重要です。
そのため、元々ある能力を伸ばす研修や、役員候補の社員に必要な能力を学習させる研修などの実施は、定期的に行っておくことをおすすめします。
また、役員のなかから経営者になるという方は少なくないため、役員としての知識やスキルを含め、経営力も高めておくと良いでしょう。
役員研修で取り上げるべき内容
ここまで役員研修の目的について解説してきました。
それらを踏まえ、役員研修ではどのような内容を取り上げれば良いのかと疑問に思う方も多いでしょう。
役員研修において、特に取り上げるべき内容は以下の通りです。
- 経営に関するマネジメント力
- 決断力、実行力
- 人的ネットワーク力
- コンポレートガバナンス(内部統制)
- 組織デザイン
- サステナビリティ経営
- ダイバーシティ経営
- テクノロジーやデータサイエンス理解
- ビジョン創造
- コンプライアンス
- リーダーシップ
- リスクマネジメント
- SDGs・DXなどの新しい取り組みに対する研修
それぞれ詳しく解説します。
経営に関するマネジメント力
現代では、VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代といわれており、デジタルテクノロジーによる進展が加速しています。
そのため、役員には変化への対応力を向上させ、企業価値を成長させられるマネジメント力が必要不可欠です。
具体例としては、経営ビジョンや経営戦略などの経営に関わるマネジメントや、ビジネスモデルの変革などを行うことが多い傾向にあります。
決断力、実行力
決断力や実行力を保有していることも役員にとっては欠かすことができません。
役員は上から指示されて行動するのではなく、「どのように会社を動かしたら良いのか」ということを自身で考えながら行動する必要があります。
場合によっては、社運を左右するような判断やリスクを抱えながらも思い切った判断するようなこともあるため、いかに冷静な決断や実行ができるかが重要です。
人的ネットワーク力
役員であれば社内外問わず、これまでに培ってきた人脈があるという方は多いのではないでしょうか。
それらの人脈に加えて、異業種の役員との交流によって特別な人的ネットワークを構築できる能力も必要な要素です。
主に、「経験の幅を広げ、異業種の知識を深める」や「社外の業務を引き受け、新しい価値観を得る」といったことを行うと、人的ネットワークは広がりやすいでしょう。
研修では、これらを踏まえて分かりやすく実施することで役員としての人的ネットワーク力が身につきやすくなるといえます。
コーポレートガバナンス(内部統制)
コーポレートガバナンス(内部統制)とは、企業が事業活動をするうえで、健全で効率的に運営するための仕組みをいいます。
役員になって間もない方やイマイチ理解できていないという方に対しては、必ずコーポレートガバナンス(内部統制)の研修を受講させることをおすすめします。
研修を通じて、コーポレートガバナンス(内部統制)の概要や役員としての役割認識を学習することで、社内管理体制を正常に機能させることが可能です。
また、今後の企業内で行うべきコーポレートガバナンス(内部統制)強化の内容を明確化することができるようになるでしょう。
組織デザイン
組織デザインとは、在籍している社員の能力を最大限に発揮できる環境を構築しつつ効率的に業務が進められる組織をデザインすることをいいます。
役員は、各部署などに指示を出すこともあるため、組織デザインに大きく関わる人材です。
そのため、研修を通じて組織のビジョンや経営戦略を理解し、具体的に組織の構築できるようになることが求められます。
サステナビリティ経営
サステナビリティ経営とは、環境や社会、経済の3つの観点において、持続可能な状態を実現する経営のことをいいます。
サステナビリティ経営は企業の長期的な継続には欠かせないため、企業活動においても考慮すべきポイントです。
役員は、サステナビリティ経営を意識しながら企業経営を担わなければならないため、研修を通じてしっかり理解することが大切といえます。
ダイバーシティ経営
役員はダイバーシティ経営も意識しながら企業経営する必要があります。
ダイバーシティとは、多様性や相違などを意味する言葉であり、ダイバーシティ経営は多種多様な人材が活躍できる組織を作り、企業の持続的な成長を図る経営戦略をいいます。
現代における多様性はさまざまであり、表面的な多様性や深層的な多様性など、非常にデリケートな要素です。
そのため、研修ではさまざまな多様性を理解し、どのような方でも能力を十二分に発揮できる機会を提供できるようにするために学習することが求められます。
ダイバーシティに関する研修や事例に関しては、以下のページからご確認ください。
『ダイバーシティの取組み事例10選。ダイバーシティとはなにかを簡単解説』
テクノロジーやデータサイエンス理解
現代ではテクノロジーが飛躍的に進歩しており、数学や統計学、プログラミングなどの理論を活用したデータの分析や解析を行うデータサイエンスが注目されています。
そのため、役員がそれらの技術に対してしっかり理解していることは経営戦略にも大きく影響します。
研修を通じて学習することで、「画期的な技術を自社にどのように活かせるか」「その技術をどこに活かせば業務効率化を図れるか」などを考えて企業経営に活かせるようになるでしょう。
ビジョン創造
企業におけるビジョンは、将来的な目的や実現したい未来像、果たすべき使命などを指しており、企業にとって欠かすことができない要素です。
そのため、ビジョンがなければ経営方針が決まっていないようなものであり、在籍している社員は不安になってしまう可能性があります。
役員は、このビジョンを創造して企業の方向性を決める場合もあり、その企業に合った的確なビジョンを作れることが求められます。
コンプライアンス
コンプライアンスとは法令順守という意味を持ち、社会的な規範に従って社会から非難されないように行動をすることを指します。
今の時代ではコンプライアンスは注意すべき要素であり、役員はコンプライアンスに関わる知識を保有していることが求められます。
そのため、研修を受講してコンプライアンスに関わる知識を学習し、コンプライアンスを守るための社内ルールの策定などを行えるようにしましょう。
コンプライアンス研修の目的や成功のポイントに関しては、以下の記事で詳しく紹介しています。
『コンプライアンス研修の目的とは?効果的な実施方法まで詳しく解説』
リーダーシップ
役員は組織をけん引していく存在であるため、リーダーシップも求められるスキルの一つです。
上記でも触れましたが、役員はビジョンの創造やビジョンの発信を行い、目標達成するために社員のモチベーションを高めていく必要があります。
そのため、マネジメントスキルやコミュニケーション能力を活用しながら、リーダーとして社員を導いていくことが求められます。
アルーが行っているリーダーシップ研修に関しては、以下のページをご確認ください。
リーダーシップ研修
リスクマネジメント
リスクマネジメントとは、将来発生するかもしれないようなリスクを想定し、あらかじめ損失や損害を最小限に抑えることをいいます。
あらゆるリスクを想定していれば、品質低下などによる企業イメージの悪化や、自然災害による被害を抑えることが可能です。
役員はさまざまなリスクの可能性を事前に想定しておき、そういった際に適切な対応ができることが求められます。
SDGs・DXなどの新しい取り組みに対する研修
SDGsやDXといった新しい取り組みに対する役員研修も実施しておくことをおすすめします。
SDGsは、サステナビリティで挙げた3つの観点について具体的な17のゴールを設定してより良い未来を築くことを目指している取り組みです。
一方、DXはテクノロジーなどをはじめ、さまざまな技術を活用して業務の自動化や働き方改革の推進を図ることをいいます。
これらは近年非常に注目を集めており、自社内で取り組むことで企業としてのさらなる成長が期待されているため、役員にとっては抑えておきたい要素でしょう。
DX人材の育成や必要スキルに関しては、以下の記事で詳しく紹介しています。
『DX人材とは?必要なスキルや人材確保の方法』
SDGsに関する研修は、以下の記事で詳しく紹介しています。
『SDGs研修の目的とは?ゲーム形式の効果的な研修例を紹介』
新任役員研修のプログラム例
ここでは、新任役員に向けて行われる研修のプログラム例を紹介します。
テーマ |
内容 |
イントロダクション |
|
事前課題(事業環境分析)の共有 |
|
ビジョニング |
|
インサイトを得る |
|
未来の顧客に向けた戦略を考える |
|
ワークショップ |
|
総括 |
|
受講者には事前課題として、事業環境分析を行ってもらいます。研修当日はビジョニングやインサイトを得るためのワークショップ、計画の素案作りなど、受講者自身が考え、手を動かす機会を豊富に設けています。役員が変革を自分ごと化し、組織をけん引していくことの重要性を学んでもらうのが目的です。
役員研修の種類・方法
役員研修には以下のような方法があります。
- 内製研修
- 外部研修
- 公開講座への参加
- コーチング
それぞれメリットとデメリットがあるため、自社の役員の課題に沿った方法を選ぶようにしましょう。詳しく解説します。
内製研修
内製研修は、社内で役員研修を企画し集合研修を実施することです。プログラム内容や教材、講師など、研修に必要な準備を全て社内で実施します。
内製研修のメリットは、自社の経営課題に合わせたプログラムを構築できることです。一般的な理論だけでなく、自社の今の課題や未来の課題に沿って議論を深めることができるでしょう。
一方、プログラムや教材をすべて社内で作成しなければならず、手間がかかることがデメリットです。役員研修の場合、講師選定の難易度も高いでしょう。社内で役員より知識と経験の豊富な人材を探すのは容易ではありません。
内製研修について詳しくは、以下のページもご覧ください。
『社員研修を内製化するメリット・デメリット|成功のポイントや流れを解説』
外部研修
研修サービスを提供している会社に委託し、役員研修を実施することもできます。役員研修に適したプログラム・講師を用意してもらえるので、研修にかかる手間を大幅に削減できます。
注意したいのは、コストがかかることと、自社の課題に合った内容にするには教材をカスタマイズしてもらう必要があるということです。教材を事前に確認し、役員研修のゴールに到達できる内容かどうかをチェックしましょう。
外部研修について詳しくは、以下のページもご覧ください。
『研修は外部委託すべき?委託している割合や委託先選定のポイント』
公開講座への参加
公開講座やセミナーへの参加も役員研修の方法の一つです。内製研修や外部研修と違って役員をひとところに集める必要がないため、役員のスケジュール調整をする必要がありません。一人からでも参加可能なので、就任タイミングに合わせて学習してもらうことができます。また、他社の人材と交流できるため、社内だけでは得られない気付きや視点を得られることも大きなメリットです。
ただし、公開講座の内容や実施時間、講師などはカスタマイズできません。自社の経営課題解決につながる内容なのかどうかは、事前にチェックする必要があります。
コーチング
役員一人ひとりにコーチをつけ、役員の成長を促すのも効果的な育成手法です。役員自身が課題や解決策を設定し実行していく過程で、コーチが介入し支援します。
コーチは役員に対して直接的な答えは提示しません。あくまでも役員の中にある答えを引き出すことに注力します。そのため、役員個人の人間的成長を促しやすいのが最大の特徴です。
ただし、大勢を一度に教育することはできないこと、短期的には効果が出ないことには注意が必要でしょう。
コーチングについて詳しくは、以下のページもご覧ください。
『コーチングとは|メリット・デメリットや必要スキルについて紹介』
役員研修の設計方法
効果的な役員研修を設計するには、インストラクショナルデザインに基づいて設計することが大切です。具体的には、以下のステップを踏むとよいでしょう。
- 人材要件を策定する
- ニーズの評価と分析
- 研修デザイン
- 教材開発
- 研修の実施
- 研修実施後の評価・効果測定
各ステップについて詳しく解説します。
Step1:人材要件を策定する
まず、役員の人材要件を策定しましょう。人材要件とは、対象の社員にどの能力を身につけてほしいのかを整理したもののことです。人材要件を作成する際には、求められるマインド、スキル、経験を抜けもれなく書き出すように注意しましょう。
役員の場合は、例えば以下のような人材要件が考えられます。
- マインド:よりよい社会・組織の実現を志向している、ミッションの達成によって実現される世界を自分の言葉で語っている
- スキル:企業の継続的な成長のKSFを特定できる、経営戦略推進に必要な資源を調達・配分している
- 経験:新規事業立案、拠点立ち上げ
Step2:ニーズの評価と分析
次に、現場・経営層のニーズの評価と分析を実施します。ニーズを把握することで、現状とあるべき姿とのギャップを明確にし、的確な研修のゴールを設定できます。
ニーズには、主に以下の5種類があります。
- 標準的なニーズ……標準的なものとの違いから生まれるニーズ
- 感覚的なニーズ……人々が何を求めているのかという感覚に基づくニーズ
- 必需的なニーズ……マーケットや流行に依存するニーズ
- 比較的なニーズ……競合との差異や、競争に基づいて発生するニーズ
- 将来的なニーズ……プロジェクトのゴールとなる、長期計画から生まれるニーズ
上記の観点で、現場や経営者にヒアリングを行い、どのようなニーズがあるのか把握しましょう。その後、具体的な研修の要件を決めるため、研修対象となる社員の分析やテクノロジーの分析、課題の分析などを進めていきます。
分析は、以下の9つのタイプに分けて実施してきましょう。
- 受講者の分析:教材を受講する対象者を明確にする。
- テクノロジーの分析:既存のテクノロジーやキャパシティを再認識する。
- 課題の分析:受講修了後の効果が、現実の仕事に役立つかどうか。
- 重要項目の分析:どのようなスキル、知識がターゲットとなるか明確にする。
- 環境の分析:組織的もしくは環境的考慮を分析する。
- 目的の分析:ターゲットとする目標を挙げて明白にする。
- メディアの分析:適切な学習メディアを選別する。
- 既存データの分析:現存する教材、マニュアル、参考書などを明確にする。
- コスト、利益の分析:コストや利益、投資に対する金額的な見返りを計算する。
参考:インストラクショナルデザインとは - 最適な学習効果のための教育設計 | SATT
Step3:研修デザイン
ニーズの評価と分析が終わったら、研修デザインを行います。
研修デザインとは、研修プログラムの仕様を固めていく工程です。具体的には、以下のような点を検討しましょう。
- 研修のスケジュール
- 研修の形式(オンライン、対面、eラーニングなど)
- 教材の準備方法や制作担当者
- 教材の構成・配布方法
- 研修の効果測定方法
Step4:教材開発
次に、研修で使用する教材を開発しましょう。
教材を開発する際は、教材開発を担当するチームを編成し、メンバーそれぞれの担当領域を明確にするのが大切です。どの内容をどのセクションで扱うのかを明確にしておかなければ、手戻りが発生する可能性があります。
また、共通のテンプレートや、雛形となる最初の教材を用意してから作業に取り組むのもポイントです。教材の統一感をもたせることができますし、部品が共通化されていればデザインの工数も最小限で済みます。
研修教材の作り方について詳しくは、以下のページもご覧ください。
『見やすい・分かりやすい研修資料の作り方を研修のプロが解説』
Step5:研修の実施
研修の使用が固まり、教材の作成が完了したら、実際に研修を実施しましょう。
研修当日は参加者の様子を丁寧に観察するのが大切です。理解の甘い部分がないか、参加者がつまずいていないかなどをチェックして、必要に応じてサポートを提供しましょう。疑問点をいつでも解決できるよう、サポートスタッフを配置しておくのもおすすめです。
Step6:研修実施後の評価・効果測定
研修を実施したら、必ず評価と効果測定を実施しましょう。
研修の効果測定を実施する際には、事前にKPIを設定して定量的に分析するのが大切です。以下のような点を中心に効果測定を実施するとよいでしょう。
- 当初目標としていた知識やスキルは身についたか
- 想定通りのスケジュールで研修は終了したか
- 研修参加者の満足度はどうだったか
効果測定の内容を取りまとめ、次回以降の研修設計に活かします。また、理解度の足りていない受講者に対するフォロー施策もこの段階で検討するとよいでしょう。
研修の効果測定の方法は、以下の記事でさらに詳しく解説しています。
『研修効果測定の方法とは|4つの評価レベルや効果測定のポイント』
役員研修の効果を高めるポイント

上記では、役員研修において取り上げたい内容について解説してきました。
それらを踏まえ、研修効果をさらに高めるポイントとしてはどういったことが挙げられるのでしょうか。
下記では、効果を高められるポイントを具体的にご紹介します。
研修のゴールを明確にする
役員研修を実施する際には、毎回ゴールを明確に設定しましょう。
「毎年やっているから」「役員に就任したらやるものだから」という理由だけで実施してしまうと、研修の効果が薄れてしまいます。受講者にも「やらされ感」がでてしまうでしょう。
「この研修で得られること」や「研修後のあるべき姿」などのゴールを明確にして研修を行うことが大切です。
経営トップとの対話
役員研修の前後に経営トップと対話することも大切です。
「役員に期待すること」や「これからの時代に求められる経営」などを話すことで、経営者と役員の間で認識合わせを行うことができ、方向性の相違を防ぐことにつながります。
他の階層の研修では経営トップが研修に携わることはあまりないかもしれません。
しかし、役員研修の場合は経営トップにも研修に参画してもらう必要があります。役員研修を企画する際には、経営トップとも議論しながら進めるとよいでしょう。
外部有識者との対話
経営トップとの対話に加え、外部の有識者との対話も研修効果を高めるポイントの一つです。
外部の有識者であれば、第三者の観点からの意見を聞くことができます。自社内で対話するだけでは気付けなかったような視点も得られるでしょう。
そのため、役員研修の前後に外部の方と話せる機会があれば積極的に会話するように意識すると良いでしょう。また、外部の有識者に研修講師を依頼することもおすすめです。研修の内容に外部の有識者の意見や経験を反映できるので、研修内容が充実することにもつながります。
適応課題にアプローチする
適応課題とは、自身や企業の価値観や考え方に根ざしており、今の価値観だと対応が難しいような課題のことをいいます。
例えば、「部下は上司の言うことを聞くべきだ」「自分のやり方でやれば絶対に成功する」というような考え方をしている上司は、部下のやり方を否定したり、部下の自発的な行動を制限したりしてしまいます。このように技術やスキルを身につけるだけでは解決できない課題を適応課題と呼びます。
こういった思い込みによる適応課題は珍しいことではなく、自身の価値観の変革や偏った思想を手放すといったアプローチをすることで改善することが可能です。
適応課題について詳しくは下記の記事をご覧ください。
『適応課題と技術的課題の例を紹介。研修で適応課題にアプローチする方法』
組織・受講者自身の課題を認識するプログラムを取り入れる
役員研修の冒頭や事前課題で、自身や組織の課題を認識する時間を設けることも研修効果の向上に効果的です。
誰かから課題を押し付けられて認識するのではなく、受講者自らが考えることでその後の研修内容を自分のことのように捉えることができます。
そうすれば研修内容をより理解しやすくなるほか、さらなる成長が期待できるようになるでしょう。
コーチングやアクションラーニングを取り入れる
研修によるインプットだけで終わらせるのではなく、受講者にコーチをつけて研修後の行動の変化を支援することも有効な手段です。
そうすることで受講者はより現実的に変化を実感することができ、研修効果を体験しやすくなります。
また、課題に対する解決策をグループディスカッションで行い、解決策の実行と振り返りを繰り返しながら個人と企業の学習能力を向上させるアクションラーニングを取り入れるのも良いでしょう。
アクションラーニングに関しては、下記の記事で具体的に解説しているので併せてご確認ください。
『アクションラーニングとは|効果や進め方・注意点について』
外部の研修会社を利用することも大切
自社内で行う役員研修だけではなく、研修を専門的に扱っている外部の会社を利用して社外研修を行うのも大切です。
外部の研修会社であれば、自社にはないような価値観に触れることができ、今までになかった発想や専門的な知識を得ることができます。
また、上記でも触れた外部有識者と会話する機会にもつながるため、研修をより良いものにできるようになるでしょう。
研修を外部委託すべきかどうかや、外部の研修会社を利用している企業の割合については、以下の記事で詳しく紹介しています。
『研修は外部委託すべき?委託している割合や委託先選定のポイント』
アルーが行っている役員研修事例

アルーは人材育成を専門的に手掛けている企業であり、役員研修をはじめ数多くの研修を実施しています。
ここでは、アルーの実際に行った役員研修の事例についてご紹介します。
コミュニケーション変革研修
経営層のコミュニケーションスタイルを見直し、健全な組織を作る研修の事例です。
経営層の中にコミュニケーションスタイルに難がある方は少なからずおり、不健全な上意下達の文化が構築されている場合があります。
具体的な事象として、「反論できない雰囲気を醸成している」や「相手は知らないと決めつけて会話している」といったことが挙げられます。
こういった不健全な環境があると、社員は十分に能力を発揮することができず、萎縮してしまいかねません。
その状態を解決を図るべく、経営層には「今の自分についての振り返り」や「自身のコミュニケーションに関する認識」、「今後求められるコミュニケーションスタイルの理解」といった内容を学んでもらいました。
さらには、それらに加え、今後の企業経営において必要な「社員の心地良さ」への理解も促進しました。
女性役員候補者育成研修
今後2年以内を目安に、役員昇進が期待されている女性部長を対象に実施した研修事例です。
役員への昇進が期待されている候補者に対し、役員になるために必要な視野・視座の獲得を促すマインドセットを行いました。
また、それぞれに合わせたフォローを行うために、研修とコーチングを組み合わせた構成としています。
この研修を通じて、受講者が「今まで築いてきたキャリアや価値観を改めて振り返り、役員となることを前向きに捉えることができる」ということを目指しています。
海外拠点長育成研修
海外の拠点長として、経営マネジメントを行ううえでの重要なスキルや考え方をケーススタディやディスカッションを通じて学習した研修事例です。
はじめに受講者の間で悩んでいることや今後の不安を共有し、共通の話題づくりを行いました。
その後、「拠点長は何をするのか」や「拠点長の業務」などを上位管理職という観点から学びます。
それに加え、現地でよく起こることに関してケーススタディを通して疑似体験をし、海外現地での実践に備えました。
役員研修ならアルーにお任せください
役員研修の目的や取り上げるべき内容、役員研修の効果をさらに高めるポイントなどについて解説してきました。
役員研修を行うことで、より的確な判断力を身につけることができ、円滑な意思決定を行うことができるようになります。
また、変化が目まぐるしい現代において、柔軟に対応できる役員がいることが企業を成長させていくうえでは欠かせないといえるでしょう。
役員研修の実施を考えている場合は、人材育成を専門としているアルーへお任せください。
アルーが長年培ってきた人材育成のノウハウを活用し、貴社に最適な役員研修をご提案します。
アルーの役員研修については、以下からお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ