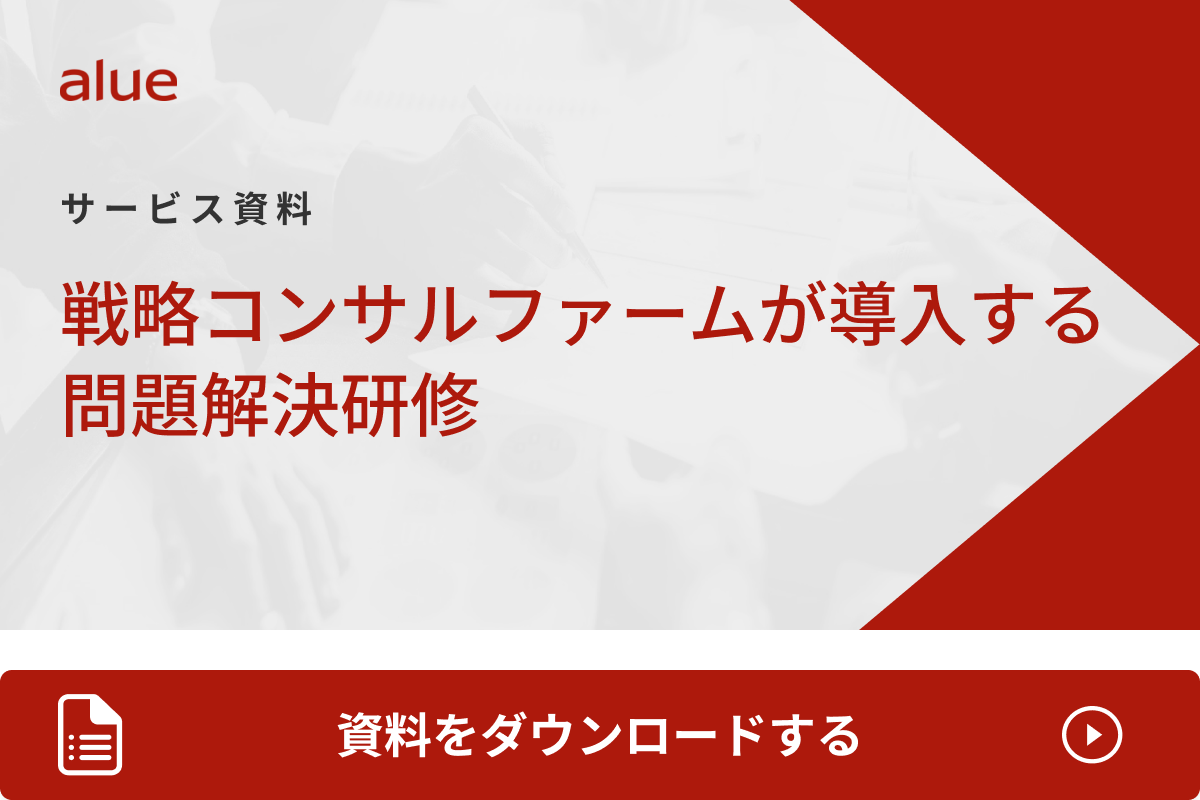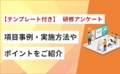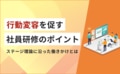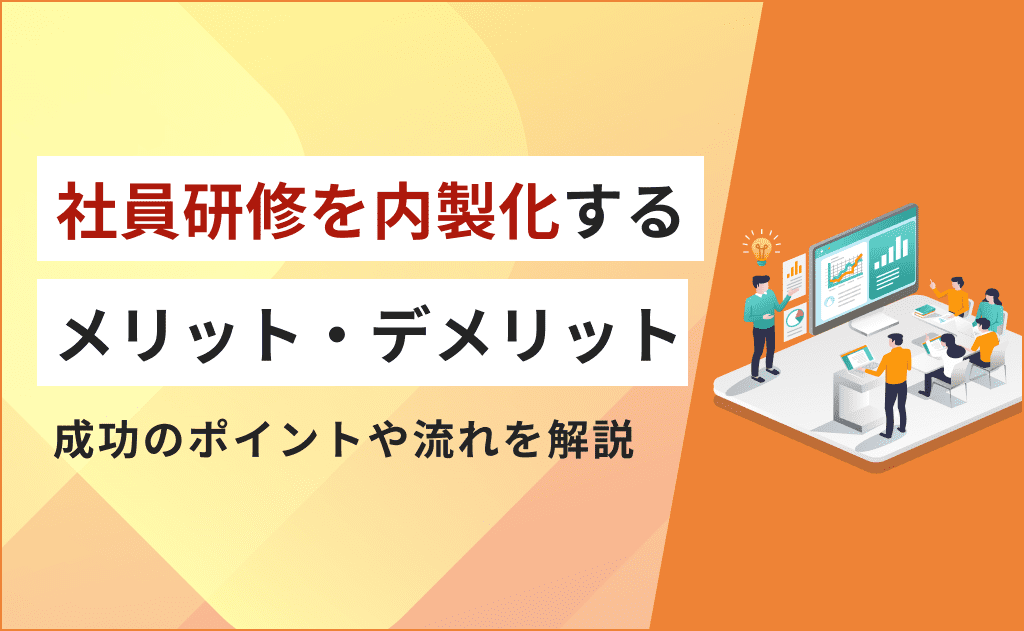
社員研修を内製化するメリット・デメリット|成功のポイントや流れを解説
「研修を内製化したいが、どのように進めるのが良いのか」や「現在実施している研修の内製化を検討するべきなのか」といった疑問を持っている担当者の方も多いのではないでしょうか。
研修の内製化には多くのメリットがある一方で、人的コストがかかるといったデメリットも存在するため、丁寧に検討したいポイントです。
この記事では、研修を内製化する流れやポイント、内製化のメリットやデメリットなどについて解説します。
より深く知るための『オススメ』お役立ち資料
目次[非表示]
企業が研修を内製化している割合は?
産労総合研究所が公表している調査「2015年度(第39回) 教育研修費用の実態調査」によると、企業が研修を内製化している割合はおよそ67.4%となっています。
研修の内製化割合は年を追うごとに低下しつつありますが、半数以上の企業が研修の内製化に取り組んでいるのが現状です。
一方、32.6%の企業は「研修の内製化に取り組んでいない」と回答しています。
内製化に取り組んでいない主な要因としては、講師を依頼できる社内人材の不足や、人事部門の負担が挙げられています。
研修を外部委託している大企業は多い
日本経済団体連合会が2020年に公表した調査「人材育成に関するアンケート調査結果」によると、専門分野における能力開発で外部との連携による育成を検討している企業は78.2%に達しています。
日本経済団体連合会を構成する企業を対象とした調査であるため、大企業では研修の外部委託が特に進んでいるといえるでしょう。
特に、外部連携先としては人材育成サービス企業が最も多く、55.6%となっています。
また、他企業や大学、高専などの教育機関とも連携している企業も一定数存在します。
研修を外部委託している割合や委託をすべきケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。
『研修は外部委託すべき?委託している割合や委託先選定のポイント』
研修内製化するメリット
研修を内製化するメリットとして、研修に対するノウハウを社内に蓄積できる点や研修を通じて受講者と講師双方のスキルアップが期待できる点などが挙げられます。
ここでは、研修を内製化するメリットについて詳しく確認していきましょう。
研修に対するノウハウを蓄積できる
研修を内製化する第一のメリットとして、研修に対するノウハウを蓄積できる点が挙げられます。
たとえば、研修を実施する際には、教材の管理方法や受講者のモチベーション管理方法といったノウハウが必要になります。
また、リモートで研修を実施する際には、ZoomやMicrosoft Teamsをはじめとした各種ツールの導入が必要です。
研修の実施を通じて、社内にこうした育成ノウハウが蓄積され、将来的な人材育成に活かされる可能性があるでしょう。
研修を通して受講者・講師ともにスキルアップができる
研修を内製化する場合、社内から講師を選抜します。
講師となった社員は、研修で話す内容を今一度見直すため、自分のスキルや知識をアップデートすることが可能です。
また、研修を内製化すれば受講者だけでなく、講師のスキルアップも期待できます。
他人に物事を説明する際には、自分の言葉で物事を噛み砕いて分かりやすく話す必要があるため、最も効率良く学習が進むともいわれています。
そのため、分かりやすい研修を目指す過程で、受講者と講師双方のスキルアップが期待できるようになるでしょう。
研修講師に求められるスキルや選定方法については、以下の記事で詳しく解説しています。『研修講師に求められるスキルとは。講師の選び方や研修を成功させるポイント』
研修の修正・改善がしやすい
研修を外部委託した場合、基本的には委託先の企業が用意している研修プログラムを利用することになります。
しかし、プログラムの修正対応は基本的になく、仮に対応してもらえたとしても研修内容の修正や改善を行う際には、金銭的コストや外部とのコミュニケーションが必要です。
そのため、こうした修正対応を煩わしく感じてしまう場合も少なくありません。
一方で、研修を内製化していれば、研修内容の修正や改善を自社で完結できます。
修正対応に時間が取られないとともに、テーマ変更などにも柔軟に対応することが可能です。
業務に直結した研修を実施できる
研修プログラムを内製化する際には、自社での実務をよく理解した人材がプログラムを作成します。
その結果、業務で必要となるスキルを効率的に身につけられる研修プログラムを作成できる点も内製化のメリットです。
経営者や現場へのヒアリングなどを丁寧に行えば、経営戦略や現場の課題と密接に連動した研修プログラムを作成できるでしょう。
また、研修設計の自由度も高く、自社ならではの独自性の高い教育プログラムを提供できます。
研修を内製化するデメリット
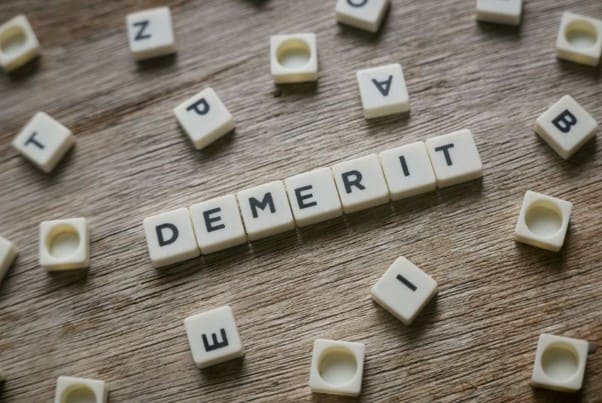
上述では、研修を内製化するメリットについてご紹介しました。
しかし、研修を内製化することには同時にデメリットも存在します。
特に、内製化する際にはコストがかかる点や、講師の育成が負担となる点には注意が必要です。
ここでは、研修を内製化するデメリットとして代表的なものを3つご紹介します。
コストがかかることもある
研修を内製化する際には、社内の人材が研修プログラムの作成や研修の実施、学習状況の管理などに携わることになります。
そのため、研修の実施のためには社内のリソースが必要です。
金銭的なコストでいえば、外部委託する場合と比べて安く抑えられるケースがほとんどですが、時間的なコストは増える点に注意が必要です。
また、講師の育成や研修プログラムの作成、研修会場の手配や効果測定といったプロセスを実施する際には人的コストも発生するため、それらに見合ったメリットがあるかどうかを確認するのが大切です。
講師を育成する必要がある
研修を内製化する場合は、社内から講師を選抜して育成する必要があります。
しかし、普段の実務に取り組んでいるなかで研修講師としてのスキルを磨いてもらうことは、キャパシティ的に厳しいことも少なくありません。
講師の育成が不十分である場合、イマイチ効果的の得られない指導を行ってしまう可能性もあります。
指導の際の心構えや効果的な話し方など、指導に必要なスキルを一から身につける必要があるという点は理解しておくことが肝心です。
講師に求められるスキルや講師に対しての育成については、以下の記事で詳しく解説しています。
『研修講師に求められるスキルとは。講師の選び方や研修を成功させるポイント』
研修プログラムの構築が難しい
研修を内製化する場合、研修プログラムの構築からはじめる必要があります。
しかし、効果的な研修プログラムの構築は容易ではありません。
経営課題の分析からはじまり、パフォーマンスの分析や課題の発見、スケジュールや教材設計といったさまざまなタスクに取り組む必要があります。
講師経験がない方が作成すると我流のプログラムになってしまったり、必要以上に時間がかかってしまう可能性があります。
研修プログラムの構築方法や流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
『研修企画の考え方や流れを徹底解説!「やるだけ」の研修は卒業しよう』
内製化に適した研修テーマ
研修を内製化することには、メリットとデメリットがどちらも存在することが理解できたのではないでしょうか。
研修を内製化するかどうかは、学びたいトピックに合わせて柔軟に判断していくのが重要です。
ここでは、内製化に適した研修テーマを3つご紹介します。
経営理念やビジョン共有の研修
研修では、経営理念やビジョンを共有することも多くあります。
特に新入社員研修では、自社の設立経緯や経営方針といった基本的な事柄まで立ち返って説明することがほとんどでしょう。
経営理念やビジョン共有を目的とした研修は、内製化するのがおすすめです。
こうした社内の方針を最も理解しているのは、経営層をはじめとした社内の人材であり、特に社長などのトップ層から直接語ってもらえば、外注して実施した場合と比べて説得力も格段に高まります。
自社のルールを共有する研修
仕事の回し方やマナーなどについて、自社独自のルールが運用されている場合もあります。
Slackをはじめとしたコミュニケーションツールの使用方法についても、独自の運用基準が設定されていることも多くあります。
こうした自社特有のルールを共有する研修も、自社で実施するのがおすすめです。
社内ルールは独自性が高いため、研修を外注する際にはそもそも何を教えるのかを外注先の担当者へ共有しなければいけません。
わざわざ手間をかけて外注するよりも、社内のルールをよく理解している人材から直接話してもらうほうがスムーズです。
業務内容に関連する研修
業務内容に関連した特定の知識を研修で伝えたいケースも多く、社内ツールの使い方や実務に直接関連するテーマなどが挙げられます。
業務内容との関わりが深いテーマについても、内製化が望ましいです。
そのなかでも、ツールの使い方や実務のコツなどについては、OJTなどで少人数指導を行うとより良いでしょう。
業務に関する内容を教えることで、講師自身のスキルアップにつながるというメリットもあります。
内製化せず外部委託したほうが良い研修テーマ
内製化したほうが良い研修テーマについて解説しましたが、なかには外部委託したほうが良い研修テーマも存在します。
外注がおすすめな研修テーマとしては、一般的な知識を身につける研修や、最新技術や専門知識を学ぶ研修、大人数で行う研修などが挙げられます。
ここでは、外注がおすすめの研修テーマを3つご紹介します。
一般的な知識に関する研修
ビジネスにおいては、新入社員や中堅社員、ベテラン社員といった特定の階層に応じて一般的な知識が求められる場面も多いです。
一般的な知識については、外注した研修で実施するのがおすすめです。
たとえば、新入社員を対象としたビジネスマナー研修や、中堅社員を対象としたロジカルシンキング研修、管理職を対象としたマネジメント研修などが挙げられます。
このような一般的な内容は、研修を専門に委託している企業に多くの育成ノウハウが蓄積されています。
そのため、社員がつまずきがちなポイントや納得してもらいやすい伝え方などをよく把握しており、効率良く教育することができるでしょう。
アルーでは、一般的な知識に関するテーマ別の研修を数多く取り揃えております。以下のページで一覧をご確認いただけます。
テーマ別研修一覧
専門知識や最新情報を学ぶ研修
社内には蓄積されていない専門知識や最新の情報について学んでほしいという場合もあるのではないでしょうか。
専門知識や最新情報を社内講師に依頼する場合、社内講師は専門知識や最新情報を自分自身で学習しなくてはならないため、大きな負担がかかってしまいます。
そのため、豊富な知識を保有している社員が在籍していないが専門性の高い研修を行いたいという場合は、外注するのがおすすめです。
そのなかでも、外国語やAI技術をはじめとしたITトレンドなどは、外注することによって社内には蓄積されていない高度な情報を提供してくれるでしょう。特に外国語はネイティブ講師に学ぶことが重要です。
アルーでは、ビジネス経験が豊富なネイティブ講師から英語を学べる研修を行っております。詳しくは以下のページでご確認ください。
ビジネス英会話研修「ALUGO」
▼ネイティブ講師から英語を学べる「ALUGO」について詳しくはこちらの資料をご覧ください。
大人数で行う研修
大人数で行う研修は、研修の管理に負担がかかり、それぞれの社員の学習状況をモニタリングする必要もあるため、研修の会場確保にもコストがかかってしまいます。
そういった大人数で一斉に行う研修も外注するのがおすすめです。
研修を専門としている企業では、対象が大人数であっても効率良く育成するノウハウが蓄積されています。
さらには、リモートやeラーニングなどもフル活用しながら最短時間で全員のスキルや知識を底上げしてくれるでしょう。
研修を内製化する流れ・手順
研修を内製化する際には、どのような手順で行えば良いのでしょうか。
研修の内製化は、主に以下の4ステップで行われます。
- 研修計画の立案と目標設定
- 講師の選定と育成
- 研修プログラムの作成
- 研修の実施とブラッシュアップ
研修を内製化する流れと手順について見ていきましょう。
計画の立案・目標設定
研修を内製化する際には、まず計画の立案と目標設定からはじめます。
この段階では、最初に経営層へのヒアリングを行い、「どのような経営課題があるのか」を明らかにしましょう。
続いて、現場へヒアリングを行って現場の課題を知り、理想と現状の間のギャップを把握します。
このギャップを埋めることが、研修の目標です。
計画の立案では、先程設定した研修の目標に基づいて、まずは研修テーマを決めると良いでしょう。
その後、研修期間や研修タイプなど、具体的な研修の概要を決めていきます。
研修計画の立案やプログラムの作成については、以下の記事で詳しく解説しています。
『研修企画の考え方や流れを徹底解説!「やるだけ」の研修は卒業しよう』
講師の選出・育成
研修の大まかな構成が決まったら、次に講師の選出と育成を行います。
社内講師を選抜する際には、以下を満たすような社員を選抜するのがポイントです。
- 豊富な経験があり、研修内容に対する理解が深い
- コミュニケーションスキルを身につけている
- 可能であれば、年齢や職位などで受講者と距離感が近い
社内講師を選抜したら、教育者として必要な能力を身につけてもらう必要があります。
その際、社内講師に丸投げとなってしまわないように指導の際の心構えやコミュニケーション技術を習得する機会を設けることが必要です。
講師の選出方法や必要なスキルについては、以下の記事で詳しく解説しています。
『研修講師に求められるスキルとは。講師の選び方や研修を成功させるポイント』
研修プログラム・カリキュラムの作成
研修講師が決まったら、研修プログラムやカリキュラムの作成に移ります。
ここでは、具体的な研修実施のスケジュールや教材の内容などについて検討していきます。
何から手をつければ良いのかと迷ったら、まずは研修で教えたい内容をリストアップすることがおすすめです。
研修全体のボリューム感が見えてくれば、具体的な研修スケジュールや教材の内容も決めやすくなります。
ただし、研修のスケジュールを設定する際には、フォローアップの日を確保するのを忘れないようにしましょう。
研修実施・ブラッシュアップ
研修の準備が完了したら、いよいよ研修を実施します。
研修中は、受講者がしっかりと研修内容をフォローできているかをよく観察するのが大切です。
また、研修の実施が終わったら、研修内容のブラッシュアップを行い、次回以降の研修へとつなげましょう。
具体例として、研修実施後に以下のようなアンケートを実施するのがおすすめです。
- 研修に対する全体的な満足度は?
- 今回の研修内容で分かったこと、分からなかったこと
- 研修内容を今後の実務に活かせそうか?
さらに、研修実施後6か月〜1年程度で再度振り返りを行い、KPI測定やヒアリングを実施するのもおすすめです。
▼研修の効果測定のコツについてまとめた資料をダウンロードいただけます。
研修を内製化させるポイント

ここまでに、研修を内製化する流れや手順について解説してきました。
それらを踏まえて、研修を内製化する際はどういったポイントに気をつけるのが良いのか気になるという方もいるでしょう。
ここでは、研修を内製化する際の代表的なポイントを9つご紹介します。
コンピテンシーを作成する
コンピテンシーとは、物事を成功させるのに必要な行動特性のことです。
たとえば、社内で業績をあげている優秀な社員たちに共通する特性があれば、それがコンピテンシーと呼ばれます。
研修を内製化する際には、理想とするコンピテンシーを作成するのがポイントです。
具体例として、マネジメント能力を育成する研修を実施する場合、「会社が理想としている上司像」が明確でなければ研修内容にも反映できません。
社内でロールモデルとなる人物像が確立されているからこそ、明確な目標を持った研修が実施できるといえます。
社員の学習動機を喚起する仕組みを作る
研修に対する受講者のモチベーションは、研修での学習効果に大きく影響を与えます。
研修を内製化する際には、社員の学習動機を喚起する仕組みを作るのも大切です。
「やりたい」という気持ちを表す動機には、以下の3つが存在します。
- 役割遂行:組織の一員としての義務や責任、期待といったアプローチ
- 課題解決:実務上で得られるメリットや結果など、学習上の有用性からのアプローチ
- 内在化:個人的な信念や価値観と学習内容を調和させるアプローチ
どの種類の動機にアプローチするのかを考えながら、種類に応じたプログラムや動画を活用するのがおすすめです。
習得してほしいスキルによって教材や育成手法を使い分ける
一言で研修といっても座学やロールプレイング、eラーニングなど、育成手法は多種多様です。
習得してほしいスキルに応じて、教材や育成手法を使い分けるようにしましょう。
先程解説した動機と同様に、研修で習得すべき技能も3種類に分けることができます。
- メタ認知的技能:自分の行動や思考を客観視して意図的に制御するスキル
- 認知的技能:抽象的な概念やルールを現実に当てはめて理解するスキル
- 動作的技能:具体的な行為や手順を記憶して、実務で再現するスキル
たとえば、抽象的な概念や知識をはじめとした認知的技能を身につけてほしいという場合は、eラーニングを活用するのが効率的です。
一方、ビジネスマナーなど動作的技能を身につけてほしいという場合は、対面形式での集合研修を実施し、ロールプレイングなどに取り組んでもらうと良いでしょう。
社員の自己効力感に気を配る
自己効力感とは、自分自身に対する「できる」という気持ちのことです。
自己効力感があれば自信につながり、積極的な学習やチャレンジを引き出すことができます。
そのため、研修を実施する際には自己効力感にも気を配るようにしましょう。
たとえば、研修内で成功例だけを引き合いに出すと、「そんなレベルの高いことは自分にはできない」と後ろ向きになってしまう可能性があります。ありがちな失敗事例とそれに対する対策も豊富に描写することで、「これなら自分もできそう」という感覚を抱いてもらいやすいです。
また、演習を実施する際には段階的に難易度をあげて、成長実感を得てもらうのもおすすめです。
「モードの切り替え」を意図的に行う
研修を内製化する際には、「モードの切り替え」を意識すると良いでしょう。
モードの切り替えとは、以下の3つの切り替えの総称です。
- 視点の切り替え:同じ場所を見続けさせない
- 思考の切り替え:インプットだけでなく、アウトプットを行う仕掛けを作る
- 気持ちの切り替え:講義を真面目に聞くだけでなく、「楽しむ」「気軽に聞く」といった意識を持ってもらう
こうしたモードの切り替えを積極的に行えば、飽きられることのない研修が実施できます。
社内全体でサポートする
研修の内製化は、一部の人事担当者や社内講師講師の力だけで成功する業務ではありません。
研修を内製化する際は会社全体の案件だと捉え、現場の教育担当者や経営者も一丸となってサポートするという意識を持つのもポイントです。
たとえば、研修に直接関わらない講師以外の社員でも、講師の本来の業務をフォローしたり、研修の際に役立つ情報を提供したりといったサポートができます。
研修内容は随時ブラッシュアップしていく
どんなに優れた研修内容でも、1年後、5年後でも有効であるとは限りません。
時代に合わせて必要とされる知識やスキルも変わり、研修を受ける側の世代としての特性の変化も起こります。
研修を実施する際には、研修内容を随時ブラッシュアップしていくことを意識しましょう。
たとえば、研修実施後にアンケートやヒアリングを実施すると、研修の課題や改善点が見えてきます。
こうした内容をもとに再度研修プランを見直して、次回以降の研修へ活かすようにしましょう。
▼研修後のアンケートのコツについてまとめた資料をダウンロードいただけます。
講師の評価制度を設ける
社内講師に研修を依頼する場合は、研修の設計と同時に講師を評価する制度を設けるようにするのもポイントです。
仮に評価制度がなかった場合、講師にとって研修は単なるボランティア業務だと捉えられてしまいかねません。
研修の質をブラッシュアップするモチベーション作りとしても、講師の評価制度は重要です。
また、講師の評価制度があることで、講師は自分自身の教育者としての伸びを的確に把握できるようになります。
外部委託と組み合わせることも大切
ここまで紹介したように、研修には内製化に適したテーマと外注に適したテーマの2種類が存在します。
「自社ではすべて研修を内製化する」「自社ではすべて外注する」といったような極端な方針を掲げるのではなく、外部委託と組み合わせながら実施するのが大切です。
たとえば、独自性の高いテーマは内製化し、最新トレンドや専門知識は外注による研修で身につけるといったパターンが考えられます。
内製化と外注を譲受に活用し、双方のメリットを活かすようにしましょう。
外部委託するべきケースや内製化した方が良いケースの見分け方や委託先の選定ポイントについては以下の記事で詳しく解説しています。
『研修は外部委託すべき?委託している割合や委託先選定のポイント』
研修のことならアルーにお任せください
研修についてお悩みであれば、ぜひアルーへお任せください。
アルーは、人材育成を専門に手掛けてきた企業であり、新入社員研修や管理職向け研修といった階層別研修のほか、eラーニングやリモート研修などの幅広い研修事例が数多くあります。
ここでは、アルーに関する特徴をご紹介します。
自社に合わせてカリキュラムをカスタマイズ可能です
「研修を外部委託したいが、ぴったりなカリキュラムを提供している企業が見つからない」と悩むことは多いのではないでしょうか。
また、既に自社独自で教材を用意しており、それを活用した研修を実施したいと考えている場合もあるかもしれません。
アルーでは、お客様の企業に合わせて柔軟にカスタマイズできる研修をご提供しています。
ヒアリングから丁寧に実施するため、テンプレートに当てはめるだけではく、お客様にぴったりな研修プログラムを用意することが可能です。
研修体系作成の支援もいたします
研修体系の作成でお悩みのケースも少なくないでしょう。
研修体系の作成を行う際には、経営課題の把握や現場の課題の把握など、やるべきことがたくさんあるため、何から手をつければ良いのか分からなくなりがちです。
アルーでは、研修体系作成の支援も行っており、豊富な育成ノウハウに基づいて、自社の課題解決に最適な研修体系をご提案することが可能です。
丁寧なヒアリングに基づいた効果的な研修体系をぜひご検討ください。
グローバル人材育成体系の構築をアルーが支援した事例は、以下のページでご確認いただけます。
「点」から「線」の育成へ。経営戦略に基づいたグローバル人材育成体系構築のポイント(株式会社ヤクルト本社導入事例)