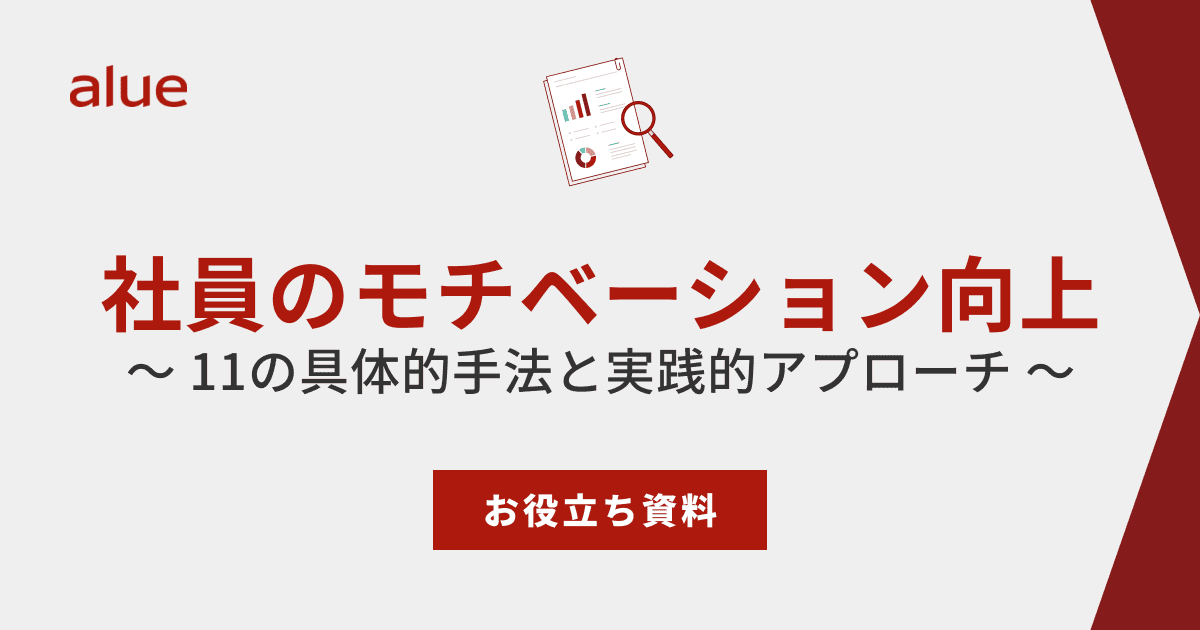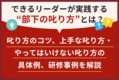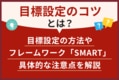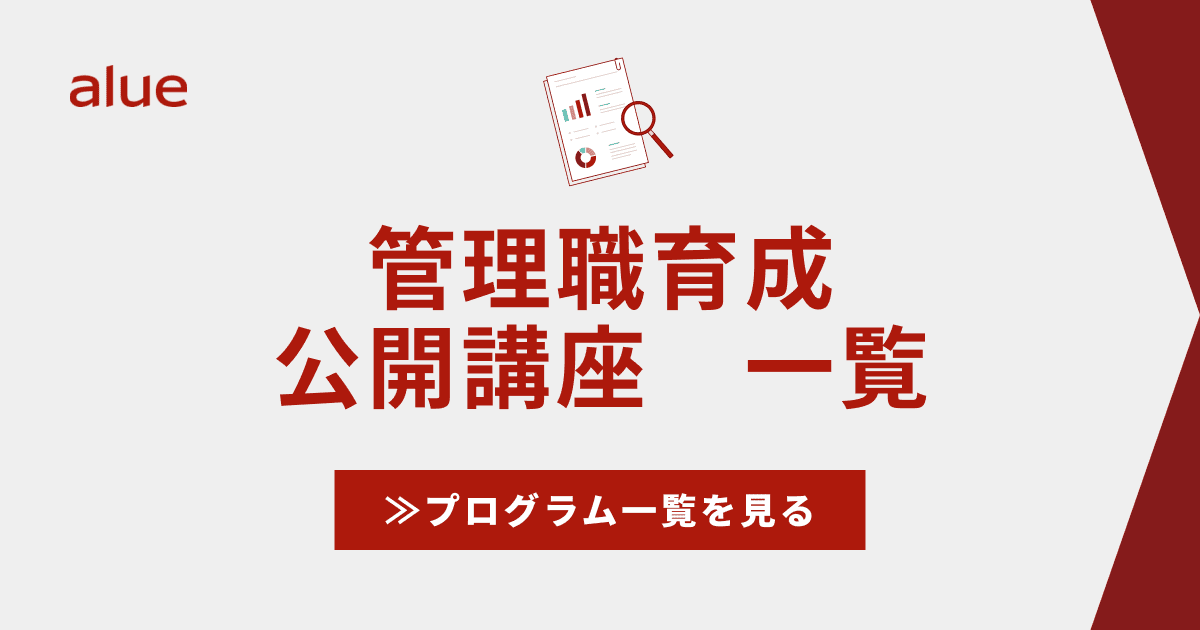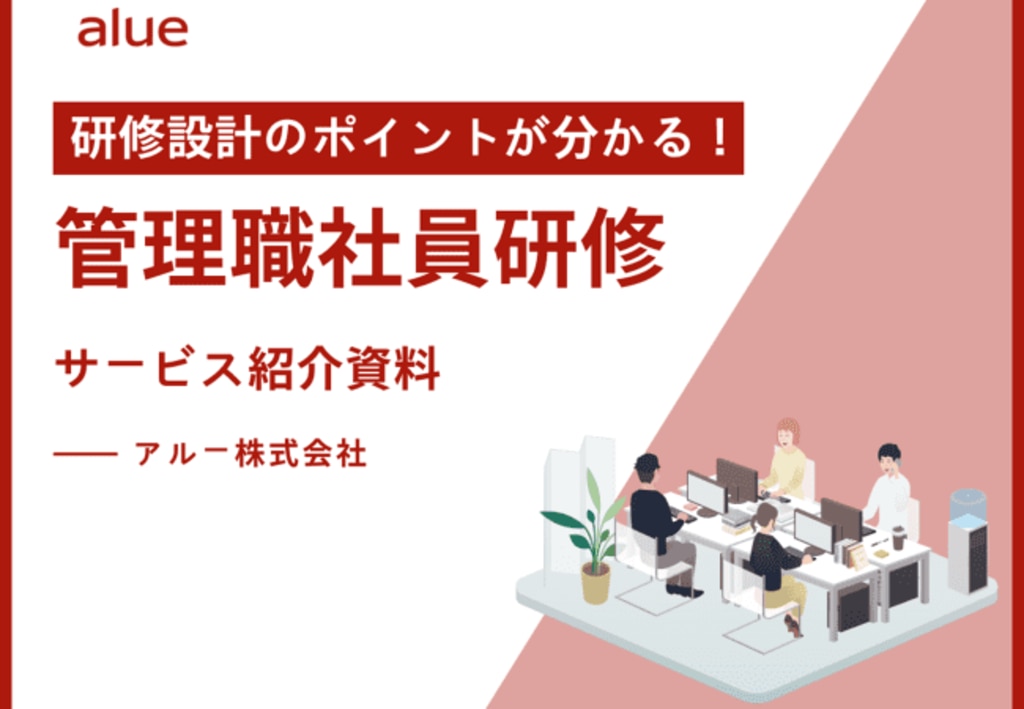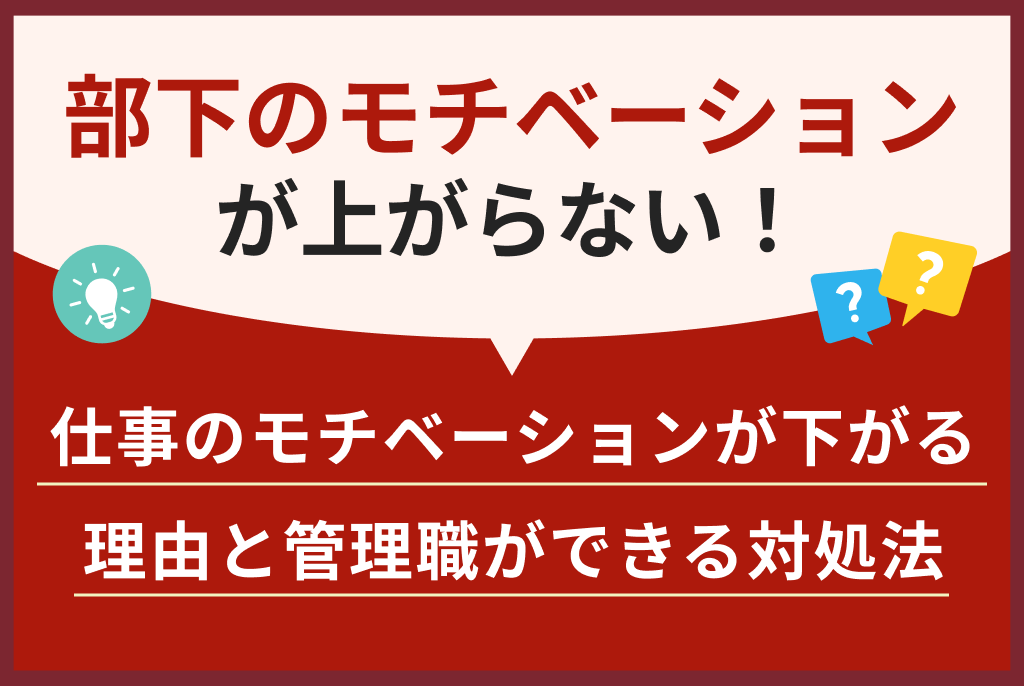
部下のモチベーションが上がらない!仕事のモチベーションが下がる理由と管理職ができる対処法
仕事は楽なものではありません。
ときには心の底から落ち込むような大変な事があったり、会社をやめたくなるような人間関係のトラブルなども起こります。どんな人でも多かれ少なかれ悩みや問題を抱えており、それをなるべく表面には出さないようにして、日々の仕事に取り組んでいます。
しかしそんななか、誰から見ても集中力が減退し、仕事へのやる気のなさが伝わってくる人がいます。また、周囲に不満や愚痴をこぼす人などもいて、自分だけでなく周りの人の集中力を奪う人もいます。仕事に対するモチベーション低下の原因は、その人やその時々でいろいろ考えられますが、原因が何であれ、仕事に集中できない状態を長い間放置してしまうと、当事者の生産性が落ちるだけでなく、チーム全体の生産性を下げ、チームの雰囲気にも影響します。
本記事のテーマは、「モチベーション低めの社員への対処法」です。
仕事へのモチベーションを落としてしまった彼らに対し、上司やチームリーダーは、どのようなコミュニケーションや指導が必要かを解説します。
▼管理職育成におすすめの研修3選

目次[非表示]
仕事におけるモチベーションとは
「モチベーション(motivation)」とは「やる気」や「動機」という意味の言葉です。もう少し詳しく説明すると、「人が目標を達成するために持つ意欲」のことを指します。つまりモチベーションが高い人とは、何かを成し遂げたいという願望や、その願望を実現するために自発的に努力する気持ちを強く、実際に行動を起こせる人、といえます。
仕事においてモチベーションは、業務の質や効率と密接に関係しています。モチベーションは、個々人がそれぞれ解決すべき課題のように思えるかもしれませんが、実はそうではありません。管理職やチームリーダーの関わり方によって部下のモチベーションは大きく左右されます。そして、部下のモチベーションは本人や組織のパフォーマンスアップに直結する重要な課題です。
モチベーションが上がらない社員の傾向

モチベーションが低下し、それが自身の言動や態度に表れてしまう人には、以下のような傾向があります。
何かあるごとに不満を口にする
仕事内容の不満、上司や会社への不満、顧客への不満など、不満を持つ対象はそれぞれ異なりますが、その不満の対象と接点があるたびに、何らかの不満を口にする人がいます。不満を持つこと自体が悪いわけではありません。問題となるのは不満と感じてからのその後の行動です。仕事への不満が生じても、モチベーションを維持できる人と、モチベーションを低下させてしまう人には、この不満を持った後の言動が異なります。
モチベーションを維持できる人は、上司に問題を伝えたり、その問題への然るべき対応を考え、現状をなんとか変えようとします。しかし、モチベーションを低下させてしまう人は、話しやすい相手に愚痴をこぼすだけに終わったり、その不満を仕事が進まない言い訳にだけ使います。また不満の中には客観的に見ても、仕事や相手側に問題があり、正当な主張として声に出すべきものもあります。しかし、これも正しく主張できる人もいれば、不満として愚痴をこぼすだけの人もいます。
自分の意見を述べない
一見するとただ自分からは意見を言うことが苦手な人、周りへ説明することが苦手な人という印象を受けることもあります。しかし実際は、周りへの不満や自分自身の内面にあるモヤモヤが原因で、仕事そのものへのやる気を減退させてしまい、自分から意見を述べることをやめてしまっている人です。
この状態にある人は、たとえば仕事で自分しか気づいていない事があっても、誰かが気づき自分の代わりに意見してくれるまで待ちます。また、自分が得意な作業や、自分自身が希望している仕事があっても、それを口に出して、自ら担当を買って出るようなこともありません。下手に自分から手を挙げてしまった結果、責任を負ったり、失敗のリスクを持つことを嫌がるためです。
リアクションも遅く、常に受け身で仕事をしている
ほとんどの人は、仕事に対していろいろと不満を感じながらも、自分自身の責任として、仕事はやらなければならないものと捉えています。しかし、その不満の大きさと責任感のバランスが保てなくなると、それはリアクションの遅さや、作業の積極性に表れてきます。たとえば、何か仕事の状況に変化があった際、モチベーションが高い人であれば、その状況変化が自分や仕事にどう影響するかを、反射的に考え、即座に行動に移します。
一方、モチベーションが低い人は状況変化への反応も遅く、まずは周りがどう動き出すかどうか様子を見ます。もしくは誰かが自分に指示を出してくるまで、自分からは動かないようにしています。
モチベーションを下げる2種類の原因
人には感情があり、とても嫌な出来事があれば、どんな人でも仕事や私生活の態度にそれが影響してしまうことがあります。またその嫌な出来事が瞬間的なものではなく、ある程度の期間続くものであれば、最初は些細なものであっても、いつしか自分では消化しきれないほどの、大きな不満や不安になってしまうこともあります。
それらモチベーション低下の要因となる不満や不安は、内的要因からできるものと外的要因からできるものの2つがあります。
内的要因によってモチベーションを下げてしまうケース
自分自身の能力不足や、性格の弱さなどから、自分の中にモヤモヤを感じ、それが要因となって仕事へのモチベーションを下げてしまうケースです。問題の原因は自分自身にありますが、それを変えていこうとするモチベーションも減退しているため、いつまで経っても状況は変わらず、モヤモヤとした気持ちを自分の中に持ち続けます。
<モチベーションを下げる内的要因>
- 自分の能力に自信がない、常に知識や経験不足を感じている
- 自分の性格上、今の仕事は自分に向いていないと考えている
- 成長している実感が持てずに将来に不安を感じている
このモヤモヤ状態に慣れてしまうと、それが自分にとって普通の状態だと思い込んでしまい、仕事全般で消極的な振る舞いが染み付いてしまいます。
外的要因によってモチベーションを下げてしまうケース
周りからの評価や、自身が理想とする環境と現実とのギャップなど、自身の外側からの影響でモチベーションを下げてしまうケースです。自分ひとりでは解決できない問題も多く、問題の中には「今は気にしてもしょうがない」と考えた方が良いものもあります。しかし、本人の中ではどうしてもそれが割り切れず、目の前の仕事に集中できなくなってしまいます。
<モチベーションを下げる外的要因>
- 自分の頑張りが評価されていない、給料や待遇が悪い
- 他の社員との評価や扱いの違いから不公平さを感じる
- 組織全体の問題がいつまで経っても改善されない
環境が変わることで、これら要因が解消されることもあります。しかし、これら要因を理由に仕事のモチベーションを下げてしまう人は、往々にして外的要因に振り回されやすいため、また別のところで不満を感じる傾向があります。
部下のモチベーションを上げるために管理職ができる3つの対処法
モチベーションが下がった部下を放置してしまうと、当事者はもちろん、組織全体にとっても良くない影響が出てしまいます。そこで管理職は、モチベーションが下がった部下にうまく対処しなくてはなりません。ここからは、部下のモチベーションを上げるために管理職ができる対処法を3つ、具体的にご紹介します。
対処法(1) モチベーションが低い社員の話を聴く
不満や不安の出かたがどうであれ、またその原因が何であれ、まずは彼らの話を聴くところから始めます。仕事へのモチベーションをすでに下げている社員には、上司やリーダーと話をすることすら嫌がる人もいますが、まずは彼らの内に閉じ込めている言葉や感情を少しでも出してもらう必要があります。
そして、彼らの話を聴くときに必要となるのが「傾聴」の姿勢です。
相手の言葉を否定しない、先入観を捨てて話を聴く、出来るだけ相手の目線で考える、沈黙が続いても良く、無理に話を聞き出そうとしないなど、あくまで相手が主役であり、相手のペースに委ねながら話を聴くことが必要です。また、話をする機会は、改まったものである必要もありません。その人が話したいことがありそうなら、1on1でじっくりと話せる時間を作り、そうでなければ、ちょっとした立ち話でも良いです。
上司やリーダーに面と向かって話すのが苦手そうな人であれば、話し相手は上司でなくても良しとし、チームビルディング研修などで、チームメンバーや同僚と話をする機会を設けることもできます。
▼傾聴についてはこちらの記事で詳しく知っていただけます。
傾聴力とは?高い人の特徴や高める方法、コミュニケーションで活かすコツを解説
対処法(2) モチベーションをコントールする必要性を理解させる
仕事へのモチベーションを低下させてしまう人は、自身のモチベーションをコントロールすることが上手ではない傾向があります。このモチベーションのコントロールが上手な人は、嫌なことがあれば、適度なところで気分転換をしたり、しっかり休みをとるなどして、モチベーションを回復させます。また、自分にとって何がモチベーションを下げて、何がモチベーションを上げてくれるのかをわかっており、状況に応じて上手にコントロールします。
その一方で、このコントロールが下手な人は、後で考えれば些細な出来事として思えるものでも、それが起きた瞬間は動揺したり落ち込んでしまいます。また、その嫌な出来事が解決した後でも、嫌な思い出としていつまでも記憶に残ってしまい、思い出すたびに自らモチベーションを下げてしまいます。
直属の上司やリーダーから「あなたは自分のモチベーションをコントロールする必要がある」と言われても、お説教をされたと思って極端に恐縮するか、「そんなこと言われなくてもわかっている」と反発されるかのどちらかです。
モチベーションのコントロールについては、セルフモチベーションやアンガーマネージメントなどの研修を受けることで、自分自身でその必要性を理解させるようにしましょう。
▼アンガーマネジメントについてはこちらの記事で詳しく知っていただけます。
アンガーマネジメントとは?やり方や6秒ルールと診断について解説
対処法(3) モチベーションが低い社員の環境を変える
1on1でじっくり話を聴き、また彼らがモチベーションコントロールの必要性を理解したとしても、彼らの今の能力や置かれている状況から、問題がすぐには解決できない場合もあります。たとえば、すでに自身の体調を崩してしまっていたり、一緒に仕事をしている顧客側に問題がある場合などです。このようなケースでは、ときにはその人の担当業務を変えたり、所属を変更するなどの仕事環境から変える対応が必要です。
また、そこまで深刻な問題とまではなっていなくても、モチベーションを低下させている人にとって、ここなら力を発揮できそうという仕事内容や配属先があれば、彼らに環境を変える希望があるか聞いてみるのも良いです。これまでずっとくすぶっていた社員が、ちょっとした環境の変化でやる気を取り戻してくれることは、決して珍しいことではありません。
組織体制を変えるタイミングではなくても、半年に一度くらいの間隔で、彼らから配属先の希望ややりたい仕事をヒアリングすることで、今、彼らが何を望んでいて、どんなところに不満を感じているのか察知できます。
“部下のモチベーションを上げられない”管理職におすすめの人材育成
部下のモチベーションを上げようとコミュニケーションを取ってもなかなかうまくいかず、悩んでいる管理職の方は多くいらっしゃいます。そして、多くの管理職がプレイングマネジャーとして日常の業務に追われ、自分のスキルアップに時間を取る余裕がありません。
企業の人事、育成担当者はそんな管理職の現状に寄り添い、日常から離れてスキルアップに集中できる、人材育成研修を企画してはいかがでしょうか。
“部下のモチベーションを上げられない”管理職を助けるための人材育成研修には、
- 管理職のスキルアップ
- 部下のモチベーションコントロール
の2種類があります。
前述のとおり部下が直属の上司から何か言われたとしても、素直に受け入れてくれるとは限りません。部下が研修の場で学ぶことが上司の助けとなることも多々あります。
管理職のスキルアップ
管理職は、まずは部下の話を聴けるようにならなくてはいけません。そのためには、傾聴のスキルや1on1のスキルを上げることが有効です。また、すべて自分で聴く必要はありません。チームメンバーや先輩社員が部下の話を聴きやすい環境をつくるために、チームビルディング能力を上げることも有効です。
関連するコラムをぜひご参照ください。
【部下のモチベーションコントロール】
仕事はモチベーションを上げることばかりではありません。むしろ、モチベーションを下げてしまうことのほうが多いです。そんなときに、自分で自分のモチベーションをコントロールする術を身につけてもらうことは、その社員にとっても、上司である管理職にとっても大きな助けとなります。
関連するコラムをぜひご参照ください。
部下のモチベーションを上げられる管理職を育成するならアルーにお任せください。
部下のモチベーションを上げられる管理職を育成する研修は、ぜひアルーへお任せください。人材育成を手掛けているアルーでは、部下のモチベーションを上げるスキルを伸ばすための研修プログラムを数多くご用意しています。
また、どんなに優れたスキルを持っていても、「部下に言うべきことを遠慮してしまう」といった誤ったマインドセットがあると、適切な部下育成ができません。アルーの提供するプログラムは、演習中心でスキルとマインドセットの両面にアプローチできることが特長です。部下のモチベーションを上げる方法やノウハウはもちろん、部下と接する際の心構えや考え方など、マインド面での成長を徹底的に引き出します。
アルーの提供するコーチング力研修は、以下のページからご覧ください。
部下のやる気を引き出すコーチング100本ノック研修
アルーの部下コミュニケーション研修事例
アルーでは、これまでにさまざまな企業で部下とのコミュニケーションスキルを磨く研修を実施してまいりました。ここからは、それらの中から特に参考となる事例を3つピックアップして紹介します。
部下コミュニケーション研修の具体的な流れやプログラムについて知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
帝人株式会社 リーダーシップ研修事例
帝人株式会社様では、人事制度の見直しにより設けられた「AS職」という新たな管理職の職掌で、期待役割に見合ったスキルや意識を開発・醸成する必要がありました。そこで、リーダーシップと指導育成力を身につけるための新任AS職研修を実施しています。
本研修プログラムでは、部下との信頼関係を構築する方法や、部下指導に役立つフレームワークなどを体系的に学んでもらいました。研修のまとめとしてアクションプランを設定し、短い研修期間ながらも現場での実践を意識させたことがポイントです。
研修後には、これまで暗黙知とされていた指導スキルが共通言語化され、研修ゴールとして設定していた期待行動・意識の発現率も68%から95%へ向上しました。
本事例の詳細は、以下のページからご覧いただけます。
【帝人株式会社研修導入事例】現場管理者としての リーダーシップを強化する 「新任AS職研修」
▼事例資料をメールで受け取る
Wismettacグループ マネージャー研修事例
Wismettacグループ様では、上場後の新たなビジネス展開を加速する中で、自己流のマネジメントを共通言語に基づく最新のマネジメント手法へアップデートしたいという課題がありました。そこで、部下の成長支援を実現するための仕事アサインを行う方法を学ぶ研修を実施しています。
本研修では、部下の成長につながる業務アサイン方法を学んでもらうだけでなく、業務アサインの際の伝え方や、アサイン後のフォロー方法まで細かく学んでもらったことがポイントです。研修後には「部下の成長支援」という視点を持った業務アサインができるようになり、現場からも「まさに困っていた内容だったのでとても参考になった」といった声が上がりました。
本事例の詳細は、以下のページからご確認ください。
【Wismettacグループ研修導入事例】多様な「個」の特性や能力を活かし、部下の成長を支援するマネージャー育成
▼事例資料をメールで受け取る
コスモ石油株式会社 新任ライン長研修事例
コスモ石油株式会社様では、組織変更に伴って、会社の将来的なキーパーソンであるライン長に役割認識を深めてもらいたいという課題がありました。そこで、新任ライン長約30名を対象とした研修を実施して、部下指導のノウハウを学んでもらっています。
本事例では、「他責から自責」をスローガンに掲げ、部下指導の際のマインドセットにも重点的にアプローチしたことがポイントです。
研修後には、ライン長の間に「伝わったことがすべて」という意識が浸透し、現場での研修に役立っています。
本事例についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
【コスモ石油株式会社研修導入事例】信じて任せる。 人をマネジメントする 新任ライン長研修の意義とは。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
本記事では、「モチベーション低めの社員への対処法」をテーマに、仕事へのモチベーションを落としてしまった部下に対し、上司やチームリーダーが、どのようなコミュニケーションや指導が必要かを解説しました。
モチベーションを落としてしまった部下を放置してしまうと、部下本人の成長はもちろん、組織の成長も阻害してしまいます。
ぜひ管理職を対象とした研修を実施して、部下のモチベーションを上げるために必要なスキルや心構えを習得してもらいましょう。アルーのコーチング力研修は、以下のページからご覧いただけます。
部下のやる気を引き出すコーチング100本ノック研修
この記事の内容を参考に、部下のモチベーションを上げられる管理職育成を実現していきましょう。