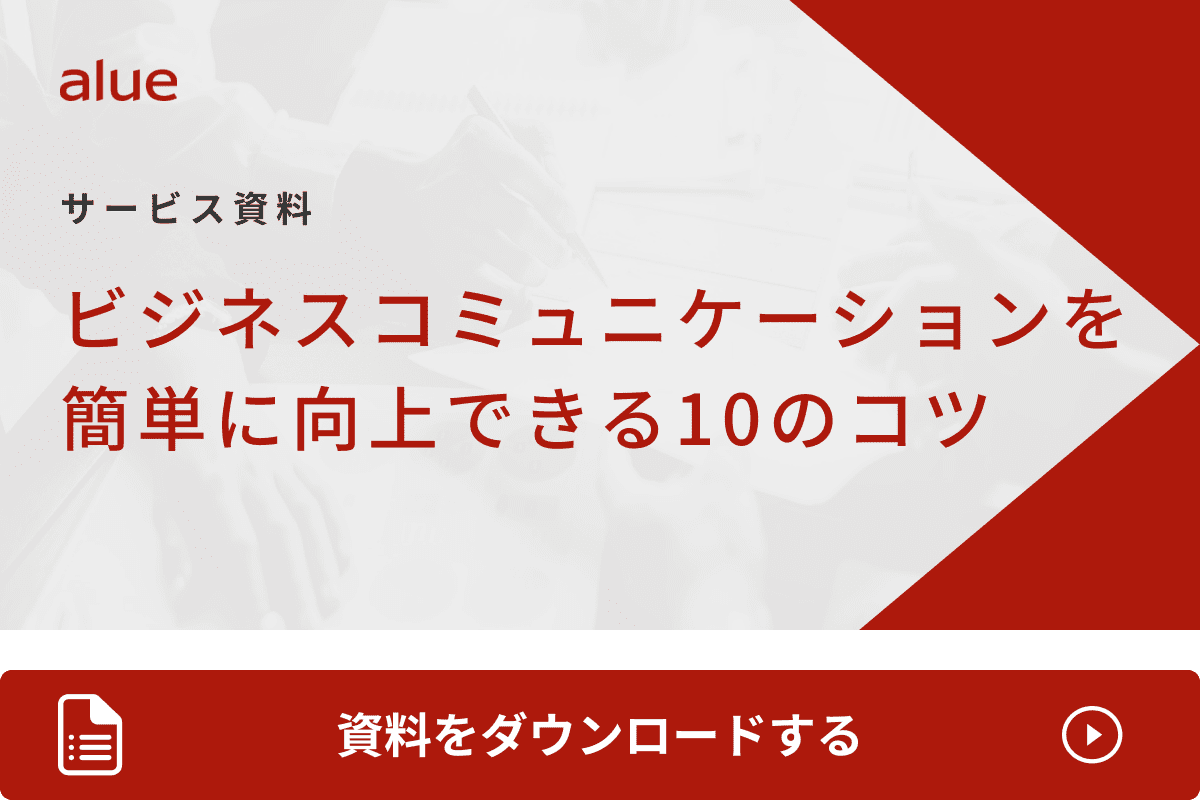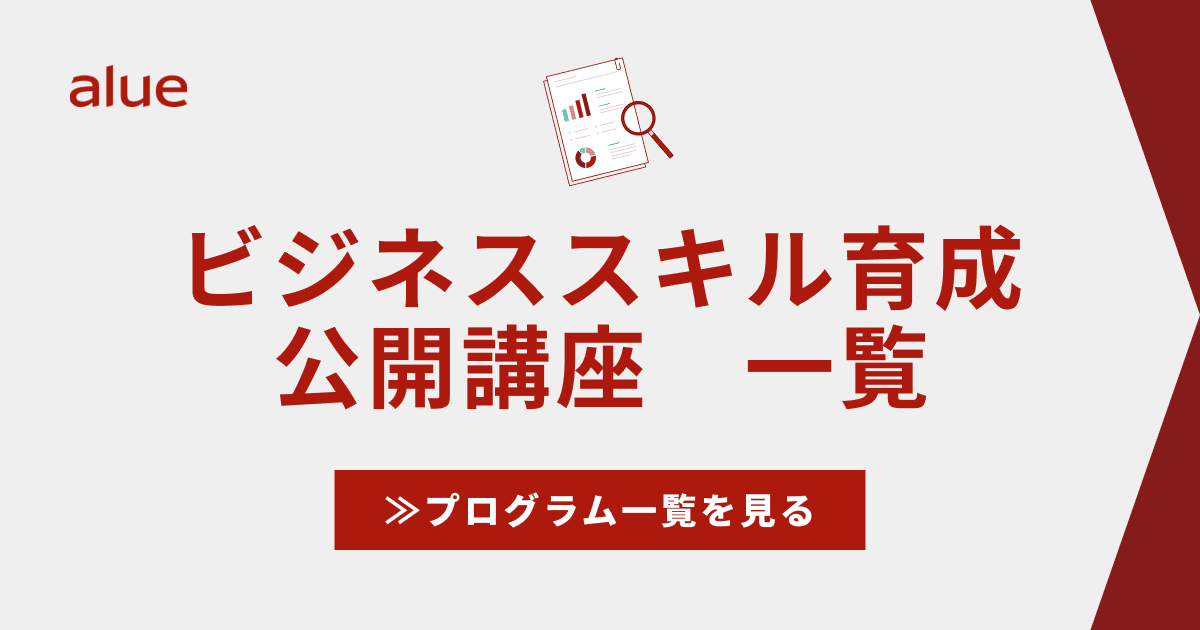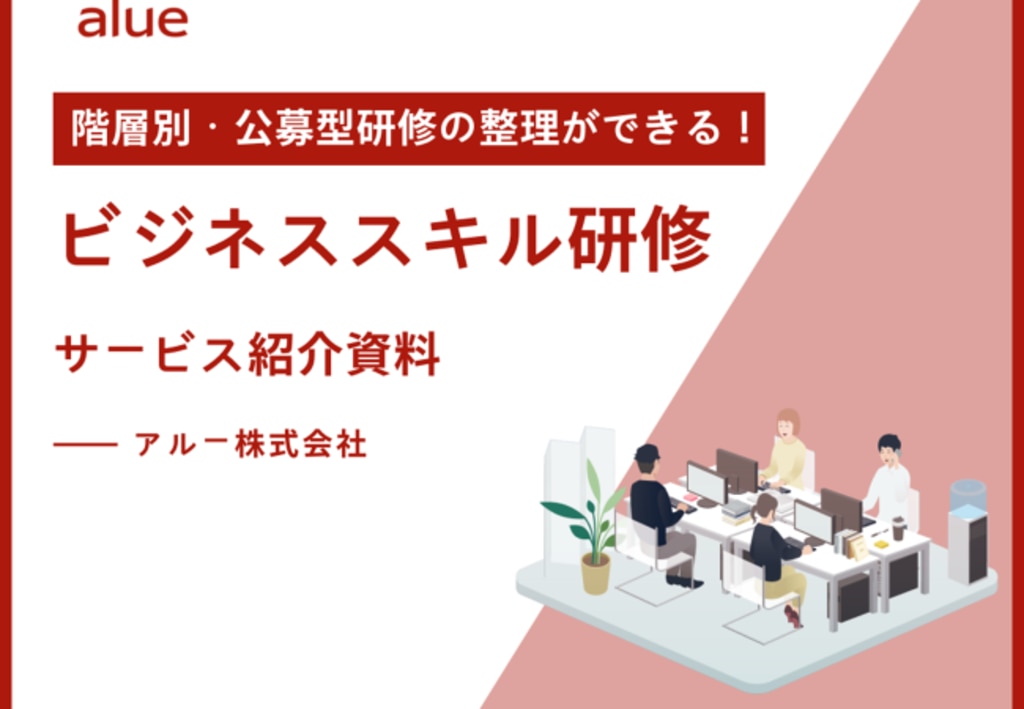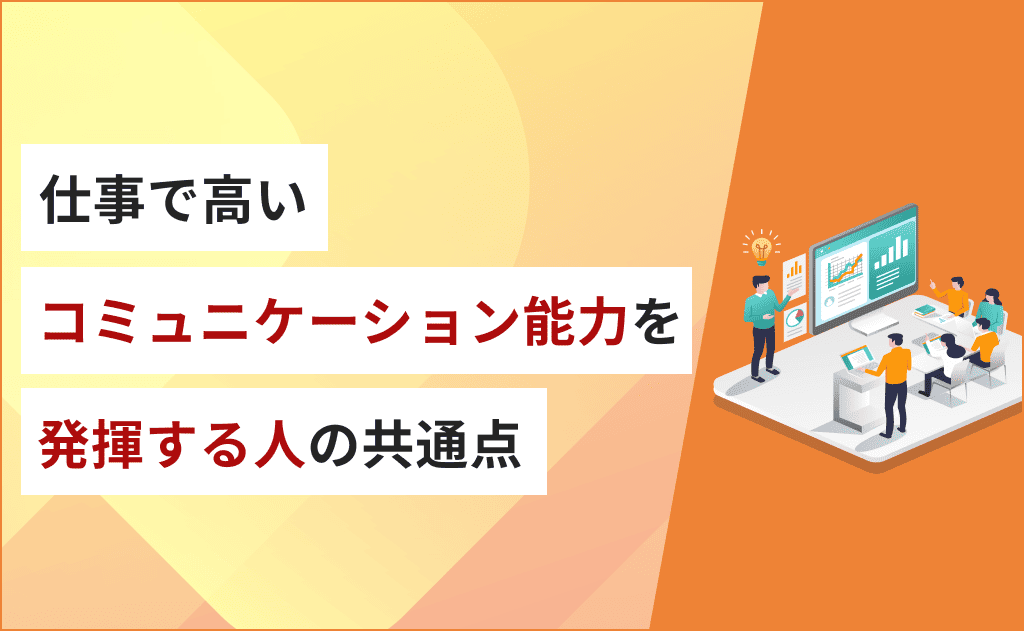
仕事で高いコミュニケーション能力を発揮する人の共通点
メールなどの非対面型のツールが広く普及している現代では、対面での直接的なコミュニケーションを苦手と感じている人が多いです。コミュニケーションの方法が多様に変化していく今だからこそ、基本となるコミュニケーションの「質」の向上が求められています。
コミュニケーション能力が高い人は、どんな環境でも適応できるので組織人としても働きやすくなりますし、会社側から見ても幅広く活躍できる人材として期待できますよね。
そこで、この記事では、コミュニケーション能力が高い人はどのような特徴があるのか、どんな話術を使っているのかを、具体例を交えながらお伝えしていきます。
より深く知るための『オススメ』お役立ち資料
目次[非表示]
そもそもコミュニケーション能力って何?
そもそも、コミュニケーション能力とはどういったスキルを指すのでしょうか。「人と話すのがうまい」など、曖昧なイメージを持っている人は多いと思いますが、具体的に把握している人は少ないですよね。
コミュニケーションとは、「感情も含めた相互理解」のことです。例えば、2人で会話をしているシーンであれば、言葉や非言語(表情や仕草、声のトーンなど)の情報を相互に交換しています。しかし、その水面下では言葉の意図や感情が隠されているのです。
この水面下の言葉の意図や感情も含めて情報共有する能力というのが、コミュニケーション能力になります。
▼仕事におけるコミュニケーション能力については、以下の記事でより詳しく解説しています。
『仕事に活きるコミュニケーション能力とは?鍛える方法や高い人の共通点』
コミュニケーション能力が高い人の特徴

コミュニケーション能力が高い人は「話の中で相手の感情や意図を読み取り、互いに情報共有できたと認識した上で、自分の意見を相手が分かるように適切に伝えることができる人」のことです。
単に「聞き上手」「話し上手」なだけではなく、お互いにとって有益になるように働きかけることが大切と言えます。コミュニケーション能力が高い人は、自然に下記の2つのコミュニケーションの力を発揮しています。
- アサーティブコミュニケーション
- ロジカルコミュニケーション
それぞれどのようなコミュニケーションなのか、詳しく解説していきます。
アサーティブコミュニケーションが得意
アサーティブコミュニケーションは、「相手の考えを尊重しながら、自分の感情や思いを抑圧せず自己主張をする」コミュニケーション方法です。
アサーティブコミュニケーションの手法としては、下記の5つが挙げられます。
- DESC(デスク)法に則った話し方ができる
- 肯定的な言葉を使用する
- 自分の気持ちを「I(アイ)メッセージ」で伝える
- 数字を用いて具体的に伝える
- 自分の強い要望を最初に伝える
それぞれの手法について見ていきましょう。
DESC法に則った話し方ができる
DESC法とは、下記の4つの言葉の頭文字から構成されています。
- Describe(客観的な状況を描写する)
- Explain(主観的な気持ちを表現する)
- Specify(提案を行う)
- Choose(代替案を提示する)
これらの4つのステップに沿って会話を進めることで、意思の伝達がスムーズになります。DESC法を製造業で使用した場合の例を見てみましょう。
機械のトラブルで、工場の製造ラインが止まってしまった(客観的な状況) 本当であれば○日に納品したいが、現状難しい(相手の気持ちを尊重しつつ、主観的な気持ちを表現する) □日に変更して頂くことは可能か(提案) もしくは△日はどうか(代替案を提示) |
上記のような順番で話せば、相手に流されることなく自分の意見を主張できます。ここで重要なのは「代替案はできるだけ多く集めておく」という点です。手持ちの代替案があればあるほど、自分の意見を採用してもらいやすくなります。
肯定的な言葉を使用する
伝えたいことはほとんど同じでも、選ぶ言葉によって相手に与える印象は変わります。ネガティブな表現をポジティブな表現に置き換えると、相手は言われたことを受け入れやすくなりますし、悪い印象を与える心配もなく、人間関係が和やかになります。
例えば、「ここの企画のここがダメ」と否定すると、相手は「(自分を)否定された」と感じてしまいます。しかし、「ここにもうひと工夫あると、もっと良くなるよね」などと肯定的に表現すれば、相手は「応援された」と前向きに受け取ってくれるのです。
肯定的な言葉を使えるようになるためには、日頃から良く使う言葉を「ネガティブワード」から「ポジティブワード」に置き換えるクセをつけましょう。
「今は忙しいのでできません」を「もう少ししたら時間が取れます」、「何でもいいです」を「どれも好きです」のように表現を変える練習をすると、すぐにポジティブワードが出てくるようになります。
自分の気持ちを「I(アイ)メッセージ」で伝える
Iメッセージとは「(私は)そう言われると悲しい」というように、「私」を主語にして主張する方法です。反対に、Youメッセージは「(あなたは)もっとできる」のように、「あなたは」を主語にして主張する方法になります。
例えば、相手が「納期を前倒ししてほしい」と依頼してきたとしましょう。この時に「直前に依頼されると困ります。(あなたは)今度は早めに依頼してください。」といった返答をすると、相手に「あなたが早めに依頼しなかったから私が困った」と捉えられて、今後何か頼む時に萎縮されてしまう可能性があるのです。
角が立たない言い回しに変えるのであれば、「直前に依頼されると(私は)時間調整が難しくなり、場合によってできない可能性があります。(もし今後同じような状況になった時は)早めに依頼していただけると(私は)助かります。」のような言い方をすると良いです。このように、「私」を主語にして主張すると、角を立てずに伝えられるでしょう。
数字を用いて具体的に伝える
ビジネスにおけるコミュニケーションでは、曖昧な言葉を避けて具体的に伝えることが求められています。具体的に話すためには、「数字を用いる」のが一つの方法です。
数字は、誰にとっても同じ尺度となります。そのため、数字を用いれば相手と自分の認識のズレがなくなり、相手に正確に伝わるのです。
数字に置き換えたほうが良い例としては、日付や数量、売上などが該当します。
「早めに仕上げてください」を「◯月△日までに仕上げてください」
「多めに印刷してください」を「300枚印刷してください」
「見積もりは高額でした」を「見積もりは100万円でした」
具体的な数字を用いることで、話の具体性が格段に増して、相手が理解しやすくなります。
ロジカルコミュニケーションが得意
コミュニケーション能力が高い人のもう一つの特徴は、ロジカルコミュニケーションが得意ということです。
ロジカルコミュニケーションとは、「論理的に自分や相手の考えを整理する」手法を指します。この手法を用いると、自分が相手に何を伝えたいかや相手が自分に何を伝えようとしているかが分かるようになり、円滑にコミュニケーションを図れるようになるのです。
ロジカルコミュニケーションの手法は、主に下記の6つです。
- 情報をピラミッド構造に整理し、分かりやすく伝える
- 相手に合わせたストーリーを作って伝える
- 相手の質問に的確に答える
- 相手の頭の中のピラミッド構造を明らかにする
- 相手が気づいていない領域を補う
- 共通の目的を設定し、ピラミッド構造を共創する
それぞれ見ていきましょう。
情報をピラミッド構造に整理し、分かりやすく伝える
情報をピラミッド構造に整理するためには、下記のように分類していきます。
- 「目的」は何か(情報を伝えることで相手に何のメリットがあるか)
- 「結論」は何か
- 「結論」にいたった構成要素は何か(事実を元にどう解釈したか)
- 「構成要素」を支える根拠(事実)は何か
これらの要素をピラミッドのように構造することで、どう話を組み立てれば良いかが見えてきます。多くの情報を4つの構造内に分類するためには、ある程度情報を整理しなければいけません。似たような情報をグループごとに分類する、目的に即した言葉を抽出する、抽出した言葉を支える根拠を揃えるといった作業をすると、情報を分かりやすく整理できます。
相手に合わせたストーリーを作って伝える
相手に適切に話を伝えるためには、「どの順序で話をすれば伝わりやすいか」「話す深さはどのくらいか(話ができる時間はどの位あるのか)」などをあらかじめ把握した上で、相手の関心度合いに合わせてストーリーを作る必要があります。
ストーリーを作る際にまずチェックしてほしいのは「受け手の関心レベル」です。これは、好意的かどうかだけではなく、「反発や批判も含めて、自分に何かしらの関心を持っているかどうか」を表します。
無関心な人に対していくら分かりやすく伝えたとしても、何も届きません。関心レベルが低い相手に伝える時は、まず関心を引き上げる努力が必要です。
次に確認すべきなのが「知識のレベル」です。受け手が自分と同程度の知識量を持っているか、まったく知らないのかでは、伝えるのに必要な情報量は異なります。相手がその分野に関する知識に乏しいのであれば、まず基本的な情報を伝えることから始めましょう。
受け手の知識レベルや関心レベルを踏まえ、どの部分を掘り下げて話すか、どの部分は省略しても良いかを検討し、ストーリーラインを用意して話すと良いでしょう。
相手の質問に的確に答える
「相手が何を知りたいか」を把握するためには、相手の質問に的確に答えることが重要です。的確に答えるためには、相手からの質問を「クローズドクエスチョン」と「オープンクエスチョン」に分類すると良いでしょう。
クローズドクエスチョンとは、「はい」と「いいえ」の2択の質問や、あらかじめ回答の選択肢が決められた質問のことです。「納品するのはAですか」「御社が使っているシステムはA,B,Cのどれですか」などの質問が当てはまります。
これに対してオープンクエスチョンは、相手の返答に制限を設けず、自由な選択肢がある質問のことです。例えば、「この映画を見て、なにを感じましたか?」「この評価をしてくださった理由はなんですか?」などがオープンクエスチョンです。
オープンクエスチョンは「相手の気持ちや考えを具体的に知りたい」という時に用いられるため、相手が「5W2H」のどれを聞いているのかについて考えましょう。5W2Hとは、下記の単語を指した言葉です。
- Why(なぜ)
- What(何が)
- When(いつ)
- Where(どこで)
- Who(誰が)
- How(どのように)
- How Much(どのくらい)
相手が何を知りたいかを把握してから答えることで、コミュニケーションがスムーズになります。
先ほど例に出した質問でいうと、「この映画を見て、なにを感じましたか?」はWhat(何が)に対する返答をする、「この評価をしてくださった理由はなんですか?」ならWhy(なぜ)に対する返答をするなどのように、的確に答えていくことでコミュニケーションがスムーズになります。
相手の頭の中のピラミッド構造を明らかにする
論理的に相手の話を整理するためには、相手の頭の中のピラミッド構造を把握することを意識すると良いでしょう。的確に把握するには、ピラミッド構造のパーツを引き出す質問スキルと、相手の話を要約して理解度を確認する要約スキルが必要です。
特に質問スキルに関しては、相手のニーズを確認するという側面もあります。相手の思考を把握するためには、下記の4つの質問が有効です。
- 状況を聴く(相手に関する基本的な事実。何に関心があるのかなど)
- 問題を聴く(前もって得ている情報があれば、ありそうな不満や課題を予想しながら質問する)
- 仮説を聴く(相手が潜在的に感じているニーズを、言葉にして顕在化させる)
- 解決策を聴く(問題は解決できるか、解決することでどんなメリットがあるか)
相手自身がニーズを把握していない場合もあります。その時はいきなり問題解決を提示するのではなく、少しずつ相手のことを知って、まずはニーズを把握するようにしましょう。
相手が気づいていない領域を補う
上記で解説したように、相手の頭の中のピラミッド構造が完璧とは限りません。どのようにピラミッドを作れば良いか分からない、情報量が不足しているためにピラミッド構造が不完全になっているという人も少なくないのです。
まず「どのようにピラミッドを作れば良いか分からない」という人には、「目的」を伝えましょう。何のために行動するのか、仕事の全体像の中でどういう意味を持つのかなどを伝えないと、方向性を誤ってしまいます。
また、ピラミッド構造が不完全な人には「オープンクエスチョン」を使って相手の考えや気持ちを確認しましょう。質問に対して声に出して話すことで、相手も考えを整理できます。
共通の目的を設定し、ピラミッド構造を共創する
上記でも少し触れましたが、相手のピラミッド構造を把握し、相手側の不足している領域を補うことができたら、いよいよピラミッドを共創する段階に入ります。
共創を行う場合は、下記の3つのステップで行っていきましょう。
- 自分と相手のピラミッド構造を改めて比較し、共通点や相違点を明らかにする
- 「自分と相手が考える目的」が何なのかを把握して、共通の目的を見出す
- 共通の目的に関連する情報を再度整理し、新たな結論を検討する
この作業を円滑に進めるには、お互いに信頼関係があるか、共通の目的はお互いにとって利益のあるものかなどを確認しておく必要があります。第三者側から見た時に「一方だけの意見なのではないか」と思われてしまう可能性もあるので、第三者に明確に説明できるよう、まずは相手との信頼関係を構築することから始めてみてください。
傾聴力がある
コミュニケーション能力が高い人は、伝える力だけでなく傾聴する力にも優れています。傾聴力とは、相手が話している事実や解釈といった表層的な事柄から、相手の話の背景にある価値観や気持ちといった深層的な事柄まで、相手の話の理屈を深く理解し共感しながら話を聴く力のことです。傾聴力に優れた人は、以下のような特徴をもっています。
- 相手の細かな表情や姿勢を読み取って、心情を推し量れる
- 相手の話を深く聴き、話への共感を表現できる
- 相手が話した内容を的確に把握して、要約できる
- 相手からさらに本音を引き出すため、うまく質問できる
傾聴力について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
『傾聴力とは?高める方法とコミュニケーションで活かすコツを解説』
非言語コミュニケーションが得意
コミュニケーション能力が高い人の特徴の一つとして、非言語コミュニケーションをうまく使っていることも挙げられます。非言語コミュニケーションとは、ジェスチャーや声のトーン、表情など、言葉を用いないコミュニケーションのことを指します。
「メラビアンの法則」によると、人と人がコミュニケーションする際には、言語情報よりも視覚情報や聴覚情報の方が相手に影響を与えやすいことがわかっています。
非言語コミュニケーションが得意だと、相手の気持ちを深く理解し、相手との距離を縮めやすくなります。
非言語コミュニケーションについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。
『非言語コミュニケーションとは?重要性やビジネスでの活用例を解説 』
相手に興味を持っている
コミュニケーション能力が高い人は、常に興味を持って人と接することができます。そして、傾聴の姿勢や非言語コミュニケーションによって相手にそのことが伝わるので、相手もコミュニケーションをとりやすくなります。
普段から相手のことをよく観察する、相手が以前発言した内容を覚えておく、など、日ごろから相手に興味をもつことで、コミュニケーションが円滑に進むようになるでしょう。
監修者からひと言
|
コミュニケーション能力が低い人の特徴

ここまで、コミュニケーション能力が高い人の特徴についてお伝えしてきました。ここからは、反対にコミュニケーション能力が低い人にはどのような特徴があるのかを説明していきます。
コミュニケーション能力が低い人の主な特徴は、下記の2つです。
- アグレッシブなコミュニケーションをしがち
- パッシブなコミュニケーションをしがち
それぞれ詳しく解説していきます。
アグレッシブなコミュニケーションをしがち
アグレッシブ(攻撃的)なコミュニケーションとは「自分の言いたいことを、相手がどのような状況なのか考えずに話す」ことです。
相手が話を聞ける状況なのか、相手が自分の話を理解しているのかなどを考えずに、一方的に言いたいことを言っているので、相手になかなか伝わりません。このような人は、「視野が狭い」という特徴があります。所謂「猪突猛進」なタイプで、思いついたら「すぐに意見を言わなければ」と、突っ走る傾向にあるのです。
パッシブなコミュニケーションをしがち
パッシブ(受動的)なコミュニケーションとは、「相手の感情や態度を優先してしまい、自分の本当の気持ちを言わずに我慢してしまう」状態を表します。特に、新入社員など社歴の浅い人は遠慮してしまいがちです。
このような人は、上司や同僚に意見を言うのが怖いという心情から、自分の意見が言えなくなってしまっています。しかし、そのような状態が続くと、ふとしたキッカケで感情が爆発してしまう可能性もあるので、注意が必要です。
相手の意見を尊重しつつ自分の意見も言う、アサーティブコミュニケーションを、少しずつで良いので取り組めるようにしましょう。会社側も、社員が気兼ねなく意見を言えるような場を設けると良いです。
アルーでは、アサーティブコミュニケーションを身につけていただくための研修をご用意しています。アサーティブコミュニケーションに必要な心構えや伝え方を複数のケーススタディを通じて学ぶことができます。
▼アルーのアサーティブコミュニケーション研修について詳しくはこちらのページをご覧ください。
アサーティブコミュニケーション研修
コミュニケーション能力が高い人の特徴的な話術

コミュニケーション能力が低い人の特徴についてお伝えしてきましたが、コミュニケーションを高めるにはどうすれば良いのでしょうか。
すぐにできる方法は「コミュニケーション能力が高い人の話術を真似する」ことです。コミュニケーション能力が高い人は、自然に下記の話術を活用しています。
- ペーシング
- イエスバッド
- バックトラッキング
それぞれどのような話術なのか、見ていきましょう。
ペーシング
ペーシングとは、声の抑揚や大きさ、会話の「間」の取り方といった非言語的コミュニケーションを用いて、相手との信頼関係を構築する手法のことです。相手に気持ち良く話してもらうには「相手の話に興味がある」ことを伝える必要があります。
そのためには、相手の話に応じた反応をする、相手の顔をしっかり見て感情を込めた相づちを打つ、「感嘆詞(共感の相づち)」に加えて「驚いたり共感したりしたポイント」を具体的に伝える、といった手法が効果的です。
また、コミュニケーション能力が高い人は、会話の中で「沈黙」する場面があります。「黙っていると気まずいのではないか」と思ってしまいがちですが、適度な沈黙を入れることで、「直前に話した言葉の意味を理解する余裕が生まれる」というメリットがあるのです。
この沈黙は一般的に「間」と呼ばれています。特に早口になりやすい時ほど、「間」を取って聞き手の負担を減らすという意識が重要です。
「間」を始めとした非言語コミュニケーションについて詳しくは以下のページをご覧ください。
『非言語コミュニケーションとは?重要性やビジネスでの活用例を解説』
イエスバット
イエスバット法は「相手の意見を肯定した後に否定的な意見を伝える」手法で、アサーティブコミュニケーションと少し似ています。
上司や同僚に否定的な意見を言うのは、なかなか難しいものです。単に「それは違う」と伝えただけでは、相手は「自分が否定された」と感じてしまうでしょう。しかし、一度相手の意見を肯定した上で否定的な意見を伝えると、否定的な感情は弱くなります。
この時に重要なのは「なぜ私(自分)は否定的な意見なのか」を伝えることです。「あなたの意見は良いと思う。でも私は○○だと思うな」のように、Iメッセージで自分の気持ちを伝えることで、相手は意見を受け入れやすくなります。
バックトラッキング
バックトラッキングとは、相手が言ったことをそのまま返す手法です。バックトラッキングを行うことで、相手は「自分が言ったことを理解してくれた」と感じます。さらに、相手が言った言葉を反芻することで、自分の中で深く理解できるというメリットもあるのです。
しかし、バックトラッキングをしているだけだと、相手は「自分の言葉をオウム返ししているだけではないか」と感じてしまうため、多用するのは控えましょう。
社員のコミュニケーション能力を高める方法
社員のコミュニケーション能力を高めるために、人事部から支援を行うことも有効です。たとえば、以下のような施策を取り入れてみましょう。
- 自己理解と他社理解を促す研修を実施する
- コミュニケーション研修を実施する
- ロジカルシンキング研修を実施する
- 1on1ミーティング制度を導入する
それぞれの制度や研修について解説していきます。
コミュニケーションの土台である自己理解と他者理解を促す研修
コミュニケーションの際の基本は、自分と相手、双方に対する理解を深めることです。自分と相手がそれぞれどういった特徴を持っているかをしっかりと理解すれば、お互いに相手の考えや気持ちを深く理解できるようになるでしょう。
コミュニケーション研修を実施する
コミュニケーション研修とは、業務を円滑に進めるためのコミュニケーションスキルを学ぶ研修です。生産性の向上や組織風土の改善につながるなどの理由から、多くの企業が取り入れています。
また、取引先企業との関係性の向上も望めるので、業績アップを図りたい企業にもおすすめです。ヒアリング力やネゴシエーション力を高めれば、顧客との関係性がよくなり、業績向上に寄与するでしょう。
自社の課題に合わせて、以下のような研修を取り入れてみてください。
≫自分と相手の両方を大切にしたコミュニケーションをできるようになってほしい場合
アサーティブコミュニケーション研修
≫Win-Winな関係を構築するためのネゴシエーション力を身につけてほしい場合
ネゴシエーション研修
≫新入社員に報連相を徹底してほしい場合
プロフェッショナルコミュニケーション~ホウ・レン・ソウ7つ道具編~
ロジカルシンキング研修を実施する
ロジカルシンキング研修もコミュニケーション能力を高めるのに有効です。コミュニケーション能力が高い人は、物事を深くスピーディーに考えたうえで相手に分かりやすく伝えることができます。この力を身につけるのにおすすめの研修がロジカルシンキング研修です。
ロジカルシンキング研修では、情報の整理の方法や論理的思考に基づいた情報伝達方法を学びます。情報をピラミッド構造で整理することができるようになるため、分かりやすく整理された状態で相手に伝えることができます。
また、相手の質問に対しても的確に答えることができるため、円滑なコミュニケーションを実現できるでしょう。
「部下からの報告内容が整理されておらず、わかりづらい」「質問をすると、的外れな回答が返ってくることが多い」といった課題を抱えている場合は、ロジカルシンキング研修を実施するのがおすすめです。
アルーでは、演習を多数盛り込んだロジカルシンキング研修を提供しています。詳しくは以下のページをご覧ください。
ロジカルシンキング研修のプログラム詳細
1on1ミーティング制度を導入する
1on1ミーティングの制度を導入すれば、上司のコミュニケーション能力を高めることができるでしょう。
1on1ミーティングとは、上司と部下が定期的に1対1で行う面談を指します。業務指示や人事評価の場とは別で設定されるミーティングです。上司が部下の悩みや目標を聞きとり、問題解決や気づきを与えて成長を支援し、成果を出すことが目的です。部下が話したいことを話し、上司はそれを傾聴することが求められます。
部下をもつ上司には、部下の話を深く理解しながら聴く「傾聴力」が求められます。研修などで傾聴力について学んでもらった後、現場で1on1ミーティングを繰り返してもらうと有効です。
1on1ミーティングは上司のコミュニケーション能力を鍛える場になるだけではなく、上司と部下の間のコミュニケーションが活発化するきっかけともなりえます。
1on1ミーティングのメリットや進め方については以下の記事をご覧ください。
『1on1とは?目的や意味がないと言われる理由、効果を高めるポイントを紹介!』
監修者からひと言 社員のコミュニケーション能力を高めるために大切なことは、1つ1つのスキルを継続的に実践する機会を作ることです。たとえば、ロジカルコミュニケーション研修で相手の目的に合わせて結論から端的に話すスキルを学んだら、職場でコミュニケーションする際に実践するかどうかでコミュニケーション能力が高まるかどうかが決まります。そのため、コミュニケーション能力を高める研修や施策を実施した後は、職場で実践してほしい行動を明確にし、積極的に取り組んでもらうように働きかけましょう。また、上司や同僚など周りのメンバーにも相談し、研修で学んだことを実践しやすい職場作りに取り組んでみてください。 |
まとめ
コミュニケーション能力が高い人は、アサーティブコミュニケーションやロジカルコミュニケーションを活用しています。反対に、コミュニケーション能力が低い人は、自分の都合で話をしたり、逆に自分が我慢してしまうことが多い傾向です。
社員のコミュニケーション能力を高めるためには、コミュニケーション能力が高い人も使用している話術を自然に使えるように社員に教育するのが効果的でしょう。
「社員にどのように教育をすれば良いのか分からない」「社員のコミュニケーション能力を効率的に向上させたい」という人事部のご担当者様は、ぜひアルー株式会社にご相談ください。ポジションなどに応じてさまざまな種類の研修を行っているだけでなく、人材育成を専門に行ってきたノウハウから質の高い研修を提供しています。
▼アルーのコミュニケーション研修について詳しくはこちらのページをご覧ください。
コミュニケーション研修
▼アルーのアサーティブコミュニケーション研修について詳しくはこちらのページをご覧ください。
アサーティブコミュニケーション研修