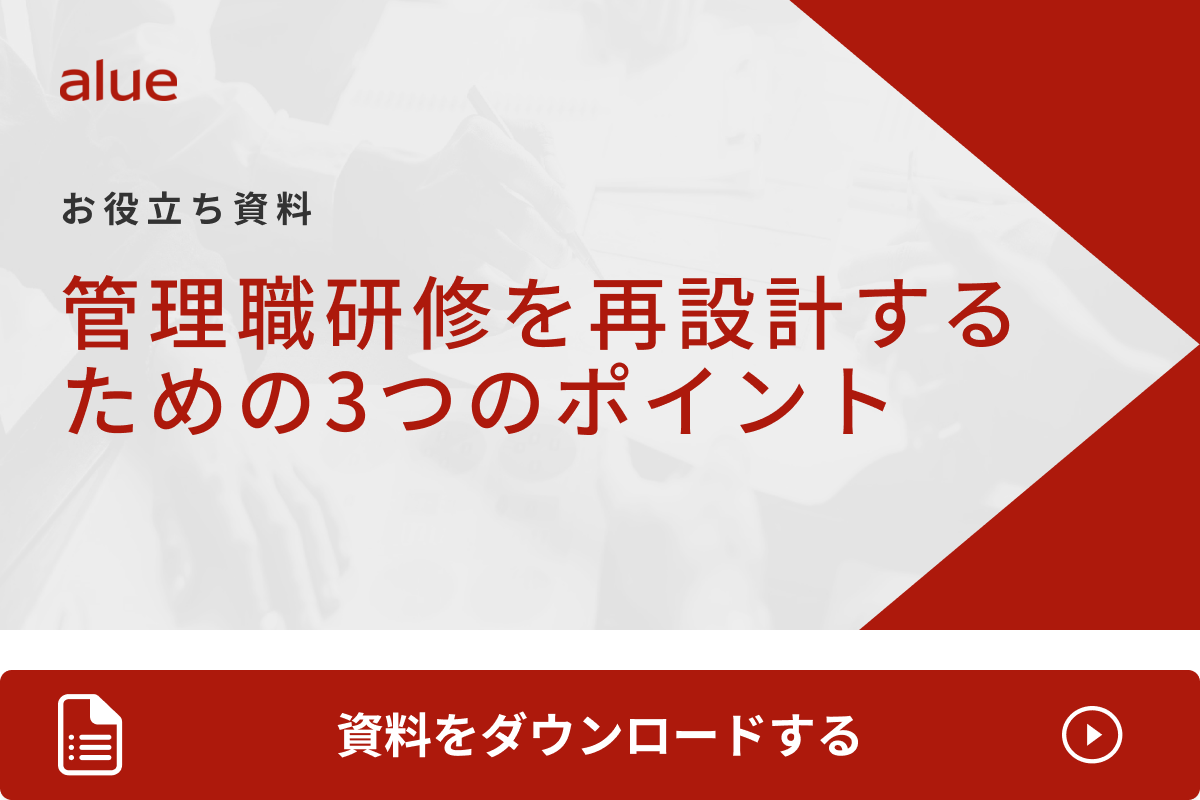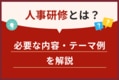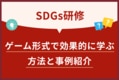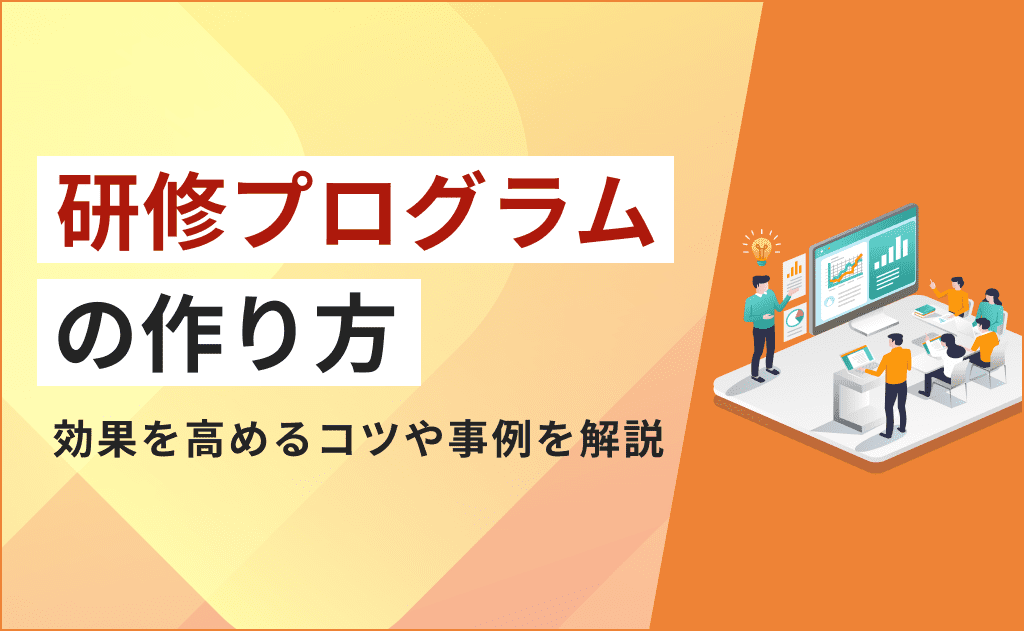
研修プログラムの作り方|効果を高めるコツや事例を解説
企業の十年後、二十年後を担う人材を育成するために欠かせないのが、研修の実施です。実際、社員の育成のため様々な研修施策を展開している企業も多いのではないでしょうか。
しかし、「いざ研修を導入しようと思ったが、研修プログラムの組み方がわからない」「現在の研修プログラムのままで本当によいのだろうか?」といった悩みを抱える担当者の方も多くいらっしゃるかと思います。
そこでこの記事では、効果的な研修プログラムの作り方やコツ、事例などについて解説します。
より深く知るための『オススメ』お役立ち資料
目次[非表示]
社員研修プログラムの作り方
研修プログラムを策定する際には、どういったステップを踏めばよいのでしょうか。
効果的な研修プログラムを作成するためには、まずビジネスにおける課題を分析するところから始め、そこから課題を抽出し、研修プログラムに落とし込んでいく必要があります。
おおまかに、次のようなステップを踏むとよいでしょう。
- ビジネスの分析
- パフォーマンスの分析
- 原因の分析
- インターベンションの選択
- 現状のニーズを分析し対象者や研修内容を決める
- スケジュールや教材構成、評価方法を決める
- 研修を社内で行うか外注するかを決定する
- 教材を作成する
- 成果を評価する
では、研修プログラムを作る際のプロセスについて詳しく解説します。
ビジネスの分析
企業のパフォーマンス向上につながる研修プログラムを策定するためには、まずビジネスにおける課題分析を行う必要があります。
例えば、以下のような事柄に取り組むとよいでしょう。
- 自社ビジネスや事業の、あるべき姿を明確化する
- 自社ビジネスや事業の、現状を明確化する
- 自社ビジネスや事業の、あるべき姿と現状とのギャップを把握し、戦略を練る
例えば、営業利益5000万円を目標としている企業の営業利益が現在3000万円であれば、埋めるべきギャップは2000万円です。実際にはこれよりも複雑に、様々な角度から課題分析を行うことになります。
パフォーマンスの分析
ビジネスの分析によって企業の目標や現状とのギャップがわかったら、次にパフォーマンスの分析を実施しましょう。ここでは、以下の3つに取り組みます。
- 戦略を実現する上で鍵となる人材は誰なのかを明確化する
- その人材のパフォーマンスの理想像を明確化する
- その人材のパフォーマンスの現状を明確化する
例えば先ほどの例でいえば、営業利益に直結する営業部が戦略実現の鍵を握るケースが多いでしょう。もちろん戦略を実現する上で鍵となる人材は、一人ではなく複数人存在することもあります。
原因の分析
パフォーマンスにおけるギャップを明確にした後は、ギャップを生んでいる要因を把握して、そこに対する課題を設定していきます。
ATD(米国人材育成機構)では、パフォーマンスギャップの主な原因として以下を挙げています。
- 組織構造やプロセス
- 資金や人材などのリソース
- 情報
- 知識やスキル
- モチベーション
- 健康と安全
先ほどの例で言えば、例えば「営業部の業務プロセスに無駄な部分が多く、担当者へ引き継ぐまでに時間がかかる」「営業職の傾聴力に課題があり、顧客からの信頼を獲得できていない」といった原因が浮かんできます。
インターベンションの選択
パフォーマンスギャップの原因が明確化したら、いよいよそれの解決策となるインターベンション(介入施策)を考えていきます。もちろんパフォーマンスギャップの解決方法は研修以外にも様々なものがあるため、まずは「パフォーマンスギャップを解決するのにどういった施策が必要なのか?」をフラットな視点で考えましょう。
社員のスキルやマインドセットが課題として浮かび上がった場合や、特定の知識を獲得してほしい場合などは、研修での解決が向いています。インターベンションを研修にすると決めたら、次のステップへ進んでください。
現状のニーズを分析し対象者や研修内容を決める
ここからは、具体的な研修プログラムの策定に入っていきます。まずは、現状のニーズを分析し、研修の対象者や研修のおおまかな内容を決めていきましょう。
なお、ニーズは以下の5つに分けることができます。
- 標準的なニーズ:標準的なものとの差異から生まれるニーズ
- 感覚的なニーズ:人々は何を求めているかという感覚に基づくニーズ
- 必需的なニーズ:需要と供給。マーケットや流行に依存するニーズ
- 比較的なニーズ:競合との違いから生まれるニーズ。
- 将来的なニーズ:プロジェクトのゴール。長期的な計画から生まれるニーズ
自社にはどの種類のニーズが存在しているのかを明らかにするとともに、OJTやeラーニング、集合研修などどのタイプの研修が向いているのかを考えていきましょう。
スケジュールや教材構成、評価方法を決める
研修の大枠が決まったら、スケジュールや教材構成、評価方法といった具体的な事項の検討に入ります。
研修スケジュールは、短めのシンプルな研修で1〜2日、長めの研修では数ヶ月に及ぶこともあります。また、研修実施後のフォローアップのスケジュールまでおさえておくのを忘れないようにしましょう。
教材構成や評価方法といった研修の基本的な仕様をあらかじめ固めて関係者とのコンセンサスをとっておけば、作り直しによるコストの無駄を防ぐことができます。
研修を社内で行うか外注するかを決定する
研修の詳細な項目が定まったら、次に研修を社内で行うか外注するかを決定しましょう。
最近は研修の受託をおこなっている企業も増えてきており、研修を外注するのもメジャーな選択肢となってきています。自社での研修ノウハウがあまり蓄積されていない場合は、すでに実施している研修の質をブラッシュアップしたい場合などは、外注もおすすめです。
なお、完全に外注か内製かの二択しかないわけではなく、例えば自社で作成した教材を用いた研修を委託したり、研修プログラム策定の段階から伴走してくれたり、といったパターンもありえます。
研修を外部委託するか迷う場合には、以下の記事も参考にしてみてください。
『研修は外部委託すべき?委託している割合や委託先選定のポイント』
教材を作成する
次に、研修で使う教材の作成を行いましょう。
研修の教材を作成する際に最も重要なことは、研修教材を作成するメンバーの間で、「誰がどの部分の作成を行うか」が明確化されていることです。複数人で作業を進める場合などは定期的にミーティングを行い、誰がどこまで作って、これから何をする予定なのかを共有するようにしましょう。
教材が一通り出来上がったら、教材作成に携わっていない第三者にチェックしてもらうとよいでしょう。細かなミスを発見できるのはもちろん、開発段階では気づかなかった改善点が見つかることもあります。
成果を評価する
最後に研修施策を実施して、効果測定によって研修の成果を評価しましょう。
研修の効果測定には、「短期的評価」と「中期的評価」の2つを用いるのが一般的です。短期的評価では、基本的に研修プログラムに対する満足度や研修内容の理解度などを評価します。一方で中期的評価では研修実施後数ヶ月〜半年程度の時期に、実務に戻ってからの行動変容や、KPIへの影響を測定します。
ここの段階で明らかになった研修の効果をもとにさらなる内容のブラッシュアップや再検討を行い、来年度以降のプログラムにつなげていきましょう。
▼研修の効果測定のポイントについて資料にまとめた資料をご用意しています。
研修の具体的なプログラム例

研修プログラムの策定ステップを解説しました。ここからは、新入社員研修、中堅社員研修、管理職研修、グローバル人材育成の4つの研修ごとに、研修の具体的なプログラム例を見ていきましょう。
具体的なプログラム例を参考に、自社でプログラムを策定する際のイメージを膨らませてみてください。
新入社員研修
新入社員研修は、企業によって実施内容に幅のある研修です。期間についても、2週間程度の短期で終了する場合や3ヶ月〜半年程度かけて行う場合もあるなど、業種や企業規模に大きく左右されます。ここでは、2週間かけて行うプログラムの例を見てみましょう。
1日目 |
会社の全体像 |
2日目 |
学生から社会人への意識転換 |
3〜4日目 |
ビジネスマナーの基礎知識 |
5〜6日目 |
報連相やPDCAなど、仕事の進め方に関する基礎知識 |
7〜8日目 |
各部署からの説明 |
9日目 |
パソコンの基本操作 |
10日目 |
新入社員研修のまとめ |
アルーが行っている新入社員研修については、以下のページでご確認ください。
新入社員研修
▼アルーの新入社員研修についての資料はこちらからダウンロードできます。
中堅社員研修
入社後3〜10年目程度の中堅社員を対象とした研修では、管理職候補として様々な能力が求められます。研修もコミュニケーション能力やコーチング能力といった特定のスキルを伸ばすために実施する場合が多いです。ここでは、中堅社員を対象としたコミュニケーション研修を実施するプログラム例を示します。
研修前 |
自分自身のコミュニケーションを振り返る |
研修日 |
研修のグランドルールの説明 |
フォローアップ日 |
研修実施後の行動変容を確認 |
アルーが行っている中堅社員研修については、以下のページでご確認ください。
中堅・リーダー層研修
▼アルーの中堅・リーダー層研修についての資料はこちらからダウンロードできます。
管理職研修
プレイヤー時代とはがらりと役割が変わる管理職を対象とした研修では、主にマネジメントについて学んでもらう機会が多いです。ここでは、短期間で実施するマネジメント研修のプログラム例を紹介します。
研修前 |
自身のマネジメントに関する課題の把握 |
研修日 |
研修のグランドルールの説明 |
フォローアップ日 |
研修実施後の行動変容を確認 |
アルーが行っている管理職研修については、以下のページでご確認ください。
管理職研修
▼アルーの管理職研修についての資料はこちらからダウンロードできます。
グローバル人材育成
最近では、グローバル進出のためにグローバル人材の育成に力を入れる企業も増えてきています。グローバル人材育成の際の具体的なプログラム例は以下の通りです。管理職研修の例と同様に、短期間で実施する研修を想定しています。
研修前 |
なぜグローバル人材が求められているのかを各自で考える事前課題の実施 |
研修日(1日目) |
研修のグランドルールの説明 |
研修日(2日目) |
1日目の内容の復習 |
フォローアップ日 |
研修実施後の行動変容を確認 |
アルーでは、グローバル人材育成サービスを提供しています。詳しくは以下のページでご確認ください。
グローバル人材育成サービス一覧
▼アルーのグローバル人材育成サービスについての資料はこちらからダウンロードできます。
研修の効果を高めるコツ
研修の効果を最大限に引き出すためには、どういった点に気をつければよいのでしょうか。
研修の効果を高めるために必ずおさえておきたいコツについて解説します。
アダルトラーニングであることを理解する
子供の学びは「ペタゴジー」と呼ばれ、主に「知識の習得」がゴールとされます。例えば学校では、算数や社会の知識を学ぶことができれば学習の目標達成です。
一方、研修をはじめとした大人に対して実施する教育は「アダルトラーニング」と呼ばれ、学ぶこと自体がゴールではありません。学んだあとにそれをどう行動変容や業績に結びつけるのかが重視されます。
両者の違いを意識して、学んだことをどう生かすかまで考えた上で研修プログラムを作成するのがコツの一つです。
▼研修受講者の行動変容を促すコツについてまとめた資料をダウンロードいただけます。
最初に研修の目的を周知させる
研修の目的がわからないままでは、研修参加者は「なぜ自分はこの研修を受けているのだろうか?」「この研修を受けることにどのような意味があるのだろうか?」と疑問に思ってしまうかもしれません。こうした疑問が払拭されないと、研修に対するモチベーションが低下してしまい、学習効果も半減してしまうでしょう。
研修プログラムを考える際には、研修の目的を周知しましょう。「この研修におけるゴールはどこなのか」「この研修を受けるとどのようなメリットがあるのか」を強調することによって、参加者のモチベーションを保つことができます。
自社の方針と個人の方針をすり合わせる
先ほども解説したように、研修参加者のモチベーションは研修における学習効果に大きな影響を与えます。せっかく研修に参加しても、研修参加者が研修に参加する意義を見出せなければ、効果的な研修は実施できません。
研修に参加するモチベーションを引き出すため、自社の方針と個人の方針を意識的にすりあわせるのもコツです。例えば「語学力を高めたい」と考えている個人に対して、「グローバル研修を受ければ、語学力やグローバルに活躍する際に必要なマインドセットも身に付きます」と説明すれば、自社の方針と個人の方針が一致して、研修に参加する意義を見出しやすくなります。
効果測定の方法を決める
研修を実施した後、何もフォローアップを行わないと研修によって生まれた成果が分かりません。研修の成果を正確に把握して次の研修につなげるためには、効果測定の方法を明確化するのがポイントです。
研修の効果測定の方法としては、例えば以下のようなものが考えられます。
- 事前に営業利益や成約率などのKPIを設定し、研修実施の6ヶ月後にKPIを再度測定する
- 研修トピックに対する関心を研修実施前と研修実施後でヒアリングして、関心の伸びを測定する
いずれにしても、明確な効果測定の手段を定めるとよいでしょう。
▼研修の効果測定のコツについてまとめた資料をダウンロードいただけます。
研修の作り方に関するよくある質問

研修のプログラムを作成する際には、いくつか疑問が出てくるかもしれません。
ここでは、研修の作り方に関するよくある質問についてまとめます。
研修講師はどのように選定すべきですか?
研修プログラムを作成する際には、研修講師を社内から選抜するか、外部へ委託して手配する必要があります。研修講師はどのように選定すべきか悩む場合も多いでしょう。
研修講師には、以下のようなスキル・スタンスが必要です。
- 受講者の育成に対する強い熱意・想いがある
- 研修内容に関する実務経験が豊富で、ノウハウや知見を持っている
- 理論と感情どちらかに偏らず双方をバランスよく扱えるコミュニケーション力
- 1対Nのファシリテーション力が高い
- 受講者に考えさせ、気づきを促す問いを作れる
- 受講者にとって分かりやすく簡潔に説明できるロジカルシンキング力
- 年代や職種、職階といった観点から、受講者との距離が近い
これらの条件に当てはまるような適任と思われる社員を社内講師として選抜するのがおすすめです。
研修講師に求められるスキルや選び方については、以下の記事で詳しく解説しています。
『研修講師に求められるスキルとは。講師の選び方や研修を成功させるポイント』
研修の振り返りはどのように行うべきですか?
研修の振り返りは、研修の学習効果を引き上げるだけでなく、研修プログラムを改善する上でも必須です。研修の振り返りはどのように行えばよいのでしょうか。
研修の振り返りは「短期的評価」と「中期的評価」の2回に分けて行うのが一般的です。記事の前半でも解説した通り、短期的評価では研修実施直後の感想や満足度といった効果を測定し、中期的評価ではKPIの測定や行動変容の把握などを行います。
短期的評価は研修実施直後から1週間以内程度に、中期的評価は研修実施後から半年後〜1年後を目安にそれぞれ実施するとよいでしょう。
▼研修の振り返りのコツについてまとめた資料をダウンロードいただけます。
面白い研修にするためにはどうしたらいいですか?
研修を実施したのに、受講者に面白いと感じてもらえない、といった悩みはよくあります。面白い研修にするためにはどのような工夫が必要なのでしょうか。
研修を面白くするためには、研修前のアイスブレイクの導入や途中休憩時の簡単なアクティビティの導入がおすすめです。アイスブレイクとは、受講者の緊張を和らげるため研修の最初に行われるアクティビティのことを指します。
例えば、自分の好きなものを紹介する「私の好きなもの」といったシンプルなものや、想像上のボールでキャッチボールをする「ボール回し」といった身体を使うものなどがおすすめです。
▼研修で使えるアイスブレイクについてまとめた資料をダウンロードいただけます。
研修のコストを抑えるためにはどうしたらいいですか?
研修実施にはどうしてもヒトやカネといったコストがかかってしまいます。研修のコストをおさえたい、というのもよくある悩みの一つです。
研修のコストをおさえるためには、eラーニングやブレンディッドラーニングを積極的に活用するとよいでしょう。タブレット端末やパソコンを通じて学習できるeラーニングを実施すれば、研修実施時の教材管理や学習状況の管理といった手間を大きく削減できます。また、研修実施のための会場確保も必要ありませんし、講師や受講者の交通費も削減といった金銭的なコストに対するメリットも大きいです。
リモートに対応した研修を作りたいのですが
コストをおさえるといった目的で、リモートに対応した研修を作りたいが、どのように実施すればよいのかわからない、というケースもあるでしょう。
研修をリアルタイムでリモート配信したい場合は、ZoomやMicrosoft Teams、YouTube Liveといったオンラインコミュニケーションツールの活用が有効です。一方必ずしもリアルタイムでなくてもよい場合は、eラーニングの学習管理システムであるLMSを導入するのがよいでしょう。リモートに対応した高品質な研修を作りたい場合は、研修を外注するのもおすすめです。
オンライン研修のやり方については、以下の記事で詳しく解説しています。
『オンライン研修のやり方やメリット・デメリットをわかりやすく解説』
研修を行うならアルーにお任せください
研修の実施を検討している場合は、ぜひアルーへお任せください。アルーは人材育成を専門に手掛けてきた企業で、受講者数年間2.3万人を超える新入社員研修を始め、数多くの研修を実施しています。
アルーでは、新入社員研修や階層別研修のほか、オンラインで実施する研修やeラーニングの活用なども幅広く支援可能です。研修実施を専門とするアルーについて紹介いたします。
研修体系の作成から支援いたします
研修体系とは、どの段階でどのようなスキルを身につけるのかを可視化した図のことです。研修体系を綿密に立てることによって、経営戦略と密接に連動した人材育成が可能になります。
アルーでは、研修体系の作成から支援することが可能です。お客様のビジネス上の課題に合わせた育成プラン作成を支援するとともに、豊富な研修ノウハウをご提供いたします。大まかな育成の流れがまだ決まっていない、という場合でも、ぜひ一度アルーへご相談ください。
グローバル人材育成体系の構築をアルーが支援した事例は、以下のページで詳しくご確認いただけます。
「点」から「線」の育成へ。経営戦略に基づいたグローバル人材育成体系構築のポイント(株式会社ヤクルト本社導入事例)
オンライン研修・eラーニングにも対応
リモートワークの普及に伴って、最近ではオンライン研修やeラーニング研修を取り入れる企業も増えてきています。オンライン研修では、従来の集合研修とは異なる育成ノウハウが必要です。また、eラーニングではLMSと呼ばれるツールの導入から始める必要があります。
アルーでは、オンライン研修やeラーニングでの研修にも対応しております。特にeラーニングについては、自社で開発したLMSである「etudes」によって、社内でのeラーニング活用を徹底的に進めます。
etudesについては、以下のページでご確認ください。
etudes
まとめ
研修プログラムの作り方や、研修プログラムの具体例などについて解説しました。
研修プログラムを作る際には、まずビジネスにおける課題の分析から始める必要があります。その後、ビジネスの課題を人材の課題に落とし込んで、育成施策を具体的に考えていく、という流れです。
研修プログラムをうまく設計すれば、自社の課題解決につながるような効果の高い研修が実施できるでしょう。ぜひこの記事の内容を参考に研修プログラムを設計して、社員の行動変容を促していきましょう。