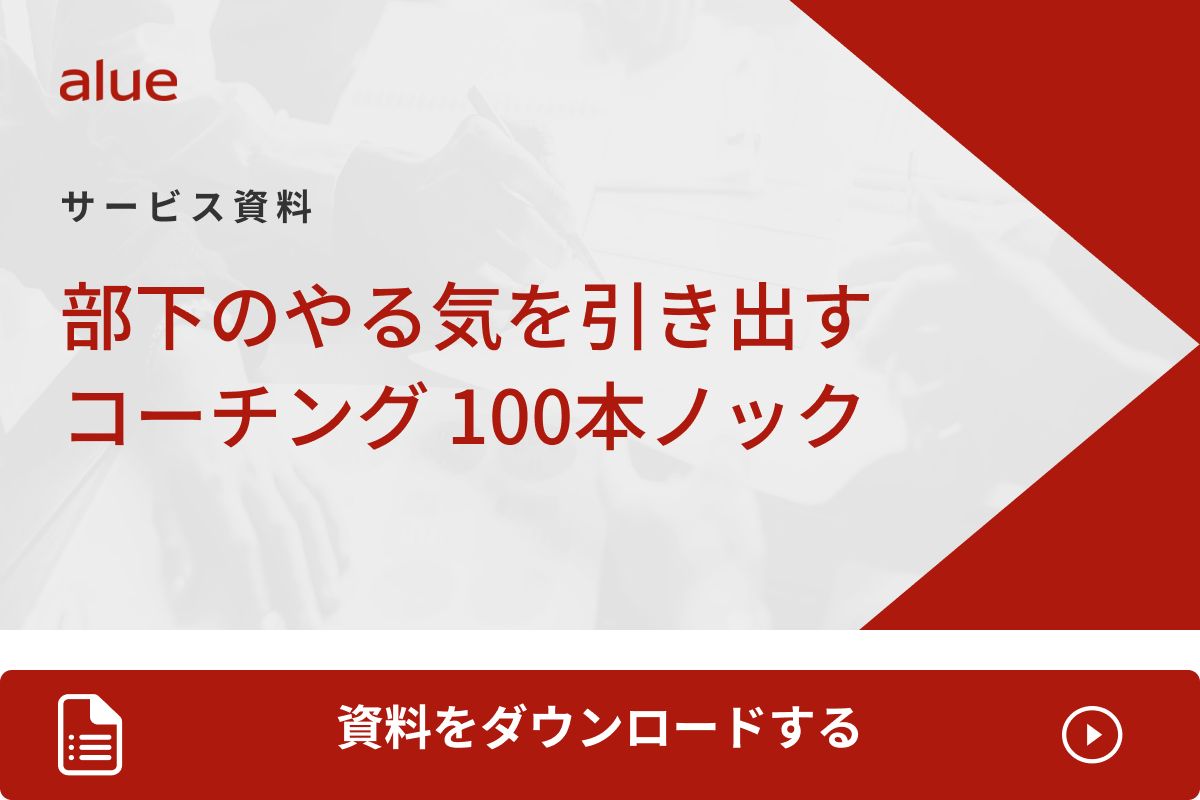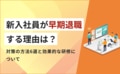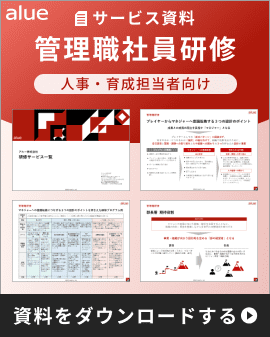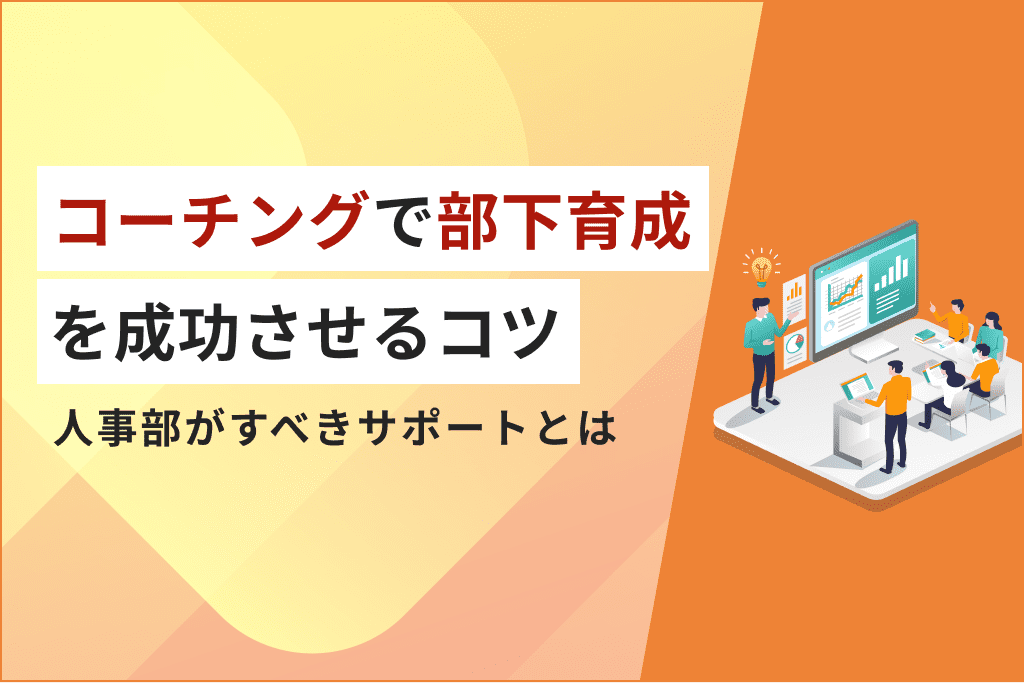
コーチングで部下育成を成功させるコツ 人事部がすべきサポートとは
近年、社員の主体性を尊重した教育手法として注目を浴びているコーチング。コーチングを正しく実践できれば、社員の主体性を引き出したり、生産性が向上したりといったさまざまなメリットがあります。部下の育成を担う管理職層に特に求められるスキルです。
そこでこの記事では、コーチングによって部下育成を成功させるコツや、コーチングの成功に向けて人事部ができるサポートを解説します。コーチング研修の事例も紹介するので、人事担当者の方はぜひ参考にしてください。
より深く知るための『オススメ』お役立ち資料
目次[非表示]
コーチングとは
コーチングとは、相手の主体性を尊重しながら、相手の気づきを促すことで主体的に行動できる社員を育成する教育手法です。コーチングを実施する際には、部下に気づきを与えるような質問を投げかけたり、部下の成長につながる目標設定をサポートしたりして、部下の成長を促していきます。
コーチングでは学習者自身の主体性が重視されるため、自律的に学習できる社員を育成しやすいという点が主なメリットです。社員一人ひとりが自律的に学習することが求められるVUCAの時代に適した教育手法として注目を浴びています。
コーチングについては以下記事で詳しくご紹介しています。
『コーチングとは|メリット・デメリットや必要スキルについて紹介』
ティーチングとの違い
コーチングとよく対比される言葉に、「ティーチング」が挙げられます。両者はどちらも部下育成の際に役立つ教育手法ですが、ティーチングとコーチングは対になる概念です。
まずコーチングでは、前述した通り部下の主体性が重視されます。上司が直接指示を出すのではなく、あくまでも本人の自主的な学習を促すのがコーチングです。
一方でティーチングは、上司が部下に向けて具体的な方法を指導する学習手法を指します。指導の際に対等な関係が重視されるのがコーチング、上下関係があるのがティーチングと考えるとわかりやすいです。
ティーチングについては以下記事で詳しくご紹介しています。
『コーチングとティーチングの違いとは|使い分けや効果をメリットを紹介』
部下育成にコーチングを取り入れるメリット
部下育成にコーチングを取り入れれば、部下が主体的に行動できるようになったり、組織の生産性が向上したりといったさまざまなメリットがあります。またコーチングを通じて、部下の傾向や適性をより正確に把握できるでしょう。
部下育成にコーチングを取り入れるメリットを解説します。
部下が主体的に行動できるようになる
部下育成にコーチングを取り入れれば、部下が主体的に行動できるようになります。
コーチングを行う際は、部下に直接指示を与えずに、部下自身による気づきを促します。そのため、部下は自ら考えて行動するクセがつき、主体的に行動できるようになるでしょう。
現代の目まぐるしく変化する情報をキャッチアップするためには、学習者の主体性が欠かせません。VUCAとも呼ばれる現代のビジネス環境では、コーチングを取り入れて主体性を引き出すメリットが大きいです。
主体性を高める方法については以下記事で詳しくご紹介しています。
『主体性とは?自主性との違いや主体性のある人の特徴・高める方法を紹介』
生産性の向上につながる
コーチングを実施して部下の能力を伸ばせば、生産性の向上を実現できます。
上司がコーチングを正しく実践できれば、問題解決力や巻き込み力といったさまざまな能力を伸ばすことが可能です。こうした能力開発によって業務が効率化し、生産性の向上が実現します。
部下の傾向や適性がわかるようになる
コーチングを実施するメリットとして、部下の傾向や適性を正確に把握できるという点も挙げられます。
コーチングを行う際には、上司と部下の間で対話を行います。その対話を進める過程で、本人も気づいていなかった思わぬ個性や能力、強みなどが見えてくる場合があります。上司が部下の特性を正しく把握できれば、本人の特性にあったサポートを提供しやすくなるでしょう。また、上司が部下を正しく理解することで、適材適所な人材配置につながる効果もあります。
コミュニケーションが活性化し、信頼関係を築ける
コーチングを実施すればコミュニケーションが活性化するため、信頼関係を築くこともできます。
コーチングを行う際には、部下と上司間での本音の対話が必要不可欠です。普段なかなか話さないような内容まで深く話すことで、自然と信頼関係が形成されていきます。その結果、コーチング以外の場面でも疑問点を相談しやすくなったり、サポートを求めやすくなったりします。また、コミュニケーションが活性化して必要な情報をスムーズに共有できるようになるため、業務の効率化にもつながるでしょう。
管理職に必要なコミュニケーションスキルについては以下記事で詳しくご紹介しています。
『管理職に必要なコミュニケーションスキルとは|コツやスキルの身につけ方を解説』
コーチングに必要なスキル

コーチングを実践するためには、上司側に「傾聴スキル」「質問スキル」「承認スキル」の3つのスキルが必要です。コーチングを実施する際には、こうした上司の3つのスキルを強化してから臨むとよいでしょう。コーチングを行う際に必要な3つのスキルを紹介します。
傾聴スキル
コーチングを行う際には、傾聴スキルが必要です。
傾聴とは、相手の話す内容に対して「善悪」や「優劣」といった自分の判断軸を使わず、ありのままを受け止めて共感するコミュニケーションスキルの一つです。物事や事実といった表面的な内容だけでなく、相手の話す内容の背後にある想いや価値観まで踏み込んで理解することが求められます。
コーチングで傾聴を活用すれば、部下がどういった悩みや課題を抱えているのかを正確に把握できるようになります。管理職が傾聴力を高める方法や、傾聴力を高めるメリットなどは以下の記事から詳しくご覧ください。
『管理職が傾聴力を高める育成方法とは?傾聴力を高めるメリットと目的』
質問スキル
相手の成長につながるような質問を投げかけるスキルもコーチングには必要です。
質問には、「クローズドクエスチョン」「オープンクエスチョン」の2種類があります。クローズドクエスチョンは「はい」か「いいえ」で答えられるような質問で、オープンクエスチョンは自由な回答を求める質問です。コーチングでは会話を発展させる必要があるため、後者のオープンクエスチョンが有効です。
質問スキルは、コーチングの実力を最も左右するスキルといっても過言ではありません。コーチングを行う際には質問の投げかけ方などを工夫しながら、相手の成長を促す必要があります。
承認スキル
コーチングを実践する際には、承認スキルも必要です。承認スキルとは、相手から引き出した答えを受け止め、認める能力を指します。
コーチングの際にありがちなのが、「褒めて終わり」になってしまうというものです。褒めることももちろん大切ですが、モチベーションを引き出すためには相手を「認める」ことが求められます。「よく頑張ったね」といった単純な声掛けだけでなく、「あなたがいたから助かったよ」「あなたはいつも努力しているね」といったように、相手を認めるフレーズを意識的に使うのがポイントです。
部下育成でコーチングを実施する際のポイント
部下育成にコーチングを実施する際には、双方向のコミュニケーションを心がけるのがポイントです。また、マンツーマンで実施したり、中長期にわたって行ったりすることも求められます。
部下育成にコーチングを取り入れる際に意識しておきたいポイントをいくつか解説します。
双方向のコミュニケーションを心がける
コーチングを行う際には、双方向のコミュニケーションを心がけましょう。
コーチングを行う際にありがちな失敗として、「いつも上司が部下に指示を与えるだけになってしまっている」というものが挙げられます。コミュニケーションが一方通行になってしまうと、部下の主体的な行動を促すというコーチング本来のメリットが活かせません。
コーチングを実施する際には、部下と上司が双方向にコミュニケーションを取るように心がけましょう。発言が偏っていると感じた場合は、必要に応じて上司が部下に考えを聞いたり、質問を投げかけたりするのが重要です。
管理職に必要なコミュニケーションスキルについては以下記事で詳しくご紹介しています。
『 管理職に必要なコミュニケーションスキルとは|コツやスキルの身につけ方を解説』
マンツーマンで行う
コーチングは、必ずマンツーマンで実施するのがポイントです。
従来の人材育成は、全員に対して同じ内容を教育する形で行われてきました。こうした画一的な教育は社員の能力を効率的に底上げできる一方で、社員の個性を尊重した教育は実現しづらいのがデメリットです。
同じ内容を教育しても、当然社員それぞれで受け止め方や感じ方は異なります。成長の速度も人それぞれです。コーチングをマンツーマンで実施することで、社員一人ひとりの個性を尊重した教育が実現できます。
短期間でなく、中長期にわたって行う
コーチングに取り組む際には、短期間で終わらせるのではなく、中長期にわたって行うよう意識してみましょう。
コーチングによる教育は、成果を実感するのに時間がかかります。答えを直接提示しないため、短期的にはティーチングや座学での研修より効率が劣ることも多いでしょう。しかし、「効果が出ないから」といって、短期でコーチングを終わらせてしまうのはもったいないです。本人が自発的に成長できるようになるまで、計画立てて中長期的に実施するようにしましょう。
答えや結論を押し付けない
答えや結論を押し付けないというのも、コーチングを実践する際のポイントです。
部下がなにかに行き詰まっている際、つい上司は「〇〇するべきだ」「こうしてみるのがいい」といったように、直接答えや結論を提示してしまいがちです。
しかし、コーチングは人それぞれの価値観や個性を尊重した教育手法です。答えを押しつけてしまうと、本人による気づきを促すというコーチングの目的が失われてしまいます。上司は、あくまでも本人が自分の力で解決するサポートをするよう意識しましょう。
部下が相談しやすい雰囲気づくりをする
コーチングを実施する際には、部下が相談しやすい雰囲気を作るよう意識してみてください。
部下が相談しやすい雰囲気を作っておくことで、壁にぶつかった際にもサポートを求めやすくなります。反対に上司がいつも忙しそうにしていると、相談や質問をためらってしまい、時間を無駄にしてしまうことになりかねません。
部下の質問へ真摯に対応するのはもちろん、積極的に上司側が話しかけるなど、相談しやすい雰囲気作りを意識してみてください。
なお、相談しやすい雰囲気を作るためには、職場の心理的安全性を向上させるのが大切です。
心理的安全性を高める方法や、人事が行うべき施策は以下のページで詳しく解説しています。
『心理的安全性とは?高める方法や人事が行うべき施策について』
コーチングによる部下育成を促進させるために人事部が取り組むこと

コーチングによる部下育成を促進させるために、人事部は何ができるのでしょうか。ここからは、コーチングによる部下育成を行っていく際に人事部ができる具体的なアクションを解説します。
管理職に「部下の自律を促す役割」を与える
コーチングによる部下育成を成功させるためには、管理職に「部下の自律を促す」という役割を与えましょう。
管理職は、「部下を教える際には、やり方を指示するのが効果的だ」という考え方にとらわれがちです。しかし、部下に直接答えを提示するやり方は、コーチングの趣旨とは異なります。まずは管理職に対して「部下の自律を促すのが大切だ」という役割認識を形成し、部下の主体性を引き出すコーチングの方向性について理解してもらいましょう。
1on1の制度を導入する
1on1の制度を導入するのも、コーチングによる部下育成を成功させるために重要です。
コーチングを行う際には、部下と上司が1対1で話すまとまった時間を取る必要があります。1on1を実施すれば、定期的に部下と上司が進捗を共有し、能力の向上に向けた方向性をすり合わせることが可能です。コーチングを実施する際は1on1ミーティングもあわせて導入し、部下の学びの場として役立ててもらいましょう。
1on1ミーティングを導入する効果や目的、事例などは以下のページで詳しく解説しています。
『1on1ミーティングの導入効果・目的とは?導入企業の事例や導入方法』
コーチング研修を実施する
コーチングによる育成を成功させるためには、上司を対象としたコーチング研修を実施するのがおすすめです。
いきなり「部下のコーチングをしてください」と言われても、何から手をつければよいのか戸惑ってしまう管理職が多いでしょう。コーチングに取り組んでもらう前に、コーチングの方法やポイント、コーチングの際の心構えなどを学んでもらうのが重要です。
本格的なコーチングに取り組む前に一度コーチング研修を実施して、コーチングのノウハウを学んでもらいましょう。アルーの実施しているコーチング研修のプログラム詳細は、以下のページからご覧いただけます。
コーチング研修のプログラム詳細
▼サービス資料をダウンロードする
上司のスタンスを変革する
上司のスタンスを変革するのも、コーチングの効果をより一層引き出す上で大切です。
コーチングがうまくいかない場合の原因は主に2つ考えられます。1つ目は、上司にコーチングスキルが身についていないというものです。2つ目は、部下育成に対する上司のスタンスが原因になっているケースです。「部下は上司の指示に従っていればよい」といった考えを上司が持っているケースが当てはまります。
コーチング研修ではコーチングスキルを高めることばかりに重点が置かれがちですが、部下育成に対するスタンスを改めてもらうことも時には必要です。スキルだけ身についても、上司が「部下育成は管理職の仕事ではない」と考えていては効果的なコーチングは実践できません。研修を通じて、人を育てることの重要性や意義、あるべき育成の姿勢について学んでもらい、スタンスの変革を促しましょう。
部下育成におけるコーチングの進め方・流れ
部下育成におけるコーチングは、以下の流れで実施しましょう。
- ヒアリング:部下の考え方やスキルといった現状を、上司が正しく把握する
- ゴールの決定:コーチング後の理想状態を明確化する
- 問題点の洗い出し:ゴールへ到達するためにはどんな課題があり、何をするべきなのかを明確化する
- アクション:上司がフォローを行いつつ、コーチングを実施する
- 振り返り:振り返りを行い、足りない部分をフォローする
上記のステップを参考にしてコーチングを進めれば、効果的に部下の自主性を伸ばすことができます。コーチングに取り組む前にゴールや問題点の明確化を行い、上司と部下の間で方針を共有するのが大切です。
コーチング研修の事例
人材育成を専門に手掛けているアルーでは、効果的にコーチングを実施するために役立つさまざまな研修を取り揃えています。ここからは、これまでにアルーが実施したコーチング研修の中から、特に参考となる事例を3つ厳選して紹介します。
なお、コーチング研修の具体的な内容や目的、メリットは以下のブログ記事で詳しく解説しています。
『【事例あり】コーチング研修の内容や目的、メリットを解説』
管理職向けコーチング研修
大手通信業のA社では、ティーチングスキルには習熟している一方で、相手の考えを引き出すコーチングスキルには課題感がありました。そのため、次長・チームリーダーのコーチングスキルを向上させ、面談の質を上げることを目的に、コーチング研修を行いました。
アジェンダ |
内容 |
イントロダクション |
研修目的の確認・講師自己紹介 |
面談の目的 |
設定した目的の進捗を確認し、状況に応じて軌道修正をするといった面談の目的を知る |
現状の部下との関わり方を把握する |
事前アンケートの結果を含めて、部下の状況にあわせた関わり方が出来ているか把握する |
望ましい面談の場を作るための心構え・スキル |
心理的安全性の確保・相手を理解する心構えに関する講義・ワーク |
面談実践 |
ケースワークを行い、面談の基本的な進め方を理解する |
まとめ |
学んだこと・質疑応答・アクションプランの作成 |
事後施策として、3人1組の少数グループを汲み、研修後にバディで研修内容の実施度合いについて振り返りを行うバディセッションを行いました。
受講者からは「日々の1on1で活かせそうな内容であり、グループワークによる情報共有も学びとなった。」「型も学びつつ、本人の特性や状態に合わせて対話することや関わり方を変える重要性について学べた。」というコメントをいただいています。
若手リーダー向けコーチング研修
B社では、年次が若い段階で管理職になるケースが多く、効果的な育成コミュニケーションやメンバーの意欲を引き出す関わり方について、理解出来ていないケースがあることを課題としていました。また、管理職自身がプレイング業務をしなければならない状況も発生しており、部下育成にあまり時間を割けていないのも課題でした。
アジェンダ |
内容 |
イントロダクション |
- |
役割認識 |
ディスカッション「管理職の役割とは」 |
マネジメント概論 |
強いチームの作り方・成功の循環サイクル 組織マネジメント |
部下コミュニケーション |
ティーチング・フィードバック・コーチングを演習で学ぶ |
行動計画立案 |
メンバーの見立てとコミュニケーションプランの立案 |
事後施策として、育成シートで立てたプランを現場のメンバーに対して実施し、1ヶ月終了後に自身で振り返りを行ってもらいました。
受講者からは、「これまで、マネジメントの目的をいかに近視眼的に捉えていたかがわかった」「コーチングのやり方に正解は無く、状況に応じて柔軟に使い分ける重要性に気付いた」などのコメントをいただいています。
部下の自発的行動を引き出すコーチング研修
C社では、環境の変化に伴って「自分で考え行動できる人」の育成ニーズが高まっており、管理職に、下位者に考えさせ気付きを与えながら自発的な行動を促すコミュニケーションをとるスキルを身に付けさせるため、コーチング研修を実施しました。
アジェンダ |
内容 |
イントロダクション |
グランドルールと研修目的、全体像を確認する マネジメントに期待される役割、成功の循環モデル、心理的安全性を担保する重要性を学ぶ |
メンバーとの関わり方 |
信頼関係構築のために必要な、心理的安全性を担保するために、メンバー一人ひとりの考え方・状況に合わせて関わり方を変えることを学ぶ |
メンバーの自発的行動を引き出す |
狙い:メンバーの自発的行動を引き出すために、職務設計を点検し見直し続けることを学ぶ |
総括セッション |
振り返り、実務においての行動計画、質疑応答 |
研修後は、リアクションアンケートで効果測定を行い、研修結果の見える化も支援しています。
コーチングスキル研修ならアルーにお任せください
アルーは、人材育成を専門的に手掛けている企業です。コーチングスキル研修なら、アルーへぜひお任せください。
コーチングを効果的に行うためには、管理職の適応課題へ積極的にアプローチして、部下育成に対するスタンスを変革する必要があります。アルーの研修プログラムは、マネージャーとしての役割認識やコーチングに必要なスタンスなど、適応課題を学べる内容が豊富に盛り込まれています。また、実際の場面を想定したシミュレーションも含まれているため、OJT指導などの実務に役立てやすいのが特徴です。
アルーの提供しているコーチングスキル研修は、以下のページから詳しくご覧ください。
コーチング研修
まとめ
コーチングを効果的に行なう方法について、コーチングの概要からポイント、人事部ができることなどを幅広く解説しました。
ビジネス環境が激しく変化する現代では、社員一人ひとりが自律的に学習を進めることが欠かせません。コーチングは、こうした時代に合った学習スタイルといえるでしょう。コーチングを正しく実践すれば、部下の主体性を引き出した効果的な教育が可能です。
ぜひこの記事で解説した内容を参考にしながら、コーチングの成功を人事部が積極的にサポートしていきましょう。