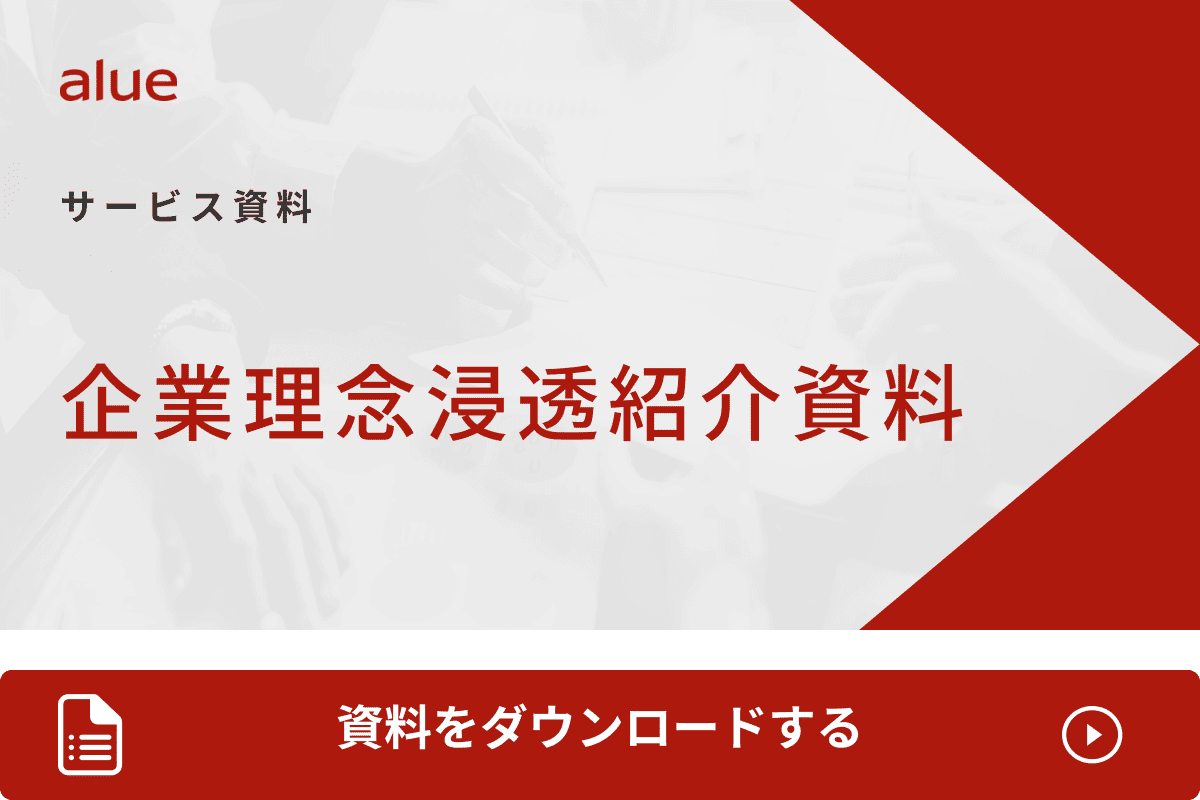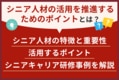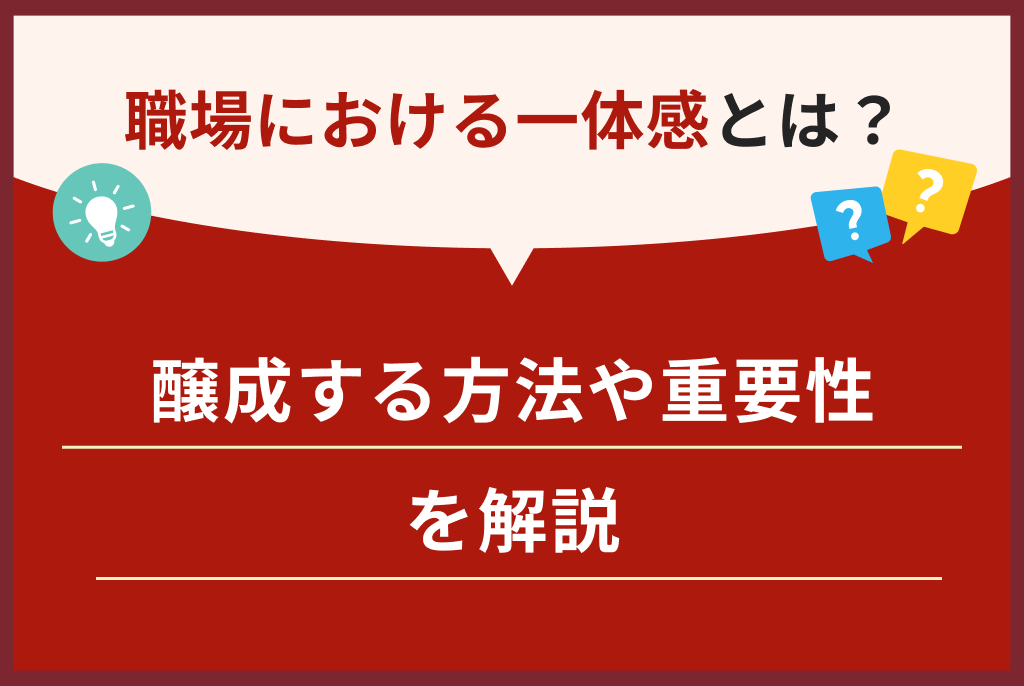
職場における一体感とは?醸成する方法や重要性を解説
一体感は、職場や組織において欠かせない要素です。強い一体感があると、信頼関係が深まり、生産性やモチベーションの向上につながります。この記事では、一体感の重要性や醸成方法、具体的な形成手法について詳しく解説します。
目次[非表示]
- 1.一体感とは
- 2.職場における一体感の必要性
- 3.一体感のない職場の特徴
- 4.職場の一体感を高めるメリット
- 5.職場の一体感を醸成する方法
- 6.職場の一体感を醸成する上での注意点
- 7.一体感を醸成する研修事例
- 8.まとめ
一体感とは
一体感とは、組織やチーム内で共通の目的や価値観を持ち、相互に協力しながら強い結束力を感じる状態のことです。職場においては、社員1人1人が共通の目標や価値観を共有し、互いに協力し合い、一体となって仕事に取り組むという状態のことを指します。個々のメンバーが組織の一員としての意識を持ち、組織全体の成功に貢献したいという強い意志を持つことで、一体感は生まれます。
一体感の醸成とは
一体感の醸成とは、組織やチーム、コミュニティなどの集団において、メンバー同士が共通の目的や価値観を共有し、協力しながら活動できる環境を作り出すことを指します。一体感を醸成するためには、共通のビジョンや目標を明確にし、円滑なコミュニケーションを促進することが重要です。また、信頼関係を築くために、互いに意見を尊重し、成功や成果を共有することも効果的です。一体感が醸成されることで、モチベーションの向上や生産性の向上につながり、よりよい成果を生み出すことができます。
職場における一体感の必要性
なぜ、一体感のある組織を作る必要があるのでしょうか。その必要性について解説します。
多様性と組織力の両立ができる
現代の組織は、多様なバックグラウンドを持つ人材が集まることが一般的です。異なる価値観や考え方を持つ人々が、一体感を持ちながら協力し合うことで、組織全体の創造性や問題解決能力を高めることができます。一体感があることで、多様な個性を尊重しながら、組織全体の力を最大限に引き出すことができるでしょう。
コミュニケーションを活性化できる
一体感がある職場では、メンバー間のコミュニケーションが活発になり、情報共有がスムーズに行われます。互いに理解し合い、協力し合うことで、誤解や無駄を減らし、効率的に仕事を進めることができます。また、一体感によって、メンバー間の信頼関係が深まり、よりオープンなコミュニケーションが促進されます。
▼コミュニケーションの活性化については、こちらの記事で詳しく知っていただけます。
『職場のコミュニケーションの重要性と活性化のための具体例8選』
離職率が下がる
一体感の高い職場では、社員の離職率が低い傾向にあります。社員は組織の一員としての帰属意識を持ち、組織に貢献したいという強い意志を持つため、離職を考える可能性が低くなります。また、一体感によって、社員は仕事に対するモチベーションやエンゲージメントを高めることができ、より長く組織に貢献したいという気持ちを持つようになります。
▼離職率については、こちらの記事で詳しく知っていただけます。
『離職防止のための研修を効果的に行うコツ|成功事例や階層別の内容を紹介』
一体感のない職場の特徴
ここでは、一体感のない職場にどういった特徴が出てくるのか解説していきます。
コミュニケーションが少ない
一体感のない職場では、社員間のコミュニケーションが不足し、情報共有が滞りがちです。互いに理解し合えず、協力関係が築けないため、誤解や無駄が発生しやすく、仕事がスムーズに進みません。コミュニケーション不足の状況が長く続くと、社員間の信頼関係を損ない、職場全体の雰囲気を悪化させる可能性もあります。
個人主義が蔓延している
一体感のない職場では、個人主義的な考え方が蔓延し、会社全体の目標よりも個人の利益を優先する傾向が見られます。社員は自分の仕事だけに集中し、他のメンバーとの協力や連携を軽視するため、組織全体の目標達成が難しくなります。また、過度の個人主義により社員間の競争を激化させ、職場全体の雰囲気が悪くなってしまうこともあるでしょう。
指示待ち社員が多い
一体感のない職場では、社員は指示待ちの状態になりがちです。自分から積極的に行動を起こすことを避け、上司からの指示を待つだけの受け身の姿勢になってしまいます。指示待ちが当たり前になってしまうと、社員の自主性や創造性が育まれず、組織全体の活性化を妨げる要因となります。また、指示待ちの状態は、社員のモチベーション低下につながる可能性もあります。
▼指示待ち社員については、こちらの記事で詳しく知っていただけます。
『上司に問題?指示待ち人間の社員を活性化する直し方・特徴・原因を解説』
職場の一体感を高めるメリット
職場の一体感を高めることは、組織全体の業績向上や社員のモチベーション向上、離職率の抑制など、様々なメリットをもたらします。一体感がある職場では、社員は互いに協力し合い、共通の目標に向かって努力するため、組織全体の生産性や効率性が向上します。また、一体感によって、社員は仕事に対する満足度や幸福度を高めることができ、より高いパフォーマンスを発揮することができます。
職場の一体感を醸成する方法
ここまでは一体感のある組織の必要性や特徴、メリットについて解説してきました。ここからは、どのように一体感を醸成していくのかについて解説していきます。
社員同士の相互理解を促進する
職場の一体感を醸成するためには、まず社員同士が互いの志向や興味関心を理解することが重要です。社員同士の交流の機会を設けるとよいでしょう。また、より深い相互理解を促進するために、ストレングスファインダーなどの診断ツールを活用したり、モチベーション曲線を描いて価値観や生い立ちを共有したりするのも有効です。キャリアデザイン研修やチームビルディング研修に「お互いを知る時間」を組み込むことでも、相互理解を促進し信頼関係を築くきっかけとなるでしょう。
▼社員同士の相互理解については、こちらの記事で詳しくご覧いただけます。
『相互理解とは?組織における相互理解を促進する施策例を紹介』
共通の目標を設定する
一体感を育むためには、組織全体で共通の目標を設定することが重要です。目標を共有することで、社員は組織の一員としての意識を持ち、目標達成に向けて共に努力するようになります。目標設定は、社員の意見を積極的に聞き取り、全員が納得できるものでなければなりません。共通の目標・指針として企業理念を浸透させるのも有効であり、組織の価値観や方向性を明確にすることで、さらに強い一体感を生み出せます。
社員の共通の目標として、企業理念を設定し、浸透させるのもおすすめです。
企業理念の浸透方法について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
『理念浸透の方法と成功事例に見るポイント』
業務に必要な情報を共有する
一体感を育むためには、組織全体で情報を共有することが重要です。情報共有を適切に行えば、社員がお互いの業務を理解し、協力関係を築きやすくなります。情報共有の方法としては、定期的なミーティングや社内報、イントラネットなど、様々な方法があります。重要なのは、情報がタイムリーに、正確に、そして分かりやすく共有されることです。
社員交流イベントの企画
社員交流イベントは、社員同士の親睦を深め、一体感を醸成する効果的な手段です。イベントを通して、社員は普段の仕事では接することのないメンバーと交流し、互いのことを理解することができます。イベントの内容は、社員の意見を反映し、参加しやすいものにすることが重要です。
フィードバック文化の推進
フィードバックを行う文化が根付いている職場では、社員同士が組織をより良くするために積極的にコミュニケーションを行うことができます。フィードバックは、上司から部下への一方的なものではなく、部下から上司へのフィードバック、同僚同士のフィードバックなど、様々な形で実施されることが重要です。また、ネガティブな指摘だけでなく、ポジティブなフィードバックも積極的に行いましょう。お互いのよい点を伝え合うことで、職場の雰囲気が明るくなり、モチベーション向上にもつながります。フィードバックを通して、社員は自分の強みや弱みを理解し、より良いパフォーマンスを発揮できるようになります。
▼フィードバックについて詳しくは以下の記事をご覧ください。
『フィードバックの意味とは?効果・実施する方法・ポイントをわかりやすく紹介』
職場の一体感を醸成する上での注意点
一体感の醸成は、生産性向上や離職率低下につながりますが、無理に作り出そうとすると逆効果になることもあります。多様な価値観を持つ社員を一つの枠にはめ込もうとすると、個性が押さえつけられ、組織の多様性が失われてしまいます。また、過度な一体感が求められる職場では、無意味な暗黙のルールや非生産的な仕事の進め方がはびこり、かえって組織の生産性が低下する可能性があります。
そのため、一体感を醸成する際は、社員の個性を尊重し、多様性と調和させる工夫が必要です。一体感の醸成を進める際には、次の3つの状態が叶えられているか、チェックしましょう。
- 企業理念や行動指針などの「誰もが守るべき原理原則」が明確で納得されている
- 原理原則を守れば個々の自由が保障されている
- プライベートでは距離を置いたとしても、仕事では率直に意見を言い合える
こういった環境を作り出すことができれば、一体感と多様性が両立した健全な組織づくりにつながります。
一体感を醸成する研修事例
ここからは、実際に一体感を醸成した研修について紹介します。
ミズノ株式会社「Global One HR Conference」事例
ミズノ株式会社は、グローバル事業強化の一環として、本社と海外現法のHRが「One Team」となることを目指し、「Global One HR Conference」を実施しました。実施に至った背景として、 従来のHR間のコミュニケーションは属人的で、リージョン間の連携が不十分だったことや、日本本社主導の情報共有に偏り、海外現法との一体感が不足していた点が挙げられます。
海外子会社のHRマネージャーを日本に招き、3日間の研修を実施しました。研修では、ゲームを通じた相互理解やMVV(Mission、 Vision、 Values)の共有、グローバルプロジェクトの深掘りとアクションプラン策定などを行いました。さらに、社長とのセッションやウェルカムディナーを取り入れ、関係構築を促進しました。
研修後リージョン間のコミュニケーションが活性化し、日本のHRも「グローバルチームの一員」としての意識を持つように変化しました。
当事例の詳細は下記ページよりご覧ください。
ミズノ株式会社Global One HR Conference導入事例
▼事例資料ダウンロード
株式会社ストルアス ポジティブシンキング研修事例
株式会社ストルアスでは、ポジティブに考える習慣をつけることを目的に「ポジティブシンキング研修」を導入しました。当初、長時間の研修に対する懸念の声もありましたが、実施後は「時間が足りなかった」「もっと学びたい」といった前向きな反応が多く寄せられました。
研修では、メンバーが研修内容を日々の業務で活かせるよう、ディスカッションを中心に進行しました。これにより、メンバー同士の関係性が深まり、意見交換が活発になりました。また、「ポジティブシンキング」という言葉が社内の共通言語となり、マネージャーとメンバーの間でも建設的な会話が見られるようになりました。
結果として、チームワークが向上し、実務においても前向きな姿勢が定着しました。株式会社ストルアスでは今後もこの学びを継続し、さらなる組織強化を目指しています。
当事例の詳細は下記ページよりご覧ください。
株式会社ストルアス様ポジティブシンキング研修導入事例
▼事例資料ダウンロード
日東電工株式会社 海外トレーニー研修事例
海外市場での成長を加速させるため、日東電工株式会社が導入したのが「グローバル人財早期育成プログラム」です。語学学習から始まり、2週間の海外短期派遣研修、1年間の海外トレーニー研修へと段階的に成長を促す仕組みを構築しました。
特に、短期派遣研修では、異文化の中で実際に働く経験を通じ、社員の意識変革を促進しました。さらに、外部コーチによるオンラインセッションを活用し、学びを深める環境を整えました。結果として、主体的にキャリアを考える力を養うことができました。受講者からは「海外で働くことの意義を言語化できるようになった」との声もあり、視野の広がりを感じた受講者もいました。また研修を通して、現地社員とオープンに話をすることが重要ということに気づけたという声もありました。個々の挑戦が、組織全体の一体感と成長を生み出しています。
当事例の詳細は下記ページよりご覧ください。
日東電工株式会社 導入事例 体系的にグローバル人財を育成するグローバル人財早期育成プログラム
▼事例資料ダウンロード
まとめ
職場における一体感とは、社員1人1人が共通の目標や価値観を共有し、互いに協力し合い、一体となって仕事に取り組む状態のことです。そのため、一朝一夕に醸成できるものではありません。継続的な努力によって、組織全体で共有される価値観や目標、そして互いに協力し合う文化を育む必要があります。一体感を育むための取り組みは、組織の規模や業種、社員の構成などによって異なります。それぞれの組織に合った方法を見つけることが重要です。
アルーでは、職場の一体感を高めるのに役立つコミュニケーション研修やチームビルディング研修をご提供しています。
アルーが提供するコミュニケーション研修について詳しくは、以下のページをご覧ください。
コミュニケーション研修