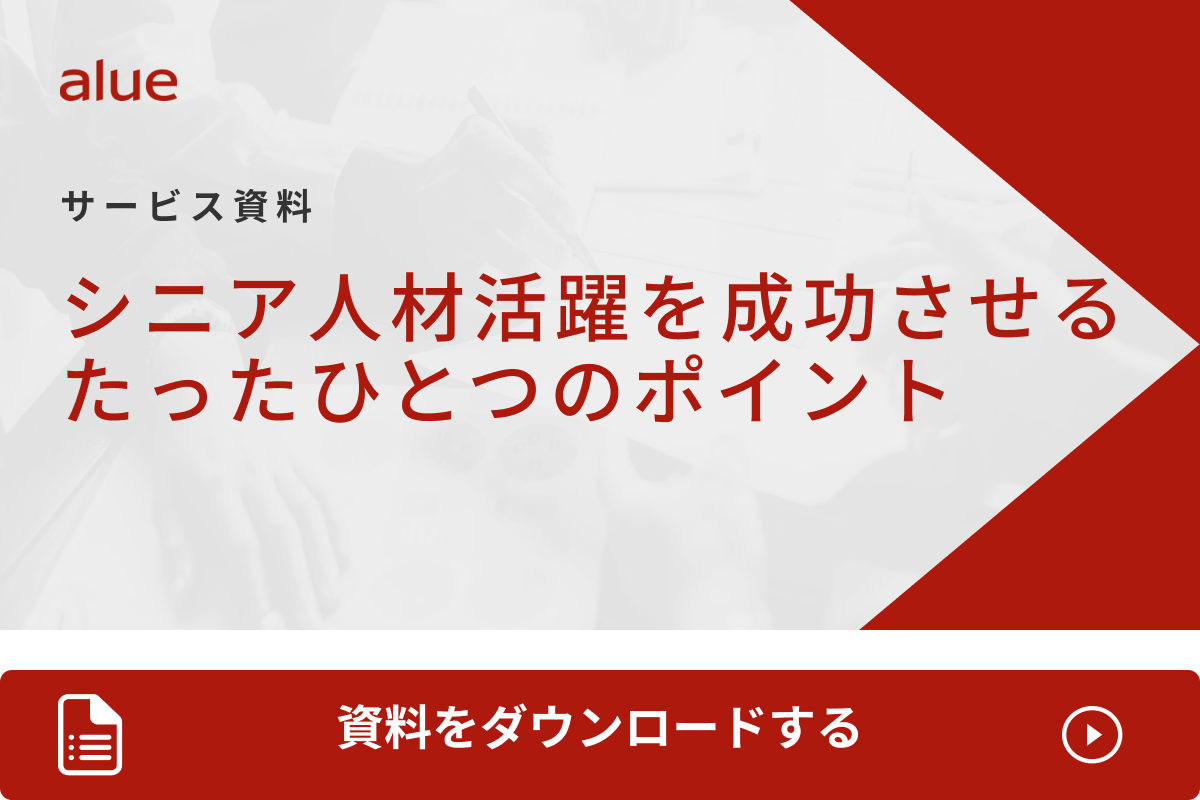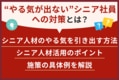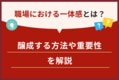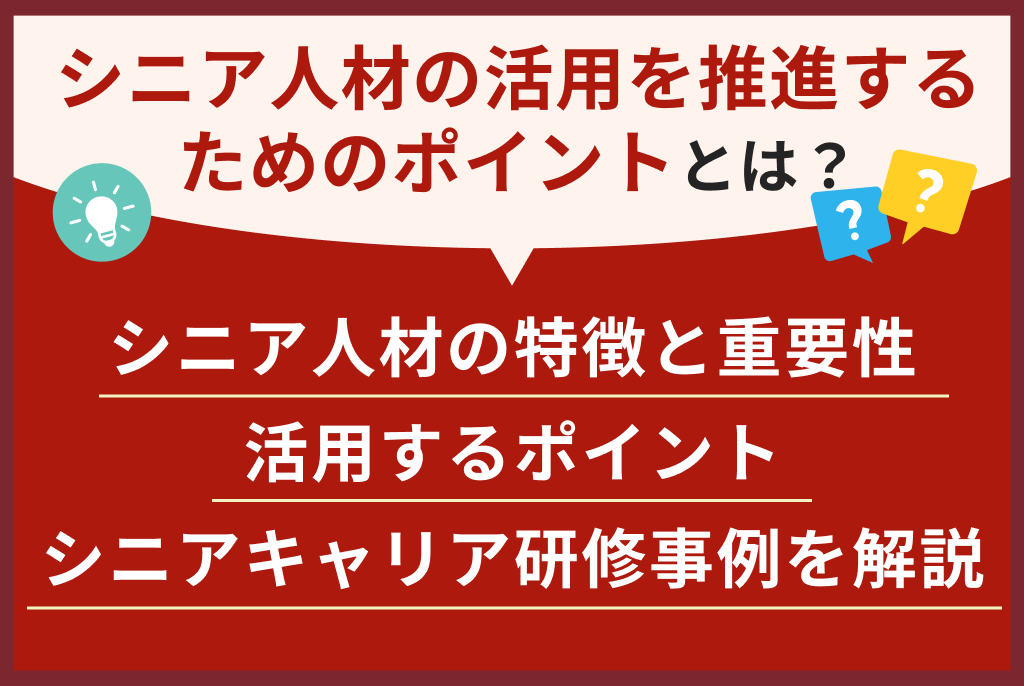
シニア人材の活用を推進するためのポイントとは?シニア人材の特徴と重要性、活用するポイント、シニアキャリア研修事例を解説
日本では少子高齢化が急速に進んでいます。
総務省統計局が公表しているデータでは、2021年の65歳以上の高齢就業者の数は、18年連続で増加し、909万人になりました。65歳~69歳の就業率も10年連続で増加し、2021年に初めて50%を超え、50.3%になりました。70歳以上の就業率も5年連続で増加しています。
この傾向は今後も続くと予想されます。少子高齢化社会という社会問題は、もうずいぶん昔から言われていますが、これを個人レベルで実際に感じられるようなシチュエーションはそうはないかもしれません。
しかし、こうしてデータで見てみると、この少子高齢化という状態は、現実の問題として私たちの目の前に突きつけられていることがわかります。そして、この少子高齢化社会の中、企業にとって切実な問題となっているのが、現場におけるシニア世代の活用です。
本記事では、シニア世代のキャリアと企業のあり方をテーマに、シニア人材の特徴と重要性、活用するポイント、シニアキャリア研修事例を解説します。
▼社員のキャリア形成のために合わせて知りたい研修3選

目次[非表示]
シニア人材の重要性
急速に進む高齢化社会の日本において、シニア人材の活用は喫緊の課題です。今後ますますシニア人材が増えていく一方で、内閣府『令和3年版高齢社会白書(全体版)』によると、現在収入を得ている60歳以上の人材の約90%が、「70歳くらいまで、もしくはそれ以上(働きたいと考えている)」と回答しています。
つまり、シニア人材の就業意欲は高いといえます。シニア人材は、これまでの社会人人生で培ってきたノウハウや技術、幅広い人脈、高いコミュニケーション能力、多様な知見を持っています。就業意欲の高い、優秀なシニア人材を活用できれば、企業に良い影響をもたらしてくれることが期待されます。
ダイバーシティ&インクルージョンの推進による全員活躍が求められている現代社会において、企業の持続可能性を高めるためには、シニア人材の活躍は必要不可欠です。
シニア世代の3つの特徴

シニア世代の年齢の定義は、国連やWHO(世界保険機構)で異なります(国連は60才、WHOは65才)。企業の中でもその定義はまちまちですが、定年を迎えて継続雇用契約や再雇用契約をおこなった人たちで、主に60才以上をシニア世代と定義しているようです。
昔のテレビドラマでは、会社を定年退職した父親が庭先で盆栽をいじる姿が、リタイアしたシニア世代の象徴的な場面として描かれていました。しかし、今は時代も変わりました。仕事も趣味ももっとアクティブになり、社会との結びつきも維持しながら働き続けるシニア世代の姿が主流になりました。
この仕事を続ける「シニア世代」の特徴をあげるとしたら、主に以下の3つになります。
<仕事を続けるシニア世代の特徴>
- これまで長い間、会社に貢献し今は仕事に一区切りがついている
- 近年の技術の進歩や、働きかたの多様化に対して自らを適合させなければならない
- 健康面やその他生活の現状維持にケアが必要となるこれまで長い間、会社に貢献し今は仕事に一区切りがついている
これまで長い間、会社に貢献し今は仕事に一区切りがついている
再雇用対象となるシニア世代は、会社で働き始めて30年以上の大ベテランであることが多く、業務知識や技術だけでなく、会社の良かったころや悪かったころの会社の歴史まで知っている人たちです。
しかし、これまでの経験からより専門的な役割で仕事を続けている人は少なく、多くのシニア世代は一般社員と同じ仕事をしています。すこし前までは管理職だった人も今は役職定年を迎えて一般社員に戻っています。会社との雇用契約もこれまでとは異なる新たな条件で再雇用される人もいれば、同じ条件でも期限付きで雇用継続の契約をする人もいます。そしてこのタイミングで新たな部署に異動し、再スタートを切る人も少なくありません。
雇用契約の一区切りだけでなく、仕事内容自体もこれまでとは変わって一区切りがついた世代といえます。
近年の技術の進歩や、働きかたの多様化に対して自らを適合させなければならない
長い間、ひたすら同じ部署で同じ仕事をしてきた人もいます。そういった人たちは、ITリテラシーや仕事に対する価値観が、若い世代に比べて偏りが大きい傾向があります。そんな彼らにとっては、IT技術の進歩に応じて仕事の手順が変わることや、これまではタブーとされていたものが認められるようになることは、とてもストレスに感じることがあります。
しかし「自分はこのやり方しか知らない」、「その考え方は受け入れられない」と突っぱねていては、あっという間に自分の居場所がなくなります。これからも働き続けるのであれば、自身のスキルや考えかたの見直しが必要な世代といえます。
健康や生活面の現状維持にケアが必要となる
やはり年齢による衰えや病気のリスクは年々高まり、健康面のケアがより大切になっています。本人はまだまだ若い、まだまだ大丈夫と思っていても、ある日、重大な病気が見つかり、即入院という事態になっても決して不思議ではありません。また、特に病気などになっていなくても、過労による集中力の低下や、モチベーションの減退などに陥ったとき、若いころに比べれば、その復調に時間が掛かるようになっています。
「シニア人材の活用」が難しい理由
少子高齢化社会が進む中、企業は慢性的な人手不足に陥っています。特に若い年齢層の人材不足は単純な労働力不足だけでなく、将来のリーダー候補を育てられないという会社の生命線にも関わる問題にもつながります。
そんな中、これとは別で向き合うべき難題を企業は抱えています。
それが本記事のテーマである「シニア人材の活用」です。単純に考えれば、若い世代が足りないことで起きる労働力不足なら、シニア人材を活用することで解消できそうな気もします。そうなれば一石二鳥なのですが、この問題はそう簡単なものではありません。このシニア人材の活用が難しい理由は主に4つあります。
シニア人材に担当してもらうポジションがない
そもそも10年後、20年後の会社を支えていくという役割をシニア人材が担うことは出来ません。その前提を考えたとき、最初にしなければならないことは、これまでシニア世代が担当していた仕事を次の世代が引き継ぐということです。
しかし、その引き継ぎをおこなえば、シニア人材のやることがなくなってしまい、今度はシニア人材のための新しい仕事、新しいポジションが必要になります。ここでシニア人材のために新たな仕事、新たなポジションを作れたとしても、会社での仕事というものは必ず複数の人が関わります。新たな仕事の流れは、そこに関係するシニア人材以外の人たちの新たな負荷となります。
仮に一人だけでできるような仕事があったとしても、それはシニア人材の孤立というまた別の問題につながります。
シニア人材が今の会社で働き続けるためには、どうしても全体の人員体制から調整が必要となってしまいます。
シニア人材のモチベーションをあげなければならない
会社にもよりますが、たいていのシニア人材は役職定年を迎えたタイミングや、再雇用契約をしたタイミングで、給与金額がガクッと下がります。またそれらと同時に、仕事内容や部署の変化、人生の節目ということでこれからはプライベートも考えたい欲求が生じるなど、さまざまな理由で仕事へのモチベーションが低下します。
別に仕事へのモチベーションなどなくても、ただ言われた作業をやってくれれば良いという会社であれば、それでも構いませんが、これは「シニア人材の活用」というよりも、「シニア人材の一時的な保護」です。
ただ言われたままやる単純作業がなくなった時、シニア人材も会社もお互いに困ることになります。また他の社員たちからどう見られるかも考えれば、シニア人材でもやはり仕事には高いモチベーションをもって取り組んでもらいたいものです。
若い世代の社員とのコミュニケーションに苦戦することがある
自分の培ってきた知見やノウハウ、人脈を若い世代に伝えたい、と思うシニア人材は非常に多いです。もちろんそれが、若い世代の助けとなることもあります。ですが、勝手な思い込みで一方的なコミュニケーションをしてしまうと、若い世代の社員にとって大きなストレスとなる場合があります。
また、上司が年下の場合には、お互いに遠慮しあいながらコミュニケーションを取ろうとして、良い関係が築けず、チームの生産性を下げてしまうこともあります。
▼年上部下を味方にするマネジメント法はこちらの記事で詳しく知っていただけます。
年上部下を味方にするマネジメント法とは?年上部下との接し方でリーダーが心掛けるべき3つのポイント
シニア人材の体力や集中力の低下を周りも理解しなければならない
年齢からくる衰えなどは、本人たちにもどうしようもないものがあります。ここで無理をして体調を壊したら働く意味がないので、シニア人材は自分自身のコンディションと相談しながら働き方を調整する必要があります。
そしてここで大事なのが、そのシニア人材の状況をシニア世代以外の人も理解することです。この理解が不足していると、若い世代から見れば、自分たちばかりが忙しくシニア人材は気楽という印象を持つことになったり、時にはシニア人材が出来ない分を、自分たちがカバーしなければならないと考え、シニア人材への直接的な不満になる場合があります。
シニア人材を受け持つ管理職は、シニア人材だけでなく、一緒に働く若手の気持ちにも配慮する必要があります。
シニア人材が活躍できる環境をつくるための新たな考え方
本当の意味での「シニア人材の活用」とは、シニア人材がイキイキと活躍しており、周りの人たちもそこから何らかの恩恵を受けている状態です。これはシニア人材が安心し、やりがいをもって働ける職場環境の形成とも言い換えられます。
この実現のために、シニア人材と会社はこれまでの認識を改め、新しい考えかたを持たなくてはなりません。具体的に認識すべきは、以下の2つです。
シニア人材と企業が共有できる目的や目標を持つ

明確な目的や目標が見出せないままの雇用延長、再雇用契約は、本人や会社の両方にとって良くない結果になります。シニア人材の気持ちとしては、一区切りつけて他のことをしたいと思っても、生活のためには働き続けなければならないというのが本音で、仕方なく雇用延長をしているのかもしれません。
しかし、仕事は楽なものばかりではなく、また常にうまくいくものでもありません。とりあえず続けた仕事において、大変な状況や失敗に直面した時、「本当はこんなことしたくない」という想いがよぎってしまったら、もうその仕事からはストレスしか感じないようになります。
溜まったストレスは一時的に発散できるかもしれません。しかし、ストレスを受けてはそれを発散するという日々の繰り返しで貴重な人生の残り時間を費やすことは、時間の浪費をこえて人生の浪費と言っても言い過ぎではありません。
また、企業側からしても、ただただ我慢しながら仕事をする人からは、文句は出てきても建設的な意見やアイデアが出てくることはないと思っています。シニア人材に対して最初はこれまでの貢献なども評価し、好意的な再雇用という形をとったとしても、日に日にその判断にも疑問を持つようになり、最後は悪い印象ばかりが先行するようになってしまいます。
こうならないためにも、雇用継続、再雇用をする際には、その目的や働いていく中での目標をなによりも早く見つけることが大切です。
「シニア人材の活用」の正解は誰も持っていない
そしてもう一つ認識すべきことは、
- シニア人材が安心して会社に所属できる環境
- 望めばまだまだ活躍できる環境
- 人生とのバランスを保ちながら働き続けられる環境
これらが実現した環境はまだどこにもなく、誰も経験したことがない未体験ゾーンであるという認識です。「シニア人材の活用」とは、日本全体で今まさに始まった段階であり、どの企業も試行錯誤で取り組んでいます。
過去のコロナ禍による政府の対応で、多くのコメンテーターが「誰も正解を知らないのだから、試行錯誤をしていくしかない」と述べていました。少子高齢化という社会の問題もこれと同じで、シニア人材の活用はこの一部です。今向き合っている問題は、日本全体で各企業が現在進行形で初めて経験しているものばかりです。
シニア人材の活用を推進するためのポイント
ここからは、シニア人材の活躍を推進するためにできることを3つご紹介します。
シニア人材の望む働き方を理解する
雇用を延長したり、再雇用をするといっても雇用形態にはさまざまな種類があります。役職はどうするのか、正社員のままなのか、あるいは契約社員やアルバイト契約にするのか、など、多様な選択肢のなかから、シニア人材が希望する働き方を選択する必要があります。
シニア人材が希望する働き方と企業の事情の両方を踏まえて、双方が納得できる働き方をみつけることができれば、シニア人材がイキイキと働け、企業にもより良い影響を与えてくれることが期待できます。
また、報酬が公正であることも重要です。シニア人材が担う仕事内容や契約形態によって、不公平感が生じないように、報酬体系や福利厚生を適切に、分かりやすく整備することが求められます。
風通しの良い職場風土をつくる
シニア人材の活用は、どの企業も試行錯誤で進めています。そんな正解の分からない状況で、シニア人材もしくは会社のどちらか一方だけが頑張ってもうまくはいきません。
そもそも、お互いのためにどう役に立てるかを考えようとしたとき、意見交換もしないまま、どちらか一方が思いついたアイデアを採用しても、たいていは的外れか押し付けにしかなりません。
- どうすれば会社の役に立てるのか?
- どうすればシニア人材が働きやすくなるのか?
お互いにお互いのことを考えれば、きっとこの問題の答えも見えてきます。またそれは、特別な研修や会議だけでなく、日々の仕事や会話の中にもそのヒントはあるはずです。
企業とシニア人材が、あるいは若い世代の社員とシニア人材が、配慮はしつつも遠慮はしない会話ができる環境をつくることが重要です。
キャリア研修を実施する
シニア人材のモチベーションが低いという課題に対する有効な施策のひとつが、シニア世代向けのキャリア研修や、研修後の定期的なキャリアコンサルです。
シニア世代向けのキャリア研修には、大きく分けて、シニア世代のお金に関する知識をインプットするものと、今後のキャリアを再構築するものの2種類があります。「シニア人材にもっと働いてほしい」と仕事面にのみ焦点を当てた研修を実施する企業も多いですが、実はプライベートを充実させることは、仕事を充実させることにもつながります。自社のシニア人材の現状を踏まえて、適切な研修を実施しましょう。
また、研修後のキャリアコンサルは、専門のキャリアコンサルをつけることが出来なければ、会社の上司でも対応可能です。シニア世代の働く目的や目標を出来るだけはやく見つけて、仕事のモチベーションに反映させていくことが大切です。
シニア人材活躍研修ならアルーにお任せください
シニア人材活躍推進なら、人材育成のプロフェッショナルであるアルーへお任せください。
アルーでは、これまでに幅広い業種・業界でシニア人材の活躍を支援する人材育成施策を支援してまいりました。例えば、シニア人材のキャリア形成を促し、シニア人材のモチベーションを上げる研修プログラムも豊富です。また、お客様が抱えている課題に合わせて、柔軟に研修プログラムをカスタマイズすることもできます。
ここからは、アルーがご用意しているシニア人材のキャリア形成に役立つ研修プログラムの中から、厳選して2つの事例をご紹介します。
55歳キャリアデザイン研修
組織に“ぶら下がる”意識の50代社員が増えている課題に対して、あらためて組織貢献のあり方と働きがいを見つけることをゴールとして実施した4時間半の研修事例です。
自分の根底にある“価値観”を言語化することで、仕事のやりがいを明確にし、自身のキャリア戦略を立てることにつなげました。
▼テーマ
55歳キャリアデザイン研修
▼ねらい
- キャリアは自分で創造していけるという自己効力感を持つ
- 自分が何を目指すのか、広い視野で考えキャリアを描く
- あらためて組織貢献のあり方と働きがいを見つける
▼内容
①オリエンテーション
研修のねらいや会社の意図を説明し、なぜ自分が研修に参加するのかを納得してもらいます。
②環境変化とキャリア自律
外部環境の変化と会社が置かれている現状を改めて理解することを通じて健全な危機意識を醸成し、シニア人材であってもキャリア自律が求められることを理解します。
③スキルの棚卸
これまで得てきたスキルの棚卸しをおこない、“肩書き”ではない、自分自身がもつリソースを知ります。
④バリューワードによる価値観の確認
自分が大切にしている価値観をあらためて言語化することで、仕事の“やりがい”を明確にします。
⑤キャリアプランニング
今後定年までにやりたいことをまとめ、自分のキャリア戦略を練ります。また、そのためのスモールステップを決め、明日からの行動変容を促します。
60歳社員『キャリア』研修
再雇用制度の対象となる60歳社員のモチベーションが低いという課題に対して、今後主体的に活躍するためにマインドを“リセット”することをゴールとして実施した、インターバル期間を挟んだ2日間の研修事例です。
社会人としての自分だけでなく、個人としての自分も取り上げ、個人としての自分を充実させることで仕事も楽しくすることができることに気づいていただき、今後の行動計画をつくることにつなげました。
▼テーマ
60歳キャリアデザイン研修
▼ねらい
- 60歳を迎えたあとの再雇用を、新たなキャリアの起点として捉えられるようになる
- チェックこれまでに培った経験やスキルを発揮し、今後主体的に活躍するためにマインドをリセットする
▼内容
①オリエンテーション
研修のねらいや会社の意図を説明し、なぜ自分が研修に参加するのかを納得してもらいます。また、自己紹介などを通じて意見交換しやすい場を醸成します。
②これからを考える視点
60歳以降のリアルとして、健康やお金について学び、何かを選択したときのメリット・デメリットについて考えます。
③自分を語り、再発見する
これまでの自分の歩みについて語り、ポジティブなフィードバックをし合うことで、自分がもつキャリア資産を認識します。
④エルダーとしてのテーマを策定する
定年後の社会人としてのテーマを設定するだけでなく、個人としての自分のテーマを設定することで、会社以外に自分を活かせる場所を見出します。個人としてのテーマも見つけることで、視野を広げて今後の自分の活躍について考えることができます。
⑤インターバル期間
エルダーとしてのテーマをさらに考えます。また、実行に移せる受講者については、実際に行動をしてみます。
⑥インターバル期間の共有
インターバル期間に取り組んだことについて共有し合い、ポジティブにフィードバックし合います。このワークを通じて、自分が大切にしている価値観を実感し、プライベートで取り組んだことが仕事にもつなげられることに気づきます。
⑦今後のキャリア
今後の行動計画を明確にし、一歩踏み出す後押しをします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
本記事では、シニア世代のキャリアと企業のあり方をテーマに、シニア人材の特徴と重要性、活用するポイント、シニアキャリア研修事例を解説しました。
シニア人材がイキイキと働くことができれば、企業も一緒に元気になれます。
正解のわからないシニア人材の活用について、自社内でオープンに議論し、自社に適切な施策を検討していきましょう。
また、アルーでは施策の検討段階からお客様に伴走いたします。
シニア人材の活用にお悩みの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。