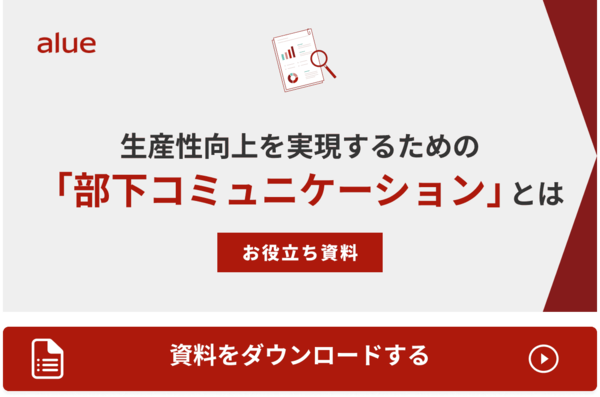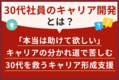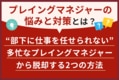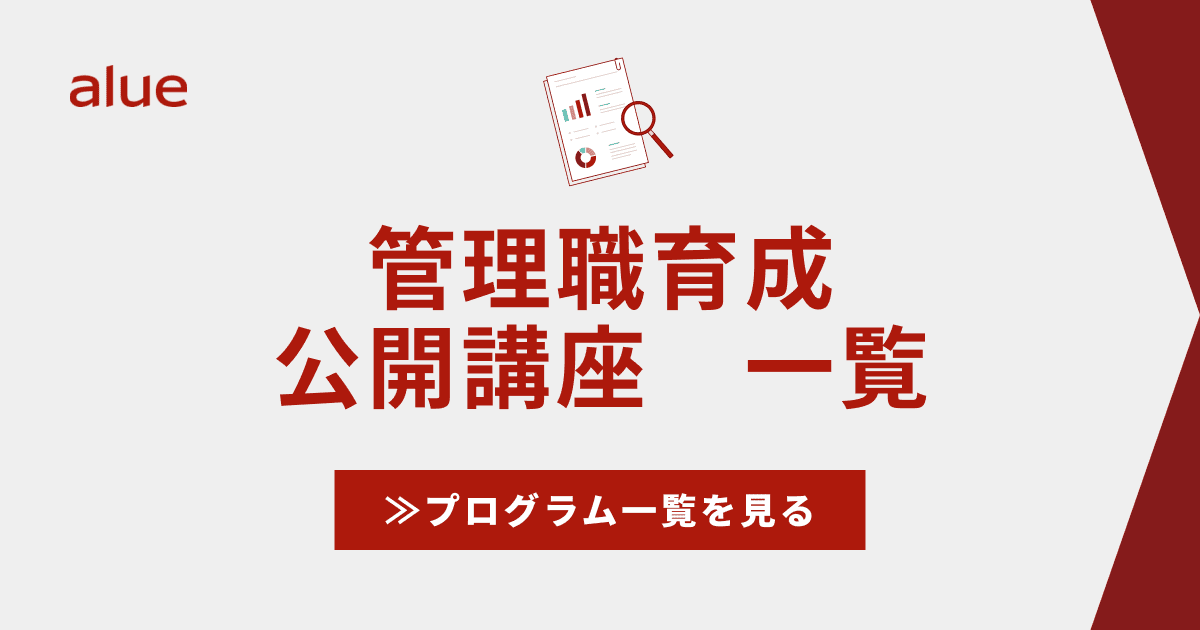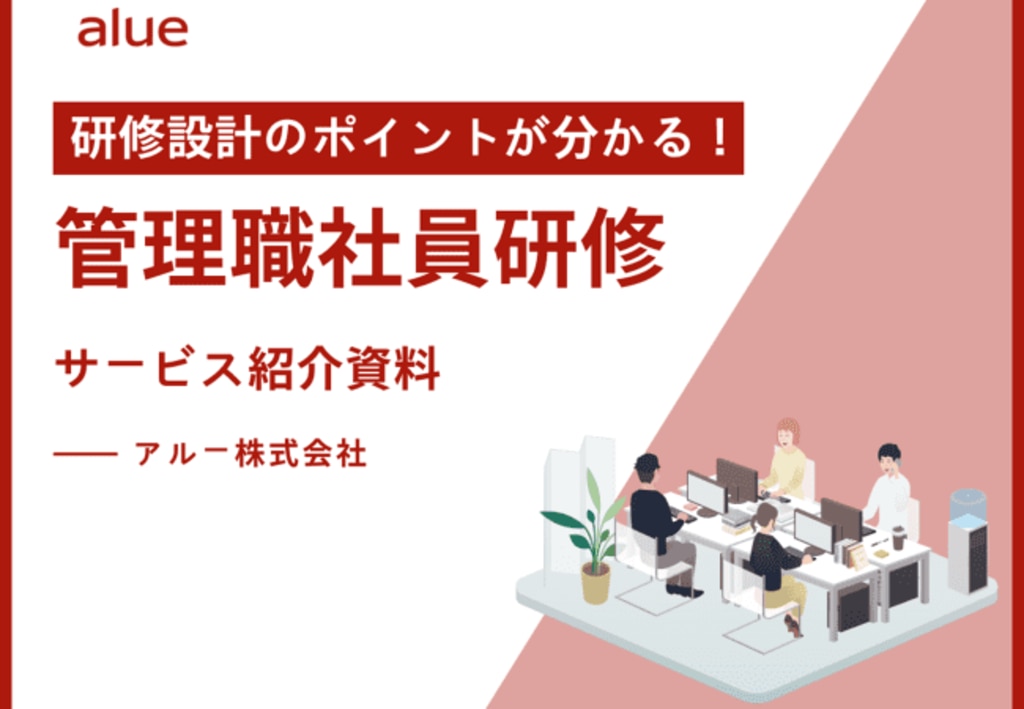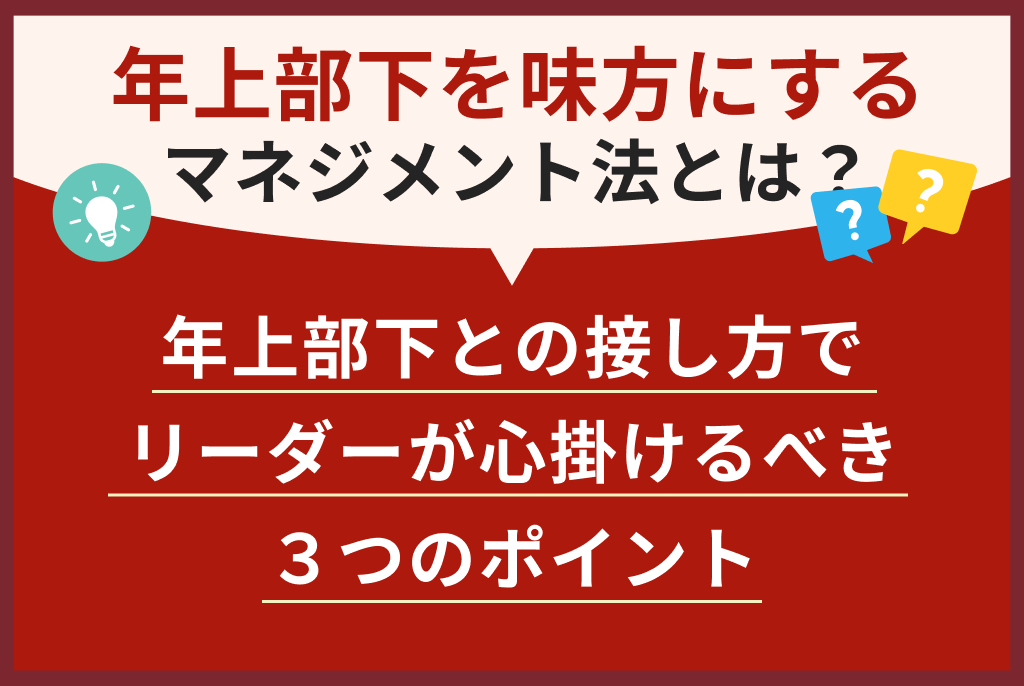
年上部下を味方にするマネジメント法とは?年上部下との接し方でリーダーが心掛けるべき3つのポイント
1990年代の前半、バブルが崩壊し、企業は事業のやり方や会社の体制について、大きな見直しをしなければならない状況に陥りました。そしてリストラや終身雇用の崩壊など、日本全体が不景気になっただけではなく、働き方のかたちまでが変わってしまう事態となりました。
この時に起きた会社の変化のひとつに、年功序列の撤廃がありました。
それまでは組織のなかで役職につく人は、勤続年数や年齢が評価の基準となっていました。その基準が会社での成果を重視するものに変化し、その結果、成果を出した人や適性があると判断された人は、年齢が若くても管理職につくようになりました。
そして現在、年上の部下を持つ管理職やリーダーの存在も当たり前になりました。
本記事のテーマは、年上の部下を持つ管理職・リーダーの悩みです。年上の部下とのコミュニケーションや信頼関係を築くために、どのような点に注意すべきかを解説します。
▼人材育成マネジメント力向上に役立つ資料3選

目次[非表示]
管理職やリーダーを悩ませる、扱いにくい年上部下の傾向 〜あなたの身近にもいるちょっと困った◯◯さん〜
勤続年数も長く自分よりも年齢が上の部下だとしても、すべての人が気難しかったり、常にコミュニケーションに気を使うわけではありません。これまで培った経験や知識も豊富で、全体の中でどんな動き方をすれば良いかなども考えながら動いてくれるような、チームの中でとても頼りになる人もたくさんいます。しかし残念ながら、なかには、チーム内でも扱いに困るような悩みの種になっている人もいます。ここではそんな年上部下の傾向をいくつか紹介します。
仕事は嫌がらず引き受けてくれるが、自身のこだわりが強い◯◯さん
どちらかと言えば職人タイプの人に多く、仕事自体は難易度の高いものでも嫌がらず引き受けてくれます。お願いする仕事のなかには、その人しか経験したことがないような仕事が多々あり、依頼する側としても、この人以外には頼めないというケースもよくあります。ここまでなら、もちろん頼れる存在といえるのですが、こういった人たちの中には、自身のこだわりが強く、たとえお客様からの要望でも受け入れてくれない人がいます。
たとえば、お客様から
「多少の間違えはあっても良いので短期間でやって欲しい」
「ここは後で変更するので、今は一旦このカタチでやって欲しい」
などの要望があった場合です。
その要望が他との兼ね合いからのものだとわかっていても、自身のやり方と合わないという理由で、承知してくれません。
ばりばりやってくれるが、わがままが目立つ◯◯さん

仕事の調整から、自分自身も手を動かし、場合によっては周りの人にも指示を出してくれるような頼れる存在です。仕事の一部を切り出してやってもらうのではなく、最初から最後までをまるまるお願いできるので、うまく力を発揮してくれるときは、本当に助かるのですが、それがうまく噛み合わないときは、一番やっかいな存在になることもあります。
このタイプの人がいるチームで一番困るケースは、その人が自身の判断で勝手にメンバーに指示を出してしまい、その指示がチームリーダーや上司のものと異なる場合です。うっかり間違った指示をしてしまうときはしょうがないのですが、リーダーや上司の出した指示と違うとわかっていても、自分のわがままから異なる指示をあえて出すことがあります。チームとしては2人のリーダーがいるような状態であり、現場のメンバーはどちらの指示に従えば良いのか困ってしまいます。
もくもくとやってくれるが、不注意や間違いが多い◯◯さん
どちらかと言えば静かなタイプで仕事をもくもくとやってくれます。上司であるこちらの立場も理解しつつ、指示されたとおり忠実に仕事をしてくれます。ふだんから自己主張してくることも少ないので、リーダーシップが強い上司であれば、チームの中に一番居てもらいたい存在です。
しかし、このタイプの人たちは、コミュニケーションスキルが低い傾向があります。
周囲の人たちと話をせずに、自分ひとりで作業をすることを好むので、ちょっとした連絡を聞き漏らしていたり、周りの人が失敗した事例も知らないことがあります。周りから得る情報が少ないため、それを参考にして自身でも気をつけるようなことが出来ず、不注意による間違いなどもなかなか減りません。また、作業内容が曖昧でどうすれば良いかわからないときも、他の人に確認しないまま自身の判断で作業を進めてしまうこともあります。
年上部下とのコミュニケーションが難しいと感じる3つの理由
会社にはいろいろなタイプの人がいるため、「この人とのコミュニケーションは苦手だな」と感じても、その理由はさまざまです。ここではさまざまな原因の中でも年上の部下でよく見られるものについて紹介します。
年上部下がこちらを下に見てくる
年上部下との会話が苦手と感じる一番の原因は、上司やリーダーであるこちらを下に見てくることです。こちらを下に見ていることは、日頃の会話のはしばしや、指示に対するリアクションなどから自然と伝わってきます。年上部下からすれば、年齢も経験も自分が上なのは事実であり、また日々の意見としても、間違ったことは言ってはいないという自覚があります。自分なりに正当性を感じているので、この状態にある年上部下に意識の変化を求めるのは難しいものがあります。
年上部下が守りに入っている
年配の人に見られる傾向ですが、経験が多いことが逆にあだとなり、仕事で自分から「わからない」と言いづらいと感じている人がいます。このように感じている人は「わからない」と言わなくても済むように、自分がわかる作業しかやろうとしません。
また、若い世代の人たちに、これまでの自分のポジションが奪われつつあることも感じており、「下手な失敗はできない」「自分が持つ知識を簡単に明け渡してはいけない」と考え、あえて消極的な姿勢を取り自分の立場を守ろうとします。
年上部下に対するこちらの期待が過大
チームリーダーや上司は、年上で経験も多い人であれば、その能力や経験をチームの中でフルに活用したいと当然考えます 。しかし、その気持ちが強すぎると、その年上の部下の経験や能力を正確に把握する前に仕事を振ってしまうことがあります。自分よりも経験年数が長いから当然できるだろうと思って、確認もせずに仕事をお願いしてしまうと、能力と仕事内容のミスマッチから、期待していた結果にならないことがあります。
年上部下との信頼関係を構築するためにリーダーが心掛けるべき3つのポイント
年上部下とのコミュニケーションをより良くするためには双方の努力が必要です。しかし、相手の考え方をこちらが変えようと思っても、そのとおりにはなかなかできないものです。ここで大切なことは、まずはこちらから年上部下に対してどう接するべきかを理解し、それを実践することが大切です。
ポイント1:年長者へのリスペクトを忘れない
会社でのポジションに違いはあっても、相手が自分より年長者であり、人生の先輩であることには変わりません。しかし、普段の仕事では、メンバーの年齢をいちいち気にすることもなく、チームでの指示命令系統から、年長者へのリスペクトも忘れがちになってしまいます。そして、こちら側の年長者へのリスペクト意識の低さを、年上の部下は敏感に感じ取ります。年上の部下がそれを不満に感じるかどうかは、その人の性格によりますが、少なくともリスペクトされていないと感じる相手に、自分から何か助けてあげようとは思いません。また、年長者へのリスペクトも意識できないような管理職やリーダーは、メンバーやお客様への配慮などもできない能力が低い人と考えることもできます 。
ポイント2:知識を人質に取られない
仕事では年上の部下であるその人しか知らないことや、その人しか経験したことがないものがたくさんあります。仕事のやり方や詳細な知識をメンバー全員で常に共有することは不可能であり、一部の人しか知らないという状態になることはやむをえません。
ここで問題となるのは、年上の部下しか出来ない仕事があるとき、こちらでは手が出せないという理由から、仕事全体の主導権までその人に握られてしまうことです。
これは本来、会社として持っているべき、仕事のノウハウに関する知識を人質に取られていることと同じです。この人しか知らない、この人しか出来ないというものがあれば、普段からそれらについて、他の人でも知っている、他の人でも出来る状態にする意識と取り組みが必要です。
ポイント3:お互いにとって何がベストであるかを共有する
リーダーや管理職には、チーム全体を運営管理し、日々の仕事でよりよい成果を出すという目的があります。この仕事の目的と比べれば、相手が年上という理由で、話しかけたり頼みごとをする際に躊躇してしまうことなどはとても些細なことです。また、この仕事の目的、チームの目的は俯瞰して見れば、その年上の部下の人自身の目的でもあります。この全体の目的についてちゃんと話をすれば年上の部下もそれについて理解してくれます。
また、こちらの要望を一方的に伝えるだけでなく、その人のやりたいこと、この先どうなりたいのかという、相手の要望をしっかり聞き入れることが大切です。お互いの目的を理解し、お互いにとって何がベストであるかを共有することができれば、それは信頼関係を築く第一歩になります。
相手が年上だからといって難しく考えすぎず、相手を理解するというスタンスで日々のコミュニケーションが出来れば、年上の部下はいつしか誰よりも頼りになる強力なパートナーになってくれることでしょう。
年上部下とのコミュニケーションや指導に遠慮してしまうときには
実際の現場では、年上の部下に、上司としてコミュニケーションを取らなくてはいけないと頭では分かってはいても、相手への指摘や指導に躊躇することがあります。とくに、年上部下との年齢がかなり離れている場合、指導を躊躇する方は多いです。このような場合、心理的な要因もあれば、コミュニケーションや指導方法が分からない、というスキル的な要因もあります。
年下の上司が「管理職としての役割」を果たすためには、自分のあり方を見直したり、コミュニケーションや指導方法をトレーニングする場を用意することも必要です。
▼管理職の役割とスキルの全体マップについては、以下の資料で詳しく解説しています。
『管理職の役割とスキルの全体マップ 』
アルーが支援した年上部下の力を最大限引き出すマネジメント研修の成功事例
人材育成を手掛けているアルーでは、これまでにさまざまな企業で年上部下の力を最大限引き出すマネジメント研修を支援してまいりました。ここではその中から特に参考となる事例を1つピックアップして紹介します。
年上部下の力を最大限引き出すマネジメントの具体的な成功事例を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
製造業界G社様事例
製造業界G社様では、組織の活性化やイノベーション創出に向けて、ダイバーシティ&インクルージョンを実現できる組織風土醸成を目指していました。その過程で、年上部下に対するマネジメントに苦慮している管理職が一定数存在しており、人事部としてこの組織課題に手を打つべく、管理職の方を対象に研修を実施しました。
本研修は、
自分の無意識の思い込みに気づく
ケース演習やロールプレイングを通じて、年上部下をマネジメントする場面でいつもやりがちなコミュニケーションを自覚する
これまでと違ったコミュニケーション手法を習得する
の流れで実施し、研修後は、管理職の方が相手とのコミュニケーションを試行錯誤するようになったといった効果が上がっています。
本研修の詳細は、以下のページで詳しく知っていただけます。
年上部下の力を最大限引き出すマネジメント研修施策例
▼事例資料をダウンロードする
年上部下の力を最大限引き出すマネジメントならアルーにお任せください
年上部下の力を最大限引き出すマネジメントのことなら、ぜひアルーへお任せください。
アルーは人材育成を手掛けている企業です。豊富な研修ノウハウを活かし、これまでに幅広い業界で年上部下の力を最大限引き出すマネジメントスキルを向上させる研修を実施してまいりました。
ここからは、アルーの提供する人材育成マネジメント研修の特徴を紹介します。
人材育成マネジメントのポイントをおさえた研修を行います
アルーでは、年上部下の力を最大限引き出すマネジメントのポイントをおさえた研修を実施します。
アルーは年間80,000人以上、累計約1,500社の企業へ人材育成の支援を実施しています。人材育成支援のノウハウが豊富なため、年上部下の力を最大限引き出すマネジメントのポイントをおさえた研修を実施することが可能です。丁寧なヒアリングと専門性を活かしたカスタマイズを通じて、それぞれの企業にとって最適な研修を提案します。
研修後の行動変容をサポートします
アルーでは、研修後の行動変容をサポートすることが特徴です。
研修にありがちな失敗として、「研修を実施したことに満足して終わってしまう」ということが挙げられます。せっかく手の込んだ研修を実施しても、実施後の行動変容が見られなければ研修の効果は得られません。
アルーでは、研修後の行動変容も徹底的にサポートします。例えば、研修後に現場での実践をサポートするチェックシートを活用することが可能です。また、研修後に上司と1on1の機会を設けるなど、必要に応じて研修参加者以外も巻き込んだ施策を提案いたします。
研修結果の見える化を支援します
アルーでは、研修結果の見える化を支援するツールである「Compath」を提供しています。
Compathは、研修前後で参加者にどのような能力の伸びがあったのかをグラフなどで見える化するツールです。能力の変化を直感的に把握できるため、研修の効果測定が抜群に楽になります。またCompathを用いれば、研修成果がひと目で分かるため、研修でどのような成果が上がったのかを経営層へ説明する際もスムーズです。
アルーの提供している行動変容支援ツール「Compath」は、以下のページから詳しくご覧ください。
Compath(行動変容にこだわる職場学習支援システム)
▼サービス資料をダウンロードする
まとめ
年上部下を味方にするマネジメントについて、年上の部下とのコミュニケーションや信頼関係を築くために、どのような点に注意すべきかを徹底的に解説しました。
多様な人材の活躍が求められるようになり、管理職やリーダーが悩む場面が増えています。自分で何とかしてしまう人もいますが、会社が管理職やリーダーのスキルを高めるサポートをすることが、これまで以上に必要になっています。
ぜひこの記事を参考に年上部下を味方にするマネジメントへの理解を深め、企業での人材育成を効果的に進めていきましょう。