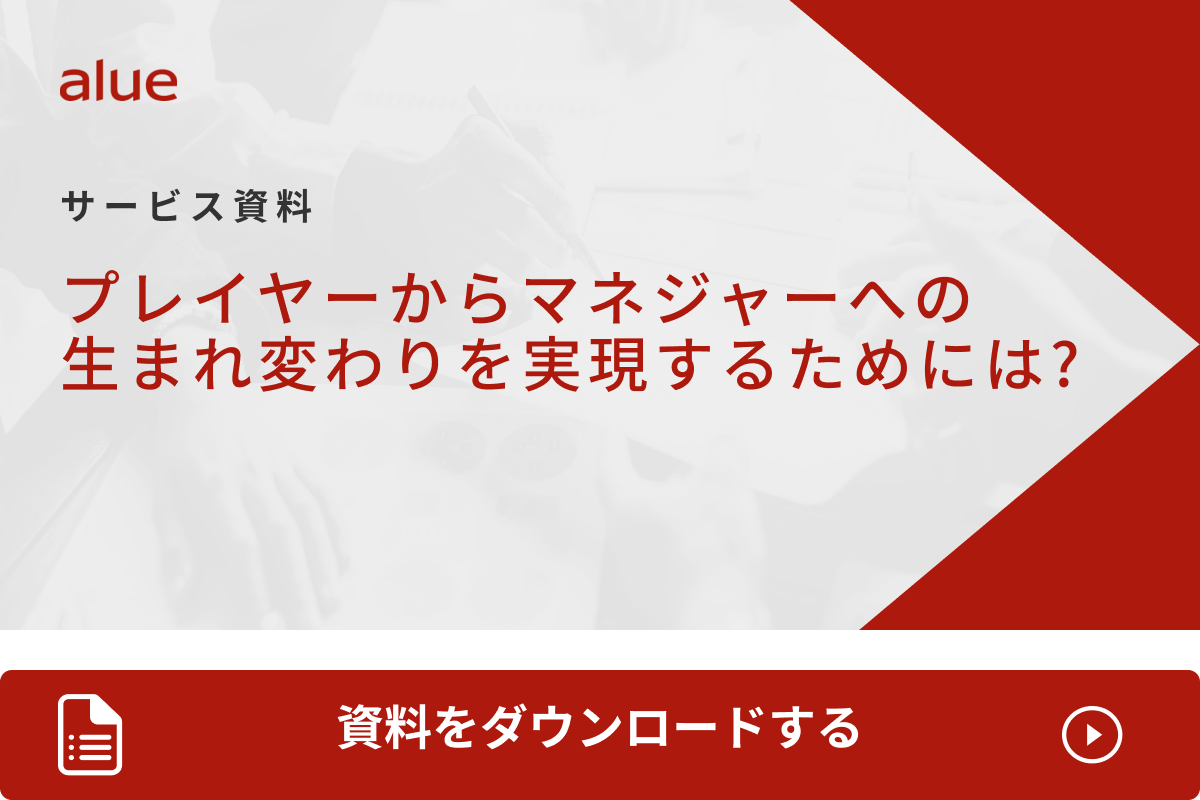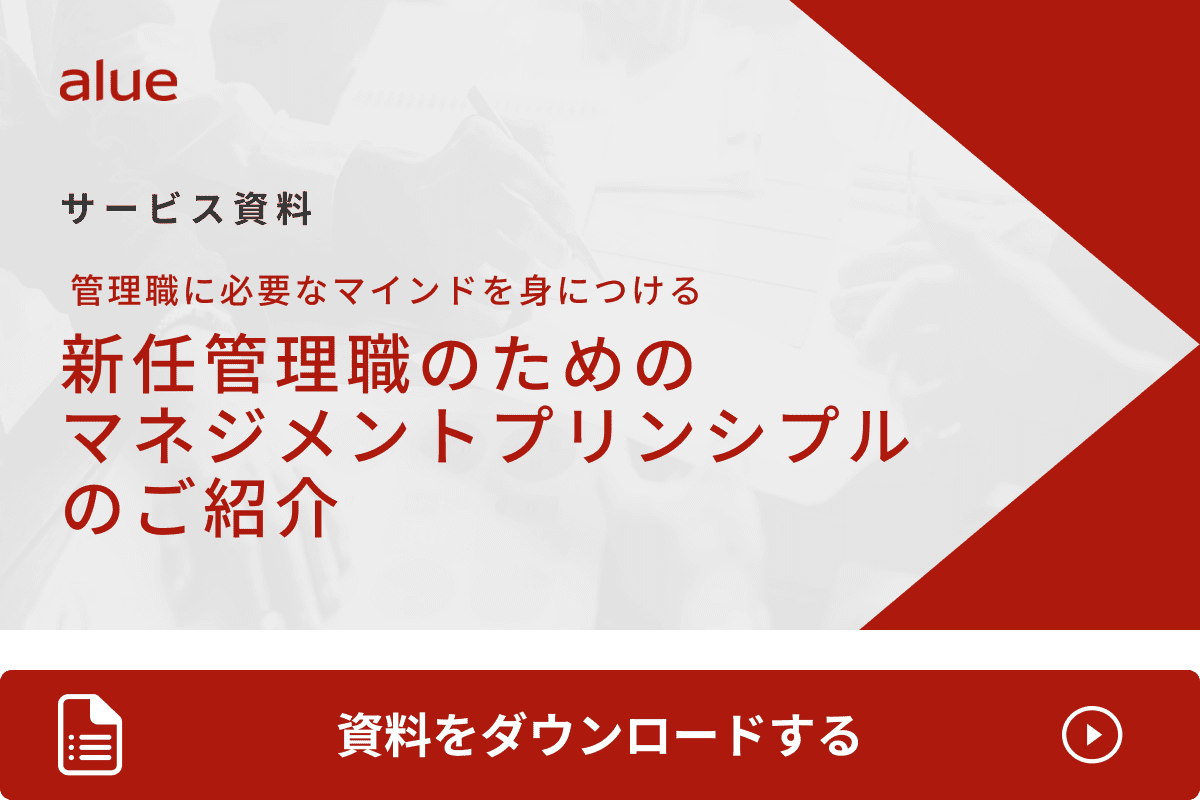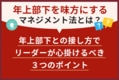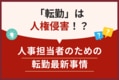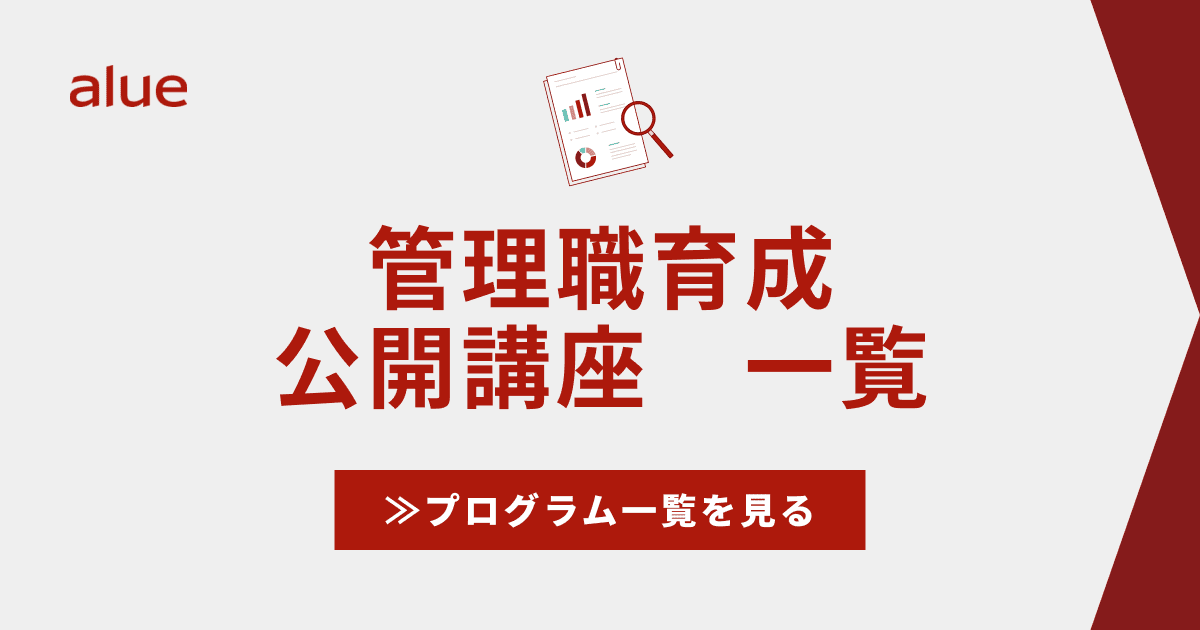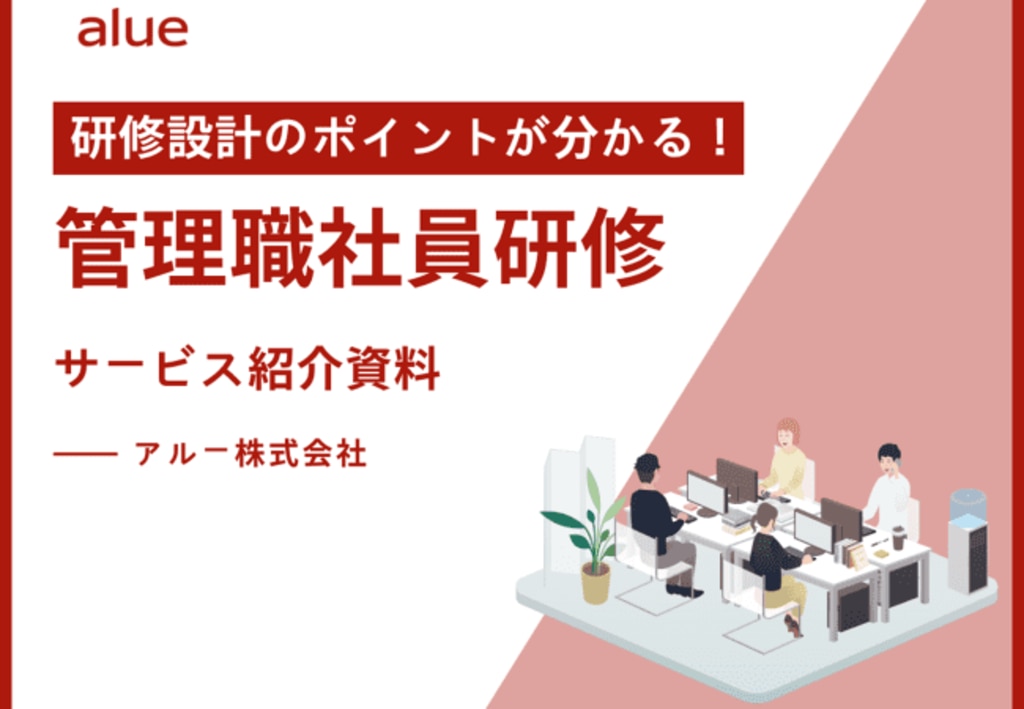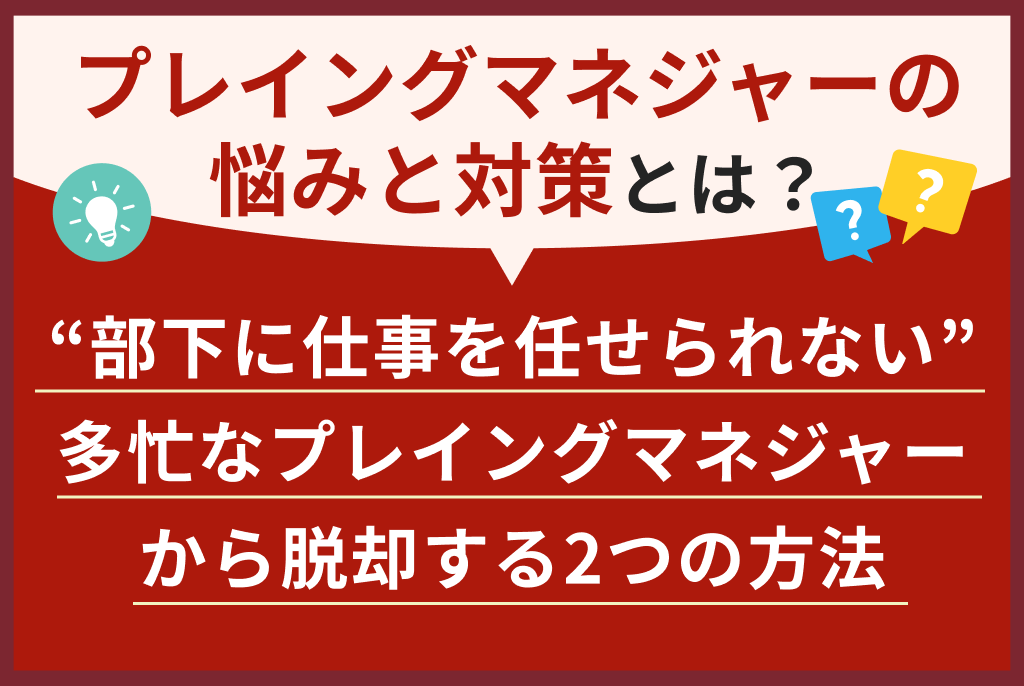
プレイングマネジャーの悩みと対策とは?“部下に仕事を任せられない”多忙なプレイングマネジャーから脱却する2つの方法
どんな有能な人でも2つの仕事を同時にすることはできません。
また、その2つの仕事の性質がまったく異なる場合、ひとつずつ進めていたとしても頭を切り替えるのに苦労したり、作業の優先順位付けに悩んだりと、大変なことがたくさんあります。そのため会社では、社員それぞれの役割を決めたりする、専門で担当する仕事を決めるなどして、各自が効率よく仕事ができるような体制をつくります。
しかしそんな中、会社では1人で2役をこなすような人もいます。
その代表的な例が、管理職・マネジャーという立場でありながら、現場のメンバーと一緒になって仕事をしている人たちです。このような立場で仕事をする管理職の人たちのことを、マネジャーでもありながら、プレイヤーでもあるという意味から、「プレイングマネジャー」と言います。
このプレイングマネジャーが、1人で2役をこなすようになった背景は、当然ながらその人それぞれの理由や、会社組織の事情などがあります。しかし、ほとんどのプレイングマネジャーに共通している悩みは、管理職やマネジャーになったものの、現場仕事の難易度や、周りのメンバーの経験不足という理由から、それまでの仕事を手放したくても手放せない、また、プレイヤーとしての現場の仕事を優先してしまい、マネジメント業務に手が回らないということです。
今回のコラムテーマは、マネジメント業務までなかなか手が回らないプレイングマネジャーの悩みと対策です。メンバーへの作業の引き継ぎのやり方、後輩社員の育成、特定の人に負荷が集中しない組織体制などについて解説します。
より深く知るための『オススメ』お役立ち資料

目次[非表示]
プレイングマネジャーに求められる管理職としての仕事内容
プレイングマネジャーが求められる管理職としての具体的な仕事内容は、主に以下のようなものがあげられます。
仕事全体の状態や実績の管理
自身が預かるグループ全体の仕事の状態および実績について、計画通りのものとなっているか、何か問題が生じていないかなどを監視し、必要に応じてより良い成果につなげる対処をおこないます。他部署と調整が必要なものなどは、他部署の上長との調整などもおこないます。
自社メンバーの管理 (※例えば、課長であれば課に所属する社員)
日々の業務の担当決めや、新たなプロジェクトが始まる際はプロジェクトリーダーを任命します。定期的にメンバーとの会話の機会を持ち、メンバーの悩みや不満にヒアリングを行います。そこで出てきた悩みや問題については自身で対処する場合もあれば、自分の上長や人事部に報告し、適切な対応を依頼します。また1年に1〜2回、メンバーの業績評価や人事考課についても一部を担当します。
協力会社の管理
自身が受け持つグループの業務遂行に、自社社員だけでなく協力会社が関わっている場合は、その協力会社との業務委託に関する契約、その協力会社の実績や納品の管理なども行います。
会社経営に関する業務
部長や会社役員と話し合う経営会議の参加、会社の中長期計画の推進や人材採用の支援などについても、現場を代表する立場として関わります。
プレイングマネジャーの厳しい実態
これまで挙げた仕事内容からわかる通り、管理職になるということは、自分の仕事だけでなく、自分以外の仕事の状態についても管理するということです。また、自身の成長や身の回りの環境だけでなく、メンバーの成長や作業環境についても考える立場になるという側面もあります。自分以外の周りの人の責任も持つため、誰もがその立場になれるわけではなく、日々の仕事でリーダーシップを発揮したりする、周りを助けられる存在になっている人が、管理職になります。
ですが、これだけ多くのマネジメント業務があれば、マネジャーとしての役割を全うするだけでも大変なことで、タイムマネジメントや実施タスクの管理は必須です。しかし、プレイングマネジャーは、これに加えて現場作業の一部を自ら担当し、有識者の立場で仕事の品質チェックなども行います。まさに1人で2人分の働きをしなければならない存在と言えます。
プレイングマネジャーから脱却するために必要な2つの方法
プレイングマネジャーの悩みである“部下に仕事を任せられない状態”を解決するためには、仕事の効率をあげてマネジメント業務を行う時間を捻出するか、現場作業を手放して空いた時間をマネジメント業務に充てるかをおこない、まずは自分の時間を確保することから始める必要があります。
前者の仕事効率アップは、自分一人でも始められるものですが、そもそも自身の仕事量が一人ではやりきれない量の場合は、仮にタイムマネジメントなどで仕事の効率アップが出来たとしても、マネジメント業務をやれる時間までの余裕が確保できるとは限りません。また、現場作業はクライアントに直結し、納期も決められていることから、マネジメント業務をおしのけて、最優先で対応しなければならない事もよくあります。これを踏まえると、プレイングマネジャーの悩みの解決は、仕事効率アップではなく、現場作業を手放して、プレイングマネジャーそのものから脱却するほうが良いと言えます。
プレイングマネジャーからの脱却①:現場作業負荷の分散
自身が担当している現場作業を他の人に振るためには、大切なことが2つあります。その一つめは、自分自身の思考の傾向として、「その仕事は自分がやった方が早い」という考え方を捨てることです。この考え方がある限り、何か作業が発生したら、まず自分がやることをイメージしてしまいます。そしてこの状態が続くことで、いつまで経っても誰かに作業を振るという発想が定着しません。
二つめに大切なことは、作業の具体的な分担方法についてです。具体的に作業を振るためには、その作業工程を整理し、準備が必要な前半と、仕上げが必要な後半にわけ、どちらか一方を別の担当に分担します。もちろんその作業をまるまる振ることができれば、それにこしたことはありません。しかし、作業全部を渡せないからこそ、今のプレイングマネジャーとしての状況に陥っているのであれば、作業を2つに分解してでも、一部を別の誰かに担当してもらうことが必要です。
そして、ここで重要なのは、2つに分解した作業は、面倒なほうを相手にやってもらうことです。一見すると大変なほうを相手に渡すので、ちゃんと出来るのか不安もあります。しかしその半分は自分が担当しています。自分が準備をしていれば、仕上げをする際の注意点を伝えることができ、自分が仕上げをする場合は、それまでの作業で不完全だったところへフィードバックすることができます。
< 作業負荷分散を効果的にする考え方と対策>
- 「自分がやった方が早い」という考えを捨てる
- 「準備が必要な前半作業」と「仕上げが必要な後半作業」で面倒なほうを分担する
プレイングマネジャーからの脱却②:後進の育成
自分にしか出来ない仕事がいくつもあると、いつまで経っても仕事を手放すことができず、新しいことを始める余裕ができません。そのためにも、自分と同程度の知識を持ち、同じように判断ができる後進の育成は避けては通れないものになります。しかし、後進の育成は、作業分担の見直しのように一朝一夕にできません。
まず相手がいることなので、自分の意思だけでどうにかできるものではありません。この人は次のリーダーになれると見込んでも、その人自身がリーダーになることを望んでいるかもわからず、仮にその意思があったとしても、自分の知識や経験はデータをコピーするかのように簡単に渡せるものでもありません。
どうすれば良いかと悩んでいるうちに、時間はどんどん過ぎていき、いつまでたっても問題が解決しない。そんな状況に置かれている管理職やリーダーはたくさんいます。後進の育成は、これをやれば確実という方法がないため、相手とやり方がはっきりしなくても、ある程度の割り切りを持ってすすめるしかありません。
自分の仕事をこなすことすらままならないプレイングマネジャーにとって、後進の育成のためだけに時間を確保することは難しいです。そのため、プレイングマネジャーはあくまで自分がすべき現場作業に時間を使い、その中で後進育成も同時に行う方法を取らなければなりません。
具体的には、日々の現場作業において特に知識やノウハウが必要なところは、メンバーにも参加させて、極力全員で行うという方法をとります。たとえばプロジェクト計画書の確認会や、作業結果のアウトプットの確認会などです。ひとつの確認作業に大勢の人間が時間を取られるので、それ自体の作業効率は高いとは言えませんが、そこでは作業だけでなく、教育も同時に行われるので、うまく出来れば、とても価値のある時間になります。そしてこれを定着させ、知識やノウハウがいきわたれば、作業分担ができる範囲も変わります。また知識がメンバー間で平準化されるので、次のリーダーや管理者は、リーダーシップの素養を持った人や、リーダーのやる気を持つ人から自然と選出することができます。
<プレイングマネジャーが後進育成を進めるための考え方と対策>
- 後進育成は現場作業をする時間のなかで同時に行う
- 知識やノウハウが必要な作業は、極力メンバーが全員参加する形式でおこなう
プレイングマネジャーから脱却するための更なる改善策 ~指示系統の見直し、下の人たちが自ら動けるルールづくり~
現場作業の負荷が分散され、後進の育成が軌道に乗っていけば、プレイングマネジャーからプレイヤーの部分が薄まり、これまで手がつかなかったマネジメント業務にも時間を掛けられるようになります。しかし、これが実現するにはある程度の時間を要します。また、日々の現場作業の状況にも左右され、一時的に現場の作業量が多くなる時や、突発の緊急作業が発生した時などは、やはりマネジメント業務よりも現場作業を優先しなければならない場面があります。これはプレイングマネジャーが現場のキーマンである以上は、避けられないものでもあります。
ここでもうひとつの改善策として手を打ちたいのが、現場のメンバーが日々の業務をする時の指示系統の見直しです。具体的には、「一定の条件を満たしていれば、現場のメンバーが自身の判断で仕事の開始もしくは終了ができるもの」の見直しです。現場のメンバーは、その内容についていくら詳しくても、会社の仕事を勝手に始めたりする、勝手に終わらせるわけにはいきません。仕事の開始と終了、またその途中でも内容に応じて上長の承認や関係者の了解が必要となります。そのため、作業の承認がマネジャーに極端に集中すると、それだけで仕事全体に影響することがあります。どういったケースであれば現場メンバーの判断で進めて良いのか、その際に報告すべき範囲など、明確なルール作りができれば、現場メンバーも安心して作業を進めることができます。
また、現場メンバーは現場の状況をもっともタイムリーかつ正確に把握している人たちです。彼らが状況に応じて即座に対処できるようになれば、組織全体のパフォーマンス向上にもつながります。現場作業のルールづくりは、プレイヤーではなくマネジメント業務の一部ですが、これを継続的に行うことで結果的に「プレイングマネジャー」という状態そのものがおこりにくい環境をつくることができます。
アルーのプレイングマネジャー研修の事例
アルーでは、業種や業界を問わずさまざまな企業へ研修を提供しています。
ここからは、アルーのプレイングマネジャー研修の事例として、課長層を対象に「プレイヤーからマネジャーへの脱却」をテーマに実施した研修を1つご紹介します。アルーのプレイングマネジャー研修を導入する際の参考にしてみてください。
プレイヤーからマネジャーへの脱却研修
マネジャーとして中長期的な仕事に時間を使いたいと考えながらも、結果として短期的な仕事を行うことに多くの時間を使っている課長層に向けて実施した研修事例です。
アルーの実施する本研修では、マネジメントに必要なマインドセットを身に付けることに加えて、実践的な演習を通じて、具体的にどのように時間の使い方を見直し、それを実現するためにどうすればいいのかを明確にすることができるのが特長です。
▼「プレイヤーからマネジャーへの脱却」研修プログラムの詳細はこちらからダウンロードできます。
プレイングマネジャーから脱却するための研修ならアルーにお任せください
アルーでは、プレイヤーからマネジャーへの脱却を実現するための研修を数多くご用意しております。プレイングマネジャーが本来期待されているパフォーマンスを出せないことにお悩みの方は、ぜひアルーへお任せください。
また、管理職の育成を総合的に行うための管理職研修もご用意しております。取引企業総数が1,400社を超えるアルーならではのノウハウを活用した管理職研修は、以下のページから詳しくご覧ください。
管理職研修
まとめ
いかがでしたでしょうか。
人手不足が深刻化する昨今、管理職に負担が集中し、マネジメントとして期待される役割を発揮できないことにお悩みの企業様が増えています。
本記事を参考に、自社に合ったプレイングマネジャー向けの育成施策を実施してみてはいかがでしょうか。
参照: プレイングマネージャーとは?意味・役割・必要スキル・成果創出のポイントについて解説|コチーム