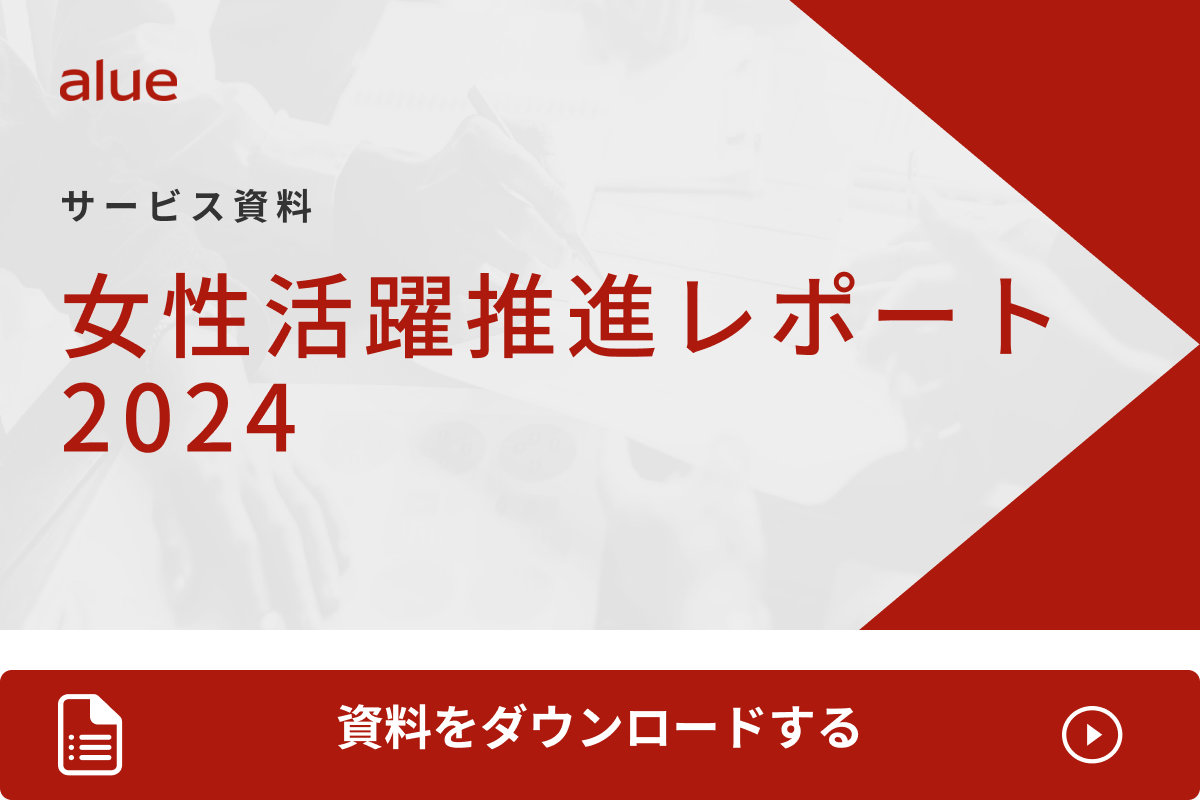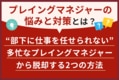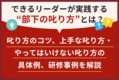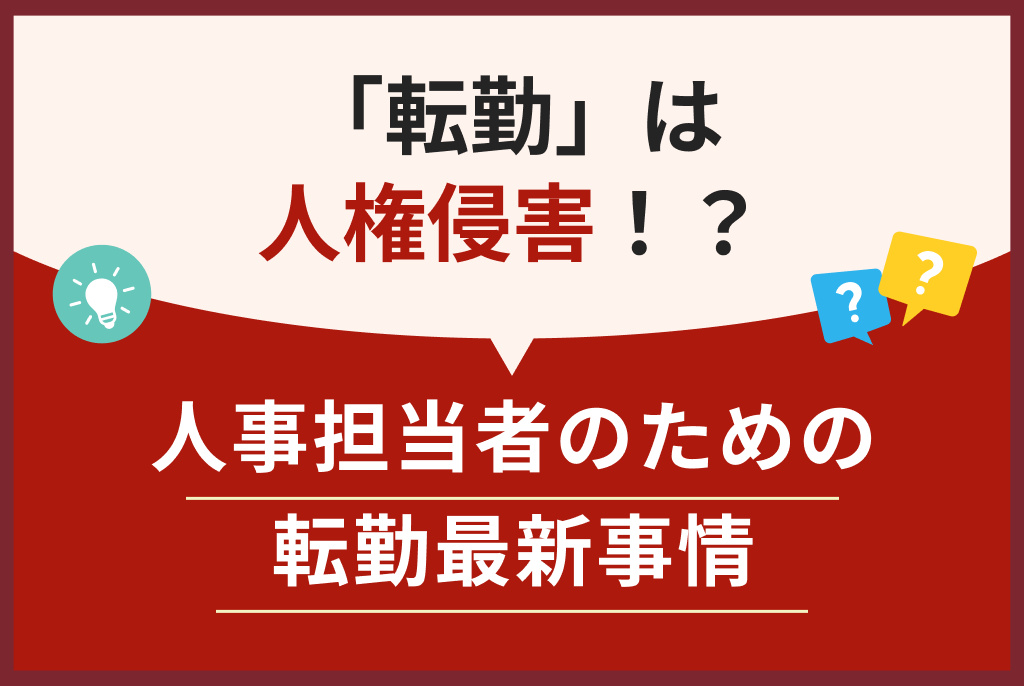
「転勤」は人権侵害!? 人事担当者のための転勤最新事情
転勤は、国内外を問わず、多くの企業が採用する人事戦略の一環として、従業員に様々な経験と成長の機会を提供する手段のひとつに位置付けられています。しかしながら海外企業(特に欧米企業)と日本企業における転勤制度の認識には大きく異なる点があります。
そのひとつが、欧米企業が転勤を「希望者に対しておこなう」という認識であるのに対し、日本企業は「希望の有無にかかわらず、(特に正規雇用の従業員は)転勤命令に従うべきもの」という認識である点です。
日本企業におけるこの認識が、今後どう変わっていくのか、今回はこの転勤制度について「人権」の観点からも取り上げていきたいと思います。

目次[非表示]
転勤の目的
転勤制度はどのような目的で制定されているのでしょうか。
まずはこの点について簡単にご紹介します。
グローバルビジョンの実現
多国籍企業においては、異なる地域や国でのビジネス展開が求められます。
とくに海外赴任(転勤)は、従業員に異なる文化やビジネス環境での経験を積む機会を提供し、グローバルな視野を養う役割を果たします。
キャリアパスの構築
転勤に伴い、職種が変わるケースもあります。こういったケースでは、従業員が異なる職種や部署での経験や人脈を得る手段となります。
これによって、従業員は多岐にわたるスキルや知識、そして人脈を身につけ、将来的なリーダーシップや専門家としてのキャリアパスを構築することができます。
チームビルディングと組織の連携
転勤を通じて、異なる拠点やチームで働くことで、従業員は多様なメンバーと連携し、コミュニケーションスキルや協働能力を向上させます。これが、企業全体の連携力やチームビルディングに寄与していくであることは言うまでもありません。
また、転勤を通じて異なる背景や経歴を持つ人材が組織内に配置されることによって、多様性を強化し、異なる視点からの意見やアイデアが生まれやすくなります。
これがイノベーションを促進し、競争力を高めることもあるのではないでしょうか。
組織の柔軟性と適応力の向上
ビジネス環境は変化し続けており、企業はその変化に柔軟に対応する必要があります。
転勤は組織全体の柔軟性や適応力を向上させ、変化に迅速かつ効果的に対処する力を養うという見方もできます。

転勤制度が人権侵害に? これからの転勤制度を考える
このように、転勤制度は単なる配置転換だけでなく、戦略的な人材管理の一環として位置づけられ、企業としての成長を促進する要因ともなるなど、多くのメリットがあることは事実です。
しかし一方で、人権の観点からは様々な問題が浮き彫りになります。
以下に、人権の観点からの転勤の問題点について考察してみます。
家族との関係への影響
転勤は単なる職場の変更だけでなく、家族との関係にも深い影響を及ぼします。とくに子どもや配偶者にとって、新しい環境への適応は大きな課題です。子どもたちは友達や学校から離れ、新たな環境での人間関係の構築が求められます。配偶者は自身のキャリアや地域社会との結びつきを失うことで、ストレスや孤独感に直面することがあります。
また、家族単位での引越しが伴う場合、安定感の喪失や生活の不確実性をもたらし、家族全体の精神的な健康に影響を与える可能性があります。
企業は、転勤をおこなう際には従業員の家族も含めたトータルなサポートを提供し、家族が円滑に新しい生活に適応できるよう努めることが求められるようになっていくのではないでしょうか。
ワークライフバランスの損失
転勤が頻繁におこなわれると、従業員は安定したワークライフバランスを維持することが難しくなります。引越しや新しい環境への適応には時間とエネルギーがかかり、これが業務への集中を妨げることがあります。
また、新しい環境での社会的ネットワークや趣味の再構築も時間を要します。このような状況下で、従業員は仕事とプライベートの調整に苦慮し、ストレスや疲労が蓄積されることがあります。
次に述べる「精神的ストレスとメンタルヘルス」とも共通しますが、人事担当者は、転勤に臨む従業員のメンタルの状態を把握し、適切なサポートを提供する必要があります。
精神的ストレスとメンタルヘルス
転勤は新しい環境への適応や不確実性により、従業員に精神的なストレスをもたらすことがあります。新しい職場での期待や役割の変化、地域や文化の違いに対する不安が、孤独感や社会的な孤立に繋がったり、また新しい環境への適応圧力は、ストレスや不安症状を引き起こすこともあります。転勤が頻繁におこなわれる場合はそのリスクが高まることは言うまでもありません。
人事担当者は、転勤に臨む従業員のメンタルの状態を把握し、適切なサポートを提供する必要があります。精神的な健康を尊重し、適切なサポートを通じて従業員の幸福感を向上させることが、企業としての責任となることは言うまでもありません。
具体例としては、転勤前や転勤後にカウンセリングのほか、精神的な健康教育の提供することや、柔軟な労働条件の検討していくことなどが、従業員が安心して働ける環境を構築する手助けとなるのではないでしょうか。
キャリア形成の不均衡
頻繁な転勤は、キャリア形成に不均衡をもたらす可能性も考える必要があります。一部の従業員が転勤の機会を得ることによって、昇進等で評価される一方、転勤を望まない従業員が正当な評価を得られないなど、人事評価上の不均衡が生じている場合、組織内でのキャリアの発展に差が生じます。このような状態を放置していると、有能な人材の流出につながりかねません。
そのような不均衡が生じている場合は、キャリア形成の均衡を図るために公正な転勤ポリシーを確立し、転勤を希望制にした上で、転勤がどのように評価に反映されるのかを明らかにすることによって、従業員の納得を得られる可能性が高くなります。このような透明性と公正性を重視したキャリアパスの構築や、スキルの習得を支援するプログラムの提供が、従業員のエンゲージメントを高める一助にもなることは言うまでもありません。
結果として、従業員が公平かつ平等な条件でキャリアを築き上げることができ、ひいては組織の活力とチームの協力が促進されるのではないでしょうか。
適切なサポートの不足
従業員を転勤させる際に、適切なサポートが提供されないケースもあります。残念ながらこういったケースは珍しいことではありません。
転勤に伴う従業員への適切なサポートが不足すると、さまざまな課題が生じます。ひとつは、新しい地域への適応を助けるカウンセリングや言語学習の支援が欠如していることです。また、住居や学校の手続き、地元の情報提供が不十分だと、従業員は転勤を受諾することが正しいのか、不安に陥ることも少なくありません。
特に子どもを養育している従業員の場合、家族向けのサポートも重要です。家族の健康や教育に関する情報提供や、配偶者の就業支援などが不足すると、家族全体が転勤による変化にうまく対処するのが難しくなります。
これまでは、「単身赴任は当たり前」としてきた企業も、今後は従業員の転勤をサポートするために、綿密な計画や情報提供、家族全体を対象とした包括的な支援プログラムの整備が求められる傾向が強まるのではないでしょうか。
転勤は女性活躍推進にも影響する
人手不足への対応や組織の柔軟性を高める観点から、多様な人材の活躍を推進する動きが広がっています。とくに女性活躍については、1985年の男女雇用機会均等法以来、官民一体となって推進されてきました。直近では、「女性版骨太の方針 2023」も公表され、女性の活躍はますます求められるようになっています。
そして転勤は、実はそんな女性活躍推進を阻害する原因のひとつにもなっています。たとえば、転勤に対するサポート不足は女性社員にとって強い不安を与えます。また、転勤できる人ばかりが昇進していくことに対する不満も、女性活躍推進に良くない影響を与えます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
転勤制度は企業人事における非常に重要な制度の一つであることも多いのですが、その反面、人権の観点から見た場合、従業員個人やその家族の幸福を重視したものではないことも珍しくありませんでした。
転勤制度を改定・策定する際には、従業員およびその家族の権利を尊重し、バランスを取るよう努めることによって、従業員のエンゲージメントを高めることも可能となります。
そのためには、人事担当者が「転勤制度」をどのように理解しているかも重要な観点となることは言うまでもありません。
人事担当者のあなたは、自社の転勤制度をどう考えているでしょうか。
お役に立てば幸いです。