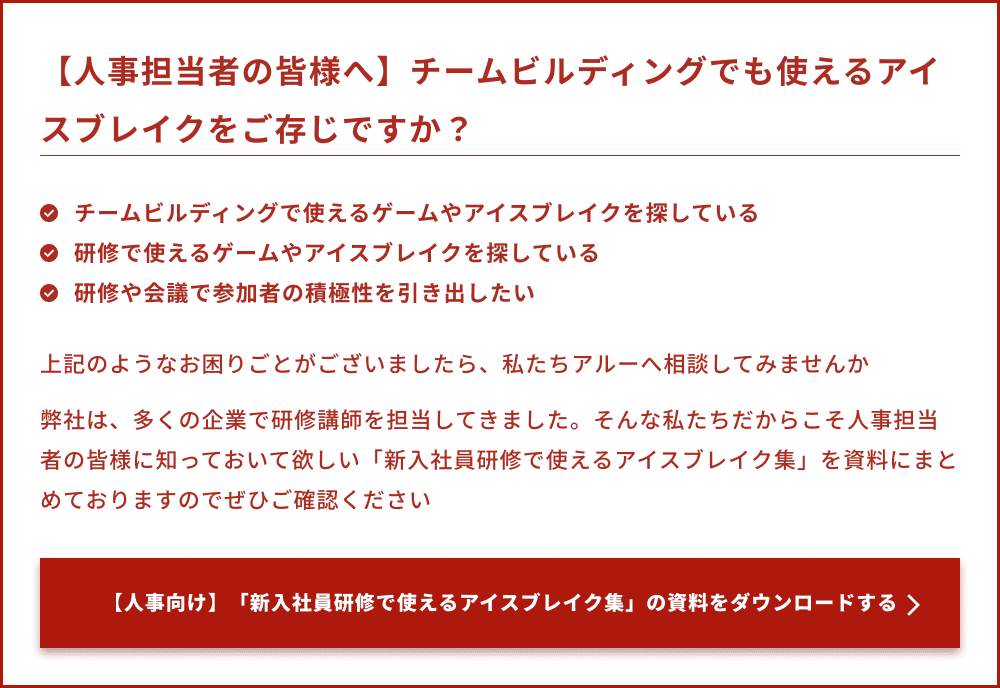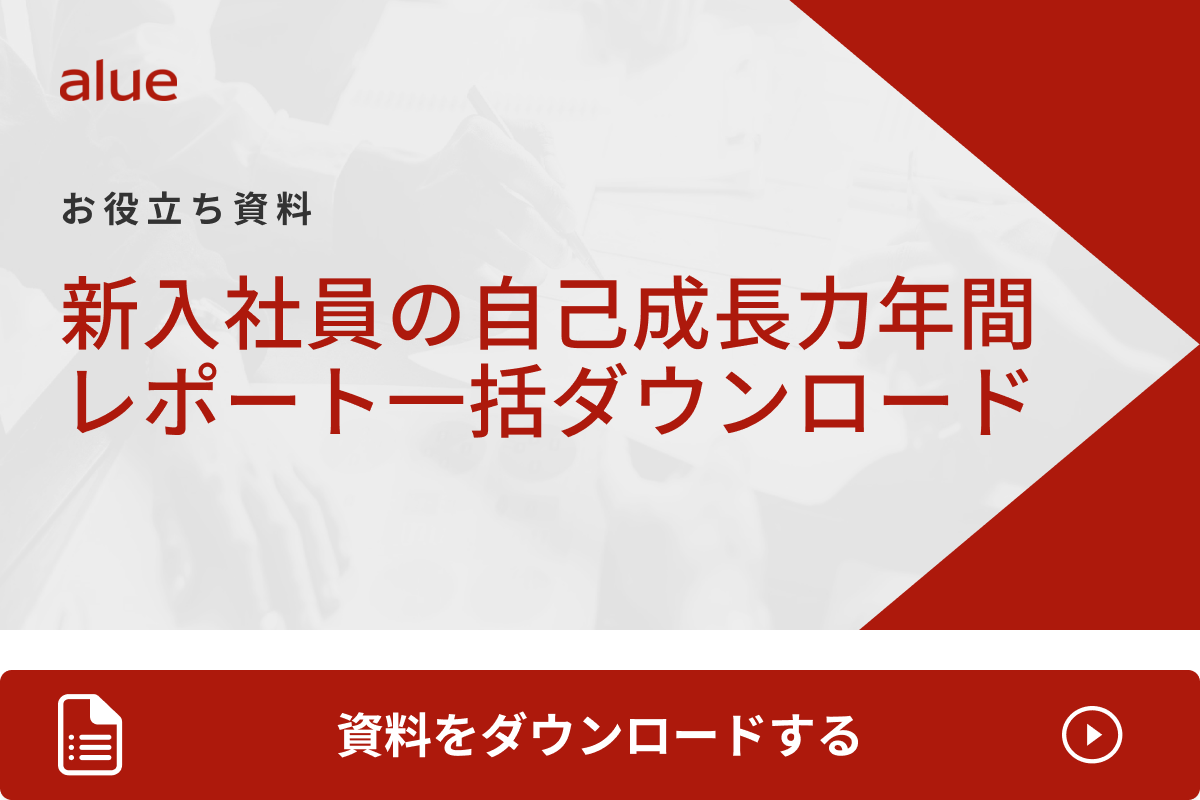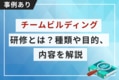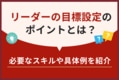相互理解とは?チームビルディングを成功させる例や促進のコツを解説
組織の結束力を高め、生産性を向上させる上で必要不可欠な相互理解。メンバーが互いのことを深く理解すれば、組織内の問題発生を抑制できるとともに、メンバー同士の連携もスムーズになります。
近年は、相互理解を促進するためにシャッフルランチやフリーアドレス制といったさまざまな取り組みが脚光を浴びています。この記事では、相互理解が必要な背景や、相互理解を深めるために必要な取り組みについてご紹介します。
目次[非表示]
組織における相互理解とは
相互理解とは、他人同士でお互いの立場や考え方、気持ちを理解しあうことです。
組織における相互理解とは、異なる部署や背景、考え方や価値観を持つメンバー同士が、上司部下、同僚同士など、どのような関係性であってもお互いのことをより深く理解し合うことを指します。
相互理解を深めることによって、メンバー同士が協力関係を築き、コミュニケーションを円滑に行えるため、生産性の向上につながります。
相互理解が重要視されている背景
それでは、なぜ相互理解は最近になって脚光を浴びるようになったのでしょうか。
主な背景としては、リモートワークの普及や転職希望者の増加、ハラスメント問題の顕在化などが存在します。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
リモートワークの普及
新型コロナウイルス流行の影響や、働き方改革で柔軟な働き方が促進されたことで、リモートワークを取り入れる企業が大幅に増加しました。一方でリモートワークの普及により、オフィスでの対面コミュニケーションが減り、メンバー同士の相互理解が難しくなったという企業も出てきています。
また、オンラインでのコミュニケーションには、言葉や表情が伝わりにくいという問題もあります。相互理解ができていれば、リモートで働いていたとしてもスムーズに連携が出来るようになるでしょう。
直接会っての意思疎通が取りづらい現代だからこそ、相互理解を深めることが重要視されているのです。
転職希望者の増加
新型コロナウイルスの流行以前から行われている働き方改革の枠組みの中で、人材の流動化も進んでいます。若者を中心にキャリア観は多様化し、転職のハードルも大幅に低くなりました。実際、総務省が実施した「労働力調査」によると、2010年代は750万人前後で推移していた転職希望者数は、2022年には900万人以上へと大幅に増加しています。
参考:労働力調査の概要|総務省
このような背景から、多様な背景を持った人材が組織に加わる機会が増えています。これにより相互理解が求められる状況が増え、教育制度や社内コミュニケーションの見直しが必要になってきます。
ハラスメントの問題化
働き方が見直される中で、職場の「セクハラ」「パワハラ」などのハラスメントも社会問題化しました。現代は、SNSを通じて瞬時に情報が駆け巡る時代です。一つのハラスメントが、会社全体、ひいては業界全体のイメージダウンを引き起こしてしまうことも珍しくありません。
ハラスメント問題の顕在化も、職場での相互理解に対する意識が高まった背景の一つです。ハラスメントを解決するためには、相手の意見や気持ちを尊重し、心理的安全性の高いコミュニケーションの場を確保することが必要です。ハラスメント研修などと並行して、相互理解に向けた取り組みを行う企業が増えてきています。
チームビルディング研修のメリット
チームビルディング研修は、チームメンバー同士の信頼関係を深め、協調性やコミュニケーション力を高めるための取り組みです。
実際にチームビルディング研修によってどのようなメリットが得られるのかを解説していきます。
リモートワークの普及
新型コロナウイルス流行の影響や、働き方改革で柔軟な働き方が促進されたことで、リモートワークを取り入れる企業が大幅に増加しました。一方でリモートワークの普及により、オフィスでの対面コミュニケーションが減り、メンバー同士の相互理解が難しくなったという企業も出てきています。
また、オンラインでのコミュニケーションには、言葉や表情が伝わりにくいという問題もあります。相互理解ができていれば、リモートで働いていたとしてもスムーズに連携が出来るようになるでしょう。
直接会っての意思疎通が取りづらい現代だからこそ、相互理解を深めることが重要視されているのです。
転職希望者の増加
新型コロナウイルスの流行以前から行われている働き方改革の枠組みの中で、人材の流動化も進んでいます。若者を中心にキャリア観は多様化し、転職のハードルも大幅に低くなりました。実際、総務省が実施した「労働力調査」によると、2010年代は750万人前後で推移していた転職希望者数は、2022年には900万人以上へと大幅に増加しています。
参考:労働力調査の概要|総務省
このような背景から、多様な背景を持った人材が組織に加わる機会が増えています。これにより相互理解が求められる状況が増え、教育制度や社内コミュニケーションの見直しが必要になってきます。
ハラスメントの問題化
働き方が見直される中で、職場の「セクハラ」「パワハラ」などのハラスメントも社会問題化しました。現代は、SNSを通じて瞬時に情報が駆け巡る時代です。一つのハラスメントが、会社全体、ひいては業界全体のイメージダウンを引き起こしてしまうことも珍しくありません。
ハラスメント問題の顕在化も、職場での相互理解に対する意識が高まった背景の一つです。ハラスメントを解決するためには、相手の意見や気持ちを尊重し、心理的安全性の高いコミュニケーションの場を確保することが必要です。ハラスメント研修などと並行して、相互理解に向けた取り組みを行う企業が増えてきています。
ハラスメント研修については以下のページをご参照ください。
『【事例あり】ハラスメント研修とは?目的や内容を解説』
相互理解を深めるメリット
相互理解が注目されてきている背景について解説しました。相互理解を深めれば、信頼関係の構築や生産性の向上、モチベーションアップなどさまざまな効果が期待できます。相互理解を深めるメリットについて解説します。
信頼関係が生まれ、生産性の向上につながる
組織内での相互理解を深めれば、信頼関係の構築につながります。メンバー同士が互いを信頼することで、組織内でのコミュニケーションがスムーズになるでしょう。相互理解を深めることでチームワークが改善され、生産性が向上するという点が大きなメリットです。
また、組織内での信頼関係があれば「失敗を恐れる必要はない」といった前向きなマインドも生まれます。そのため、信頼関係があるチームではチャレンジングな業務にも向き合いやすくなり、革新的なアイディアが生まれやすくなるといったメリットもあります。
心理的安全性の確保につながる
心理的安全性とは、メンバーが「自分の意見や考えを自由に話せる」と安心できる環境のことを指します。心理的安全性が高いチームは、メンバー同士がオープンにコミュニケーションを取ることができるため、ミーティングや面談の場でも率直な意見交換ができるようになります。
相互理解が深まることで、心理的安全性が確保されるという点もメリットの一つです。メンバーが自分の考えやアイディアを自由に発言できるため、組織の意思決定の改善も期待できます。
メンバーのモチベーションUPにつながる
「メンバーのモチベーションが低く、業績が向上しない」といった課題を抱えているチームも少なくありません。メンバーのモチベーションは、チームのパフォーマンスに大きな影響を与えるものです。
相互理解が深まれば、メンバー同士が互いの仕事や役割に興味を持ち、関心を寄せるようになります。そのためメンバーのモチベーションが高まり、より高いパフォーマンスを発揮できるようになるでしょう。また、相互理解によってメンバー同士が互いにサポートし合えるようになるため、個々のストレスを軽減することもできます。
個性や強みを活かしたマネジメントができる
相互理解が深まれば、メンバー同士がお互いの個性や強みを認識できるようになります。また、チームのリーダーもそれぞれのメンバーの特性を把握できるため、個々の強みを活かしたマネジメントができるようになります。
具体的には、メンバーが抱えている課題にあわせたフォローを実施できるようになるでしょう。また、個人の強みを活かすことができるため、個々のパフォーマンスが向上することが期待できます。
組織内のコミュニケーションがスムーズになる
組織内の連携でミスが出てしまうと、業務効率の低下につながります。組織として高いパフォーマンスを維持するためには、メンバー同士のコミュニケーションが欠かせません。
相互理解が深まればメンバーが相手の立場や状況を理解できるようになるため、コミュニケーションがスムーズになります。コミュニケーションのミスやメンバー間の認識のズレが減少するため、業務プロセスが改善し、中長期的な業績向上にもつながるでしょう。
相互理解が図れないと起こる弊害
相互理解を促進するメリットについて解説しました。メンバー間の相互理解を促進しなければ、どのような弊害が発生してしまうのでしょうか。
相互理解が進まない場合、離職率の低下や業績の低下、さらには人間関係のトラブルといった問題点が発生します。相互理解が取れない場合に生じる弊害について確認しましょう。
離職率の増加
厚生労働省が公表している「職場のハラスメントに関する実態調査」によれば、職場でのコミュニケーション不足はパワハラやセクハラといったハラスメント行為に直結することが明らかになっています。同調査によれば、「上司と部下のコミュニケーションが少ない」と感じている社員は、そうでない社員と比較してパワハラやセクハラの経験率が15%〜20%程度増加しています。
相互理解が図れないと、メンバー同士のコミュニケーションが不十分なことで生じるハラスメント行為やストレスが蓄積され、それが離職に繋がることがあります。また、職場の雰囲気が悪化してやりがいや達成感が減少することで、離職を選択する社員が増えることも考えられます。
業績の低下
相互理解が図れない場合、業務プロセスやタスクの進捗状況についてのコミュニケーションが不足します。コミュニケーションが不足してしまうと、業務が意図せず重複してしまったり、チェック事項の抜け漏れ、進捗遅延などが発生したりする可能性が高まります。また、このようなミスが多発すればメンバーのモチベーションも大きく低下します。
こういった背景から、相互理解の不足が組織の業績低下に直結することは少なくありません。収益や生産性の低下はもちろん、顧客からの信頼喪失といった業務全体の成果に影響を与えることもあるでしょう。
人間関係のトラブル
相互理解が図れないと、人間関係にトラブルが発生することもあります。メンバーの持つ意見や意図が食い違って対立関係が生じ、チームワークが低下してしまう可能性が高いです。
また、コミュニケーション不足は職場でのストレスやプレッシャーの増加も招きます。最悪の場合、パワハラやセクハラ、モラハラといったトラブルにも発展してしまうでしょう。さらにこういったトラブルが人事や法務に大きな負担をかけ、組織全体にとって悪影響をもたらす可能性もあります。
相互理解が深まらない原因
相互理解が職場で必要なことはご理解いただけたと思います。しかし、メリットがあると分かっていても実際の職場では相互理解が進まないことが多々あります。相互理解が進まない原因を解説します。
自分のことを開示できない
相互理解をするためには、メンバーが自己開示する必要があります。お互いにビジネス上の経歴や得手不得手などを知ることができれば業務が円滑に進みます。また、趣味や特技などのプライベートを共有することで、ビジネス上だけでない人間関係の構築も期待できるでしょう。
しかし、メンバーが自己開示が苦手だったり、職場の雰囲気が悪く自己開示することに消極的になったりすることがあります。そうすると、メンバーとしては「どこまで踏み込んでいいのか」が不安になり、遠慮したコミュニケーションになってしまいます。結果として、お互い自己開示ができず相互理解が進まない可能性があります。
自己開示の苦手なメンバーのサポートをしたり、職場の雰囲気をよくしたりといった活動が必要になるでしょう。
不誠実な対応をするメンバーがいるため、不信感が生まれる
約束を守らなかったり、個人情報をむやみやたらに他人に喋ってしまったりするメンバーがいた場合、周囲の人はその人を信用できず、コミュニケーションが停滞してしまいます。
そのようなメンバーが多い場合、社会人としての基本を認識してもらうための研修を実施することも検討しましょう。
▼アルーの社会人の基本研修はこちらからご覧ください。
社会人の基本100本ノック
▼社会人の基本研修の資料はこちらからダウンロードできます。
相手への興味がない
メンバーの多くが、そもそも相手への興味をもてず「理解したい」という気がない場合も相互理解が進みません。人に対する興味がないと、相手に質問をしないだけでなく、自分のことも開示できないことが多いです。
相互理解には、メンバーが互いに興味をもって自己開示し合うことが必要です。人に興味がない、というメンバーが多い場合には、相互理解の重要性を啓蒙したり、楽しく相互理解を図れる施策を取り入れたりすると効果的でしょう。
相互理解を深めるための施策

相互理解を深めるためには、相互理解促進に向けた施策に取り組むのが有効です。最近では上司と部下が1対1で対話する機会を設ける「1on1ミーティング」や、あえて異職種の仕事に取り組んでもらう「ジョブローテーション制度」などを取り入れる企業が増えてきています。
ここでは、相互理解を深めるために有効な施策をご紹介します。
自己理解と他者理解を深める
相互理解を深めるためには、まずメンバーそれぞれが自分自身についてよく理解することが必要不可欠です。相互理解を深めるための土台として、自身や他者の強みや特性を客観的に把握できるツールやメソッドを導入するとよいでしょう。
中でも、アメリカのGallup社が開発した「ストレングスファインダー」はいくつかの質問に答えることで自分自身の強みを明確にできるため、自己理解に活用されています。ストレングスファインダーなどで見つけた強みや特性をお互いに共有すれば、メンバー内での相互理解が深まります。
また、同じく自己理解のために使われる「MBTI®(※注)」は、心理学者・ユングの考え方をベースに作られたメソッドです。
※注:MBTI is a registered trademark of the Myers&Briggs Foundation in the United States and other countries.
シャッフルランチ
シャッフルランチとは、普段の業務の中ではなかなか接点のない社員同士でグループを組んでランチに行ってもらい、メンバーと交流を深める制度です。
シャッフルランチも、相互理解を深めるための有効な施策の一つです。部署の垣根を越えた横のつながりを構築できるのはもちろん、入社して間もない新入社員の顔を覚えたり、普段顔を合わせない部長と知り合えたりなど、縦のつながりも強化できます。
1on1ミーティング
1on1ミーティングとは、主に上司と部下の2人で行う個別のミーティングのことです。日頃の業務の進捗状況や困っている点について尋ねるのはもちろん、普段はなかなか踏み込まない相手の率直な意見や本音を引き出すこともあります。
メンバー内の相互理解を深めるため、1on1ミーティングを導入する企業も多いです。キャリアプランや仕事観についてなど、相手の深い部分まで理解できるのが1on1ミーティングの特徴といえます。1on1ミーティングについてさらに詳しく知りたい方は、以下の解説記事をご覧ください。
1on1ミーティングの導入効果・目的とは?導入企業の事例や導入方法
アルーでは、1on1ミーティングを効果的に実施するための研修をご提供しています。「1on1ミーティングを導入することになった」「1on1ミーティングを導入しているがあまり効果が出ていない」という人事担当者様は以下の研修プロブラムもぜひご覧ください。
▼1on1ミーティングの基本について学べる研修はこちら
▼1on1ミーティング研修についての資料はこちらからダウンロードできます。
ゲームやワークショップの実施
相互理解を深めるためには、ゲームやワークショップの実施も効果的です。特に最近ではリモートワークで希薄化したコミュニケーションを取り戻すために、手軽に打ち解けることのできるゲームを取り入れる企業が目立っています。
例えば人狼ゲームや謎解きゲームを導入すれば、互いの思考法や特性について把握できるとともに、ゲーム外でコミュニケーションを取るきっかけにもなるでしょう。
フリーアドレス制度
フリーアドレス制度とは、従来のように社内での座席を固定せず、あえて空いている場所を自由に選んで仕事に取り組んでもらう制度のことです。部署や役職によって席が指定されることはなく、オフィス内の空いている場所ならどこでもOKというスタイルが多く導入されています。
フリーアドレス制度を導入すれば、部署や役職の垣根を越えたコミュニケーションを促進できます。プロジェクトやチーム外のスタッフとも積極的にコミュニケーションを取ることで、思いもよらなかったつながりが生まれ、相互理解が深まるのです。
ジョブローテーション制度
ジョブローテーション制度とは、定期的に部署異動させたり、職務を変更したりする制度のことです。いつもは取り組まない業務に取り組んでもらうことで、日頃は関わらない部署とコミュニケーションが生まれ、相互理解が深まるという効果が期待できます。
ジョブローテーションを通じて様々な部署の社員とのつながりを増やすことで、他の部署の職務内容や役割を理解することができます。相互理解以外にも、幅広いスキルを育成できる、俯瞰的な視野を育てられる、といったメリットがある施策です。
相互理解を深めるために必要なスキル
相互理解を深めるためには、どういったスキルを身につけるのが効果的なのでしょうか。
相互理解を深める前に「人として興味を持つ姿勢」や「傾聴力」などを育てておけば、相互理解のための施策もさらにスムーズに進むことが期待できます。相互理解を深める際に身につけておきたいスキルについてご紹介します。
人として興味を持つ
ここでいう「人として興味を持つ」とは、相手の人となりに対して一個人として興味を持ち、共感することです。ビジネス上の関係として情報収集しようとするのではなく、相手に一人の人間として興味を持つ姿勢を身につければ、相手の気持ちや立場を深く理解し、お互いの関係をさらに深めることができます。
人として興味を持つためには、ビジネスに関すること以外にも、趣味や共通の話題など、幅広く話してみることが効果的です。自分が興味を持っていることや自分自身が経験したことについて話せば、相手との共通点を見つけることができ、より効果的なコミュニケーションが生まれます。
傾聴力
傾聴力は、相手の話をしっかりと聴き、理解するためのスキルです。相手の話を深く理解することによって、相手の想いや気持ちを理解することができます。傾聴力も、相互理解を深めるためのコミュニケーションを取る際に極めて重要なスキルです。
傾聴力を高めるためには、例えば以下のような点に注意してみるとよいでしょう。
- 相手の話を遮らず、相手が話している際はしっかりと聴き入る
- 相手が言ったことを適宜要約したり、自分の理解を確認したりする
- 相手の話にしっかりと共感し、共感していることを伝える
傾聴力を身につければ相手の意見や思いを尊重できるようになるため、相互理解に必要不可欠な信頼関係の構築も促進されます。
傾聴力については『管理職が傾聴力を高める育成方法とは?傾聴力を高めるメリットと目的』の記事もぜひ参考にしてください。
傾聴力は部下を持つ管理職にも求められます。管理職の傾聴力を鍛えるコツについて、資料にまとめました。こちらからダウンロードください。
管理職に求められる、部下の本音を引き出すための研修プログラムもございます。
▼こちらから研修概要をダウンロードいただけます。
アサーティブコミュニケーション
をしっかりと伝えることが重要です。アサーティブコミュニケーションは、自分自身の意見や気持ちを適切に伝えるスキルを指します。アサーティブコミュニケーションを身につければ、相手に配慮しながら自分の意見や気持ちをはっきりと伝えることができるようになるため、相互理解の促進に役立ちます。
アサーティブコミュニケーションのスキルを高めるためには、「自分の考えと相手の考えをともに大切にする」という姿勢を意識するとともに、自分自身の意見を適切に伝える手法を身につけるのが効果的です。アサーティブコミュニケーションの能力を高める研修については、以下のページで詳しく解説しています。
相互理解を深めるポイント

相互理解を深める施策を行う際には、相互理解を深める際のポイントについて知っておくとよいでしょう。これらのポイントをおさえて施策を実施することで、より相互理解がスムーズに促進され、質の高い相互理解が実現できます。
相互理解を深めるためのポイントとして代表的なものを3つ、紹介します。
自己開示をする
自己開示とは、自分自身の内面について相手に伝えることです。まずは自分自身の趣味や生い立ち、感じていることなどを言葉で相手に表現することで、相手に自分自身を理解してもらうことができ、相手の情報も教えてもらいやすくなります。
初対面の人ともスムーズに距離を縮められるようになるテクニックなので、相互理解を深める際にはぜひおさえておきたいポイントの一つです。
不信感を持たせない言動をする
相手とコミュニケーションを取る際には、何でもかんでも話したり、ひたすら質問を続けたりすればよいわけではありません。相手との相互関係を深めていくためには、不信感を持たせない言動をすることが必要です。
例えば、必要以上にプライベートな情報について質問したり、あまり相手が興味を持っていない話題について話し続けたりしないように注意が必要です。相互理解に取り組む際には相手との距離感をしっかりと見極め、適切な距離感を保つようにしましょう。
公私関わらず個人として興味関心を持つ
ビジネス上の関係として割り切って相手と接していると、どうしても表面的な情報交換になりがちです。業務の進捗状況や仕事の話題に終始してしまうと、相互理解は深まりません。
相手との信頼関係を築くためには、公私関わらず相手に興味関心を持つことが重要です。例えば、相手の趣味や興味を持っていること、家族構成などについて質問することで、相手との共通点を見つけることができます。また、相手が困っていることや悩んでいることがあれば、相手に寄り添い、問題解決に向けて協力することが大切です。
リモートワーク下で相互理解を深めるポイント
新型コロナウィルス流行により、リモートワークが一般的になりました。リモートワークでは顔を合わせる機会が減るため、より意識的に相互理解を促進していく必要があります。特に、管理職と部下の間での相互理解には注意が必要です。以下に、リモートワーク下での相互理解のポイントを3つご紹介します。
クローズドスペースでのチャットを活用する
リモートワーク下で用いるチャットツールには、全てのメンバーが閲覧できるオープンなチャットと限られたメンバー・個人間でやりとりするクローズドなチャットの2種類があります。オープンチャットは情報共有などには有効ですが、オープンチャットでは言いづらい課題を部下が抱えている可能性があります。その場合、個人チャットなどクローズドでのコミュニケーションを行うようにしましょう。
クローズドスペースでのコミュニケーションの方が、プライベートなことや愚痴などを含めて深い話ができる傾向にあり、相互理解が進みやすいです。
1on1ミーティングの時間を定期的に設ける
リモートワーク下では対面する機会が少なくなるため、意識的に1on1ミーティングの時間をとることが重要です。1on1ミーティングを通してキャリアプランを確認したり、そこからブレイクダウンして現在や今後の業務内容についても話すことができます。また、チャットでは説明しきれない悩みや課題も議題に上げることができます。
積極的なドキュメント化・ナレッジ共有をする
業務を推進するうえで「何を実行するのか」「期待される効果」「進捗」などを都度ドキュメント化して共有することを意識しましょう。リモートワーク下では、誰が何をしているのか、業務の進捗はどうなのかを把握しづらくなります。そのため、「誰が、なぜ、何をしているのか」を可視化することで相互理解が深まります。
また副次的な効果として、ドキュメント化することで社内にナレッジが溜まり、企業としての成長にもつながります。
相互理解を深める取り組みの事例
相互理解を深めるための施策や、相互理解を深める際に知っておきたいポイントについて解説しました。実際、こういった施策を導入し、チーム内での相互理解の促進に成功した企業は数多く存在します。ここでは相互理解を深める取り組みの成功事例として、アルーの提供する相互理解への取り組み事例と株式会社ヤクルト本社、株式会社アカツキの取り組みの3つを紹介します。
アルーの事例
日々の業務の中でコミュニケーションに課題が生じていたり、コミュニケーションがメンバーのストレスにつながっていたりすることは珍しくありません。人材育成会社のアルーでは、相互理解を深めるためにMBTI®(※注)やストレングスファインダーを活用しています。
MBTI®(※注)で自分の認知スタイルについて学びを深めたのち、社員の強みを発見するストレングスファインダーを全社員に実施しています。結果を全社員に共有した上で相互理解ワークショップに活用しており、効果的な相互理解を促進しています。
※注:MBTI is a registered trademark of the Myers&Briggs Foundation in the United States and other countries.
株式会社ヤクルト本社
株式会社ヤクルト本社では、記事の中でも紹介したジョブローテーション制度を導入しています。入社後10年の間で、どの社員も3つの部署を経験するように制度が運用されており、営業、企画、総務や経理といった幅広い職種に取り組めるのが特徴です。
ヤクルト本社では、こういったジョブローテーションを通じて、必然的に多くの社員が部署の垣根を越えた関わりを持つようになりました。従業員一人一人がさまざまな価値観に触れることができ、部門間での連携もスムーズになった成功事例です。
参考:Sustainability Report 2022|ヤクルト本社
株式会社アカツキ
株式会社アカツキでは、本記事の中で紹介したシャッフルランチをさらに工夫した独自のランチ制度を実施しています。会社負担で役員とランチできる機会を設けることで、上下関係を超えた相互理解の促進を目指しています。
世代の離れがちな一般社員と役員では、価値観や考えていること、目指す方向性なども大きく異なります。こういったランチ会を通じて新入社員や若手社員が会社の目指す方向を理解できるのはもちろん、役員側も若手の価値観について理解を深めることができ、経営方針の改善や生産性の向上につながっているのです。
参考:提供する自分たちがそうあるべき。だから社内のメンバーをワクワクさせる為だけの組織が存在します | Akatsuki TERRACE
まとめ
相互理解を深める取り組みや、相互理解を深める際に知っておきたいポイントなどについて細かく解説しました。相互理解を深めれば部署間での連携がスムーズになる、上下の垣根を超えたコミュニケーションが可能になる、といった様々な効果が期待できます。
相互理解を深めるための取り組みは今回紹介したもの以外にも様々なユニークなものが生まれてきており、今後もますますそうした取り組みは注目されていくでしょう。ぜひこの記事の内容を活用して相互理解を深める施策についての理解を深め、自社の生産性向上につなげてください。