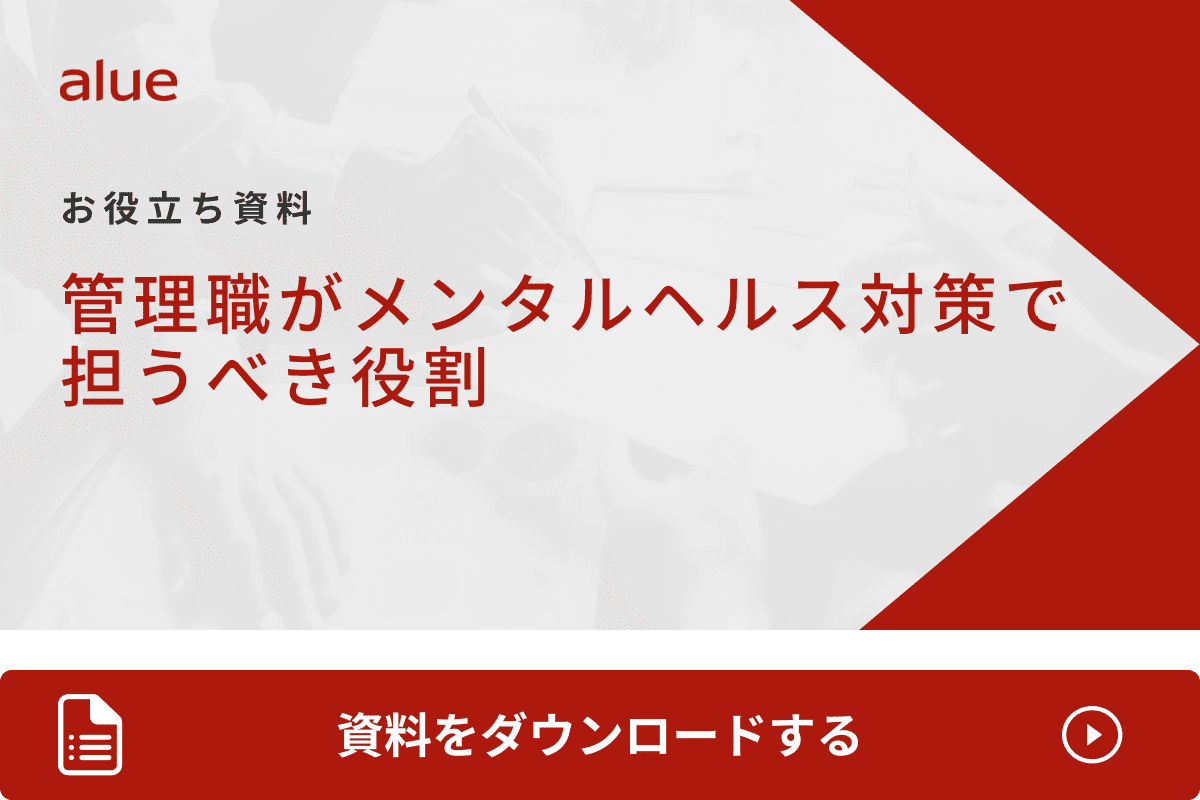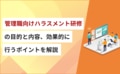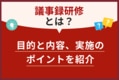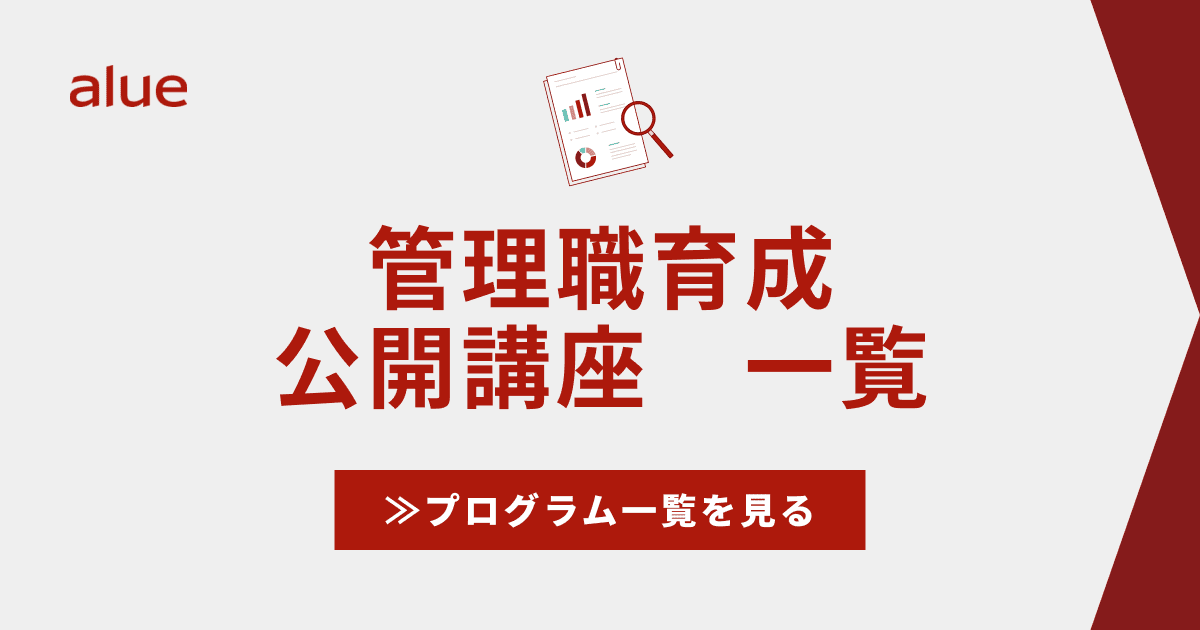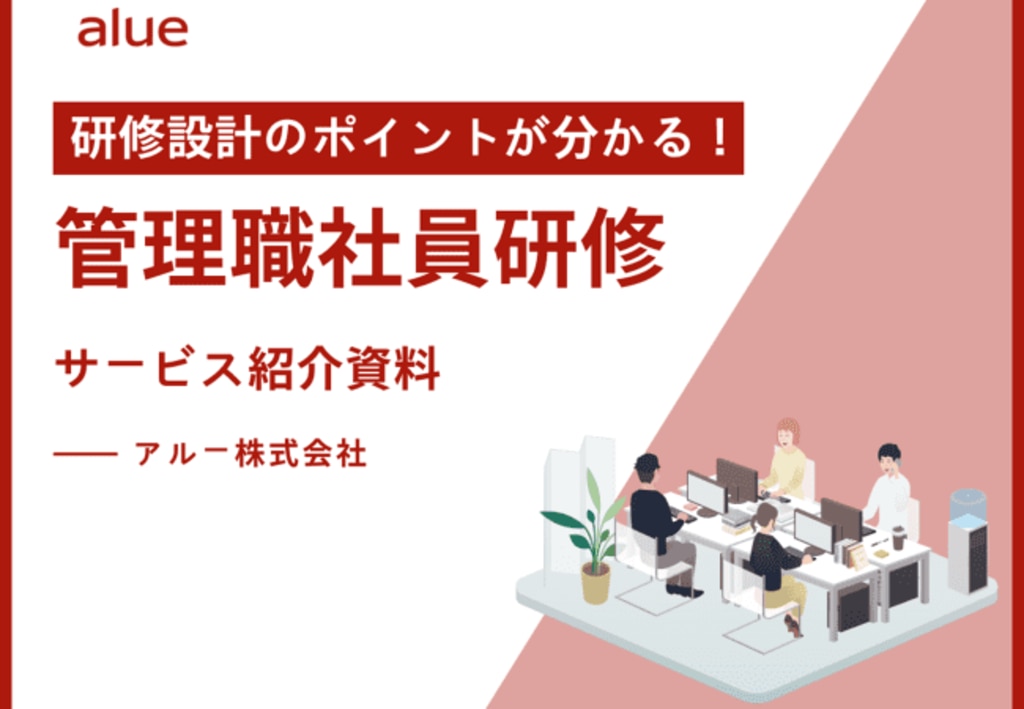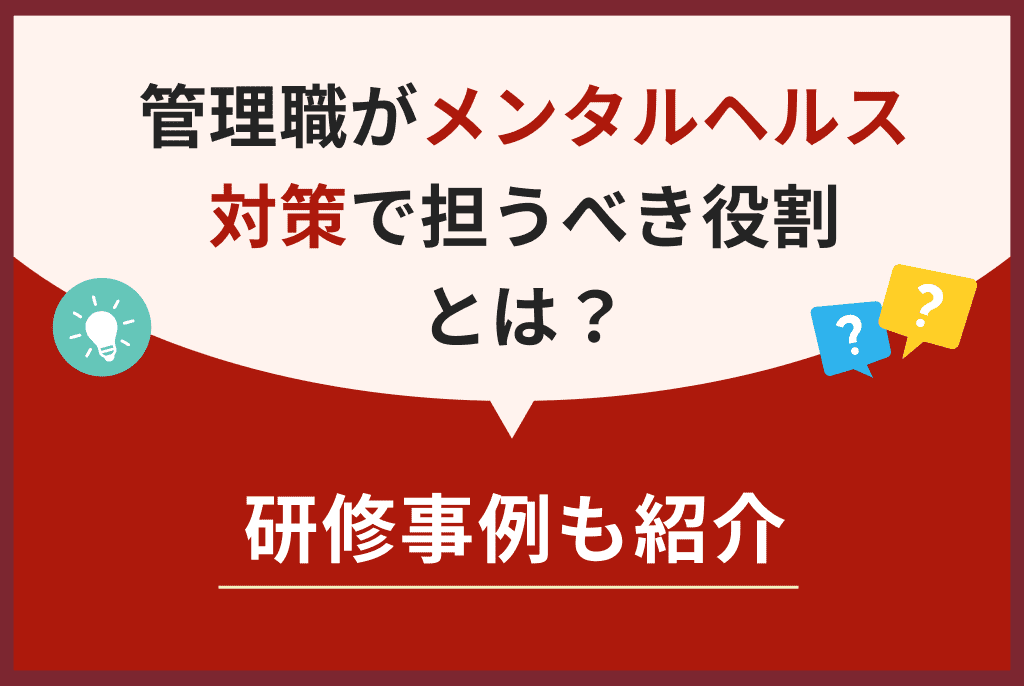
管理職がメンタルヘルス対策で担うべき役割とは?研修事例も紹介
近年、社員のメンタルヘルスが仕事のパフォーマンスを大きく左右することがわかってきました。メンタルヘルスは離職率とも深い関係があるため、企業側は社員のメンタルヘルス向上を積極的に行う必要があります。
社員のメンタルヘルスを維持する上で大切な役割を果たすのが、社員を指導する立場にある管理職です。この記事では、管理職がメンタルヘルス対策で担うべき役割や具体的な対応、メンタルヘルス研修の内容などを解説します。
成のポイントを解説します。ぜひ参考にしていただき、人材育成を成功させてください。
より深く知るための『オススメ』お役立ち資料
目次[非表示]
企業におけるメンタルヘルス対策の重要性
企業におけるメンタルヘルスは、近年ますます重要視されるようになってきています。どうして企業におけるメンタルヘルス対策がこれほどまでに推進されるようになったのでしょうか。
理由としては、国によるストレスチェック制度の義務化やワークスタイルの変化などが挙げられます。企業におけるメンタルヘルス対策の重要性を解説します。
「ストレスチェック制度」が2015年に義務化されている
ストレスチェック制度とは、企業側が定期的に社員のストレス状況のテストを実施することを定めた制度です。ストレス状況に対する自己理解を深めてメンタルヘルス不調を防いだり、メンタルヘルス不調の起きにくい労働環境を実現したりするといった目的があります。
ストレスチェック制度は、2015年に50人以上の従業員を抱える事業所を対象に実施が義務付けされました。こうした背景から企業側のメンタルヘルスに対する意識が高まり、社員のメンタルヘルス対策を推進する企業が増えてきています。
メンタルヘルスは離職率に深い関わりがある
メンタルヘルス対策が推進されるようになった背景として、メンタルヘルスと離職率に深い関係があることがわかってきた点も挙げられます。厚生労働省が2021年に公表した実態調査によると、過去1年間にメンタルヘルス不調によって休業したり、退職したりした労働者のいる事業所の割合は10.1%でした。
参考:令和3年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概況|厚生労働省
メンタルヘルス不調によって社員が離職・休職した場合、残された社員の負担が増大してしまう可能性もあります。そのため、メンタルヘルス不調が起きないような環境を事前に整えておくことが重要なのです。
ワークスタイルの変化でメンタルヘルス不調は多様化している
ワークスタイルの変化も、メンタル不調に対する取り組みが強化されるようになった一因です。新型コロナウィルスの流行以降、テレワークを積極的に取り入れる企業が増えてきました。こうした働き方は便利な一方、職場でのコミュニケーションが希薄化してしまうといった課題も存在します。
実際、テレワークによるコミュニケーション不足で相談できる人がいなくなってしまったり、孤独感を覚えたりする社員は多いです。新たな働き方によって多様化したメンタルヘルス不調に対応するため、企業側の対策が求められています。
新たな働き方に対応したオンラインコミュニケーションについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
『オンラインコミュニケーションの課題とその解決のための一工夫』
厚生労働省が推奨する「4つのメンタルヘルスケア」とは

社員のメンタルヘルス不調を防ぐため、厚生労働省は以下の4つのメンタルヘルスケアを推奨しています。
- セルフケア
- ラインによるケア
- 産業保健スタッフなどによるケア
- 社外の資源によるケア
セルフケアとは、企業が研修の実施などを通じて社員にメンタルヘルスに対する正しい理解を促進し、ストレスへの対処を促すケアです。ラインによるケアとは、職場環境の改善や社員からの相談に応じるなど、管理監督者が行なうべきアプローチを指します。
企業が社員のメンタルヘルスケアを推進する際には、このような複数の視点からアプローチするのが大切です。このほか、産業保健スタッフが積極的に携わったり、医療機関との連携など社外資源を活用したりする方法も推進されています。
メンタルヘルス対策を行う上での管理職の役割
メンタルヘルス対策を行う上では、管理職が大切な役割を担います。例えば部下がいつもと違う様子を見せたら適切な対応を行う必要がありますし、部下からの相談には的確に応えるべきです。また、管理職自身のメンタルケアも忘れないようにしましょう。
メンタルヘルス対策を行う際の管理職の役割を解説します。
管理職自身のメンタルケア
管理職が部下のメンタルヘルスを適切にケアするためには、管理職自身のメンタルケアが欠かせません。まずは、管理職自身がメンタルヘルス不調に陥らないような環境を整える必要があります。
例えば社内にメンタルヘルスの相談ができる窓口を設置したり、部署をまたいだコミュニケーションを推進する仕組みを作ったりするのがよいでしょう。運動施設を充実させる、会社の敷地に緑を増やすといった取り組みも、職場環境の改善を通じたメンタルヘルス対策の一環です。プレッシャーやストレスのかかりやすい管理職だからこそ、積極的にメンタルヘルス対策を行う必要があります。
特に新任管理職は、マネジメント面や精神面などに関する悩みを抱えやすいです。新任管理職の悩みを解決するための施策については、以下の記事で詳しく解説しています。
『新任管理職の悩み解決にはオンボーディングが必須!人事が取り組むべき施策』
いつもと違う部下の把握と対応
管理職によるラインケアを実践していく上では、部下の「いつもと違う」様子を管理職が察知して、対応する必要があります。いつもと違う様子としては、例えば以下のようなものが考えられます。
- 遅刻や早退、欠勤が増える、無断欠勤がある
- 残業や休日出勤が増える
- 思考力や判断力が低下したり、勤務態度が悪化したりする
- 職場での会話がなくなる、不自然な言動が目立つ
こうした様子が部下に見られたら、背後に病気が隠れている可能性もあります。管理職は必要に応じて産業医のところへ相談に行かせたり、あるいは管理職自身が相談に行ったりして、適切な対応を取ることが大切です。
部下からの相談への対応
部下から相談があれば、管理職は真摯に対応する必要があります。自分から進んで情報を得る「積極的傾聴」を意識しながら、部下からの相談対応にしっかり時間を割きましょう。
管理職は部下の抱える課題を把握したら、組織の制度改善や施策導入を通じて対策を実施したり、内容によっては産業医やカウンセラーへの相談を促したりする必要があります。また、部下からの相談対応を行うためには、日頃から部下が相談しやすい環境を整えるのが重要です。管理職の方から積極的に声をかけるといった点も意識させましょう。
積極的傾聴に関してや傾聴力を高める方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
『管理職が傾聴力を高める育成方法とは?傾聴力を高めるメリットと目的』
メンタルヘルス不調の部下の職場復帰支援
メンタルヘルス不調から復帰した部下は、「職場で自分はどう思われているのだろうか」「また病気が悪化しないだろうか」などと、様々な不安を抱えています。復帰した以上はしっかりとパフォーマンスを発揮してもらいたいと考えるのは管理職として自然なことですが、管理職はメンタルヘルス不調から復帰した部下の気持ちをまずは受け止めることに努めましょう。
部下との対話や傾聴を通じて信頼関係を構築できれば、「上司は自分のことをわかってくれている」と感じてもらえ、復職した部下の負担は大きく軽減されます。また、管理職がそうした姿勢を見せれば、他の部下も安心感を覚えたり、緊張が和らいだりするでしょう。
管理職に求められるコミュニケーションスキルについては、以下の記事で詳しく解説しています。
『管理職に必要なコミュニケーションスキルとは|コツやスキルの身につけ方を解説』
管理職が知っておくべき部下のメンタル不調のサイン

部下のメンタル不調のサインを把握しておくことは、管理職が部下のメンタルを把握する上でとても重要です。
部下のメンタル不調のサインとして、欠勤や早退の増加、勤務態度の悪化などが挙げられます。メンタル不調が起こると、仕事に対する前向きな気持がなくなってしまいます。職場から距離を置きたいといった気持ちが、結果として遅刻や早退、欠勤といったサインとして現れる場合があります。
また、仕事のパフォーマンスが低下したり、報連相が滞ったりするのもメンタル不調のサインです。仕事でのミスが増えたり、以前ほどコミュニケーションが活発でなくなったりした社員に対しては、管理職側から積極的に声をかけるといった配慮が求められます。
管理職が行うべきラインケアの具体的な対応
管理職が行うべきラインケアとしては、部下や同僚の様子を観察したり、声掛けをして傾聴したりするといったものが挙げられます。また、職場に存在するストレスを特定し、制度運用などを通じて改善するのも管理職の役割です。
管理職が行うべきラインケアの具体的な対応を見ていきましょう。
部下・同僚の様子を観察する
管理職が部下や同僚のいつもと違う様子に気づくためには、日頃から部下や同僚のことをよく観察しておく必要があります。いつも自分の仕事ばかりに集中するのではなく、広い視野を持ってメンバーが順調に仕事を進めているか確認する姿勢が大切です。
具体的には、部下の席へ様子を見に行ったり、1on1などで定期的に順調かどうか確認したりするとよいでしょう。ただし観察しすぎると部下へかえってプレッシャーを与えることにもなるため、あくまでも必要に応じて自然に観察するのが重要です。
1on1を実施するステップや進め方に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
『1on1とは?目的や意味がないと言われる理由、効果を高めるポイントを紹介!』
声掛けをし、話を聴く
部下の不調に気づくためには、積極的に管理職側から声掛けをしたり、話を聴いたりすることも有効です。
部下から相談がない場合でも、悩みごとがないとは限りません。特に入社から間もない社員は、「忙しそうな上司にいつ相談すればよいのだろうか」と相談をためらってしまう場合もあります。こうした不安を解消するためにも、管理職が積極的に部下の様子を気にかけてあげるとよいでしょう。また、相談を受けた際には仕事を進めながら相談を受けたり途中で自分の話をしたりせずに、しっかりと相手の悩みを傾聴する姿勢が大切です。
傾聴のコツについて詳しくは以下の記事をご覧ください。
『管理職が傾聴力を高める育成方法とは?傾聴力を高めるメリットと目的』
職場ストレスを特定し、改善する
部下のメンタル不調が起こる場合には、職場にストレスを与える原因が存在する場合があります。こうした際には、管理職が職場ストレスの要因を特定し、改善することが大切です。
ストレスの原因として特に多いのが、職場での人間関係やコミュニケーション不足です。人間関係に関する問題は、社員間でのコミュニケーションが偏っていたり、足りなかったりすると発生しやすくなります。シャッフルランチやフリーアドレス制の導入を働きかけたり、ミーティングで積極的に話す機会を設けたりと、意識的に対策しましょう。
管理職が職場内のコミュニケーション改善に時間をかけられない場合、人事部からチームビルディング研修を提案するのもおすすめです。チームビルディング研修の目的や事例に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
『【事例あり】チームビルディング研修の目的やおすすめのゲームを紹介』
心理的安全性を高める
心理的安全性とは、組織に対して覚える安心感のことです。心理的安全性が高いと「この組織ならどんな意見を言っても大丈夫」「ありのままの自分でいられるな」と感じられるため、チーム内の意見交換が活発になったり、誰もが居心地のよい組織となったりします。
メンタルヘルス不調に対するラインケアとしては、心理的安全性を高めるのも有効です。メンバーの傾聴力を高めたり、意見交換の際に意見を尊重する姿勢を見せたりなど、心理的安全性を高める施策を講じましょう。
心理的安全性を高める方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。
『心理的安全性とは?高める方法や人事が行うべき施策について』
仕事の調整や医師への受診を勧めるかの判断をする
会社は医療機関ではないため、メンタルヘルスに関する病気を治療することはできません。管理職は必要に応じて、仕事の量を調整したり、医師への受診を勧めたりといった対応を取りましょう。
なお、結果的に休職が必要と判断された場合にはチーム内の協力が欠かせません。他のメンバーの業務量が極端に増えてしまうと、休職に対するネガティブな意見が出る可能性もあります。メンバーとよく話し合って業務量を調整するなど、メンバーの離脱時にも協力しあえる風土を醸成しましょう。
管理職向けのメンタルヘルス研修とは
メンバーのメンタルヘルスを管理することは、チームのパフォーマンスを向上させる上で極めて大切です。チームのメンタルヘルス管理を実現するためには、管理職に対するメンタルヘルス研修が役立ちます。
管理職向けに実施するメンタルヘルス研修の目的や、メンタルヘルス研修の内容を解説します。
メンタルヘルス研修の目的
管理職向けに実施するメンタルヘルス研修の目的としては、以下のようなものがあります。
- メンタルヘルスとパフォーマンスの深い関係に気づき、意識を高める
- 事例に基づいてメンタルヘルスへの理解を深め、正しい対応を学ぶ
- 部下とのコミュニケーションによってメンタルヘルスを管理する方法を学ぶ
- 自分自身のメンタルヘルスの不調に素早く気づき、的確にアプローチする方法を知る
管理職にメンタルヘルス研修を実施すればメンタルヘルス管理能力が向上し、パフォーマンスの向上や離職・休職防止といった様々な効果が期待できるのです。
メンタルヘルス研修の内容
メンタルヘルス研修では、まずメンバーのメンタルヘルスが仕事のパフォーマンスへどう影響するのかを学んでもらいます。その後、メンバーのメンタルヘルスを管理する方法について、ケーススタディなどで取り上げるのがおすすめです。
また、メンバーのメンタルヘルスを管理する際には、メンバーと管理職の間でのコミュニケーションが必要不可欠です。メンバーからの悩みをしっかりと受け止めて理解する「傾聴力」や、部下との信頼関係を構築するためのコミュニケーション力、マネジメント手法について学んでもらいましょう。
メンバーのメンタルヘルス管理に欠かせない管理職のコミュニケーションスキルについては、以下の記事で詳しく解説しています。
『管理職に必要なコミュニケーションスキルとは|コツやスキルの身につけ方を解説』
アルーのメンタルヘルス研修の事例

コールセンターを運営するA社では、スーパーバイザー職がチームメンバーや自身のストレスをうまくコントロールできていないという課題がありました。
そこで、アルーではストレスコントロール力の向上を目的に、コールセンター部門に所属している管理職120名を対象にメンタルヘルス研修を実施しました。メンタルヘルス不調の原因を分析し、「互いを尊重する姿勢の不足」「相談や質問へのためらい」「反対意見へのおそれ」という3つに分けてアプローチを行いました。互いを尊重する風土を醸成するためのメンバーとの関わり方やモチベーション管理の手法を学んでもらった結果、管理職のマネジメントスタイルの改善を通じて適切なメンタルヘルス管理を実現した事例です。
まとめ
管理職がメンタルヘルス対策で担うべき役割や、管理職を対象としたメンタルヘルス研修の目的や内容を解説しました。メンバーのメンタルヘルスは、チームのパフォーマンスを大きく左右する大切な要素です。
管理職が適切にメンバーとコミュニケーションを取ってマネジメントを行えば、メンバーのメンタルヘルス不調を未然に防いだり、早期に発見できたりします。ぜひこの記事の内容を参考にメンタルヘルス対策を実施して、チームのパフォーマンス向上や離職防止につなげていきましょう。