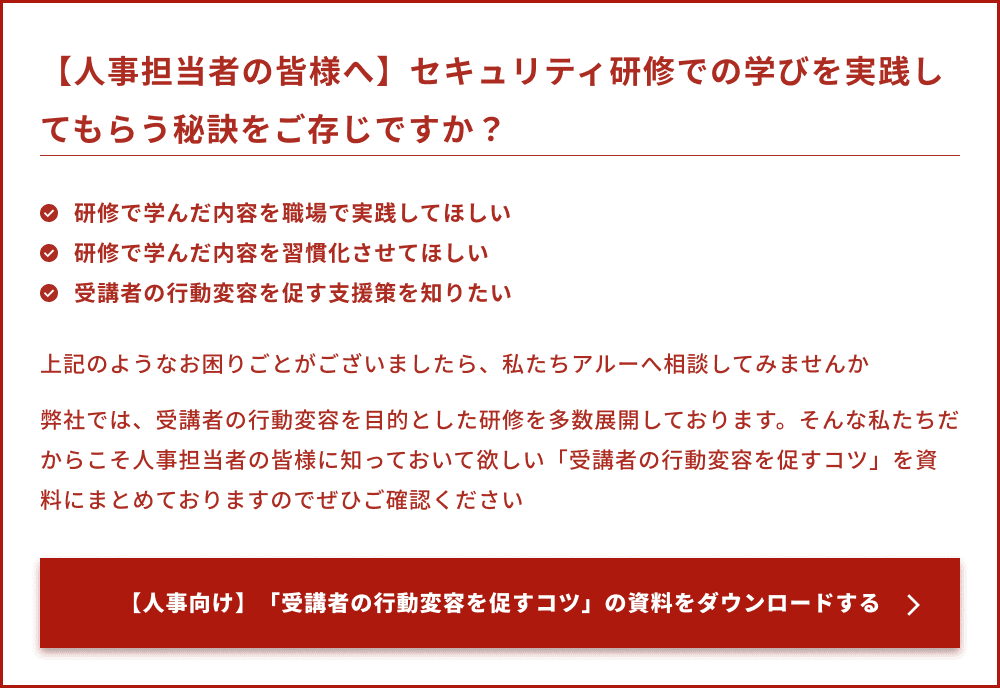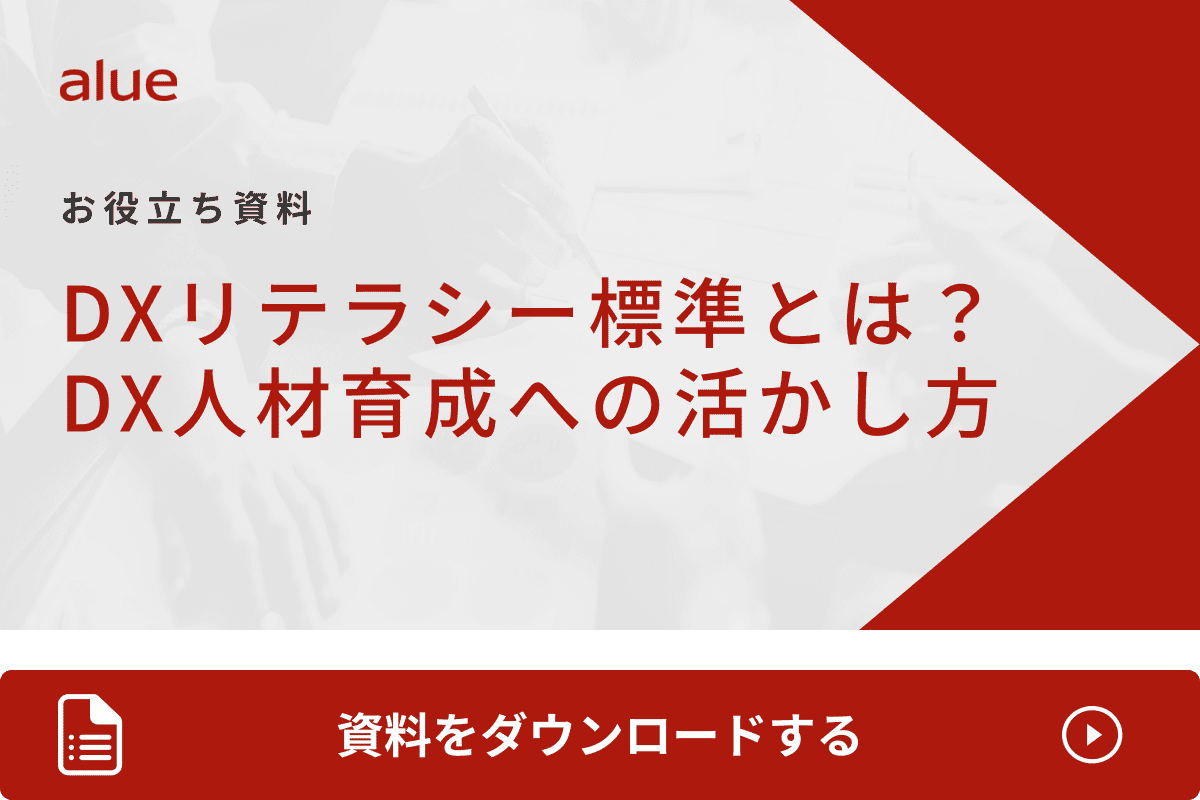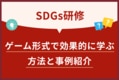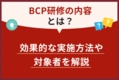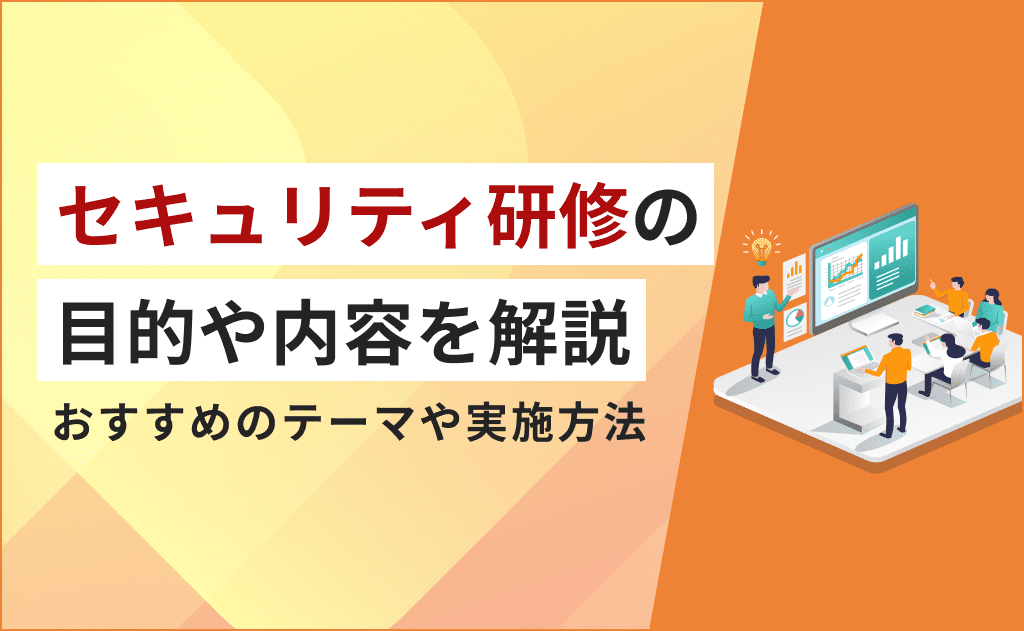
セキュリティ研修の目的や内容を解説。おすすめのテーマや実施方法
ビジネスの至る所でITが活用されている昨今、セキュリティは企業にとって重要な課題です。セキュリティによるリスクを最小限に抑えるためには、社員に対してセキュリティ研修を実施するなど日頃からの備えが欠かせません。
そこでこの記事では、セキュリティ研修を実施する目的や内容を解説します。セキュリティ研修を実施したいと考えている人事担当者の方は、ぜひご参考にしてください。
目次[非表示]
セキュリティ研修とは
セキュリティ研修とは、サイバー攻撃やSNSによるトラブルなど、企業の直面する様々なセキュリティリスクを抑えるために実施される研修のことです。ITリテラシーやネットワークに関する基本的な内容から、SNSの使い方のルールまで幅広い内容が扱われます。業種や業界を問わずITが様々な場面で活用されるようになっている昨今、セキュリティ研修の重要性はますます高まっているといえるでしょう。
最新版「情報セキュリティ10大脅威」
一言で「情報セキュリティ」といっても、その内容は様々です。まずは、情報処理推進機構(IPA)が発表している、組織に対する情報セキュリティ10大脅威を見てみましょう。
順位 |
脅威の種類 |
1位 |
ランサムウェアによる被害 |
2位 |
サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃 |
3位 |
標的型攻撃による機密情報の窃取 |
4位 |
内部不正による情報漏えい |
5位 |
テレワーク等の |
6位 |
修正プログラムの公開前を狙う攻撃 |
7位 |
ビジネスメール詐欺による金銭被害 |
8位 |
脆弱性対策の公開に伴う悪用増加 |
9位 |
不注意による情報漏えい等の被害 |
10位 |
犯罪のビジネス化 |
(引用元:情報セキュリティ10大脅威2023|情報セキュリティ|IPA独立行政法人情報処理推進機構)
組織としての脅威では、ウィルスに感染したコンピュータを動作させるために身代金を請求するランサムウェアによる被害が1位にランクインしています。また、機密情報の窃取や情報漏えいなど、情報を外部へ流出させる脅威が目立っているのも特徴です。
セキュリティリスクは経営リスクである
セキュリティリスクは、企業にとって経営リスクといっても過言ではありません。例えば情報流出事案が発生してしまった場合、損害賠償を請求される可能性が高いです。
また、金銭的なリスクだけでなく、社会的信用が低下してしまうリスクもあります。情報流出や不正アクセスといった問題が発覚した場合、直接被害が及ばなかった取引先やユーザーからの評価も低下してしまう可能性が高いです。
新入社員に特に必要とされる
情報セキュリティは全社員が身につける必要がありますが、特に情報セキュリティ関連でのトラブルが目立つのは新入社員です。学生時代には問題にならなかったということも、社会人としてはモラル違反になることを知ってもらう必要があります。情報セキュリティ対策を考える際には、新入社員を重点的に教育しましょう。
中でも、SNSに関連するトラブルが圧倒的に多いのは新入社員です。企業内の機密情報を軽い気持ちでSNSへ投稿してしまったり、職場への悪口の書き込みが拡散されてしまったりと、SNSに関連したトラブルは跡を絶ちません。日頃からSNSに慣れ親しんでいる年代だからこそ、重点的な教育が必要です。
新入社員への情報セキュリティ研修について詳しくは以下の記事もご覧ください。
『新入社員研修でのIT研修|おすすめのカリキュラム・ポイントについて』
セキュリティ研修の目的
セキュリティ研修を実施する目的は、情報セキュリティによるトラブルを未然に防ぐことです。例えば先述したような情報流出などの事案が発生してしまうと、企業は金銭的・社会的に多大な損害を受けてしまいます。
こうしたリスクを最小限に抑えるためには、社員に対して情報セキュリティ研修を実施し、正しいIT技術の活用方法を学んでもらうことが欠かせません。IT技術に関する基礎知識やSNSを使う際のルール、関連する法律などについて幅広く学んでもらい、セキュリティリスクを可能な限り減らしましょう。
セキュリティ研修の企画の流れ
セキュリティ研修を企画する際には、まずセキュリティ研修を実施するタイミングを決めましょう。その後、対面研修やオンライン研修などの研修スタイルを決定し、研修の対象者など詳細を詰めていくという流れです。
セキュリティ研修を企画する際の流れについて、ステップごとに意識したい点も交えながら解説します。
実施のタイミングを決める
セキュリティ研修を実施する際は、まず研修を実施するタイミングを決めましょう。その他の研修スケジュールと照らし合わせながら、研修に最適な日程を絞り込んでいきます。一般的には、新入社員が入社する4月に実施する企業が多いでしょう。
なおセキュリティ研修は、新入社員から管理職まで全社員が対象となる研修のため、参加人数が多くなりがちです。多くの人が参加しやすくなるよう、繁忙期をできるだけ避けるといった工夫をしてみてください。
研修スタイルを選択する
研修のスケジュールが決定したら、研修スタイルを選択しましょう。情報セキュリティ研修を実施する際のスタイルとしては、対面研修やオンライン研修、eラーニングやブレンディッドラーニングなど複数のスタイルが考えられます。
それぞれの研修スタイルには一長一短があるため、自社の規模や状況にあったスタイルを選択するのが重要です。それぞれのスタイルの特徴を詳しく解説します。
対面研修
対面研修は、研修会場へ社員に集まってもらって実施するタイプの研修です。講師が研修会場で講義を行うオーソドックスなものはもちろん、ディスカッションやグループワークなどを取り入れたアウトプット重視の研修も実施できます。
対面研修のメリットは、参加者と講師、あるいは参加者同士のコミュニケーションが取りやすい点です。互いに意見交換をしながら研修を進められるため、研修でのコミュニケーションが一方通行になることを防げます。一方で後述するオンライン研修などに比べると、研修の運営コストはやや高めです。
オンライン研修・eラーニング
オンライン研修は、ZoomやMicrosoft Teams、YouTube Liveといったオンライン会議ツールを活用して実施する研修です。対面研修に比べると、研修会場へ直接出向かなくてよいというメリットがあります。情報セキュリティ研修は全社横断的に実施するケースも多いため、研修を効率よく実施したい場合にはおすすめです。
また、ビデオなどの学習教材をオンライン上で配信して学習を進めるeラーニングの手法も有効です。ITに関連する知識は社員間で差がつきがちですが、eラーニングを活用すれば個人個人の理解度に合わせた学習ができます。
オンライン研修のポイントについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
『オンライン研修のやり方やメリット・デメリットをわかりやすく解説』
ブレンディッドラーニング
ブレンディッドラーニングはeラーニングと対面研修を併用して実施する研修スタイルです。基礎知識などのインプットはeラーニングで実施し、インプットした内容を基にしたディスカッションなどのアウトプットを対面形式で実施します。
ブレンディッドラーニングのメリットとして、効率的なインプットを叶えつつ、双方向のコミュニケーションや受講者のアウトプットも行なえる点です。情報セキュリティ研修では、個人情報保護法やSNSのトラブル事例などをeラーニングでインプットし、セキュリティ対策を考えるディスカッションを対面形式で実施するといったスタイルが考えられます。
ブレンディッドラーニングについて詳しくは以下の記事をご覧ください。
『【事例あり】ブレンディッドラーニングとは?効果的な方法や注意点を徹底解説』
研修の対象者を決める
研修スタイルが決まったら、研修の対象者を決めましょう。もちろん理想は全社員に情報セキュリティを身につけてもらいたいところですが、実際には全社員へ一度に研修を実施するわけにはいきません。情報セキュリティのリスクが潜在的に高い社員を中心に、情報セキュリティ研修に参加してもらう社員の優先順位付けを行いましょう。
記事の冒頭でも紹介したように、最近では新入社員によるSNS関連のトラブルが増えてきています。SNSによるトラブルを防ぐためにも、新入社員は重点的に教育を実施するのがおすすめです。
効果測定の方法を決める
研修を実施する際に大切なのが、効果測定です。せっかく研修を実施しても、効果を測定せずに放置してしまっては、研修の意味が半減してしまいます。研修によってどのような効果が生まれ、どのような行動変容につながったのかを把握するための方法を予め決めておきましょう。
例えば、研修終了後に時間をおいてフォローアップ研修を実施したり、振り返りシートを記入してもらったりといった方法が考えられます。eラーニングやオンラインで研修を実施した場合には、内容の理解度テストに取り組んでもらうのもよいでしょう。
研修の効果測定の方法は、以下の記事で詳しく解説しています。
『研修効果測定の方法とは|4つの評価レベルや効果測定のポイント』
【監修者からひとこと】 セキュリティ研修の企画には、研修スタイルの選定も含まれます。対象が全社員で、目的がコンプライアンスの場合、eラーニングを活用すると効果的です。特にLMSを導入していれば、全社員の受講状況やテスト合格状況を簡単に管理でき、人事の事務作業の負担を最小限に抑えて運用することが可能です。 |
セキュリティ研修の内容・おすすめテーマ

セキュリティ研修を実施する際には、具体的にどういった内容を扱うのがよいのでしょうか。
セキュリティ研修の内容としては、個人情報保護法などの法律や、SNSを利用する際のルールなどメディアポリシーについて学んでもらうのがおすすめです。また、情報セキュリティポリシーや攻撃メールについての理解も深めてもらいましょう。
情報セキュリティ研修で扱う内容について、それぞれ細かく解説します。
個人情報保護法について
個人情報の保護は情報セキュリティの中でも特に優先的に対処しておくべき事項です。情報セキュリティ研修では、個人情報の保護について学んでもらうとよいでしょう。
まずは、個人情報保護法という法律が存在することを知ってもらい、違反した場合には懲役や罰金などの罰則が設けられていることや、具体的に何が規制されているのかについて知ってもらいましょう。また、情報が流出した際にはこうしたペナルティが課されるだけでなく、企業が社会的な信頼を失うことを理解してもらうのも重要です。個人情報流出事例とそれによる損害を紹介し、自分事として捉えてもらえるよう工夫しましょう。
eラーニング個人情報保護講座のカリキュラム例
個人情報保護法はeラーニングで学んでもらうのもおすすめです。以下は、アルーが提供する個人情報保護講座のeラーニングカリキュラム例です。
No. |
タイトル |
概要 |
形式 |
|
1 |
個人情報保護法講座 |
個人情報保護法に対して、下記テーマに関する正しい理解を得る
|
動画 |
40 |
2 |
確認テスト |
動画で学んだ内容を確認する |
テスト |
10 |
SNS利用などのメディアポリシーについて
今の時代、ほぼすべての社員がプライベートで何らかのSNSを利用しています。SNSを社員が利用するということは、企業にとって潜在的な情報セキュリティのリスクでもあります。
情報セキュリティ研修では、SNS利用時のメディアポリシーを伝えるのも重要です。たとえプライベートでしか使っていないアカウントであっても、プロフィールや投稿の内容から勤務先が特定され、会社にまで被害が及ぶケースは少なくありません。研修では、「どういった投稿が問題になるのか」「どういった影響があるのか」を伝え、必要に応じてSNSの利用ルールを設定するのもよいでしょう。
情報セキュリティポリシーについて
情報セキュリティポリシーとは、「企業にはどういった情報資産があり、どのような脅威からどのような手段で守るのか」を明確にした企業としての基本方針です。情報セキュリティを確保するための具体的な体制や対策、運用方針などがまとめられています。
情報セキュリティ研修では、企業の定める情報セキュリティポリシーを理解してもらいましょう。情報セキュリティポリシーを設定しても、認知されていなければ効果がありません。研修の中で、「自社にはどういった情報セキュリティポリシーがあり、どのような運用がされているのか」を理解してもらいましょう。
個人を標的にした攻撃メールについて
特定の個人を標的にメールを送信し、サイバー攻撃を仕掛ける手口が増えてきています。「標的型攻撃メール」と呼ばれており、メールを開封した社員を通じて社内の機密情報が漏えいする事例が確認されています。
個人を標的にした攻撃メールについて情報セキュリティ研修で取り上げるのもおすすめです。まずはこうした攻撃の手口があることを伝えた上で、「怪しいメールは開封しない」「万が一開封してしまったらネットワークから切り離す」といった基本的な対応策をレクチャーしましょう。
【監修者からひとこと】 セキュリティ研修の内容やおすすめのテーマは多岐にわたります。例えば、サイバー攻撃の種類と対策や、パスワード管理に関するテーマがあります。現在の課題に対応するだけでなく、将来的に起こりうるリスクに備えるためにも、どのようなテーマがあるか全体像を把握しておくことが重要です。 |
セキュリティ研修を効果的に実施するポイント

セキュリティ研修を効果的に実施するためには、社員に当事者意識を持ってもらうことが重要です。また、身近な話題として捉えてもらうためにも、再現性の高い研修内容にしたり、セキュリティ事故の危険性を周知したりする必要があります。
セキュリティ研修の効果を高めるために意識しておきたいポイントを3つ解説します。
社員に当事者意識をもってもらう
IT機器を活用する以上、ウィルスに感染したり、何らかのトラブルに巻き込まれたりする可能性はゼロではありません。情報セキュリティに関するリスクは、全社員が関わるものです。
情報セキュリティ研修を成功させるためには、まず社員に当事者意識を持ってもらうことが重要です。できるだけ身近なトラブル事例を取り上げたり、日常生活で経験しうる内容を取り上げたりするなど、すべての社員にとって身近な話題であるということを理解してもらえるように工夫しましょう。
再現性の高い研修内容にする
せっかく研修を実施しても、知識を現場で活用できなくては意味がありません。情報セキュリティ研修を実施するのであれば、日頃から実践できるよう実用的な内容を取り上げる必要があります。
情報セキュリティ研修を成功させるためには、再現性の高い研修内容にするよう意識しましょう。そのためには、知識のインプットだけではなくアウトプットにも力を入れることが大切です。例えば「日頃から情報セキュリティを高めるために何ができるか考える」といったディスカッションを実施するなど、参加者同士の意見交流をおこないながら、実務での活用を促しましょう。
セキュリティ事故の危険性を周知する
情報セキュリティに関する脅威といっても、いまいちその危険性がピンとこないという社員は多いです。「情報の流出や漏えいは情報部門だけに関わるもの」「自分には関係ない」といった誤解をしている場合も少なくないでしょう。
研修を実施する際には、セキュリティ事故の危険性を周知し、皆が高いセキュリティ意識を持つことが欠かせないのだと理解してもらうことが大切です。例えば個人情報保護法に違反してしまった際には懲役や罰金などの罰則が設けられていること、情報漏えい事案が発生すると企業は社会的な信用を失うことなど、セキュリティ事故の危険性をしっかりと認識してもらいましょう。
【監修者からひとこと】 セキュリティ研修を効果的に実施するポイントとして、LMS(学習管理システム)の活用があります。LMSを使えば、全社員への受講案内や受講管理を簡単に行うことができ、人事の研修業務の負担を最小限に抑えて運用することが可能です。 |
セキュリティ研修は社内で実施できる?

セキュリティ研修を社内で実施することは不可能ではありません。しかし、社外サービスを活用したほうが情報セキュリティ研修がうまくいくケースが多いのも事実です。自社で研修を実施する場合と、社外サービスを活用する場合のメリットやデメリットを解説します。
自社で研修を行うメリット・デメリット
自社で研修を行うメリットとして、金銭的コストが抑えられる点が挙げられます。社員へ講師を依頼するため、講師への謝礼などの負担が発生せず、トータルの費用は安く抑えられる場合が多いでしょう。また、社内の人材が研修を企画するため、研修内容を自社に沿ったものにしやすいというメリットもあります。
一方、研修運営に社内のリソースを割く必要があるため、時間的なコストが大きい点がデメリットです。また、社内にはないノウハウを取り入れることは難しいため、社外サービスと比べると研修の質はどうしても見劣りします。
自社で研修を行うメリット・デメリットについて詳しくは以下の記事もご覧ください。
『社員研修を内製化するメリット・デメリット|成功のポイントや流れを解説』
社外サービスで研修を行うメリット・デメリット
人材育成のプロフェッショナルである社外サービスを活用することも選択肢の一つです。社外サービスで研修を行うメリットは、社内にはないノウハウを取り入れられるという点です。情報セキュリティに精通した講師が、最新のITトレンドなども交えながらわかりやすく説明してくれるでしょう。
一方、当然ながら講師への謝礼といった金銭的なコストは発生します。最近では人材育成への補助金や助成金も充実しているため、こういった資金を活用するのも手です。
研修の外部委託をするメリットや使える助成金などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
『研修は外部委託すべき?委託している割合や委託先選定のポイント』
セキュリティ研修の委託先の選び方
まず、教材を自社に合わせてカスタマイズできるかどうか確認しましょう。
人材育成業者の中には、業者の準備したテンプレートに沿った研修のみを提供しているところもあります。こうした場合カスタマイズが難しく、自社にあった研修内容にできないという難点があります。
アルーでは、カスタマイズ専任担当が付き、自社に合った研修のカスタマイズを提案いたします。
また、講師がITやセキュリティに関する経験を持っているかも重要なポイントです。ITに精通した講師であれば、専門性の高い内容も噛み砕いてわかりやすく説明してくれるでしょう。アルーでは、厳しい認定基準を基に選抜された約550名の講師から、ITやセキュリティ研修に特化した講師をアサインしています。そのため、専門性の高い研修を行うことが可能です。
全社員にセキュリティ研修を実施する際には、eラーニングと併用できるかも確認しましょう。eラーニングを用いれば、受講者が多くても事前学習や事後テストなどを効率的に実施できます。eラーニングと集合研修を組み合わせることで、より効果的な研修となるでしょう。
アルーでは、LMS「etudes」を利用してセキュリティ研修を実施頂けます。詳しくは下記よりご確認ください。
コンプライアンス|LMS・クラウド型eラーニングシステム「etudes(エチュード)」
セキュリティ研修はアルーにお任せください
セキュリティ研修をご検討の場合は、ぜひアルーへお任せください。人材育成を専門としているアルーは、新入社員研修や階層別研修はもちろん、情報セキュリティ研修も豊富な実績がございます。
アルーの情報セキュリティ研修の特徴は、eラーニングに対応しており、柔軟なカスタマイズが可能な点です。eラーニングと組み合わせながら実施することで、知識のインプットとアウトプットの相乗効果により効率的な学習を進めることができます。セキュリティ研修でお悩みの場合は、ぜひアルーへお気軽にご相談ください。
etudesのセキュリティ研修について詳しくは下記よりご確認ください。
コンプライアンス|LMS・クラウド型eラーニングシステム「etudes(エチュード)」