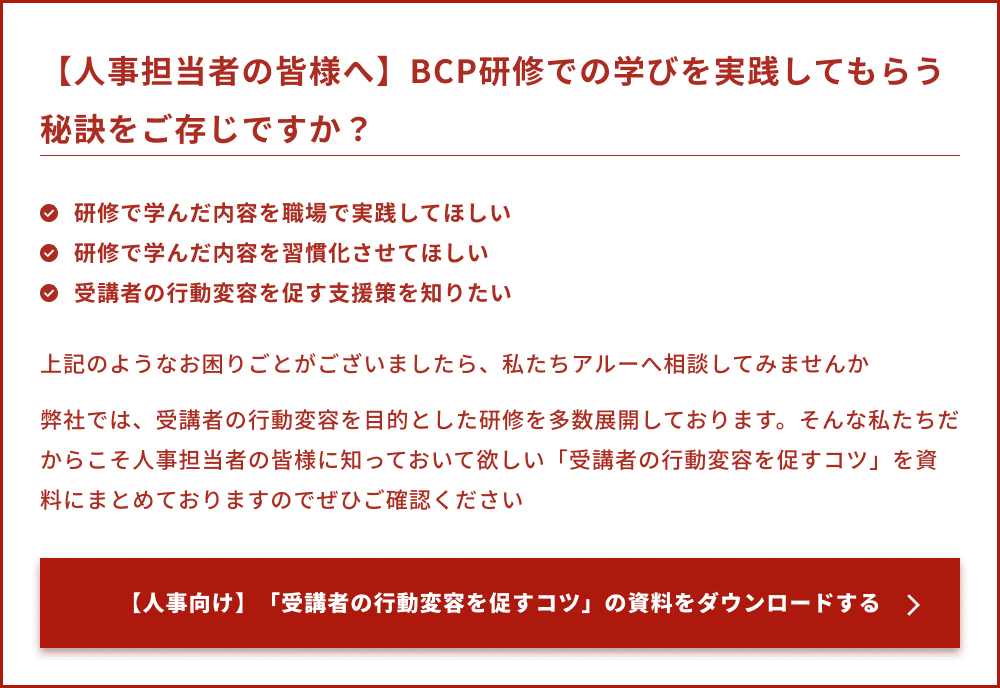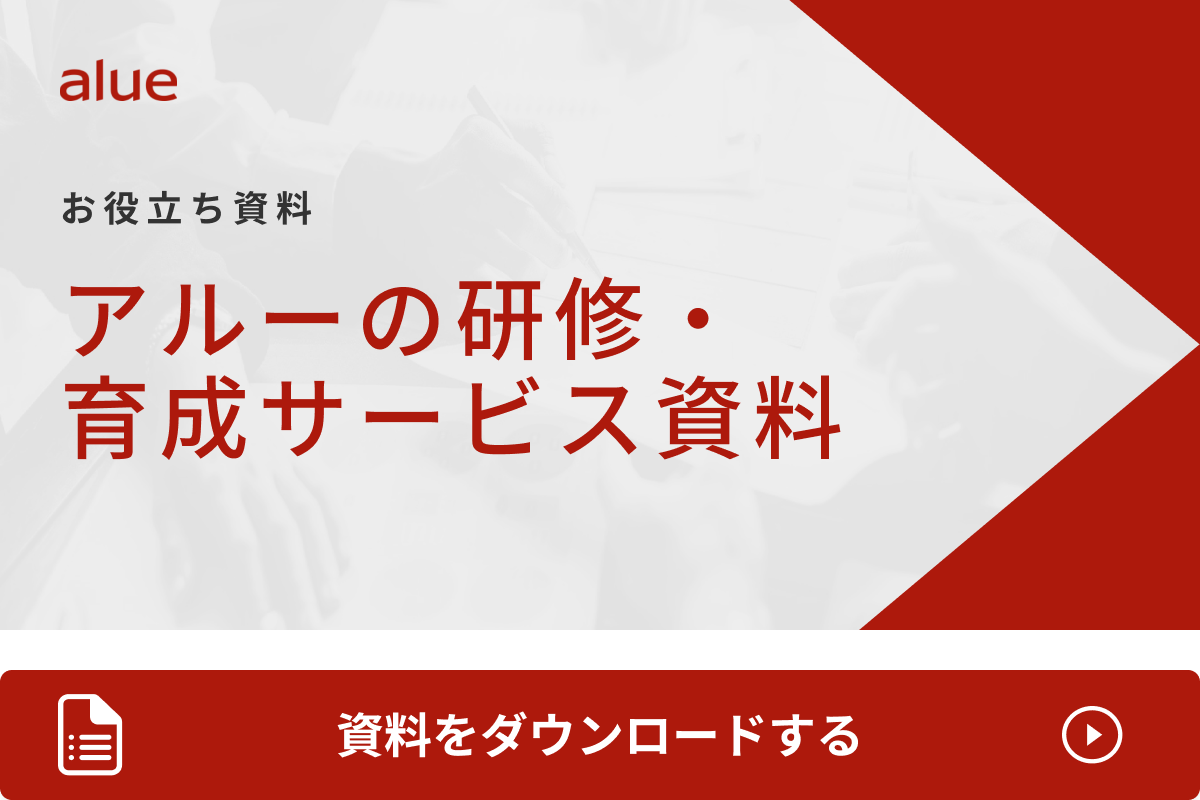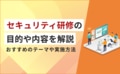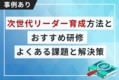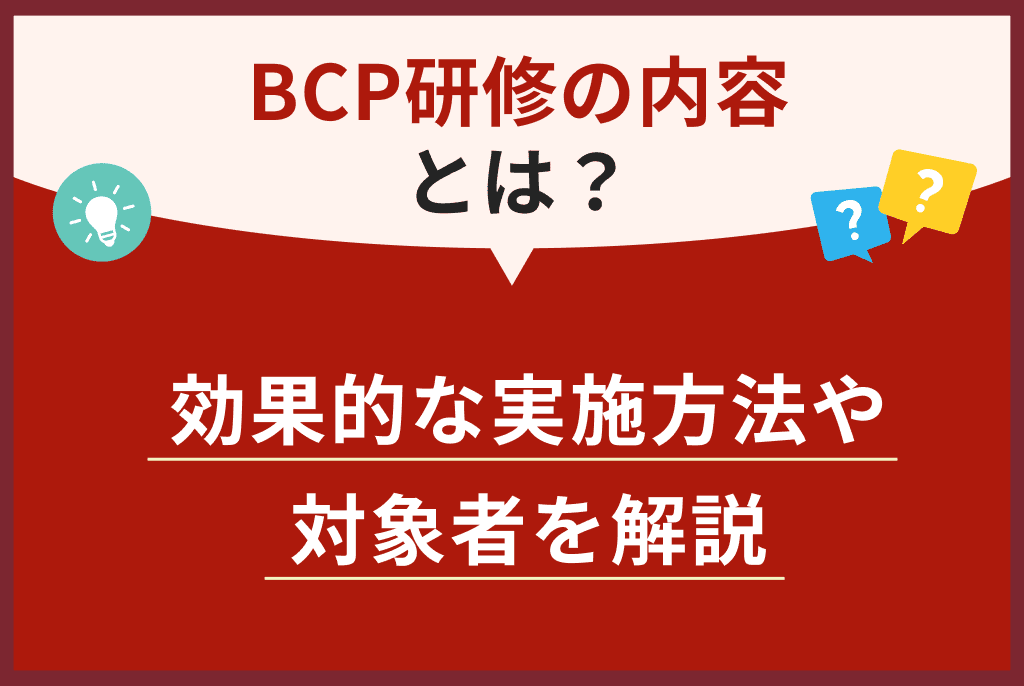
BCP研修の内容とは?効果的な実施方法や対象者を解説
日本は地震が非常に多い国です。東日本大震災や熊本地震などが記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。また、地震以外にも台風や豪雨、新型コロナウィルスを始めとする感染症の流行など、企業の事業継続を脅かすリスクはたくさんあります。
こうした中で注目されているのが、BCP(事業継続計画)です。自然災害が起こった場合でもいち早く事業を再開し、継続するための計画のことを指します。この記事では、BCPの策定や運用のために有効なBCP研修について、研修の内容や実施方法、対象となる社員などについて解説します。
目次[非表示]
BCP研修とは
BCP研修とは、自然災害やシステム障害、不祥事といった危機的状況下でも企業が事業を継続できるようにするため策定するBCP(Business Continuity Plan)について扱う研修です。まずはBCPの目的や概要について学び、具体的な事例を用いたケーススタディに取り組むという流れが多いです。また、BCP策定担当者向けにはBCPの策定方法などもより具体的に伝えます。
その他、BCPの内容の確認、災害などのトラブル発生から事業復旧までの流れの確認やリスク分析などが含まれます。BCPチームの編成方法からBCPの文書化、一般社員への周知まで、BCPに関する幅広い内容を扱うのがBCP研修の特徴です。
BCP研修の重要性
日本は、地震や台風などの自然災害が非常に多い国です。BCP研修を実施して社員のBCPに対する理解を深めれば、こうした自然災害への備えとなります。
また、BCPは企業にとってリスクマネジメントの一つです。中小企業でのBCP策定は未だにあまり進んでいないのが現状ですが、新型コロナウィルスの流行など予測の難しい事態が増えてきている現代だからこそ、BCP研修は重要性を増していると言えるでしょう。
企業のBCPに対する意識は
帝国データバンクの調査(2024年6月)によると、BCPを策定している企業は19.8%に過ぎませんが、『策定意向あり』の企業は50.0%と4年ぶりに5割を超えました。自然災害やサイバー攻撃、感染症といったリスクに備えるため、多くの企業が従業員の安否確認手段の整備や情報システムのバックアップを行っています。
一方、スキルや人手、時間の不足がBCP策定の大きな障壁となっており、特に中小企業では「必要性を感じない」という声も多い状況です 。
出典:帝国データバンク 事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査(2024年)
BCP研修の対象者
BCP研修の対象者は幅広いですが、メインとなるのはBCP策定の担当者です。また、すでに自社で策定されているBCPをブラッシュアップしたい社員も対象となります。BCPの作成方法や要点について体系的に学べば、BCPの策定に役立つスキルが身につくでしょう。
この他、BCPを運用する上で特に内容を把握しておくべき管理部門のリーダーや、BCPを事業戦略に組み込みたい経営層も対象となります。さらに、防災に対する意識づけや災害時の対応について理解を深めることを目的に、全社員を対象として実施するケースもあります。
BCP研修の目的
BCP研修の目的は、端的に言えばBCPについて理解を深めることです。実効性の高いBCPを策定するためには、BCPの役割や要点をおさえる必要があります。BCP研修を通じてBCP策定に必要なノウハウを学び、実際のBCP策定に役立ててもらうのが目的の一つです。
また、BCPに対する理解を深め、効果的に運用できるようにすることも大切です。BCPがどういった目的で策定されていて、実際に災害が発生した際にはどのような対応を取るのかをあらかじめ把握しておけば、もしものときにも落ち着いた対応が取れるでしょう。
監修者からひとこと |
BCP研修によって学ぶ内容
BCP研修では、具体的にどういった内容を学ぶのでしょうか。
BCP研修ではBCPの目的や構造、BCPの策定方法について扱うケースが多いです。また、全社員を対象として実施する際にはBCPや防災への意識づけ、災害時の対応方法などを取り上げるのもよいでしょう。BCP研修で学べる内容を解説します。
BCPの目的
BCPを策定する際には、そもそもどうしてBCPが必要とされているのかを理解する必要があります。BCP研修では、BCPが策定されている目的を取り上げることがおすすめです。
BCPの重要性や役割がわかると、BCPを実際に策定する際にどういったポイントをおさえればよいのかも見えてきます。まずは企業活動の中でBCPは重要な存在であり、リスクマネジメントとして取り組む必要があるということを理解してもらうところから始めましょう。
BCPの構造
BCPの目的について学んでもらうのと同時に、BCPの構造についても取り上げるとよいでしょう。ここではBCPにはどのような項目が設けられているのかなど、BCP全体の枠組みについて解説します。緊急時対応や安全確保のための初動、危機管理計画など災害時の行動計画として何が書かれているのかを説明するのもおすすめです。
また、BCPは多くの場合、企業の事業計画や中長期経営計画と連動して策定されます。事業計画や経営計画とBCPがどう関わっているのかを考えながらBCPに対する理解を深めれば、BCP全体の方向性が見えてくるでしょう。
BCPの策定方法
BCP策定の担当者を中心とした研修を実施する際には、BCPの策定方法について体系的に取り上げましょう。自社の事業計画や経営計画を見ながら、自社にどのようなBCPが必要なのかを考えていきます。参考として、BCPのサンプルや他社のBCPの概要などを提示するのも有効です。
なお、BCP策定方法について学ぶ際には、ワークショップでBCPの演習計画を立ててみるなど、アウトプット型の演習に力を入れるのが重要です。ディスカッションやグループワークを通じてBCPへの理解を深め、自社のBCP策定へつなげましょう。
BCPの運用方法
BCP研修では、策定されているBCPの運用方法について考えてもらうのもおすすめです。せっかくBCPが策定されていても、いきなり災害時にBCPを活用するというのは簡単ではありません。災害が発生した際に、具体的にどういった行動を取り、BCPを運用するのか研修で考えてもらいましょう。
具体的には、災害発生時の対策本部の設置から事業復旧までの流れや、対策本部の具体的な活動内容について考えてもらうのがおすすめです。また、ステークホルダー分析などを通じて、災害時の組織体制を整理するのもよいでしょう。
BCPや防災への意識づけ
BCP研修では、BCPや防災への意識づけを扱うのも有効です。全社員を対象として実施するBCP研修では必ず取り上げたい内容となります。
まずは、自社で策定されているBCPについて説明し、BCPや防災に関する知識を深めてもらうのがおすすめです。対策に関する議論や、社員同士でのディスカッションを通じて災害への備えを進め、防災への意識を高めてもらいましょう。
災害時対応の方法
BCP研修では、災害発生時の対応について取り上げるのもよいでしょう。こちらも、全社員を対象として実施するBCP研修で取り上げたい内容です。災害発生時に求められる知識やスキルを中心に取り扱います。
具体的には、心肺蘇生法などを始めとした応急措置の方法について学んでもらうのがよいでしょう。また、IT部門でのサーバー復旧の方法など、部門に応じて必要な内容を盛り込むことも重要です。災害が発生した際にどういった行動を取るのかをまとめる必要があります。
BCP研修を実施するための準備

BCP研修を実施する際には、まず研修の実施期間を決めましょう。その後、座学で実施するのか、あるいは動画やオンラインで実施するのかなど、研修スタイルを決めていきます。
BCP研修を実施するための準備について、2段階に分けて解説します。
実施期間を決める
BCP研修を実施する際には、まず研修の実施期間を決めましょう。BCP研修は、1日程度の短期集中型で実施されることが多いです。研修の運営に関わる関係者のスケジュールを踏まえながら、研修を実施する日を絞り込んでください。
BCP担当者のみに対して実施する場合は、BCP担当者の日程や日常業務の忙しさなども考えながら日程を選定しましょう。全社員を対象としたBCP研修を実施する際には、なるべく多くの社員が参加しやすくなるよう、繁忙期はできるだけ避けるのがおすすめです。
研修スタイルを決める
研修のスケジュールが決まったら、研修スタイルを決めていきます。研修スタイルは大きく分けると「座学」「動画視聴」「オンライン研修・eラーニング」の3種類です。それぞれに一長一短があるため、BCP研修で扱う内容に合った研修スタイルを選択するのが重要です。BCP研修を実施する際の3つの研修スタイルについて、メリットやデメリットも交えながら解説します。
座学
BCP研修のスタイルの1つ目は、座学による研修です。あらかじめ確保した研修会場へ社員に集まってもらい、講師による講義形式で研修を進めていきます。
座学スタイルの長所としては、BCPに関する基礎知識を体系的に学べるという点です。知識のインプットに向いているスタイルで、BCP策定の際に知っておきたいノウハウや関連知識をまんべんなく学ぶことができます。一方で座学の短所は、座学のみだと研修内容が身につきにくい点です。講師の話を聞いたあとでディスカッションやグループワークを取り入れるなど、アウトプットの場を確保する工夫が求められます。
動画視聴
BCP研修は、動画視聴スタイルで実施されることも多いです。災害防止を目的とした動画は、数多く公開されています。こうした動画を活用してBCP研修を実施し、動画の視聴を通じて災害への意識を高めるのもよいでしょう。
動画視聴の長所は、実際の災害のイメージなどが湧きやすい点です。また、研修を実施する側の負担も少なく、大人数の社員を効率的に育成できるでしょう。ただし動画だけではインタラクティブなやり取りができないため、座学と同様にアウトプットと組み合わせるのが重要です。
オンライン研修・eラーニング
BCP研修を実施する際には、オンライン研修やeラーニングを活用するのがおすすめです。オンライン研修では、ZoomやYouTube Liveなどを活用しながら研修を進めていきます。研修実施側の負担も少なく、必要に応じて動画教材を交えながら研修を進めることが可能です。
オンライン研修のやり方やポイントについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
『オンライン研修のやり方やメリット・デメリットをわかりやすく解説』
eラーニングでは、BCPに関するノウハウを主に動画教材としてまとめ、それを配信します。個々の進度に合った学習ができるとともに、一度に大人数の社員に対して実施できる効率のよい育成手法です。
アルーでは、eラーニングの学習管理に便利なLMS「etudes」を提供しています。
etudes
研修資料を準備する
国や役所が実施しているBCP作成例を参考にしながら、研修資料を準備するのも有効です。具体的な事例やテンプレートを参考にすることで、実践的な研修内容を提供でき、社員の理解が深まります。例えば厚生労働省の介護施設・事業所のBCP作成例は研修資料も充実しており、参考になります。詳細は厚生労働省のページをご覧ください。
出典:介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修
BCP研修を効果的に実施するポイント
BCP研修を効果的に実施するためには、事業継続計画作成に必要な手順を学び、事業継続マネジメントの要点を学ぶのが有効です。また、知識の定着を図るため、演習やワークショップなどの実践的な内容を意識的に取り入れるのもよいでしょう。
BCP研修を効果的に実施するポイントを解説します。
「事業継続計画作成」の手順を学ぶ
実効性の高いBCPを作成するためには、BCP作成の手順を学ぶことが重要です。特に、手順については一部の経営層だけではなく、管理部門のリーダーやBCP担当など、必要に応じて様々なメンバーに学んでもらう必要があります。
なおBCPを作成する手順は、以下の通りです。
- BCP策定のチームを編成する
- 基本方針を作成する
- 重要性の高い業務を選定する
- 目標復旧時間(RTO)を設定する
- リスク分析を行い、ボトルネックを把握する
- BCPの決定や文書化を行う
以上のような流れを社員へ説明し、BCP策定に役立ててもらいましょう。
事業継続マネジメントの要点を学ぶ
BCPを作成しても、それがうまく運用できなければ意味がありません。BCP研修を成功させるためには、事業継続マネジメントの要点を学んでもらうのも重要です。
BCPを効果的に運用するためには、以下の4点に注力するとよいでしょう。
- BCPの対応マニュアルを用意する
- BCPの日常化に取り組む
- 緊急時の連絡網を作成する
- BCP訓練を実施したり、当事者意識を醸成したりする
BCP研修を通じて、作成したBCPを実際の運用につなげるマネジメント方法について考えてもらいましょう。
演習やワークショップで実践的に学ぶ
BCP研修を成功させるためには、演習やワークショップなどで実践的に学ぶのも有効です。ディスカッションやグループワークなどに取り組んでもらうことで、インプットした知識の解像度が上がるほか、知識が定着しやすくなります。
演習の際には、例えば「感染症が流行し、本社社員の多くが出社できなくなった」「地震の発生によりサーバーダウンが発生した」といった具体的なケースを想定したテーマを設定しましょう。具体性の高いテーマを設定すれば、より実感が湧きやすく、社員の当事者意識を高められます。
BCP研修に関するよくある疑問

この記事の最後に、BCP研修を実施する際によくある疑問をまとめてご紹介します。BCP研修の実施を検討している方は、参考にしてみてください。
BCP対策の実施は義務?
BCP対策の実施は、多くの企業の場合義務ではありません。実際、中小企業ではBCP対策が十分にできていないところも多いです。
とはいえ、BCP対策は企業のリスクマネジメントの一つとしてとても重要なものです。実際、介護施設等では2024年4月からBCPが義務化されました。義務の有無に関わらず、BCPは日頃から取り組んでおくべき対策と考えておきましょう。
BCPの内容は職種によって変わる?
BCPの本質は変わらないため、BCPの基本的な構造が職種によって大きく変わることはありません。多くの場合、災害発生時に取るべき対応や災害発生時のチーム編成などを職種に関わらずまとめています。
ただし、災害が発生した際に取るべき対応の中身は職種によって変わる場合があります。例えばIT部門の場合はサーバーの復旧に注力する必要がありますし、生産部門の場合は生産設備の復旧などがメインとなります。BCPの構造や目的が変わることはありませんが、具体的な内容については職種によって異なると理解しておきましょう。
BCP研修は自社で実施できる?
BCP研修は自社でも実施できますが、社外サービスの活用をおすすめします。理由は、BCPを効果的に策定し、運用するためにはBCPに関する深い知識やノウハウが必要だからです。実際にBCPを策定したことがあったり、経営経験があったりする人材でないと、講師を務めるのは難しいでしょう。
社外サービスの場合は、BCP策定に関するノウハウを持った講師も多く在籍しています。豊富な経験に基づいた内容を話してくれるため、説得力もあり、受講者のスキル向上に役立つでしょう。
監修者からひとこと |
BCP研修ならアルーにお任せください
アルーは、人材育成を専門としている企業です。BCP研修の実施をご検討の場合は、ぜひアルーへお任せください。
アルーでは、お客様の企業の課題に合わせて柔軟にカスタマイズできる研修をご提供しています。また、この記事で解説したオンラインでのBCP研修実施や、eラーニングを活用したBCP研修の実施にも対応しております。BCP研修に関するお悩みは、ぜひお気軽にアルーへご相談ください。