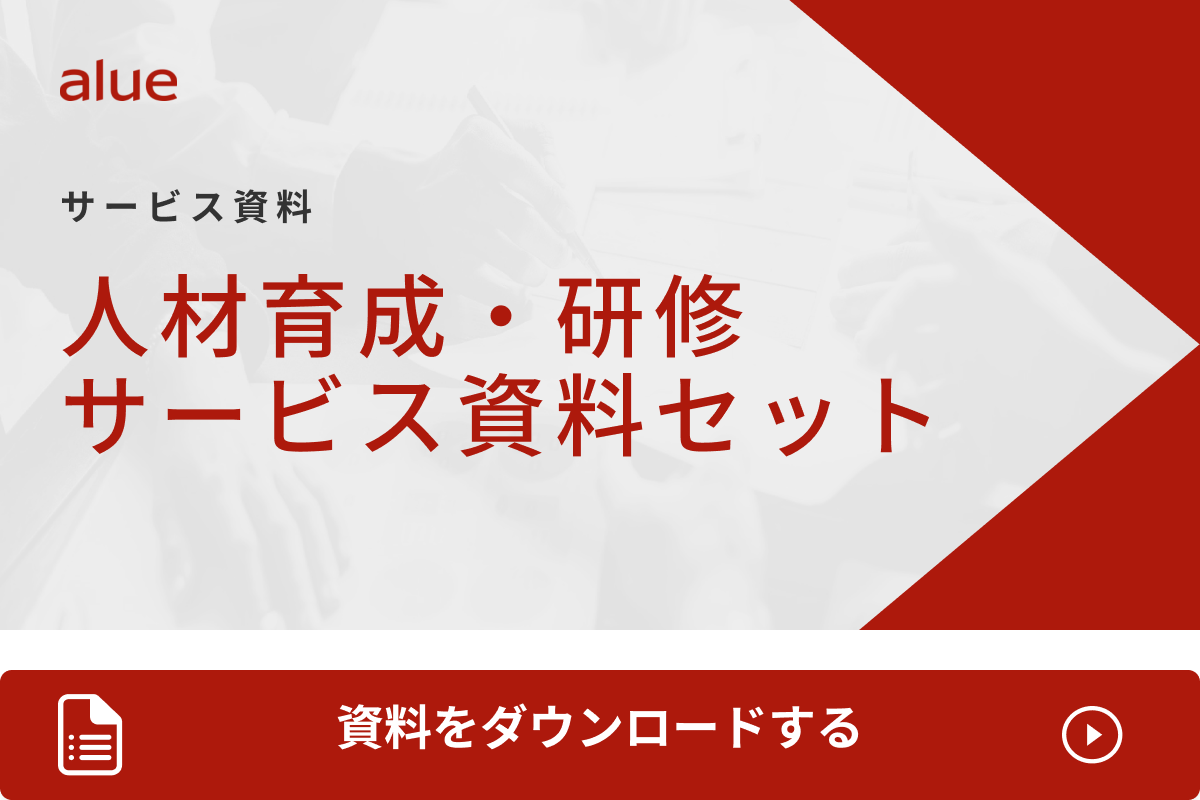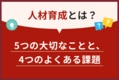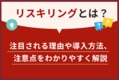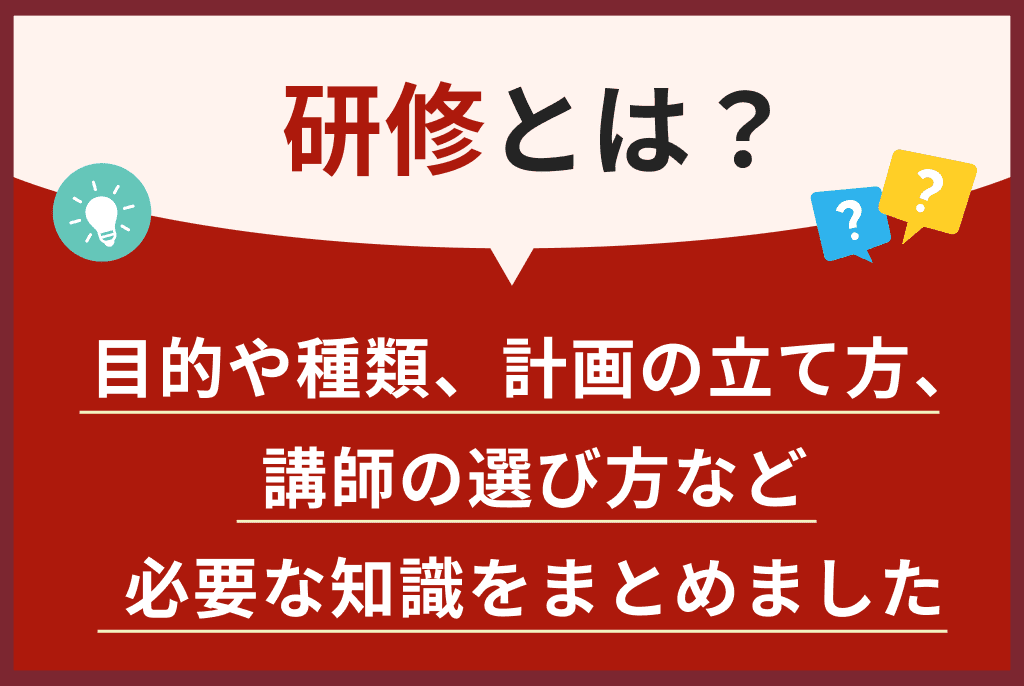
研修とは?目的や種類、計画の立て方、講師の選び方など必要な知識をまとめました
OJTや座学、eラーニングなどを通じて業務に必要な知識やスキルの習得を目指す研修は、社員のスキルアップは企業の成長に必要不可欠です。
そのため、業種や業界を問わず、何らかの形で社員研修を実施している企業が多くあります。
研修を成功させるためには、研修の意義や目的をしっかりと理解したうえで綿密な研修計画を練ることが欠かせません。
この記事では、研修の目的や意味、さらには研修を成功させるポイントなどについて細かく解説します。
より深く知るための『オススメ』お役立ち資料
目次[非表示]
- 1.研修とは
- 2.研修の目的・意味とは
- 3.研修の手法
- 4.研修の種類
- 5.研修計画の立て方
- 6.意味のない研修と言われないコツ
- 7.研修レポートの書き方
- 8.オンライン研修のコツ
- 9.研修講師の選び方
- 10.研修資料の作り方
- 11.研修のことならアルーにお任せください
研修とは
研修とは、従業員が業務を進める際に必要なスキルや知識を習得し、作業の効率化や品質の向上、生産性の向上などを図るために実施されるさまざまな教育プログラムのことです。
一言で研修といってもその種類は多彩で、新人教育やキャリアアップ研修、専門スキル研修、マネジメント研修など、目的に応じた幅広いプログラムが実施されます。
また、研修は従業員の能力向上だけでなく、社員同士のコミュニケーションの促進や、企業の理念や価値観の共有といった観点からも重要です。
最近ではeラーニングなど、従来のOJTや集合型研修以外のさまざまな研修方式を採用する企業も増えてきています。
研修の目的・意味とは
研修以外にも、専門学校をはじめとして知識を習得できる環境は数多く存在します。
また、近年ではオンラインスクールなどで専門知識を身につけるケースも少なくありません。
しかし、いつでも学べる環境が整っている現代においても、企業が主体となって研修を実施することには意味があります。
第一に、企業が研修を実施することを通して、企業の方向性を反映した人材育成が可能になるという点が挙げられます。
また、社員の能力の底上げを図ることによって、DXやDE&Iといった職場の変革を推進しやすくなるということも望めます。
研修を実施する具体的なメリットを以下で紹介します。
企業・個人間のビジョン共有
企業側は、社員への研修を通じて企業が求める人物像や企業の目指す方向性を従業員に共有できます。
企業側がどのような方向に向かって中長期的に何を目指しているのかを周知すれば、目標達成に向けた施策もスムーズに打ち出せるようになるでしょう。
さらに、企業と個人の間でビジョンを共有すれば従業員のエンゲージメントを向上させることも可能です。
このように企業への思い入れが増すことにより、離職率の低下やモチベーションアップといったさまざまな効果を期待できるでしょう。
階層ごとのレベル・方向性の統一
階層内に能力のムラが存在すると、一部の優秀なエース社員にのみ頼ってしまうという状況が生まれてしまいます。
こうした状況が続いてしまうと、優秀な社員の離職や異動といった事態に対処することが難しくなり、組織の将来性にも悪影響を与えます。
研修を実施する意義として、階層ごとにレベルや方向性を統一できるという点も大きいといえます。
新入社員の間でレベルを統一するのはもちろん、部長や課長の間で足並みを揃えることによって、より生産性の高い組織を目指すことが可能です。
業務に必要なスキルの向上
研修では、業界知識や社内でよく用いる専門用語など、業務に必要な知識を伝達することも多くあります。
研修の場でこうした知識やスキルを伝達すれば生産性の向上が期待でき、業務に必要なスキルを向上させられることも研修の大きな意義の一つです。
また、個人の成長をサポートすることは自社の競争力向上に直結する可能性があります。
さらには、スキルを磨くことで自社の社員のキャリアに対する意識が高まり、モチベーションが向上するといった効果もあるでしょう。
全社的なスキルアップ
最近、注目されている取り組みであるDXやDE&Iを推進するためには、一部の社員のみが知識を持っているだけでは不十分です。
たとえばDXの場合では、全社員が満遍なく一定のITスキルを持つことによって、はじめて生産性向上に直結するDXが実施できるようになります。
このように企業全体のスキルアップや変革を目指せるということも研修を実施する目的の一つです。
社員の能力を底上げすることができれば、会社の目指す目標を実現しやすくなるでしょう。
研修の手法
研修には、大きく分けて「OJT」「Off-JT」「eラーニング」という3つの手法があります。
これらの手法には、それぞれメリットとデメリットが存在するため、研修の内容に合わせて適切に運用していくことが大切です。
研修を実施する際に考えられる手法について、具体的に解説します。
OJT
OJTとは、「On-the-Job Training」の略称です。
日頃の仕事を実践しながら業務に必要なスキルや知識を身につけてもらう研修手法で、若手や中堅、ベテランを問わず、幅広く適用できる方式でもあります。
OJTを採用するメリットとして、実務に直結する実践的な知識が身につきやすいという点が挙げられます。
また、OJTトレーナーと深い関わりができることによって、上下間の信頼関係を構築しやすいという点もメリットです。
一方でOJTの教育の質はトレーナーに大きく左右されるため、OJTトレーナー向け研修を実施するといった対策が求められます。
▼アルーのOJTトレーナー研修について詳しくはこちらのページをご覧ください。
Off-JT
Off-JTとは、「Off-the-Job Training」の略称で、OJTとは反対に日頃の業務を離れて行うタイプの研修手法です。
日頃の業務を一度離れて研修のための時間を確保し、集合型研修に参加するといった形式が多くなっています。
Off-JTの最大のメリットは、教育の質にムラを出すことなく効率的に知識を伝達できるという点です。
一方、デメリットとしては、身につけられる知識が一般的なものに限られ、実務的なスキルは伝達しづらい点や、研修のための時間確保が現場に負担を与えやすい点が挙げられます。
eラーニング
eラーニングとは、パソコンやスマートフォン、タブレット端末を通じて配信される教材を用いて行われる学習のことです。
最近ではオンライン上で教材を配信し、受講者は好きな時間にそれを視聴して学習を進めてもらうというeラーニングを研修に活用する企業が増えてきています。
eラーニングを活用すれば、会議までの待ち時間や通勤時間など、スキマ時間を用いた学習が可能です。
また、会場や講師の確保といった研修にかかるコストを削減することにもつながります。
一方で、研修参加者は基本的に個々で教材を視聴する形となるため、上手にモチベーション管理を行う必要があります。
OJT・Off-JT・eラーニングのメリット・デメリット
OJTとOff-JT、eラーニングにはそれぞれ下記のようなメリットとデメリットがあります。
育成手法 |
メリット |
デメリット |
OJT |
|
|
Off-JT |
|
|
eラーニング |
|
|
OJTの大きなメリットは、座学やマニュアルだけではなかなか身につかないような実践的な知識を効率的に身につけてもらえるという点です。また、O指導者となる先輩社員も、OJTを通じて自身が持っている知識を改めて整理することができます。先輩社員と後輩社員とのコミュニケーションが増えるため、縦のつながりが強化されるという点も大きなメリットです。
一方でデメリットとしては、指導担当によって育成の幅に差が生まれてしまうという点が挙げられます。また、指導担当に負担がかかってしまうことも課題となっている企業は多いでしょう。
Off-JTのメリットは、業界知識やビジネスの型、ビジネスマナーといった内容をまとめて学習することで、体系的な知識を身につけることができる点です。また、教育の質を均一化させやすいという点も挙げられます。
デメリットは、実践的な知識が身につくとは限らない点や現場の経験によるスキルは伝えづらいという点です。
eラーニングのメリットは、集合研修よりコストを抑えて効率的に育成施策を運用できる点です。費用だけでなく、人事担当者側の工数が削減できる点も大きな魅力です。また、受講者にとっては、時間や場所を気にせずどこでも学習できる、反復学習ができるというメリットがあります。
一方でデメリットとしては、自社で動画教材を作成する手間が発生すること、研修をきちんと受けるかどうかが受講者の主体性に影響されてしまうことが挙げられます。また、講師や他の受講者とのコミュニケーションは取りづらいこと、実技実習のスキルは身につきづらいこともデメリットです。
研修の種類

一言で研修といっても階層ごとに実施する階層別研修や、身につけたいスキルに分けて実施するスキル別研修など、その種類は多くあります。
研修の内容に合わせて適切に研修の種類を選定すれば、より質の高い教育が可能です。
ここでは、研修について代表的な種類を6つご紹介します。
階層別研修
階層別研修は、新入社員や中堅社員、管理職など、社員を階層ごとに区切って行われる研修のことです。
また、部長職や課長職など、役職ごとに区切って行われる場合もあります。
階層別研修を実施することで、それぞれの階層でレベルを統一しやすくなります。
新入社員には「ビジネスの基礎知識やビジネスマナーを伝える」「管理職にはマネジメント手法を伝える」など、それぞれの階層に合った知識を効率的に伝達できるでしょう。
さらに、同じ世代や同じポジションの社員が一度に集まることによって、横のつながりを強化することも期待できます。
スキル別研修
一般的に研修は、部長や課長、新入社員や中堅社員など、同じ属性の社員を集めて行われることが多いです。
ですが、「今後部下育成を行う社員に、OJTのやり方について伝えたい」「全社員にロジカルシンキングの基礎力を身につけさせたい」など、スキルごとに研修を行うこともあります。
スキル別研修を実施する際には、会社全体や部署、チーム、階層別にどのようなスキルが必要かを洗い出し、研修の対象者と内容を決めるとよいでしょう。
業種別研修
IT業や製造業、サービス業など、業界別に異なるスキルが求められることは非常に多いです。
そのため、業種ごとに必要とされるスキルや知識に特化した研修が実施されることもあります。
こういった場合では、自社で内製する場合と、外注の両方のケースがあります。外部で開催されるものに参加する場合は、質の高い教育を受けられることはもちろん、研修参加者同士で人脈を築くこともできます。
職種別研修
「企画やマーケティング職には情報収集能力を身につけてほしい」「営業にはコミュニケーション手法やクレーム対応術を身につけてほしい」など、職種ごとに異なる能力が求められる場面も少なくありません。
そのため、営業や開発、企画、バックオフィスなど、職種ごとに区切って研修が行われるケースも多いです。
職種別研修を実施することで、それぞれの職種で必要とされる能力を集中的に身につけられるため、生産性の向上に直結しやすい研修手法といえます。
選抜研修
企業側が身につけてほしい能力のなかには、必ずしも全社員が身につける必要はないものもあります。
たとえば、「管理職候補となる優秀な人材には、若手社員の段階でマネジメント能力を身につけてほしい」といったようなケースが考えられます。
このような場合に行われるのが選抜研修です。
選抜研修では、上司の推薦や評価などによって研修参加者を決定したうえで研修が実施されます。
研修に選抜された社員に会社からの期待が伝わると同時に、責任感を持ってもらえるといった特徴があります。
公募研修
公募研修は、全社員に研修の参加を必須とするのではなく、立候補者を募集したうえで研修に参加したい社員のみに研修へ参加してもらう方式のことです。
あらかじめ研修の内容や目的、期間などを明示して、研修に参加したい社員を募集します。
公募研修を実施する最大のメリットとして、モチベーションの高い社員が集まりやすいという点が挙げられます。
自ら学ぼうとする社員が参加しているため、学習効率も向上するでしょう。
また、公募研修への参加を通じて、社員が自分自身のキャリアについて振り返るきっかけを与えることもできます。
研修計画の立て方
研修を行う際には、行き当たりばったりの研修とならないように注意する必要があります。
そこで重要になってくるのが綿密な研修プランの策定です。
事前にしっかりと人材要件を策定し、人材育成の全体像を定めることによって、より効果的な研修が実施できます。
研修計画を立てて研修を実施するまでの具体的な流れについて解説します。
人材要件を策定する
人材要件の定義とは、各階層で求められるスキルや知識を明確にしたうえで、それらと紐づくように育成体系や研修体系を整備することを指します。
研修を実施する際には、最初に人材要件を定義しましょう。
人材要件を策定する際には、「どのような人材が求められているのか?」を経営者へのヒアリングを通じて明らかにすることが大切です。
また、現場へも同様にヒアリングを行い、「現場では何が不足しているのか?」「現場で求められている人物像は何か?」を把握します。
これら2つをすり合わせながら、どういった人材育成が求められているのかを明確にしましょう。
人材育成の全体像を策定する
前ステップで確定した人材要件を踏まえて、人材育成の全体像を考えます。
その際、抽象的な人材要件から、具体的な「あるべき人物像」へと落とし込んでいくことが重要です。
また、あるべき人物像をもとにしながら具体的な能力についても考えていきましょう。
たとえば、「お客様に満足される対応ができる人材」を目指すとなった場合、コミュニケーション能力やクレーム対応能力、説明のための商品知識といった具体的なスキル・知識を定めます。
研修の対象者を選定する
人材育成の全体像を踏まえながら、研修の対象者も選定していきましょう。
研修対象者となる人材は、身につけてほしいスキルに合わせて変化するため、柔軟な検討が必要です。
たとえば、リモートワークの方法や基礎的なITスキルといった内容の場合は、全社員が対象となるでしょう。
一方で、マネジメントスキルや専門知識といったような限られた社員に集中的に教育するのが効果的なものも存在します。
現場の上司や経営層へのヒアリングなども実施しながら、適切な研修対象者を決定してください。
研修の目的と目標とする成果を設定する
研修のゴールがあやふやなままだと研修の効果が半減してしまいかねません。
また、後述のステップで解説する研修の効果測定も難しくなってしまう可能性があります。
研修の対象者を選定したあとは、研修の目的やゴールとなる成果を明確に設定します。
研修のゴールを設定する際には、カークパトリックモデルを基に行うと効果的です。
カークパトリックの4段階評価モデルは、以下の通りです。
- レベル1:反応 参加者は育成施策が気に入ったか
- レベル2:理解 参加者は知識やスキルを習得できたか
- レベル3:行動 参加者は研修で得たものを現場で活用できているか
- レベル4:結果 参加者の行動変容によって、実際に成果がでているか
具体的にいくつかのマイルストーンを設定して、研修の着地点を定めましょう。
プログラムを選定し、研修を実施する
研修の目的やゴールが定まったら、研修プログラムを選定し、研修を実施する段階に入ります。
研修プログラムを選定する際には、前ステップで定めた研修のゴールと現状のギャップを把握することが大切です。
両者のギャップを認識したうえで、それを埋めるために必要なプログラムは何かを考えていきましょう。
研修を実施する際、研修で知識を伝えるだけでなく、その知識を現場で活かすサポートまでセットで行うように意識します。
実践方法までを併せて伝えることによって、「知識は身につけたが活用法が分からない」といった事態を防ぐことが可能です。
効果測定を行う
研修実施後には、必ず効果測定を実施しましょう。
研修の効果がどれほどあるのかを定量と定性の両面から把握することで、今後の研修内容のアップデートにもつながります。
具体的には、研修終了時のアンケートを通じて、「研修が有益だったか?」「業務に活かせるイメージが湧いたか?」といった点を把握しましょう。
その後、半年や1年といった期間が経ったあたりで改めて売上や利益率、目標達成率などの数字を見ながら研修効果の測定を行い、継続的に研修の内容を改善してみてください。
研修の効果測定方法について詳しくは以下のページをご覧ください。
『研修効果測定の方法とは|4つの評価レベルや効果測定のポイント』
意味のない研修と言われないコツ

研修は有効な育成手法の一つですが、「研修をしても意味がない」と感じている社員がいることも事実です。「意味がない」と感じさせないためには、いくつかのポイントを抑えて研修を企画・運営する必要があります。
効果的な研修を実施するためのポイントを紹介します。
研修効果を定義してから設計する
研修を企画する際は、研修のゴール、効果、成果を先に定義しましょう。
ゴールを知識習得におくか、行動変容や意識転換におくかで企画も設計も変わります。また、知識習得がゴールだとした場合、その効果または成果は何かも定義するとよいでしょう。例えば、研修後に知識習得を測るテストを実施して、90点以上を合格とする場合、90点以上のスコアを得た受講者が100%となることがゴールになります。このようにゴールを明確にすれば、研修内容の設計方法や事後テストの内容、テストで合格ラインに達しなかった受講者をどうフォローするかなど、なにを考えなければいけないかを明らかにすることができます。
研修を安心安全の場にする
研修は、批判や修正を行なう場ではなく、対話のための場にすべきです。研修企画担当者や講師がこの認識を持つことはもちろん、受講者にも以下のような注意事項を伝えると良いでしょう。
- 意見に勝ち負けをつけない
- 他の受講者の意見に耳を傾け、理解する
- 結論よりプロセスを重視する
研修を安心安全の場にし、受講者が意見を言いやすく、能動的に学習ができるようにすれば、学習内容も身につけやすくなります。
現場と目的・ゴールをすり合わせる
現場で使うスキルや現場で求められている人物像と研修の目的・ゴールをすり合わせることも重要です。人事側や企業側のみで研修計画を立てるのではなく、必ず現場にヒアリングをするなどして、現場と研修の目的をすり合わせておきましょう。
研修前に目的を理解してもらう
研修前には、「この研修を受けてどうなってほしいのか」「この研修はこのスキルを身につけることができる」という、研修の目的を理解してもらうための時間を設けましょう。
受講者に、「この研修を受けて、どのようになりたいですか?」「この研修であなたが身につけたい力は何でしょうか?」と逆に質問するのも良いでしょう。人事側の目的に受講者が自ら気付くことによって、「こうなるために、研修をしっかりと受けよう」という気持ちを起こさせることができます。
研修の内容をOJTに取り込む
研修で知ったことや分かったことをすぐ使えるように、研修内容をOJTに落とし込むことが大切です。
研修内容は「必要なことを知る」「わかる」だけではなく、使えるようにならなければなりません。「知っている」「わかる」の次の段階である「使える」ようになるためには、アウトプットの場が必要です。
アウトプットの場として、OJTを活用しましょう。
研修後にOJTを通して実践を積み、上司にフィードバックを貰ったり、定期的にチームで共有したりすることで、研修内容が身につきやすくなります。
スキルの習得だけでなく価値観の変容も促す
研修ではスキルや知識を与えるだけでなく、受講者側の価値観にもアプローチする必要があります。
例えば、「1on1ミーティングを成功させるため、傾聴スキルを身につけてほしい」というような研修の目的があったとしても、受講者側が「部下は上司の指示に従うべき」「自分のやり方が正しいので、部下が変わるべき」と考えていては、研修後の行動変容は望めず、「研修をしても意味がなかった」と思われてしまうでしょう。
研修内で「自分が変わる必要があると自覚する」「無意識に持っていた考え方に気付く」というプロセスを取り入れることが大切です。受講者が自身のもっている価値観に気づくためのワークを積極的に取り入れましょう。
できていないことを洗い出してもらう
受講者が研修は意味がないと感じる理由の一つとして、「自分はスキルがあるし、実践できている」と受講者が思い込んでいることも挙げられます。
例えば、受講者に「部下の話を聴き、アドバイスをしてあげられていますか?」と質問をすれば、「できている」「心がけている」という回答が得られるかもしれません。ですが、「部下と接していて、こうなったらいいのにと思うことはありませんか?」「時間がかかるなと感じている業務はありませんか?」と質問をすると、「何もありません」と答えられる人は少ないでしょう。
たとえば、次のような事前課題やワークを行ってできていないことを洗い出してみることをおすすめします。
- 現状の時間の使い方を把握する
- 自身の業務で上手くいっていることと上手くいっていないことを把握する
- 自身の判断の傾向から現状を把握する
このような洗い出しは、事前課題や研修の冒頭で行うと良いでしょう。
座学だけでない研修方法を取り入れる
「座学で講師の話を聴くだけ」の形式の研修は、飽きられてしまったり、ラジオのように聞き流しながら業務を行ったりする受講者もいるかもしれません。
研修では、座学だけでなくシミュレーション形式の演習や、グループディスカッションを行い、受講者が発言したり、行動をしたりする形式を取り入れることも大切です。
実際の業務に近い内容でロールプレイを行ったり、他の受講者と意見を出し合ったりすることで、聴くだけの研修よりも記憶に残りやすく、スキルが身につきやすくなります。
研修後のフォローを行う
研修の効果を十分に発揮させるためには、研修後に継続的に研修の内容を実践したり、学習を継続したりすることが必要です。
継続的な学習や職場での実践を行なってもらうために、人事側や企業側で研修後のフォローを行うことが大切です。数か月後にフォローアップ研修を行う、OJTに組み込み、定期的に研修内容に沿った行動の成果を発表しフィードバックを行うなど、フォロー体制を整えておきましょう。
研修後にアンケートを実施し、次に活かす
研修後に研修の理解度や、研修の満足度などをアンケートで集計することで、次の研修の参考になります。
研修後に受講者からのアンケートで「この部分が分かりにくかった」「ここはよくわかった」などの声を次の研修に活かすことで、より効率的に研修を行うことができるでしょう。
研修レポートの書き方
研修を実施した後は研修担当者と受講者の双方がレポートを作成し、学びの振り返りや次回以降の研修企画のブラッシュアップに活かすことがおすすめです。研修担当者側と受講者側のそれぞれ、レポートの内容について解説します。
研修担当者側のレポート
研修担当者側のレポートには以下のような項目を盛り込みましょう。
- レポート作成日
- 研修名
- 研修日時
- 研修を実施した場所
- 講師名
- 参加人数
- 研修内容
- 受講者のアンケート結果
- 講師からの所感
- 総括
レポートを書く前に、あらかじめ受講者に対してアンケートやテストを実施して研修の効果測定をしておきましょう。今回の研修が効果があったのかどうかをしっかりと確認した上で、改善できるところなどを詳しく記載する必要があります。
研修の効果測定方法については以下のページをご覧ください。
『研修効果測定の方法とは|4つの評価レベルや効果測定のポイント』
受講者側のレポート
受講者側のレポートには以下のような項目を盛り込みましょう。
- レポート作成日
- 研修名
- 担当講師名
- 受講者氏名
- 研修日時
- 研修を実施した場所
- 研修目的
- 研修の要点
- 研修を受講した感想
受講者には研修で学んだ内容や職場で活かせそうなことについて、具体例を挙げて記載するように指導しましょう。「楽しかった」「役に立った」という感想だけでは、具体的に良かった点、悪かった点を分析することができません。
レポートのテンプレートや例文を提示し、有益なレポートが集まるように工夫しましょう。
研修レポートの書き方やテンプレートについては以下のページをご覧ください。
『研修レポートの書き方とは?例文やテンプレートを紹介』
オンライン研修のコツ
リモートワークが浸透し、オンライン研修が一般的になってきました。オンライン研修には、地方拠点や海外拠点などの多拠点の社員が集まることができたり、会場を押さえる必要がなかったりと、多くのメリットがあります。
しかし、オンラインだからこそ気を付けなければいけないポイントもあります。オンライン研修を実施する際に知っておきたい、成功のコツを紹介します。
事前準備を行う
主催側、受講者側ともにネットワークの接続確認やデバイスや音響設備などの機器の動作確認などの事前準備を、スケジュールの余裕をもって怠りなく行いましょう。
通信トラブルや研修資料のファイルがうまく開かないなどの小さなアクシデントでも、研修の場で生じると講師や他の参加者を待たせることになります。結果的に学ぶべき内容を省略せざるを得ないといった事態にもなりかねないため、想定できるトラブルは事前に対処できるようにしておくことが大切です。
ゲームなどでアイスブレイクを行う
オンライン研修では集合研修と違い、受講者同士のコミュニケーションが自然に発生することは非常に稀です。研修を始める前に参加者でゲームや雑談をしてアイスブレイクする時間を設けましょう。
最初にアイスブレイクを行うことで、緊張がほぐれるとともに受講者同士のコミュニケーションも取りやすくなるのでおすすめです。
研修におすすめのアイスブレイクについて詳しくは以下のページをご覧ください。
『研修で使えるアイスブレイク11選!新入社員研修にもオススメ』
メリハリのある進行を心がける
画面を見続けることになるオンライン研修では、思ったよりも受講者の集中力は続きません。目安としては、10分講義をしたら10分は作業や発言をしてもらうくらいのメリハリをつけるようにしましょう。
また、講師側は対面で講義しているときよりも身振りなどのリアクションを大きくし、声のトーンを上げてはっきり話すなど画面を通して見た時にわかりやすい話し方も考えなければなりません。
進行サポートメンバーを配置する
オンライン研修では受講者の様子や理解度をリアルタイムで把握できないため、受講者をサポートしつつ進行を助けるスタッフを配置しておくことが成功のポイントです。
講師以外に受講者に発言する機会を与える役割や、集まった意見をまとめる役割を担うスタッフがいることで研修がスムーズに進行します。
研修講師の選び方
講師は研修の質を左右する大きな存在です。
社内で講師を探す際には以下の3つのポイントを重視しましょう。
- 研修テーマに対するノウハウや知見を持っている
- コミュニケーションスキルがある
- 受講者との距離感が近い
実務の面で優秀な社員が講師としても優秀だとは限りません。
研修テーマに対する専門性だけでなく、受講者とコミュニケーションを取って信頼関係を構築するスキルがあるかどうかもチェックしましょう。
研修講師の選び方や講師に求められるスキルについて詳しくは以下のページをご覧ください。
『研修講師に求められるスキルとは。講師の選び方や研修を成功させるポイント』
研修資料の作り方
研修資料は、研修当日だけでなく後から見返した際にもわかりやすく作成する必要があります。具体的には、以下の構成で組むとよいでしょう。
- 講師紹介
- 研修の目的
- 目次・タイムライン
- グランドルール
- アイスブレイクのテーマ
- 受講者への問いかけ
- 講義・解説
- ワーク・解答例
- 学習内容の振り返り
- 学んだこと・アクションプランシート
図解やメモ用紙なども上手に活用することで、わかりやすい資料を作成することができます。
研修資料の実際のスライド例や作成ポイントについては以下のページをご覧ください。
『新入社員研修資料の作り方とポイント。研修のプロの見本を公開!』
新入社員研修以外の研修でも使えるポイントが盛りだくさんです。
研修のことならアルーにお任せください
アルーは、企業のグローバル人材育成をはじめ、新入社員向け研修や中堅社員研修、管理職研修など幅広い研修を手掛けている企業です。
人材育成を長年手掛けてきた企業ならではの豊富なノウハウを活用した高品質な研修をご提供しています。
研修の外部委託をご検討の際や、研修でお困りの際はぜひアルーへお任せください。
階層別研修やスキル別研修など、幅広い育成プログラムをご用意しております。
人材育成のプロフェショナルの知見を活かし、オーダーメイドの研修をご提案いたします。
▼アルーの人材育成サービスについては、以下のページをご確認ください。