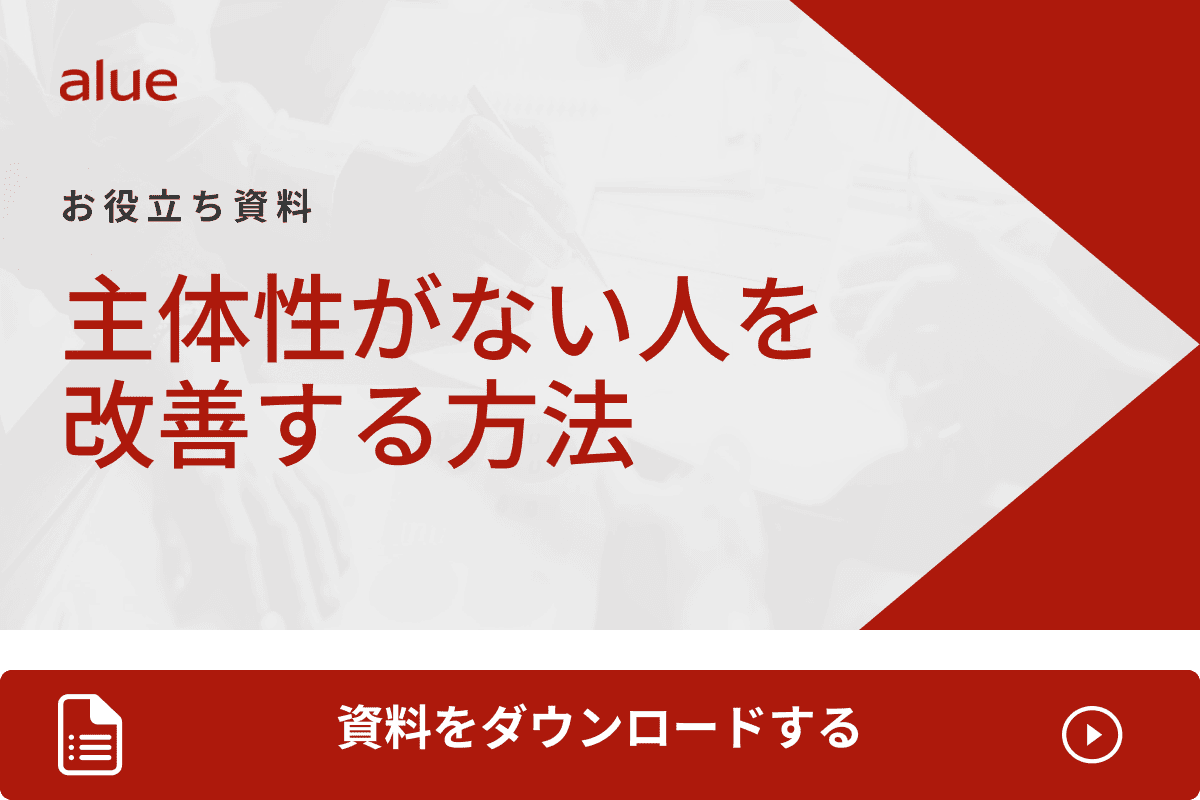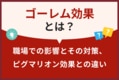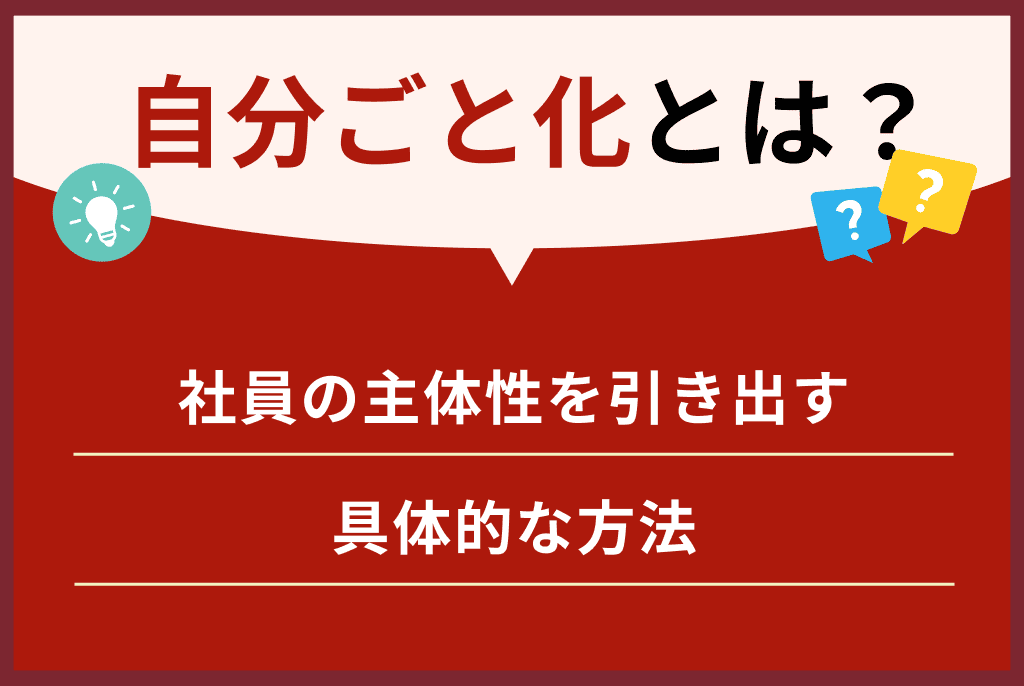
自分ごと化とは?社員の主体性を引き出す具体的な方法
組織全体の成長には、社員一人ひとりが「自分ごと」として仕事に取り組む姿勢が不可欠です。この記事では、社員の主体性を引き出し、組織全体の活性化に繋げるための具体的な方法を解説します。
目次[非表示]
- 1.自分ごと化とは
- 2.自分ごと化の重要性
- 3.自分ごと化を阻む要因
- 4.自分ごと化するメリット
- 5.自分ごと化を職場で促進する方法
- 6.自分ごと化を促進する研修事例
- 7.まとめ
自分ごと化とは
「自分ごと化」とは、組織やチームの目標、課題を自分のことのように捉え、主体的に行動する状態を指します。単に業務をこなすだけでなく、その結果や意味、組織全体への影響を深く理解し、自らの責任として行動できていると、「自分ごと化できている」と言えるでしょう。
組織において自分ごと化が進むと、社員のモチベーションが向上し、生産性の向上、イノベーションの促進、離職率の低下など、多くのポジティブな影響が期待できます。社員が組織の目標達成に貢献する意欲を高めるためには、自分ごと化が不可欠です。組織全体で自分ごと化を推進することは、持続的な成長と成功の鍵となります。社員一人ひとりが組織の一員として責任を共有し、主体的に業務に取り組むことで、組織全体のパフォーマンスは飛躍的に向上します。
自分ごと化は、組織の文化として根付かせる必要があり、そのためには社員のリーダーシップやコミュニケーション能力の向上、評価制度の改訂など、組織全体での取り組みが求められます。
自分ごと化の重要性
ここからは、自分ごと化の重要性について解説していきます。
社員個人にとっての重要性
自分ごと化が重要である理由は多岐にわたります。まず、社員が組織目標を自分自身の目標と捉えることで、モチベーションが向上し、主体的な行動をとれるようになります。これにより、業務効率の向上や創造的な問題解決が期待できます。
また、社員が組織の一員としての責任感を強く持つことで、チームワークが強化され、一人ではなしえなかったような成果に繋がります。自分ごと化が進むことで、社員は仕事に対するやりがいや達成感を感じやすくなり、組織に長く在籍し貢献したいと考えてくれるかもしれません。
組織にとっての重要性
ビジネス環境が急速に変化する現代において、自分ごと化は組織の競争力を維持し、成長を続ける上で不可欠な要素となっています。技術革新、市場のグローバル化、顧客ニーズの多様化など、ビジネスを取り巻く環境は常に変動しています。このような状況下で企業が生き残るためには、社員一人ひとりが変化を敏感に察知し、自ら考え、積極的に行動する必要があります。指示待ちの姿勢では、迅速な意思決定や柔軟な対応が難しく、ビジネスチャンスを逃す可能性が高まります。自分ごと化された組織では、社員が自ら課題を発見し、解決策を提案することができるようになります。これにより、イノベーションの創出や業務プロセスの改善につながり、組織全体の生産性向上に繋がるでしょう。
さらに、自分ごと化を促進することは、社員のエンゲージメントを高め、企業へのロイヤルティを向上させます。社員が自社の成長を自らの成長と結びつけて考えられるようになれば、組織全体の持続的な発展につながります。ビジネスの成功のためには、組織全体で自分ごと化を推進する取り組みが不可欠です。
自分ごと化を阻む要因
社員一人ひとりが自分ごと化の姿勢を持つことは重要ですが、実際にはすべての社員が自分ごと化の視点を持てているとは限りません。自分ごと化を阻む要因について解説します。
組織目標やビジョンの共有不足
組織目標やビジョンが十分に共有されていない、または理解されていない場合、社員は自身の業務と組織全体の目標の関連性を認識しにくくなります。これにより、自分の仕事が組織にどのように貢献しているのかを理解できず、業務への主体性が失われがちです。社員が自分の役割の意義を理解することで、業務へのモチベーションが向上します。
トップダウン型の組織構造
トップダウン型の組織では、社員が自らの意見やアイデアを発信する機会が限られます。その結果、指示された業務をこなすだけの受け身な姿勢になりやすく、仕事に対する主体性が低下します。社員が意思決定プロセスに関与し、自身の考えを反映できる環境を整えることが重要です。
意見や提案の評価不足
社員の意見や提案が適切に評価されない場合、主体的に行動しようとする意欲が低下します。組織としては、社員のアイデアを積極的に受け入れ、フィードバックを行う仕組みを整えることが求められます。評価の仕組みが整っていないと、社員は「どうせ意見を出しても無駄だ」と感じ、積極性が失われる可能性があります。
コミュニケーション不足と企業風土
組織内のコミュニケーションが不足している、または風通しの悪い企業風土では、社員が安心して意見を表明しにくくなります。心理的安全性が欠如していると、社員は自分の考えを発信することを避け、組織全体の活力も低下します。上司と部下の間でオープンな対話ができる環境を整えることが、自分ごと化の促進につながります。
自分ごと化するメリット
社員が自分ごと化ができるようになると、どのようなメリットがあるのでしょうか。自分ごと化することによるメリットについて解説します。
自分ごと化による主体性の向上と業務効率化
組織において社員が自分ごととして業務に取り組むことで、主体性が高まり、業務効率が向上します。社員が受け身ではなく、自ら課題を発見し解決策を考えるようになることで、業務プロセスがスムーズに進みます。結果として、無駄な作業の削減や迅速な意思決定が可能となり、組織全体のパフォーマンス向上につながります。
チームワークの強化とエンゲージメント向上
自分ごと化が進むことで、社員同士が協力し合い、チームワークが強化されます。お互いを尊重しながら仕事を進めることで、より大きな成果を上げることが可能になります。また、社員が企業に対する愛着や誇りを持つことで、エンゲージメントが向上し、離職率の低下につながります。結果として、企業は優秀な人材の定着を促し、長期的な成長が期待できます。
イノベーションの促進と自己成長の機会創出
社員が自発的に新しいアイデアを提案できる環境が整うことで、組織全体の創造性が向上します。社員が仕事に対するやりがいや達成感を感じることで、モチベーションが高まり、自己成長を促す好循環が生まれます。こうした環境は、組織の持続的な成長と発展に不可欠であり、企業競争力の向上にも寄与します。
自分ごと化を職場で促進する方法
自分ごと化を促進するには、目標を共有したり定期的にフィードバックしたりして、社員のモチベーションを高める必要性があります。ここでは、自分ごと化を促進する方法について解説していきます。
目標設定と共有
自分ごと化を促進するためには、まず、組織全体の目標を明確にし、それを社員にしっかりと共有することが重要です。目標設定のプロセスにおいては、社員を巻き込み、意見を積極的に取り入れることが望ましいです。社員が目標設定に関わることで、その目標に対するコミットメントが高まり、自分ごととして捉えやすくなります。目標は、具体的で測定可能なものに設定することが重要です。これにより、進捗状況を把握しやすくなり、社員従業員のモチベーションを維持することができます。
目標達成に向けた具体的な計画を立てる際も、社員が主体的に関与できるように、チームごとに話し合いの場を設けることが効果的です。
また、目標達成の進捗状況は定期的に共有し、フィードバックを行うことが重要です。これにより、社員従業員は自身の貢献度を実感することができ、さらなるモチベーション向上へと繋がるでしょう。目標設定と共有のプロセスにおいては、透明性を重視し、社員が疑問や懸念を気軽に表明できるような雰囲気を作ることが重要です。
目標設定について詳しくは、以下の記事をご参照ください。
『リーダーの目標設定のポイントとは|必要なスキルや具体例を紹介』
コミュニケーションの活性化
組織内のコミュニケーションを活性化させることは、自分ごと化を促進する上で非常に重要です。特に、部を超えたコミュニケーションが滞っている場合が多いため、部門間コミュニケーションを積極的に推進してみましょう。部門間の連携を強化するためには、定期的な情報共有の場を設けることが有効です。例えば、部門間の代表者が集まる会議や、情報共有のための社内SNSなどを活用しましょう活用することができます。これにより、部門間の壁を取り払い、組織全体としての協力体制を構築することができます。
また、社員が気軽に意見やアイデアを発信できる環境を整備することも重要です。例えば、オープンなコミュニケーションを促すためのワークショップや、匿名で意見を提出できるシステムを導入すると効果的でしょうことができます。
さらに、上司と部下の間でのコミュニケーションを密にすることも重要です。上司は部下の意見をしっかりと聞き、フィードバックを行うことで、部下の成長を促し、エンゲージメントを高めることができます。
コミュニケーションを活性化させるためには、組織全体でコミュニケーションスキルを向上させるための研修を行うことも効果的です。社員が互いを尊重し、協力し合える環境を作ることで、組織全体のパフォーマンスを向上させることができます。
組織コミュニケーションを活性化させるコツについて詳しくは以下の記事をご覧ください。
『職場のコミュニケーションの重要性と活性化のための具体例8選』
フィードバックと振り返りの機会を与える
社員の成長を促し、自分ごと化を促進するためには、定期的なフィードバックと振り返りの機会を設けることが重要です。フィードバックは、社員の行動や成果を具体的に伝え、改善点や強みを明確にするために行います。フィードバックを行う際は、一方的に伝えるのではなく、社員との対話を通して行うことが望ましいです。これにより、社員は自身の成長を実感し、モチベーションを高めることができます。フィードバックは成長を促すためのものなので、人格攻撃や一方的な批判は避けましょう。
また、定期的な振り返りの機会を設けることで、社員は自身の業務プロセスや成果を客観的に見つめ直し、改善点を発見することができます。振り返りでは、成功体験だけでなく、失敗体験からも学びを得ることが重要です。振り返りを通じて、社員は課題解決能力や自己学習能力を向上させることができます。
フィードバックと振り返りを効果的に行うためには、上司が部下との信頼関係を構築し、安心して意見を交換できる環境を作ることが重要です。フィードバックは、成長を促すための建設的なものであるべきで、人格攻撃や一方的な批判は避けるべきです。フィードバックと振り返りの機会を定期的に設けることで、社員は成長を実感し、自分ごととして業務に取り組むことができます。
フィードバックについて詳しくは、以下の記事をご参照ください。
『フィードバックの意味とは?効果・実施する方法・ポイントをわかりやすく紹介』
オープンなコミュニケーションと心理的安全性の確保
自分ごと化を組織に定着させるためには、オープンなコミュニケーションと心理的安全性の確保が不可欠です。
社員が安心して自分の意見やアイデアを表明できる環境を作ることが重要です。心理的安全性が確保された組織では、社員は失敗を恐れずに新しいことに挑戦することができ、その結果、イノベーションが促進されます。失敗を責めるのではなく、そこから学びを得ることを奨励することで、社員の成長を促すことができます。また、社員が安心して相談できるような相談窓口を設けることも、心理的安全性の確保に繋がります。
オープンなコミュニケーションを促進するためには、上司は部下の意見を積極的に聞き、尊重する姿勢を示す必要があります。また、社員同士が互いに意見を交換し、協力し合えるような場を設けることも効果的です。さらに、組織全体でコミュニケーションスキルを向上させるための研修を行うことも重要です。
オープンなコミュニケーションと心理的安全性の確保は、社員のエンゲージメントを高め、自分ごと化を定着させるために欠かせない要素です。
心理的安全性について詳しくは、以下の記事をご参照ください。
『心理的安全性とは?作り方や高める方法、ぬるま湯組織との違いについて解説』
成功体験の共有
社員のモチベーションを向上させ、自分ごと化を促進するためには、成功体験を組織全体で共有することが有効です。成功体験を共有することで、社員は自身の仕事が組織に貢献していることを実感し、達成感ややりがいを感じることができます。成功体験を共有する際は単に結果を報告するだけでなく、そのプロセスやそこから得られた学びを共有することが重要です。これにより、他の社員は成功の秘訣を学び、自身の業務に活かすことができます。また、成功した社員を褒め称え、その努力を認めることも重要です。これにより、社員のモチベーションが向上し、さらなる成功を目指す意欲が湧いてきます。成功体験を共有することで、組織全体の一体感が増し、チームワークが強化されるでしょう。
成功体験を共有するためには、社内報や社内SNSを活用する、成功事例発表会を開催するなど、様々な方法が考えられます。まずは特定の部署のみなど小さく始め、自社に合った方法を見つけていきましょう。
自分ごと化を促進する研修事例
アルーでは社員の自分ごと化を促進するための研修を数多く提供してきました。その中から3つの研修事例をご紹介します。
亀田製菓株式会社 グローバル人材育成研修事例
亀田製菓株式会社は、海外事業の強化を進める中で、海外で活躍できる技術者の不足という課題に直面しました。国内で培った米菓製造技術を世界に展開するには、単なる技術者ではなく、異文化の中でリーダーシップを発揮できる人材が必要と感じていました。そこでグローバル人材育成体系の構築に着目しました。2030年を見据え、必要な人員数や能力要件を明確化し、語学力と異文化適応力の強化を柱とした研修を導入しました。英会話研修や異文化プログラム、赴任前後の研修など、多角的なアプローチを採用しています。特に、マレーシアでの異文化体験プログラムは、実践的な学びとして好評でした。研修を通じて、技術者の意識にも変化が生まれました。かつては「求められれば海外へ行く」という姿勢だった社員が、「ぜひ海外で挑戦したい」と前向きになりました。英語力向上だけでなく、キャリア観にも変化が現れました。
この取り組みは、単なる語学教育にとどまらず、企業文化の変革にもつながっています。今後は、国内外の人材をフラットに交流させ、適材適所の配置を進めることで、さらなる成長を目指していく考えです。
亀田製菓株式会社の取り組みについて詳しくは以下のページをご覧ください。
亀田製菓株式会社導入事例 海外事業の中長期成長戦略を実現するグローバル人材育成体系
株式会社ファイントゥデイ リーダーシップスキル開発研修事例
株式会社ファイントゥデイでは、資生堂からの転籍社員と中途採用社員が混在する中で、共通のマインドやスキルレベルが揃っていないことが課題でした。そのため企業のパーパスやバリューを全社員に浸透させるため、階層別の研修を導入しました。
社員を「上級管理職層」「ミドルマネジメント層」「メンバー層」の3つに分類し、それぞれに適した研修を実施しました。上級管理職には、戦略を理解し自分の言葉で伝える「アッパーマネジメント研修」を、ミドルマネジメントには課題を把握し適切な指導を行う「コーチング研修」を実施しています。また、メンバー層には、自発的に行動し戦略を実行に移す「セルフリーダーシップ研修」を提供しました。研修には、企業のパーパスやバリューと個人の価値観を結びつける対話の時間も取り入れ、組織文化の醸成を促しました。
研修後、エンゲージメントサーベイで「パーパスやバリューの浸透度」のスコアが43%から50%弱へ向上しました。また、受講者の行動変容が確認されました。人事担当者は「評価制度に組み込む前に、社員が自発的に行動できる環境を整えることが重要」と語り、今後はこの行動を企業文化として定着させていく方針です。
株式会社ファイントゥディの取り組みについて詳しくは、以下のページをご覧ください。
株式会社ファイントゥデイ導入事例 全社員に異なるアプローチで企業パーパス浸透の一歩目となった研修事例
株式会社明治 キャリア自律の促進研修事例
株式会社明治では、社員の自律的な成長を促すため、新たな選択型研修「PICKUP」を導入しました。従来の階層別研修では、社員が学びたい内容を自由に選べず、同質化が進む傾向がありました。社員の主体性を高め、キャリア自律を促進することを目的に、誰もが必要なスキルを自ら選び、学びたいタイミングで受講できる仕組みに変更しました。
研修は実践的な内容が重視され、グループワークを多く取り入れた設計にしました。受講者からは「学びが仕事に直結する」「社員同士の交流が深まった」と好評を得ています。人財開発グループの担当者は「学びの文化を根付かせることが今後の課題」と感じています。今後は社内での認知度向上を図り、社員が自ら成長する企業風土をより強化していく予定です。
当事例について詳しくは下記ページをご覧ください。
株式会社明治導入事例 社員が学びたいものを学べる研修体系によるキャリア自律と自律型人財の促進
まとめ
自分ごと化を促進することは、組織全体の成長と発展に不可欠です。社員が組織の目標を自分自身の目標として捉え、主体的に行動するようになることで、業務効率が向上し、イノベーションが促進されます。自分ごと化を促進するためには、組織目標の明確化と共有、コミュニケーションの活性化、フィードバックと振り返りの機会の提供、オープンなコミュニケーションと心理的安全性の確保、成功体験の共有など、様々な取り組みが必要です。これらの取り組みを組織全体で継続的に行うことで、社員は仕事に対するやりがいや達成感を感じ、エンゲージメントを高めることができます。
社員の自分ごと化促進にお悩みであれば、ぜひアルーにご相談ください。社員のマインドセットを変えるための研修を多数ご用意しています。
アルーに相談する