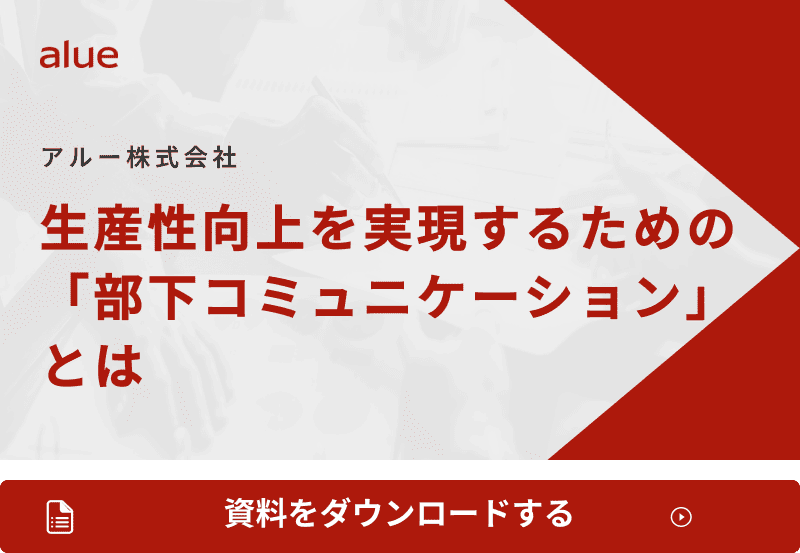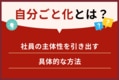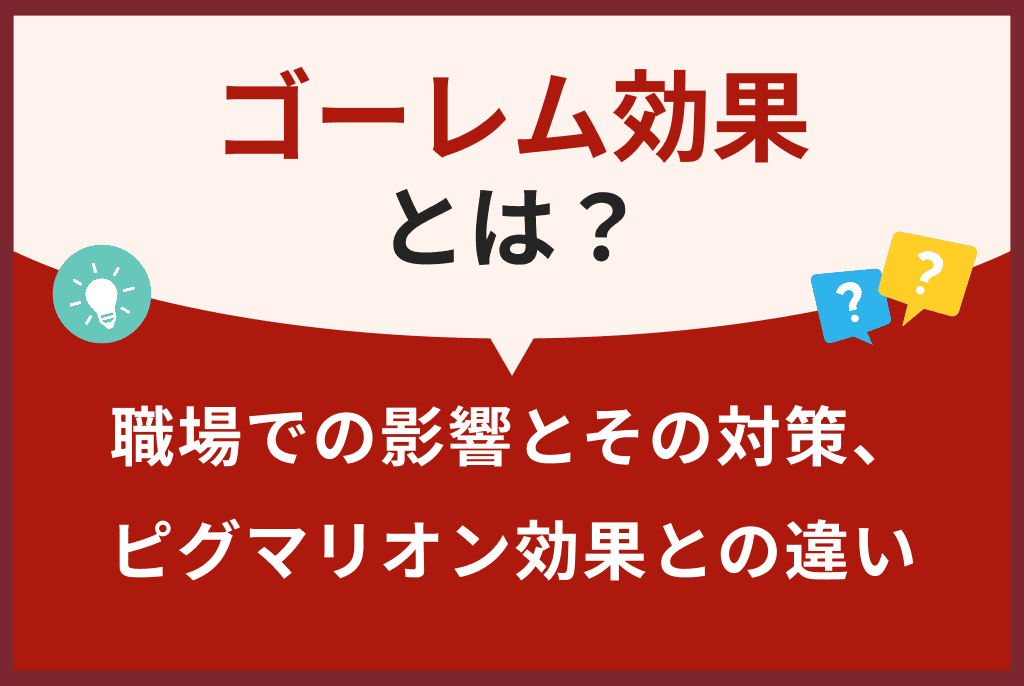
ゴーレム効果とは?職場での影響とその対策、ピグマリオン効果との違い
ゴーレム効果は、他者からの低い期待が、その人のパフォーマンスを低下させる心理現象です。職場でゴーレム効果が生まれると、社員の成長や組織全体の生産性に悪影響を与える可能性があります。本記事では、ゴーレム効果のメカニズム、ピグマリオン効果との違い、職場での具体的な影響、そしてその対策について解説します。
目次[非表示]
ゴーレム効果とは
ゴーレム効果とは、他者からの低い期待が、その人のパフォーマンスを実際に低下させる心理現象です。これは、上司などの周囲の人が、特定の個人に対して低い期待を抱くことで、その人の行動や成果が、その期待どおりに低下していくというものです。ゴーレム効果は、自己成就予言の一種であり、他者からのネガティブな評価や期待が、個人の能力発揮を妨げるメカニズムとして機能します。
ゴーレム効果の種類
ゴーレム効果は、主に二つの種類に分類されます。一つは、絶対的ゴーレム効果です。これは、期待を抱く側が、期待される側に対して直接的に否定的な言動をすることで、パフォーマンスの低下を招くものです。例えば、上司が部下に対して「どうせできないだろう」といった言葉を投げかけることで、部下の意欲をそぎ、結果的にパフォーマンスが低下することがあります。
もう一つは、相対的ゴーレム効果です。これは、否定的な評価を受けている組織に所属すると優秀な人のパフォーマンス低下を招くものです。
ゴーレム効果とピグマリオン効果との違い
ゴーレム効果と対照的な心理効果として、ピグマリオン効果があります。ピグマリオン効果は、他者からの高い期待が、その人のパフォーマンスを向上させる現象です。周囲からの肯定的な期待は、個人の能力を最大限に引き出す原動力となるのです。ゴーレム効果とピグマリオン効果は、期待というものが人の行動や成果に及ぼす影響を示す、二つの極端な例であると言えます。職場においては、社員一人ひとりに高い期待を持ち、肯定的なフィードバックをすることが、組織全体の成長に不可欠です。両効果を理解することで、より効果的な人材育成や組織運営が可能になります。
職場におけるゴーレム効果の例
職場では、上司や同僚の低い期待がゴーレム効果を引き起こし、社員のパフォーマンス低下につながることがあります。例えば、新入社員が「仕事が遅い」と決めつけられ、簡単な業務しか任せてもらえないと、自信を失い、成長の機会を奪われてしまいます。また、過去にミスをした社員が「どうせまた失敗する」と思われると、プレッシャーから本来の力を発揮できなくなります。例として、 新入社員が資料作成のミスを一度指摘されたことで「この人には重要な資料を任せられない」と判断され、単純作業ばかり割り当てられると、成長の機会を奪われることになります。このような環境では、社員のモチベーションも下がり、組織全体の生産性が低下する恐れがあります。
職場におけるゴーレム効果の具体的な影響
ゴーレム効果とは、他社からの低い期待により、パフォーマンスを実際に低下させるということが分かりました。ここでは、具体的な影響について解説していきます。
社員の自己肯定感の低下と意欲の喪失
職場においてゴーレム効果が及ぼす最も大きな影響の一つは、社員の自己肯定感の低下と意欲の喪失です。上司や同僚から低い評価や否定的な言葉を受け続けることで、社員は自身の能力に自信を持てなくなります。その結果、新しい業務への挑戦を避けたり、業務への積極性を失ったりする可能性があります。これは、個人の成長を妨げるだけでなく、組織全体の生産性低下にもつながります。自己肯定感が低下すると、ストレスや不安が増大し、メンタルヘルスにも悪影響を及ぼす恐れがあります。職場では、社員の自己肯定感を高め、意欲を引き出すための取り組みが不可欠です。
チーム全体のパフォーマンスへの悪影響
ゴーレム効果は、個人だけでなくチーム全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼします。チーム内で特定のメンバーに対する低い期待が共有されると、そのメンバーの貢献意欲が低下し、チーム全体の士気も下がることがあります。また、メンバー間で不平等感が生まれると、協力体制が崩れ、チームワークの悪化を招くことがあります。特定のメンバーを冷遇したり、期待しない態度を取ったりすることは、チーム全体のコミュニケーションを阻害し、非効率な業務運営につながります。チームリーダーは、メンバー全員に対して公平な期待を持ち、ポジティブなフィードバックをすることで、チーム全体のパフォーマンスを向上させる必要があります。
ゴーレム効果への対策
ここからは、ゴーレム効果への対策について、被評価者側ができることと管理職・組織ができることの両方を紹介します。
被評価者側ができるゴーレム効果への対策
被評価者側がゴーレム効果による悪影響を回避するためには、自己肯定感を高めることが重要です。自分の強みや成功体験を認識し、それを積極的に振り返ることで、自己評価を高めることができます。また、目標を小さく分割し、達成感を積み重ねることも有効です。自己肯定感を高めるための具体的な方法には、以下のようなものがあります。
- ポジティブな言葉を意識して使う
- 自分の良いところを書き出す
- 成功体験を振り返る
さらに、周囲からのネガティブな評価に過度に反応せず、自分自身の価値を信じることが大切です。自己肯定感が高い人は、他者の評価に左右されず、自らの能力を最大限に発揮できる可能性が高いです。
管理職・組織ができるゴーレム効果への対策
組織レベルでは、ゴーレム効果を防止するために、ポジティブなフィードバックが不可欠です。社員のよい点を認め、具体的な行動を褒めることで、自己肯定感を高め、意欲を引き出すことができます。フィードバックは、定期的に行うだけでなく、タイミングも重要です。業務の成果が出た直後や、良い行動が見られた際に、速やかにフィードバックすることで、効果を最大化できます。また、フィードバックは、一方的な評価ではなく、対話を通じて行うことで、社員の成長をサポートすることができます。加えて、事実をありのままに認識することも重要です。先入観や過去の印象にとらわれず、現在の成果や行動を客観的に評価することで、不当な低評価を防げます。また、事実を肯定的に捉える姿勢も欠かせません。たとえミスをしたとしても、その過程で得た学びや成長の可能性に目を向けることで、前向きな職場環境を維持できます。組織全体で、ポジティブなフィードバック文化を醸成することが、ゴーレム効果を防ぎ、より良い職場環境を作る上で非常に重要です。建設的なフィードバックは、社員の成長を促し、組織全体の活性化につながります。
ゴーレム効果を防ぐためのマネジメント研修
ゴーレム効果は、管理職が意識的に対策を講じることで、その影響を最小限に抑えることが可能です。部下に対して低い期待を持たず、ポジティブなフィードバックや成長の機会を提供することで、ゴーレム効果を防ぐことができます。
そのために、管理職研修を実施することが有効です。研修を通じて、管理職はゴーレム効果のメカニズムやその影響、そして具体的な対策方法を学ぶことができます。例えば、部下とのコミュニケーションの改善方法や、ポジティブなフィードバックをどのように行うかといった実践的なスキルを身につけることができ、職場でのパフォーマンス向上に繋がります。
アルーでは管理職の部下コミュニケーションを改善する研修を多数実施しており、管理職が実践的なスキルを学べる機会を提供しています。具体的なケーススタディを元に、理論だけでなく実際の職場で役立つスキルを習得できます。研修を通して管理職がゴーレム効果を予防し、より良い職場環境が作られます。
アルーの管理職研修について詳しくは以下のページをご覧ください。
管理職研修
ゴーレム効果対策に役立つマネジメント研修事例
職場でゴーレム効果が発生することを防ぐには、管理職がマインドを変え、部下コミュニケーションに必要なスキルを身につけることが重要です。アルーが提供した部下コミュニケーション研修の事例を3つ紹介します。
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 マネージャー層と課長代理層を対象にした研修事例
東京海上日動あんしん生命保険株式会社では、「対話」を重視した組織マネジメント研修を実施しました。従来の研修は必須研修だったため受講者が受け身になりがちだったという課題がありました。そこで、主体的な学びを促すため公募型へ変更しました。マネージャー向けの「アドバンス」と、課長代理層向けの「ベーシック」の2クラスを設け、適切な対話スキルを習得することを目的としています。
研修では、メンバーとの対話の量と質を向上させることに重点を置きました。受講者同士の交流や実践を通じて、マネジメント観を見直す機会となり、受講後のNPS(満足度指標)も非常に高評価でした。人事担当者からは「社員が主体的に学び、組織全体に対話が根付いた」との声が寄せられています。
本事例に関して、以下のページでより詳しくご覧いただけます。
東京海上日動あんしん生命保険株式会社導入事例 外部の知見を取り入れた体系的な組織マネジメント研修
▼事例資料ダウンロード
コスモ石油株式会社 新任ライン長研修事例
コスモ石油株式会社では毎年、新任ライン長を対象とした研修を実施しています。2014年は30名が参加し、「他責から自責」をスローガンに掲げ行いました。
研修は3日間で、初日は人事評価制度に関する実務研修、2日目以降は役割認識を深める内容でした。特に、講師の厳格な指導により、受講生が真剣に学ぶ環境を整えました。
グループワークでは技術系と事務系を混合し、異なる視点を学ぶ機会を提供しました。異業種交流を通じ、組織全体の連携を強化する目的もありました。
研修後、受講生からは「伝えたつもりでも伝わっていないと気づいた」「異なる業務環境の理解が深まった」との声があり、実務に直結する学びが得られました。
本事例に関して、以下のページでより詳しくご覧いただけます。
コスモ石油株式会社導入事例 信じて任せる。 人をマネジメントする 新任ライン長研修の意義とは。
Wismettacグループ マネジメント研修事例
Wismettacグループでは、従来、管理職が自己流のマネジメントを行っていましたが、組織の成長に伴い、多様な価値観を持つチームを率いる必要性が高まりました。そこで、体系的なマネジメント手法を学ぶ場として、2022年度から本格的な研修を開始しました。
初年度は「共創型のリーダーシップ」をテーマにオンライン研修を実施し、2023年度には「メンバーの成長課題と業務アサイン」に焦点を当てた集合研修を実施しています。管理職歴の浅いリーダーにとって、現場の課題解決に役立つ実践的な学びの機会となりました。
研修後、管理職の意識が変化し、部下とのコミュニケーションの質が向上しました。人事担当者からは「研修を継続し、自己啓発が根付く文化を作りたい」との声も聞かれます。
本事例に関して、以下のページでより詳しくご覧いただけます。
Wismettacグループ導入事例 多様な「個」の特性や能力を活かし、部下の成長を支援するマネージャー育成
▼事例資料ダウンロード
まとめ
ゴーレム効果は、職場において、社員のパフォーマンスやモチベーションを著しく低下させる要因となります。この心理現象を理解し、適切な対策を講じることで、より良い職場環境を構築することが可能です。個人レベルでは、自己肯定感を高め、周囲からのネガティブな評価に左右されない強い心を養うことが大切です。組織レベルでは、ポジティブなフィードバック文化を醸成し、社員一人ひとりの成長を支援することが不可欠です。また、マネジメント層は、ゴーレム効果に関する知識を深め、効果的なマネジメントスキルを身につける必要があります。ポジティブな職場環境は、社員の成長を促し、組織全体のパフォーマンスを向上させます。ゴーレム効果への対策は、社員と組織の成長に不可欠な取り組みです。