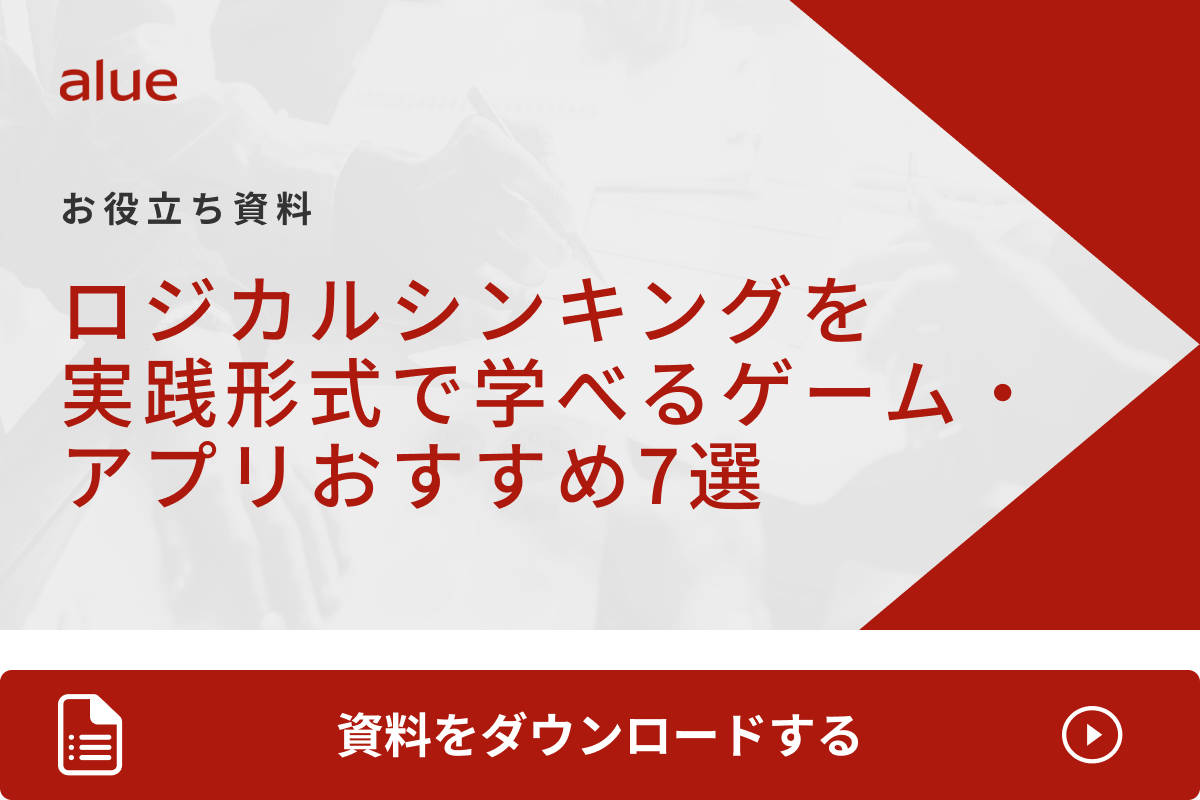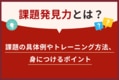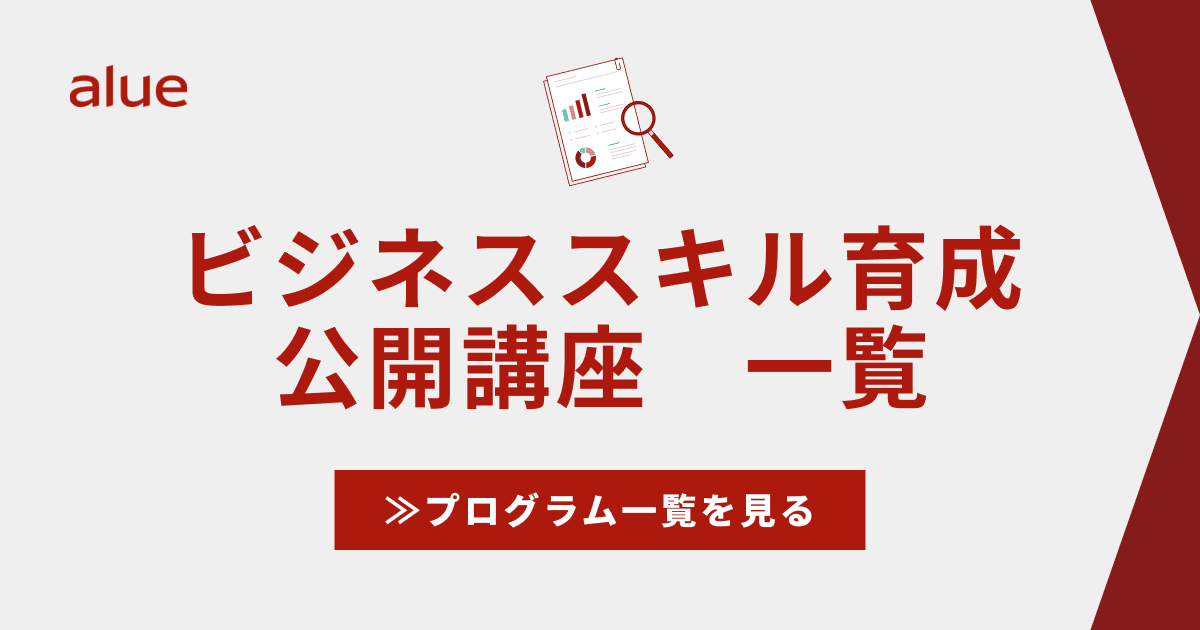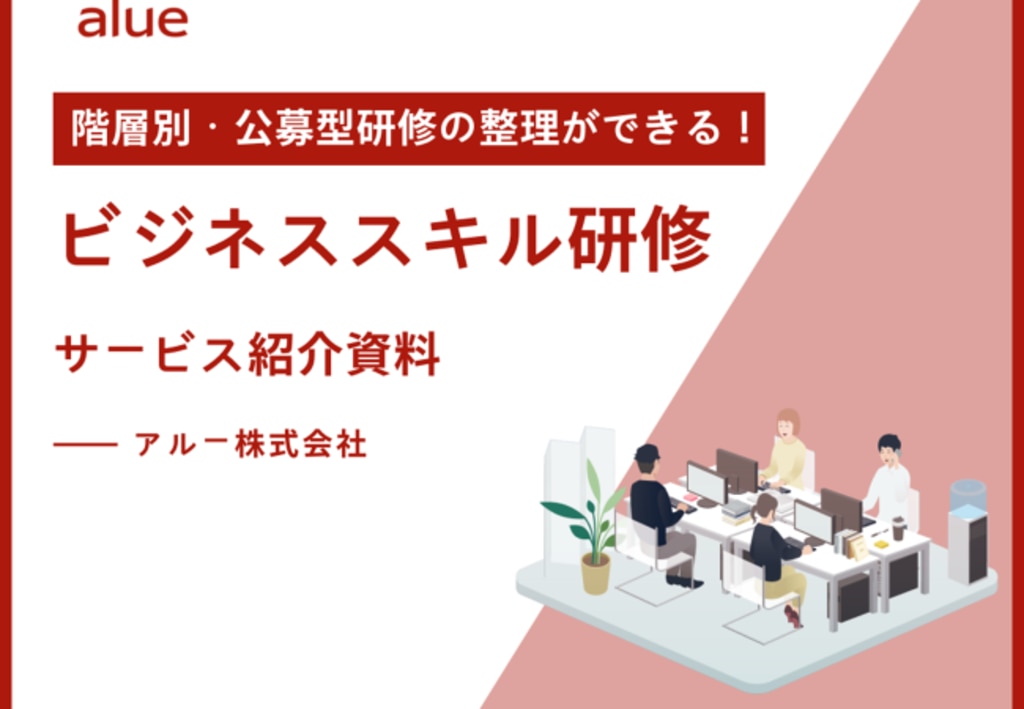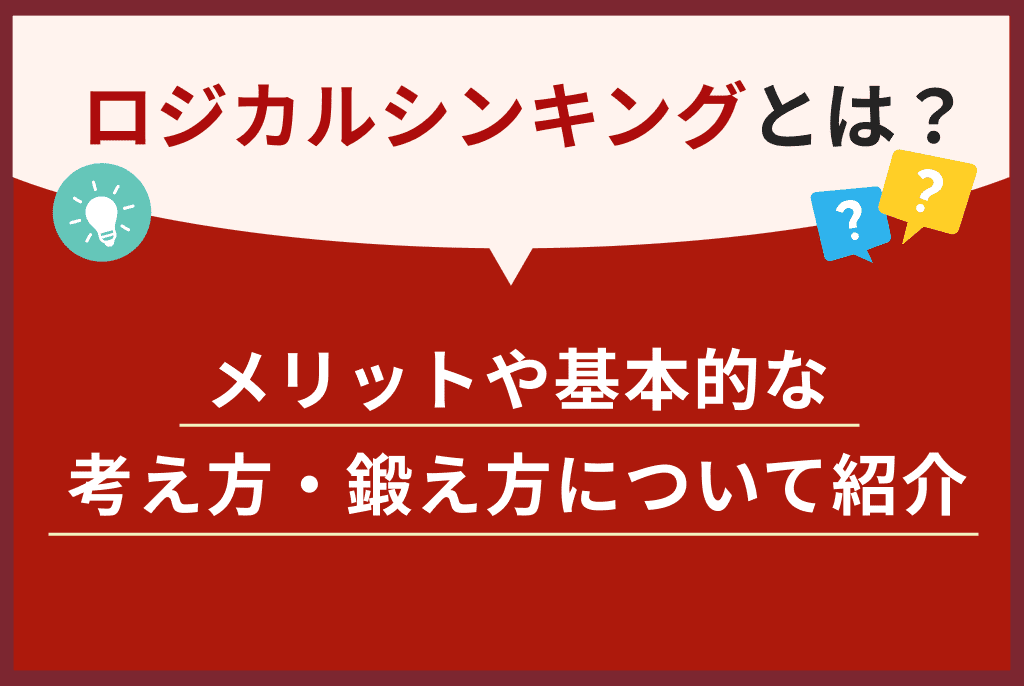
ロジカルシンキングとは?メリットや基本的な考え方・鍛え方について紹介
ビジネスの多くの場面でデータが活用されるようになってきた昨今、論理的に物事を考えるロジカルシンキングの重要性はますます増しています。ロジカルシンキングを鍛えるためには、ロジカルシンキングでよく用いられる思考法やフレームワークについてしっかりと理解した上で、思考をおこなうことが重要です。
ビジネスシーンでも役立つことの多いロジカルシンキングについて、身につけるメリットや基本的な考え方、鍛え方などについて解説します。また、人事担当者の方に向けて、社員に身につけてもらう方法についてもご紹介します。
より深く知るための『オススメ』お役立ち資料
目次[非表示]
ロジカルシンキングとは
ロジカルシンキング(論理的思考)とは、物事を深くスピーディに考えた上で、それをわかりやすく伝えるため、体系的に筋道立てて考える力のことです。ビジネスの現場では、矛盾の生じない合理的な結論を求められる場面が数多く存在します。ロジカルシンキングのスキルを身につけることで、納得感のある意思決定を行ったり、素早く課題解決を行ったりすることができます。
クリティカルシンキングとの違い
クリティカルシンキングとロジカルシンキングは、両方とも論理的思考を基盤としていますが、異なる点もあります。
クリティカルシンキングは、疑問を持ち、批判的に分析することに重点をおいています。情報や主張を受け入れる前に、それらを慎重に評価し、必要に応じて質問を投げかけることで、より深い理解を得ることが目的です。
一方、ロジカルシンキングは、証拠や前提条件を評価し、論理的なルールに従って推論を行い、最終的に正しい答えを得ることが目的ですので、前提条件を批判したりはせずに推論を行う部分で違いがあります。
ラテラルシンキングとの違い
ビジネスの現場における思考法の中では、「ラテラルシンキング」という言葉も有名です。ラテラルシンキングは日本語にすると「水平的思考」となり、既存の枠組みや偏った視点にとらわれない思考のことを指します。
ラテラルシンキングにおいては、「これまでの前提にとらわれない」「既存の発想にとらわれない」という点が重視されます。あくまでも既存の価値観に縛られない発想を重視するのがラテラルシンキングであるため、筋道だった考えを重視するロジカルシンキングとはまた違った意味を持っているのです。
ロジカルシンキングの概念が広まった背景

ロジカルシンキングの能力が重視されるようになってきた背景として、ビジネスが高度化・複雑化してきたということが挙げられます。個人の趣味嗜好が多様化した現在においては、常に新しい商品やサービスを生み出し続けることが必要です。無駄のないロジカルな説明をおこなうことができれば、企画の提案や商品の売り込みといった場面でも説得力を持った立ち回りができます。
また、IT化の進展によりデータが重視されるようになったという背景もあります。今や顧客データはほとんどがデジタル上で管理されている時代です。これに伴って、蓄積された膨大なデータからいかに論理的な結論を導き出すのか、というロジカルシンキングはますます重視されてきています。
ロジカルシンキングを鍛えるメリット
ロジカルシンキングの概要や、ロジカルシンキングが広まった背景について説明しました。それでは、ロジカルシンキングを鍛えることの具体的なメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
ロジカルシンキングの能力を高めると、ビジネスの効率化を始めとした様々な恩恵があります。ロジカルシンキングを鍛えるメリットについて見ていきましょう。
コミュニケーションがスムーズになり、仕事の効率がアップする
ロジカルシンキングを鍛える最大のメリットとして、論理的な思考によってコミュニケーションがスムーズになり、仕事の効率がアップするという点が挙げられます。ビジネスの現場においては、社内外の関係者と情報共有をしながら進めていくことが必要不可欠です。この際に、感情的な説明を多く交えてしまっては説得力がありません。
相手に納得感を持って自分の考えを受け入れてもらうためには、論理が飛躍したり破綻したりしない、首尾一貫した説明が求められます。ロジカルシンキングを鍛えることで、例えば説得力のある提案ストーリーを構築できる、ツボをおさえた上司への簡潔な報告ができるといった効果が期待できます。部署内を始めとした社内外とのコミュニケーションに無駄がなくなり、スムーズに仕事が進むようになるのです。
やるべきこと・考えるべきことの抜けモレが減る
ロジカルシンキングの能力を磨くことで、物事を常に抜かりなく考えることができるようになります。その結果、仕事においてやるべきことや考えるべきことの抜けモレが減るという効果が期待できます。
例えば「営業部署の売上が目標に達していない」という問題があったとします。ロジカルシンキングの能力が高い社員は、考えられるあらゆる原因を列挙しながら考えることができます。また、ロジカルシンキングは「お客様へ抜けモレのない商品説明をおこなう」といった場面でも有効です。
ロジカルシンキングの実際の手法・フレームワーク
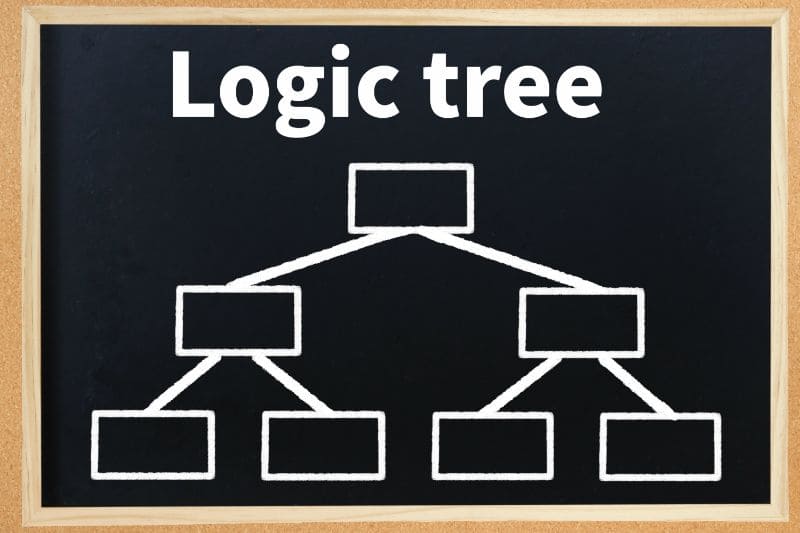
ロジカルシンキングには、様々な手法やフレームワークが存在します。実務で役立つロジカルシンキングを身につけるためには、これらのフレームワークをバランス良く身につけることが重要です。ロジカルシンキングを身につけるためによく用いられる、実際のフレームワークについて解説します。
ピラミッドストラクチャー
ピラミッドストラクチャー(ピラミッド構造)とは、結論から根拠へ向けたピラミッドを構築する思考法のことです。ピラミッドの一番上には、事実であると説得したい結論を置き、その下にその結論の根拠となる事柄を置きます。さらにその下の階層に、根拠の裏付けとなる根拠を配置することで、結論への説得力を高めていくのです。
ピラミッドストラクチャーを用いた思考法は2種類あり、「仮説→根拠→事実」と仮説から出発する論理展開をおこなうトップダウン・アプローチと、「事実→根拠→仮説」と事実から積み上げて論理展開をおこなうボトムアップ・アプローチの2つがよく用いられます。
グルーピング
グルーピングとは、混在する情報のなかから共通点を見つけ、グループごとに分類を行う能力のことを指します。例えばアンケートを実施しても、結果をどのように整理すればよいのか分からないこともあるのではないでしょうか。数あるデータを抜けもれなく上手くまとめ上げる際に必要な能力が、グルーピングという考え方です。
グルーピングの際は、まずデータを概観し、意味のある分類の切り口を見つけ出します。その後、それぞれのグループに情報を分類していき、グループの構成を確認することで最終的なグルーピングが完成します。グルーピングは、ロジカルシンキングをおこなう上での土台となる重要な能力です。
So What?
“So What?”とは、日本語にすると「つまり、何?」という意味です。会議やディスカッションが長引くと、つい本題から逸れたわかりにくい結論となってしまうことはないでしょうか。このような場合に役立つのが、”So What?”の観点です。
導き出された結論に対して”So What?”と今一度問いかけることで、他人に伝わりやすい単純明快な結論を目指すことができるようになります。ロジカルシンキングの力を伸ばす上では、”So What?”という問いかけを意識することも重要です。
Why so?
ロジカルシンキングにおいては、”Why so?”という問いかけも重視されます。”So What?”と似ている言葉ですが、”Why so?”は日本語にすると「どうしてそうなったの?」という意味です。結論に対して”Why so?”と問いかけることで、今一度結論に至るまでの根拠や論拠を見直すことができます。
例えば一見筋道だった考えが展開できたように見えるディスカッションであっても、思いもよらぬ論理の飛躍や重要な観点の抜けモレが発生していることがあります。”Why so?”という問いかけをおこなうことで結論に至った論理展開を再検証するという効果があるのです。
MECE
ロジカルシンキングにおいては、”MECE”も重要なキーワードです。MECEとは、”Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive”、日本語にすると「互いに被りがなく、全体としてモレがない」といった意味を持っています。
MECEという考え方が身につくと、情報にダブりを含むことなく、なおかつ網羅的に捉えることができるようになります。MECEの考え方を活用して顧客属性を分析したり、売上データを分類したりすることは、ロジカルシンキングを展開する上での土台ともなるためとても重要です。
ロジカルシンキングの基本となる推論方法
ロジカルシンキングを展開するためには、3つの基本的な推論方法が存在します。先ほど紹介したフレームワークと合わせてこれらの推論方法を身につけることで、全体を通して首尾一貫した説得力のある思考が展開できるようになります。ロジカルシンキングの基本となる3つの推論方法について見ていきましょう。
帰納法
1つ目の推論方法は、帰納法と呼ばれる推論方法です。帰納法とは、複数の実例から共通点を見出すことで結論を導き出すというプロセスを指します。
例えば「売上データを見ると30代の売上が多いから、30代向けにもっと販促施策を展開しよう」といったような考え方が帰納法にあたります。帰納法による推論の精度を上げるためには、なるべく多くの実例を考慮することが重要です。偏った視点にならないように注意するとともに、データの中から論理を抽出する分析力が求められます。
演繹法(三段論法)
演繹法とは、三段論法とも呼ばれ、あらかじめ決められたルールや基準に事象を当てはめていくことで結論を導き出す推論方法のことです。帰納法と対をなす概念であり、既に決められた事柄や一般論に基づいた論理展開を行います。
例えば、キャンペーンの開催時期について検討する場合に、以下のような演繹法(三段論法)を活用することができます。
前提1.競合店とキャンペーンが重なると客が分散する。
前提2.客が分散すると、販売目標に悪影響が出る。
結論:競合店とキャンペーン開催時期が重ならないようにするべきだ。
このように、演繹法を活用することで、既存の情報を基に、いつキャンペーンを開催するかを推論することができます。
既にある方針や一般論を根拠としながら、新しい情報を組み合わせて論理を積み上げていく演繹法も、帰納法と並んでロジカルシンキングにおける重要スキルです。
弁証法
弁証法には、「討論する」「対話する」といった意味があります。ビジネスにおける弁証法では、まず「テーゼ」と呼ばれる命題が提示されます。そして、テーゼと矛盾する命題である「アンチテーゼ」が提案され、最後にそれら2つの命題の矛盾点を解決する統合案である「ジンテーゼ」が提案されるという流れです。
わかりやすく例えると、会議において案Aが出され、それに反論する案Bが出され、最後に案Aと案Bを統合する案Cが出される、といった流れが弁証法にあたります。高いロジカルシンキング能力を持った人材は、常に弁証法の考え方を用いながら自問自答を重ねており、その結果としてブラッシュアップされた議論やアイディアが導き出せるのです。
ロジカルシンキングを学ぶ上でのポイント

ロジカルシンキングはビジネスの現場において常に求められる、汎用性の高いスキルです。それでは、ロジカルシンキング力を高めるためには具体的にどのようなポイントに気をつければよいのでしょうか。
ロジカルシンキング力を高めるためには、因果関係をはっきりさせる、ロジックをシンプルにするなど、いくつか思考法におけるポイントが存在します。ロジカルシンキングを学ぶ上でのポイントについて解説します。
因果関係をはっきりさせる
ロジカルシンキングの土台となるのは、「Aという物事が原因となってBという物事が発生する」という因果関係です。ロジカルシンキングのスキルを磨くためには、まず因果関係をはっきりさせることを意識してみましょう。
この際、自身が無意識のうちに抱いている偏見や先入観に左右されないことが大切です。常に「他にも原因はないだろうか?」「本当にここに因果関係があるのだろうか?」と自問自答を重ね、自分の考えている因果関係の正しさを検証していく必要があります。
ロジックをシンプルにする
一つのことに集中して考えていると、つい論理が複雑化してしまうことがあります。複雑な論理は要点が相手に伝わりにくくなってしまうばかりか、論点がぶれてしまい全体の説得力が低下してしまう原因にもなりかねません。
ロジカルシンキングをおこなう上では、できる限りロジックをシンプルにすることが大切です。論点が整理された単純明快な論理は、相手を説得するのにも役立ちます。議論が込み入ってきたときは今一度論点を整理して、結論に至るまでのプロセスを明確にすることが必要です。
前提条件を確認する
ロジカルシンキングの能力を高めるためには、前提条件をしっかりと確認することも非常に大切です。人間は無意識のうちに「これまでの常識」「今までの偏った経験に基づいた知識」といった前提条件にとらわれています。
議論の土台となる出発点に思い込みや先入観があると、論理が上手く展開できません。これまでの自分の思考プロセスを今一度確認して、「無意識に前提としている事柄は本当に正しいのか?」と検証することが大切です。
常に目的を意識する
論理的な思考が行き詰まってしまうと、つい「どのような問題を解決するために思考しているのだろうか」という目的意識を見失ってしまうことがあります。議論の着地点となる目的を見失ってしまうと、論理が迷走し、「結局なにを言いたかったのかわからなくなってしまった」という事態を招きかねません。
高いロジカルシンキング力を持った人材は、常に目的意識を持った思考を展開することができます。「この議論はどこへ向かっており、どのような問題を解決するための議論なのか」という観点を常に心に留めておくことが大切です。
相手の立場も考慮する
ロジカルシンキングをおこなう際には、ただ単に相手へ正論を押し付ければよいというわけではありません。自身の考える「正しい論理」に固執しすぎると、相手に不快感を与えてしまうこともあります。
伝え方を変えるだけでも、相手に与える印象は変わります。論理の押しつけによって人間関係をこじらせないためにも、相手の立場を考慮することが大切です。
ロジカルシンキングを身につけてもらう方法
ロジカルシンキングを身につけるためのポイントについて解説しました。ロジカルシンキングを構成する要素は多岐にわたるため、なかなか一朝一夕で身につくものではありません。社員のロジカルシンキング力を高めるためには、毎日コツコツと行う継続的な取り組みや研修が必要です。
この記事の最後に、ロジカルシンキングを身につけてもらう方法について解説します。
ロジカルシンキングのフレームワークを伝える
「ピラミッドストラクチャー」や「MECE」、「ロジックツリー」などのフレームワークを知っておくことで、ロジカルシンキングが苦手な社員でもロジカルシンキングを実践しやすくなります。
ロジカルシンキング研修などで、基本のフレームワークを伝えましょう。
ロジカルシンキングのフレームワークについては以下の記事をご覧ください。
『ロジカルシンキングのフレームワーク11選。思考方法や活用方法を解説』
日常業務でロジカルシンキングを意識してもらう
上司への報連相や議事録作成など、日常業務にロジカルシンキングを取り入れることを意識してもらうことも有効です。報連相の際にロジックツリーを基に結論と根拠を述べるようにしたり、情報収集の際にMECEを意識するとよいでしょう。日常業務の中で繰り返し実践することで、意識しなくてもロジカルシンキングを使いこなせるようになります。
ロジカルシンキング研修でケーススタディを扱う
ロジカルシンキング研修を実施する際には、講義だけでなくケーススタディをプログラムに組み込みましょう。講義で正しい知識を身につけた後に、受講者自らが考えてアウトプットを出すことにより、「わかる」の状態から「できる」の状態に変化できます。
ケーススタディは受講者にとって身近な内容を取り入れると効果的です。たとえば新入社員であれば、上司への報連相や議事録作成のケーススタディを実施するのがおすすめです。
アルーのロジカルシンキング研修は、ケーススタディを豊富に取り入れ実践の機会を設定していることが特徴です。詳しくは以下のページをご覧ください。
ロジカルシンキング研修
▼サービス資料をダウンロードする
ロジカルシンキングの例題を解いてもらう
ロジカルシンキングの例題を解いてもらうのも有効です。ロジカルシンキング研修後に理解度テストとして実施すると、どの程度内容を理解できたかチェックする指標にもなります。
ロジカルシンキングの例題は以下の記事で紹介しています。
『ロジカルシンキングの例題10選|解答例や学習方法を紹介』
▼ロジカルシンキングの例題集をダウンロードする
ロジカルシンキングの注意点
ロジカルシンキングを取り扱う際には、いくつかの注意点があります。以下の3点について、社員にも周知した上でロジカルシンキングの習得に取り組んでもらいましょう。
コミュニケーションは「論理的」なだけではうまくいかない
ロジカルシンキングはコミュニケーションを円滑にする際にも有効ですが、論理的であることばかりに重きを置くと、コミュニケーションの阻害要因ともなりえます。相手の感情を考慮せずにただ正論を押し付けてしまった場合、人間関係の悪化に繋がることがあります。論理的に整理された意見を提示することは重要ですが、相手の感情や意見を尊重することも同様に大切です。
ロジカルシンキングと同時に、アサーティブコミュニケーションを身につけてもらうことも検討しましょう。アサーティブコミュニケーションは、自分と相手のどちらも大切にしたコミュニケーション手法のことです。
アサーティブコミュニケーションについて詳しくは以下のページもご覧ください。
『アサーティブコミュニケーションとは?職場での事例やデメリットを解説』
理論と現実の乖離が起こる場合がある
ロジカルシンキングは、論点を単純化することで、議論を容易にし、理解を深めることができます。しかし、この単純化が行き過ぎると、理論と現実のギャップが生じるリスクもあります。理論上は正しいかもしれませんが、現実はもっと複雑であることを念頭に置くべきです。
思考法に固執しない
ロジカルシンキングに過度に固執することも問題です。ロジカルシンキングは有効なフレームワークの一つに過ぎません。固定された枠組みに縛られすぎると、創造性や柔軟性が損なわれ、革新的なアイデアが生まれにくくなります。特に新しい分野やイノベーションの創出においては、ロジカルシンキングだけに依存しない姿勢が重要です。
これらの点に注意を払いながらロジカルシンキングを活用できれば、より効果的かつ円滑なコミュニケーションと問題解決が期待できます。
まとめ
ロジカルシンキング力でよく使われるフレームワークや思考法、さらにはロジカルシンキング力を磨く方法について解説しました。ビジネスの至る場面でデータが重視されるようになってきた昨今、論理的な考えを展開する能力は職種を問わず求められるようになってきています。論理的な思考を展開することは、ビジネスを円滑に進める上でも重要なことです。ぜひこの記事の内容を参考にして、ロジカルシンキング研修を企画・実施してみてください。
▼ロジカルシンキング研修について詳しくはこちらのページをご覧ください。