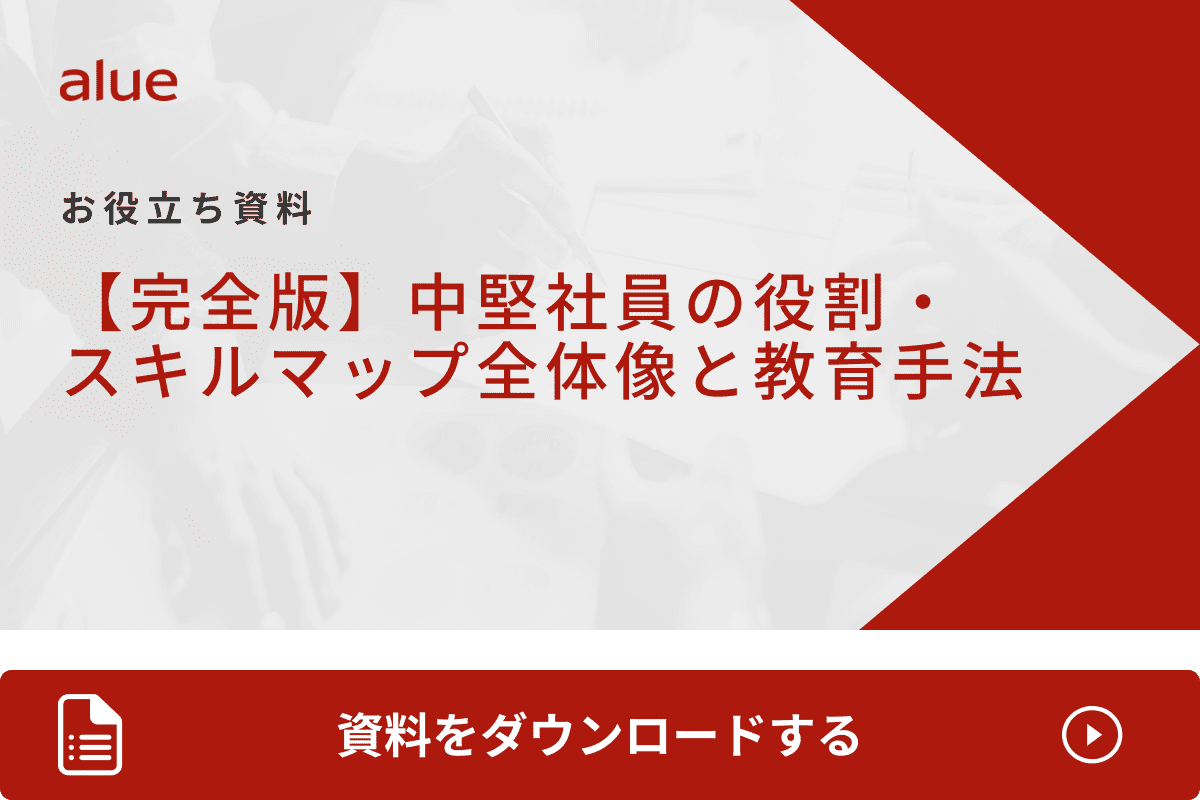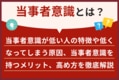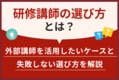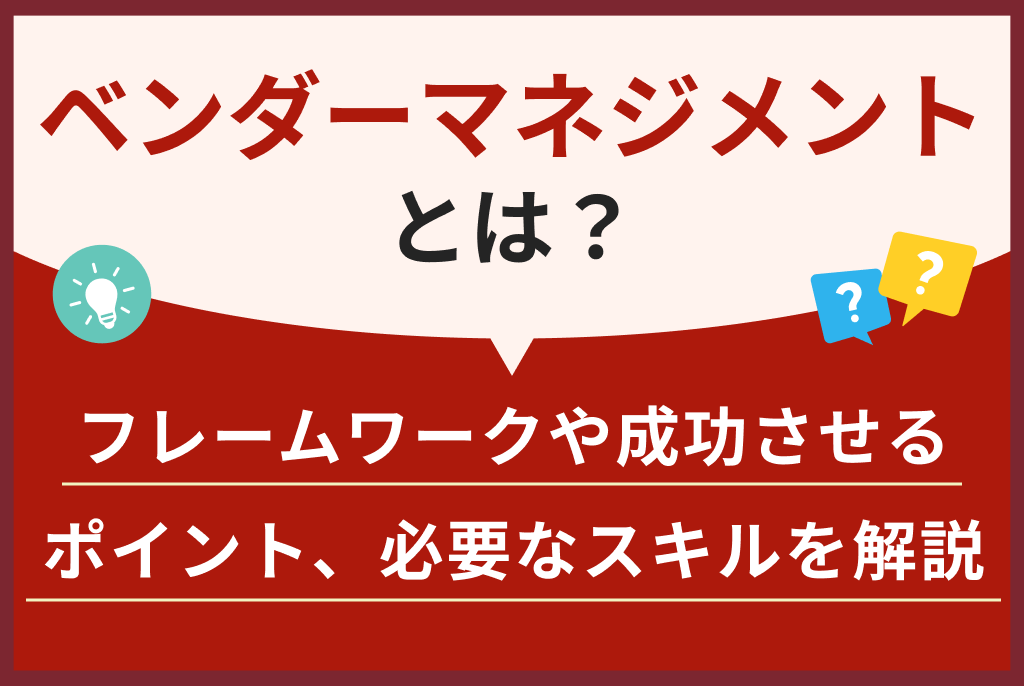
ベンダーマネジメントとは?フレームワークや成功させるポイント、必要なスキルを解説
近年、慢性的な人手不足が続いています。各企業は日々の通常業務ですらアウトソーシング化をはかり、なんとかやりくりしているという状況も今では当たり前の話になりました。そしてIT技術の進歩もめざましく、ついこの前、世に出てきた技術やサービスが、あっと言う間に過去のものになっています。こんな2つの背景もあり、多くの企業が、たとえば自社の通信・ネットワーク環境の構築や、自社業務に関するシステム開発を、いわゆるITベンダーと呼ばれる協力会社に担ってもらっています。このように、外部の協力会社(ベンダー)と協力して何かをすることが当たり前になっています。しかし、そこには協力会社との関係性がうまくいかず、思ったような成果を出せずに苦労している企業もたくさんあります。
そこで本記事では、ベンダーマネジメントをテーマに、自社のビジネスやバックオフィス業務をサポートしてくれる協力会社(ベンダー)との関わり合いについて、ベンダーマネジメントの基本的なやり方、その際の注意点などについて解説します。
▼中堅社員育成におすすめの研修3選

目次[非表示]
ベンダーマネジメントとは
ベンダーマネジメントとは、その言葉のとおり「ベンダー(協力会社)」を「管理」することです。何のために何を管理するのかと言うと、ベンダーとの関係性を良好な状態に保つために、ベンダーとの契約、ベンダーからのアウトプットの品質(状態)、その他日々の業務での問題点など、自社とベンダーが関わり合うものを全般的に管理します。
「管理」と聞くと、どこか上から目線な言い方のようにも聞こえます。相手ベンダーからもよく思われないのでは?と感じる人もいるかもしれません。しかし、実態はそんな印象とはまったく逆です。ベンダーマネジメントがうまく出来ている企業は、日頃からベンダーとの連携が密に取れており、彼らとの関係性も良好です。お互いのビジネスにおいてWIN-WINの関係が築けています。
逆にベンダーマネジメントがいい加減な企業は、仕事の指示が曖昧になったり、コミュニケーションミスが起こりやすい状況にあります。そしてそれらが原因となり、プロジェクトの納期やコストも超過することもあります。納期・コストの超過は、ベンダーにとっても喜ばしい状況ではありません。ベンダーマネジメントとは、企業とベンダーの双方にとって必要な取り組みといえます。
ベンダーマネジメントが担う役割

役割その1 「契約の管理」
協力会社(ベンダー)との協業は、それに関する契約書が交わされることで、はじめて成立します。どうせこの後で契約書ができるからといって、契約書ができる前に企業側が指示をしてはいけないですし、協力会社はその指示を受けてもいけません。それだけ仕事の契約書は絶対であり、それが守れなければ法律違反にもなってしまいます。
そして仕事が完了すれば、納品書や請求書といった対価の支払いに関する一連の契約書類が必要となります。またこれ以外にも、定期的に更新される契約や、発注依頼とは異なり、機密情報漏洩を防ぐための機密保持契約もあります。
ベンダーマネジメントでは、これら契約書類に対し、その不手際のせいでお互いの仕事に支障が出たりしないように、その内容や期限を適切に管理します。
役割その2 「品質(成果物・サービス/納期/費用)の管理」
ベンダーからのアウトプット全般の品質を管理します。アウトプットとはベンダーから納品される成果物や、その他サービス全般を指します。それら成果物やサービスが、企業側が想定していた水準を満たしているかを定期的に判断します。
たとえば、協力会社がシステム開発をするITベンダーであれば、彼らが提供するシステムそのものの性能、関連するドキュメントの正確性や充実度、何か不測の事態が起きた際のサポート内容などが、彼らのアウトプットになります。企業側はそれらの出来具合が想定していた水準にあるかを判断し、それを下回っていた場合は、その事実を伝えるとともに、その原因を協力会社と一緒になって考えます。また、サービスや成果物が水準を満たしていても、それが納期を超えてしまっていたり、予定の費用を超過してしまっては、お互いに求めていた結果になったとは言えません。そして納期超過や想定以上の支出は、次のプロジェクトや年間の計画に影響する場合もあります。
このような状態に陥らないためにも、仕事が完了する前から、成果物の品質やスケジュールの進行状況などには特に目を配る必要があります。
役割その3 「問題・リスクの管理」
ベンダーとの関係性を良好に保ち、それを維持していくためには、契約や成果物の状態だけでなく、そこで発生するさまざまな問題や、これから問題に発展するかもしれないリスクにも適切な対応が必要です。
いくら契約書や品質の管理を適切に進めても、実際の仕事では、それらとは関係ないところで、パワハラやモラハラになりかねない問題が起きたり、昨今のコロナ禍のような仕事自体が継続できない問題が発生することがあります。このような問題に直面した時や、この先、問題になるかもしれない事柄を見つけた時は、速やかに協力会社と相談し適切な対応を行います。
ベンダーマネジメントの具体的な手順
ベンダーマネジメントのやり方は、企業やプロジェクトの規模、これまでの企業とベンダーの関係性など、さまざまな要素を考慮し、両者にとってちょうど良い管理方法を探りながら行います。
しかし、はじめて協業するベンダーとは、その感覚がまだないため、概ね以下の手順で行われます。
<ベンダーマネジメントの手順>
- ベンダーの選定
- 契約の締結
- コミュニケーション方法の確立
- 品質評価と改善
ベンダーの選定
企業側のニーズに応えてくれる協力会社を選定します。選定候補を見つける際は、協力会社のホームページなどを見て企業側から問い合わせをしたり、これまで付き合いのある会社から紹介されたり、協力会社の営業担当からコンタクトがある場合などさまざまです。
そして、候補の中から協力会社を選定するまでには、協力会社の営業担当や、実際に仕事を担当してもらう部門の部門長との面談などでお互いの条件などを確認します。
今後その協力会社とお付き合いしていくかどうかは、協力会社のこれまでの実績や現状の体制などをみて、こちらのニーズに対応できるだけの要員がいるか、問題が生じた際にリカバリーできる仕組みがあるかなど、総合的な判断をして決定します。
契約の締結
ベンダーの選定後、最初に行うのは契約の締結です。契約書類の手続きは、実際の仕事がスタートするまでに、ひととおり済ませる必要があります。
契約の締結には、契約の目的、期間、報酬の支払い、契約解除事由などについて明記する基本契約書が必要となりますが、この他にも自社の業務に関わる仕事をしてもらう関係上、機密情報保持契約も必須の契約書類となります。
コミュニケーション方法の確立

契約が完了すれば、実際の仕事が始まります。ここで忘れてはいけないのが、「ベンダーの仕事の状況」をタイムリーに知る方法を確保することです。ベンダーの状況や、仕事の仕方などで、十分な情報がなければ、ベンダーとの関係性を管理したくても、やりようがないからです。
たとえば、『月に1回ペースでベンダーの営業担当から状況報告をしてもらう』、『プロジェクトに関する仕事であれば週に1回ペースで進捗状況を報告してもらう』など形態はさまざまです。
また報告を受けるばかりではなく、企業側の今後の予定や将来のビジョン・戦略を伝える場なども定期的に持つと、お互いの目的意識なども一致して、よいパフォーマンスが発揮しやすくなります。
ここで定期的なコミュニケーション方法を特に決めず、「何か問題があった時に話をしましょう」としてしまうと、いざ問題が発覚した際は、すでに手遅れという状況にもなりかねないので注意が必要です。
品質評価と改善
定期的に成果物やサービスの質について評価し、その結果をベンダーと共有します。評価の判断材料は、現場からのヒアリング結果などをもとに判断する場合もあれば、ベンダーから定期的に行われるパフォーマンスや品質に関する報告を使用する場合もあります。
しかし、現場社員からは「協力会社にはもっと頑張ってほしい」というニーズがあがり、協力会社からは「もう十分すぎるほど頑張っています」という逆の所感が出てくる傾向があります。
そのため、どちらか一方の情報で判断するのではなく、両者の言い分を聞いたうえで公平な評価をする必要があります。そしてその評価の結果が企業側にとって満足するものであれば、ベンダーに感謝の意を伝え、そうでなければ問題の原因分析や対処を双方で協力しながら取り組むことが望ましいです。
ベンダーマネジメントを成功させる3つのポイント
成功のポイントその1:一方的な関係性にならない
企業とベンダーの関係性は、仕事を発注する企業側と受注するベンダー側という見方ができます。また別の見方をすれば、仕事の遂行を依頼する側と、引き受ける側でもあります。両者の立場の違いははっきりしていますが、この関係性はどちらか一方が、もう一方の言いなりになってしまうリスクがあります。
たとえば、ベンダーが仕事を受注したいために無理な注文を受けるとか、企業側ではやれる人がいないために、ベンダーのやり方や言い値のままに仕事を発注してしまうなどです。お互いに協力しながら最善を考えるというよりも、どちらか一方の要望だけがとおる状態は、「無理を通せば道理が引っ込む」とも言われるように、必ずしも最適な方法とは言えず、結果的にも良い成果が出るとは限りません。
成功のポイントその2:現場の実態と乖離しない
企業とベンダーとのコミュニケーションにおいて、お互いの管理職同士が話をする場面は珍しくありません。お互いに決裁権を持ち、社員への指示もすぐに出せるので、何か問題が発生した場合などは、とてもスピーディーな対応ができます。
しかし、ここでの両者の会話が現場の実態を把握しないままに行われてしまうと、そのしわよせは現場のメンバーが被ることになります。現場にいる社員たちとは関係のないところで、上位者だけで話がまとまってしまうことはどこにでもある話ですが、現場の実態とあまりにも乖離した計画や方針は、現場のメンバーを疲弊させ、品質低下や別のリスクを生んでしまう原因になります。
成功のポイントその3:事なかれ主義にならない
「事なかれ主義とは」何か問題が発生した時でも、あえて波風を立てないように取り計らい、問題がおさまるまで何もなかったかのように振る舞うことです。もちろん、問題によっては解決までにある程度の時間が必要なため、今は何もせずにしばらく様子を見た方が良い場合があります。また下手に解決に乗り出し、そこに予定外の人的リソースを割いてしまうと、それをきっかけに他のところで別の問題が発生する場合もあります。
ベンダーとの仕事で発生する問題は、どんなものでも会社間の問題として扱われるため、ちょっとした問題でも大事になりかねません。そのため、現場のリーダーやマネージャーは、問題が起きてもとりあえず様子を見る傾向にあります。しかし、この様子見にあまりにも慣れすぎてしまうと、迅速な対処が必要な時でも、様子を見るというスタンスになってしまいます。行き過ぎた様子見は、見て見ぬフリをしていることと同じになってしまうので注意が必要です。
ベンダーマネジメントに必要な3つのスキル
ここからは、ベンダーマネジメントを活用する人材に必要な、3つのポータブルスキルをご紹介します。
ベンダーとのコミュニケーションを円滑に進めるスキル
ベンダーマネジメントをうまく活用するためには、
のような、コミュニケーションスキルが必要です。明瞭で適切なコミュニケーションをおこない、相手と認識の齟齬を生じさせないようにすることで、自分が所属する企業とベンダー(協力会社)との付き合いを良好にすることができます。
プロジェクトマネジメントスキル
社内外の多くの人間が関わるプロジェクトを進めいくうえで、プロジェクトマネジメントスキルを身につけることも必要です。また、そのなかでリスクマネジメントも必要になります。
▼プロジェクトマネジメントの手法や成功させるポイントはこちらの記事で詳しく知っていただけます。
プロジェクトマネジメントとは?代表的な手法・成功させるポイントを解説
リーダーシップ
社内外のプロジェクトのメンバーとコミュニケーションを取りながら、最終的な決定をおこなうベンダーマネジメントには、リーダーシップが必要です。
プロジェクトの成功という同じ目的をベンダーと共有し、ときにはベンダーを積極的にリードしてプロジェクトをみずから推進していくことが求められます。
アルーのベンダーマネジメント研修事例

人材育成を手掛けているアルーでは、社員のベンダーマネジメントスキルを伸ばすための研修を数多く実施しています。ここからは、アルーが実施している研修の中から特に参考となる事例を1つご紹介します。ベンダーマネジメント研修の具体的なプログラムについて知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
ベンダーマネジメント研修事例
ここからは、弊社で実際に実施しベンダーマネジメント研修の事例をご紹介します。総合演習も含めた1日間の研修事例です。
▼テーマ
ベンダーマネジメント
▼ねらい
ベンダーマネジメントの全体プロセスを把握し、必要なポータブルスキルを身につける
▼内容
①オリエンテーション
トレーナーと受講者間でベンダーマネジメントの全体感や実践する際にむずかしい点などについて話してもらい、これから始まる研修で各自がベンダーマネジメントの何を重点的に学ぶべきかを意識してもらいます。
②ベンダーマネジメントの必要性
そもそもベンダーマネジメントがなぜ必要かを学び、学習意欲を高めます。
③ベンダーマネジメントにおけるプロセスの全体像
ベンダーマネジメントの全体プロセスを知り、各フェーズでの留意点やうまく進めるためのコツを学びます。
- ベンダーの評価と選定
- ベンダーとの契約締結
- ベンダーと仕事を進めるプロセス開発
- 品質評価
- 継続的な改善プロセス
④ベンダーマネジメントに必要なコミュニケーションスキル
ベンダーマネジメントを活用するために必要なコミュニケーションに焦点を当て、具体的な場面を想定した演習を実施し、現場で実践できるようにします。
- ベンダーへのフィードバック
- Win-Winの関係を築くためのネゴシエーション
- 問題が発生したときのクレーム対応
⑤まとめ
研修の振り返りをおこない、アクションプランを作成することで、現場での実践を後押しします。
まとめ
本記事では、ベンダーマネジメントをテーマに、フレームワークや成功させるポイント、必要なスキルについて解説しました。
今後も人手不足が深刻化することが予想されるなか、外部の協力会社とつまく付き合えるかどうかは、仕事の生産性に直結する大きな問題となり得ます。
ぜひこの記事の内容を参考に、ベンダーマネジメントスキルを高める施策や研修を効果的に実施していきましょう。