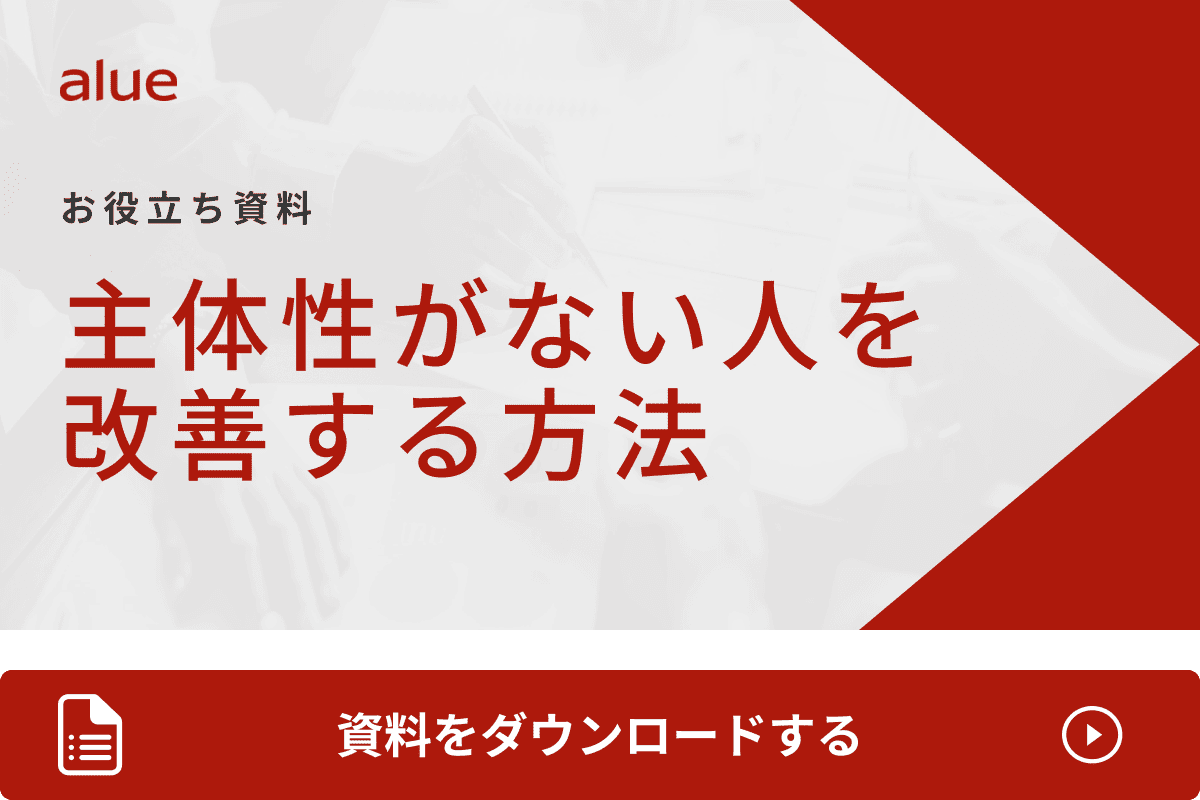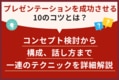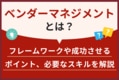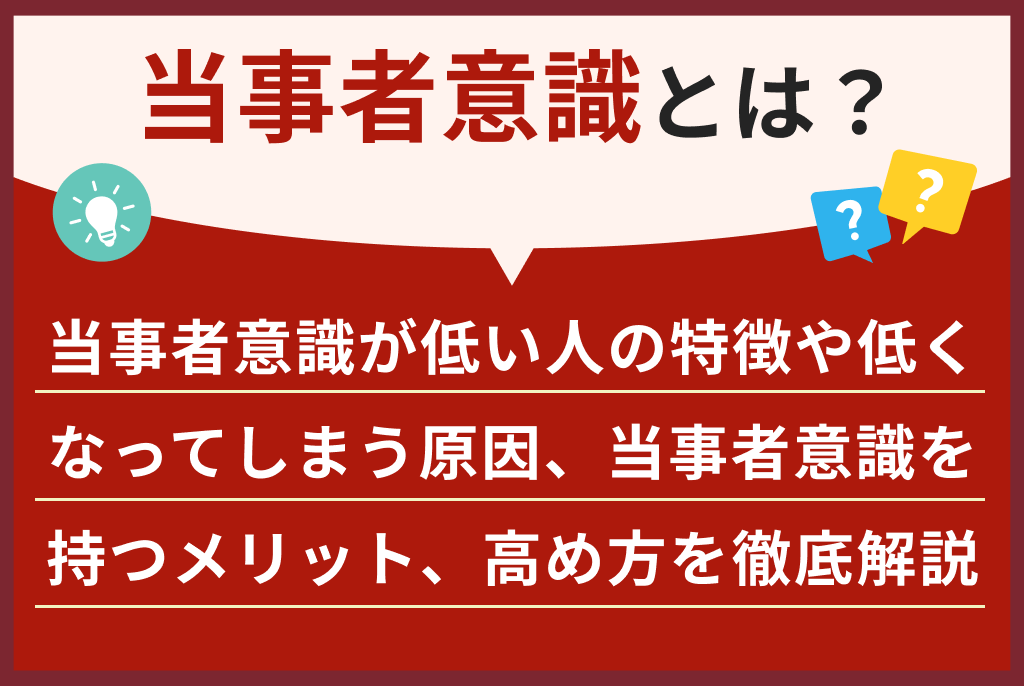
当事者意識とは?当事者意識が低い人の特徴や低くなってしまう原因、当事者意識を持つメリット、高め方を徹底解説
- 会社を変革しないと生き残れるか分からないのに、社員に危機意識が感じられない
- 問題意識を口に出すことはあるが、批評家のような立ち位置に留まろうとする
- 会議など公の場で思っていることを発言しない
- 会社や組織、トップ層にのみ変わることを求め、自分が変わる必要性に目を向けない
のような社員に悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
ビジネスパーソンには、仕事に当事者意識をもち、責任を感じて取り組むことが求められます。ですが、そんなことは分かっていても、当事者意識や責任をもつことをためらう方が多くいらっしゃいます。
そこで本記事では、
- 当事者意識とは何を意味するか
- 当事者意識が低く、責任を引き受けることができない人の特徴や原因
- 当事者意識をもち、責任を引き受けるメリット
をご紹介します。

目次[非表示]
当事者意識とは何か
当事者意識とは、「自分自身が、その事柄に関係すると認識していること」や、「その事柄の直接の関係者であるという自覚」という意味です。つまり、ビジネスの場面で当事者意識を持つというのは、自分は企業の大切な関係者の一人であるという事実を理解し、仕事は自分にとって価値があり、責任を伴う事柄だと認識している状態を意味します。
当事者意識と責任感の違い
当事者意識と同じように、仕事の場面でたびたび使われる言葉に、責任感があります。責任感とは、「ある役割を担う人がもつ、道義的な思想、合理的な判断、利害感情に影響されて醸成される意識」という意味です。わかりやすく言うと、「自分の仕事をきっちりやろう」のような、道徳観や意思のことです。責任感をもっているかどうかは、自分自身の問題であり、自覚しやすいものです。
一方で、当事者意識は、自分が直接の関係者であることを気づいていないことがよくあります。前述の、「問題意識を口に出すことはあるが、批評家のような立ち位置に留まろうとするのような人」は、責任感はあるが当事者意識がない、ということになります。
組織に当事者意識の低い人がいるデメリット
仕事に当事者意識をもち、責任を引き受けて取り組むことができないと、受け身の姿勢になり、周りで起こることは“身に降りかかるもの”と考えるようになります。そうすると、たとえば仕事で失敗してしまったときに、自分を被害者だと思い、言い訳や他人への非難を繰り返して逃れようとします。また、結果として苦しい思いが続き、自分が何も学ぶことができないだけでなく、組織内にあきらめの空気が蔓延するなどのデメリットが生じます。この状態を、被害者意識の悪循環に陥っている状態、といいます。完璧な人間はいませんので、誰もが「自分は被害者だ」と思うことはあります。ですが、そこにずっと囚われないように、気を付けなくてはいけません。
当事者意識が低下している人の兆候
ここからは、被害者意識に囚われたときにすぐに気づけるように、当事者意識が低く、責任を引き受けることができなくなっている危険な兆候をご紹介します。
言い訳を並べる

仕事でミスをしたり、計画通りに進まなかったりと何か問題が発生したときに、まっさきに周りの人や環境のせいにして、言い逃れをしようとします。実際、自分ではどうしようもできないこともありますが、言い逃れはいつの間にか当たり前のように定着し、自分以外を攻める攻撃的な態度に発展してしまいます。
無視する/様子をみる
問題があるのに気づかないふりをしたり、その問題の影響を受けているのに知らんぷりします。ハラスメントの事実や残業時間をごまかすなど、いつか明らかになることを先延ばしにして、自分の首を絞めてしまう結果となることは驚くほど多いものです。また、状況が改善することを願いつつ何もしない、「様子をみる」行動にも注意が必要です。
人まかせにする
仕事は自分の責任でおこなうものではなく、他人ありきのものという意識をもち、責任感も低くすぐに人に頼ろうとします。何かをしなければ成果は得られないと気付いているものの、巻き込まれたくないという思いが強く、「余計な」責任を負いたくないと考えている状態です。いちいち具体的な指示を求め、「何をすればいいか教えてほしい」という言葉がよく聞かれると黄色信号です。
なぜ当事者意識が低くなってしまうのか
なぜ被害者意識の悪循環に陥り、当事者意識や責任をもつことができなくなってしまうのでしょうか。ここからは、その原因を3つご紹介します。
仕事の目的を理解できていないから
仕事の本質や目的を理解できないと、何のために仕事をしているかが分からず、どうしてもやりがいや情熱が欠けてしまいます。結果、「やらされ感」が生まれ、「他人ごと」になります。
周囲の状況が把握できないから
周りのメンバーがどのくらい会社にコミットしているかわからないと、自分がとるべき行動のレベル感がわからなくなり、当事者意識がもちにくくなります。特に日本人は周りをみて自分の足並みを揃える考え方が身についているため、輪からあえて外れるような行動を恐れます。また、忙しいプレイングマネジャーにありがちですが、自分のことに精いっぱいで周囲の状況が把握できなくなることもあります。
言い訳をするほうが楽だから
当事者意識をもち、責任を引き受けて仕事に取り組むよりも、言い訳をするほうがはるかに“楽”です。遅刻をする、約束を破る、担当作業を怠る、などさまざまな場面で言い訳があふれています。言い訳には、失敗の本当の理由や考えるべき事情がある場合もありますが、それが当たり前になると個人にとっても組織にとっても悪い影響が生じます。
当事者意識を持つことのメリットとは
当事者意識をもち、仕事の責任を引き受け主体的に働くことのメリットには、以下の5つが挙げられます。
主体性のある行動ができる
当事者意識をもち、仕事の責任を引き受けることは、主体的な行動につながります。また、仕事をやり遂げようとモチベーションが上がり、仕事への愛着も強くなります。「やらされている仕事」から「自分がやるべき仕事」に変わることで、目標達成に向けたプロセスが自分ごととなり、誰かに依存するのではなく、自分で素早く、的確に判断するようになります。
やりがいが生じる

主体的に動くときには、最善を尽くすことに意識が向かいます。考えられる方法の中で最もよい方法は何かを考え、自分に与えられた役割を果たそうとすると、自分が期待されている以上の結果につながりやすくなります。そのような行動や結果は、上司や部下、同僚との強い信頼関係を生みますし、当然、自分の評価にもつながります。人間関係が良好になったり、評価がよくなれば、やりがいが生じます。ときには、重要な役割を任されることにつながり、やりがいが増えることもあります。
自律的な成長につながる
仕事を最後までやり遂げるということは、そのために努力をする、ということです。努力をすることで、自分自身へ負荷をかけることになります。人は、自分に課せられたハードルを越えることで成長することができますが、努力をし続けることは困難です。これは、新人でも管理職でも同じです。やりがいを感じる、やりがいが増えることは、努力をし続けることにつながります。
変化を受け入れやすくなる
変化を受け入れやすくなることもメリットのひとつです。とくに最近は、業務効率化、グローバル化、DX推進、多様な人材活躍、リスキリングなど、企業を取り巻く環境の変化が多岐にわたり、かつ変化のスピードが速くなっています。そんなVUCAの時代、自分の市場価値を高めることは、ビジネスパーソンにとって大きなテーマです。
人は、自分の行動を変えようとしても、これまでの成功パターンなどが頭に浮かび、なかなかうまく進みません。当事者意識をもち、仕事の責任を引き受けることで、変わるべき点を率直に受け入れ、自分の価値を高め続けることができます。
組織の成果につながる
主体的に行動するようになれば、与えられた仕事を果たすだけではなく、組織としての目標達成も個人の責任の一部だと社員が受け止めるようになり、自分の業務を超えた部分にも責任を感じるようになります。会社の利益、顧客からの苦情、情報共有、組織間コミュニケーションなど、会社全体の事柄に対して、社員一人ひとりが責任を感じるようになることで、目的とビジョンが共有され、組織が強くなり、成果を上げられるようになります。
社員の当事者意識を高めるためにできること
社員に当事者意識を高めてもらうためにできることには、どのような方法があるのでしょうか。ここからは、社員の当事者意識を高める方法を4つご紹介します。
期待役割を伝える
社員が当事者意識を持つ際に、通常「業務目的」に対して当事者意識を持とうとします。業務目的とは、たとえば、より多くのクライアントに自社サービスの価値を届ける、とか、クライアントの満足度を高める、などです。あるいは、上の立場になると「経営課題や事業課題」に対して当事者意識を持つことが求められます。自分に期待されている役割を正しく認識することで、自分が何に対して当事者意識を高めるべきなのかをはっきりすることができます。
ビジョンや価値観に基づいた目標設定をおこなう
組織には組織の大切にしているビジョンや価値観がありますし、社員個人にも大切にしているビジョンや価値観があります。それらのビジョンや価値観を重ね合わせることで、組織の成長と自分の成長の両方を前向きに考えられるようになります。とくに近年の若手社員は、自分のビジョンや価値観を大切にする傾向が強いため、単に短期的な数字目標を決めるだけでは離職を招く恐れが高まります。
意見交換の機会を増やす
チーム内や部署内、あるいは部門の垣根を超えて意見交換できる場を増やすことも有効です。自分の意見を言える、あるいは聞き入れられる、という場があることで当事者意識が高まります。メンバー層が自分から、「意見交換をしたい」と提案することは非常に難しいですので、上司や人事などが意見交換の場を増やす工夫をするのがおすすめです。
評価と振り返りをおこなう
目標は立てただけでは意味がありません。会社や自分が成長するために立てた目標に対して、どのような行動ができたか記録し、振り返り、フィードバックを受けることで、次の行動につなげることができます。評価と振り返りを適切におこない続けられると、自分の仕事の意味づけができ、当事者意識を高めることにつながります。
社員の当事者意識を高めるためのコーチングのステップ

当事者意識をもち、責任を引き受けられるようになるには、まず、自分がその状態にあるか否かに気づかなくてはいけません。リフレクションを活用して、個人で振り返り、現状に“気づくこと”ができる人もいますが、目の前の忙しさに追われ十分な振り返りをおこなうことが難しい場合もあります。そこでここからは、コーチングによるフィードバックを活用し、周囲の協力をもとに“気づかせる”方法をご紹介します。
仕事に当事者意識と責任をもつ、ということを理解できたからといって、ずっとその状態が保てるわけではありません。しかし、職場であれば先輩や上司がコーチとなり、フィードバックすることで、気づかせることができます。ただし、「言い訳してるぞ」などと釘をさしても押しつけのように感じ、被害者意識が強くなってしまいます。「私は正しくて、あなたは間違っている」というような態度が伝わらないように、「この問題を一緒に解決しよう」といった姿勢で指導する意思を明確に表す必要があります。また、後輩や部下のためにコーチングしても、立場の違いから「何か別の目的があるかも」など誤解が生じ、信頼が得られない場合もあります。そうならないためにも、次の5つのステップでコーチングを進めます。
ステップ①:傾聴
相手が言い訳に逃げて、被害者意識を持っている状態であることを意識しながら話を聞きます。たとえば、相手の言葉を同情的に聞く、などの手法があります。
▼傾聴の方法やポイントはこちらの記事で詳しく知っていただけます。
傾聴力とは?高い人の特徴や高める方法、コミュニケーションで活かすコツを解説
ステップ②:受容
仮に相手が言い訳に逃げていたとしても、簡単にはそこから脱することができないと自分に言い聞かせ、相手の気持ちに理解を示します。たとえば、乗り越えるべき問題を認め、どんな人にもつらいことが起きるなどと同意を示します。
ステップ③:質問
少しずつ当事者意識と責任がもてるように、質問を繰り返します。たとえば、「求める結果を出すために何ができますか」、「この状況を変えるために何ができますか」などと質問します。
ステップ④:フィードバック
相手がこちらの話を聞く気になったところでフィードバックし、相手の行動に対して改善点や評価を伝え、軌道修正を促します。
▼フィードバックの方法やポイントはこちらの記事で詳しく知っていただけます。
フィードバックの意味とは?効果・実施する方法・ポイントをわかりやすく紹介
ステップ⑤:コミットし、フォローする
改善に向けてアクションプランを考え、途中経過を報告してもらうようにします。部下が遠慮しているようなら、必ず上司から声をかけ、相手のことを気にかけながら、部下の話を聞いて理解に努めます。このとき、改善がみられるたびに褒めると効果があがりやすくなります。
社員の当事者意識を高める研修ならアルーにお任せください
社員の当事者意識を高める研修なら、ぜひアルーへお任せください。
人材育成を手掛けているアルーでは、社員の当事者意識を高める育成プログラムを数多くご用意しております。アルーの実施する育成プログラムでは、グループワークや実践を通じて当事者意識を高めることが特長です。例えば社員の当事者意識を高めるため、自分の担当業務を捉え直し、自分を再定義するワークをおこなうことで、当事者意識を高めることができます。また、管理職に対して、メンバーが当事者意識を持ち続けられるようコーチングスキルを高める研修もあります。
お客様の企業の抱える課題に合わせて、研修内容を柔軟にカスタマイズすることも可能です。例えば、新入社員から中堅社員を幅広く対象とした研修もあれば、女性リーダー層を対象とした研修など、ターゲットを絞った研修を実施することもできます。社員の当事者意識を高めるための施策をご検討の際は、ぜひお気軽にアルーまでご相談ください。
社員の当事者意識を高める研修事例
アルーでは、これまでに幅広い企業で社員の当事者意識を高める研修の実施を支援してまいりました。ここではそれらの中から特に参考となる事例を1つ紹介します。
社員の当事者意識を高めるための具体的な研修方法について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
【サービス業】若手社員研修
システム会社のB社では、ジョブ型人事制度の導入に向けて、当事者意識を持ち、主体的に行動できる社員の育成を目指していました。そこで、若手社員を対象として特に主体性を伸ばすことをテーマにした研修を実施しています。
本事例は事前課題と4時間の研修当日、事後課題の3つで実施されています。事前課題では1年間の振り返りを行い、主体性を発揮するうえで重要な自分自身のモチベーションを見つめ直してもらいました。研修では主体性を発揮する方法を扱い、事後課題としてアクションプランの実践を行っています。
受講者からは、「新入社員から2年目になることへの不安もあったが、今後自分がどのような行動をしていく必要があるのか、具体的なイメージをもって考えられる機会となった」、「個人ワークやグループワークが沢山あったことで自身の今までの行動を見直したり、新たな目標を考えることができた」などの声があがりました。今後の目標を立て、業務に対して前向きに考えてもらうことに成功しています。
本事例の詳細は、以下のページからご覧ください。
【研修事例】仕事へのオーナーシップを持ち、ひとりだち意識を得る
▼事例資料ダウンロード
まとめ
いかがでしたでしょうか。
当事者意識を持つことで、自分と組織、両方の成長を実現することができます。
一方で、当事者意識を持ち続けることは、誰にとっても意外と難しいものです。
ぜひ本記事を参考に、当事者意識を高める研修や、当事者意識を持ち続けられるようサポートする取り組みをできることから取り入れてみましょう。