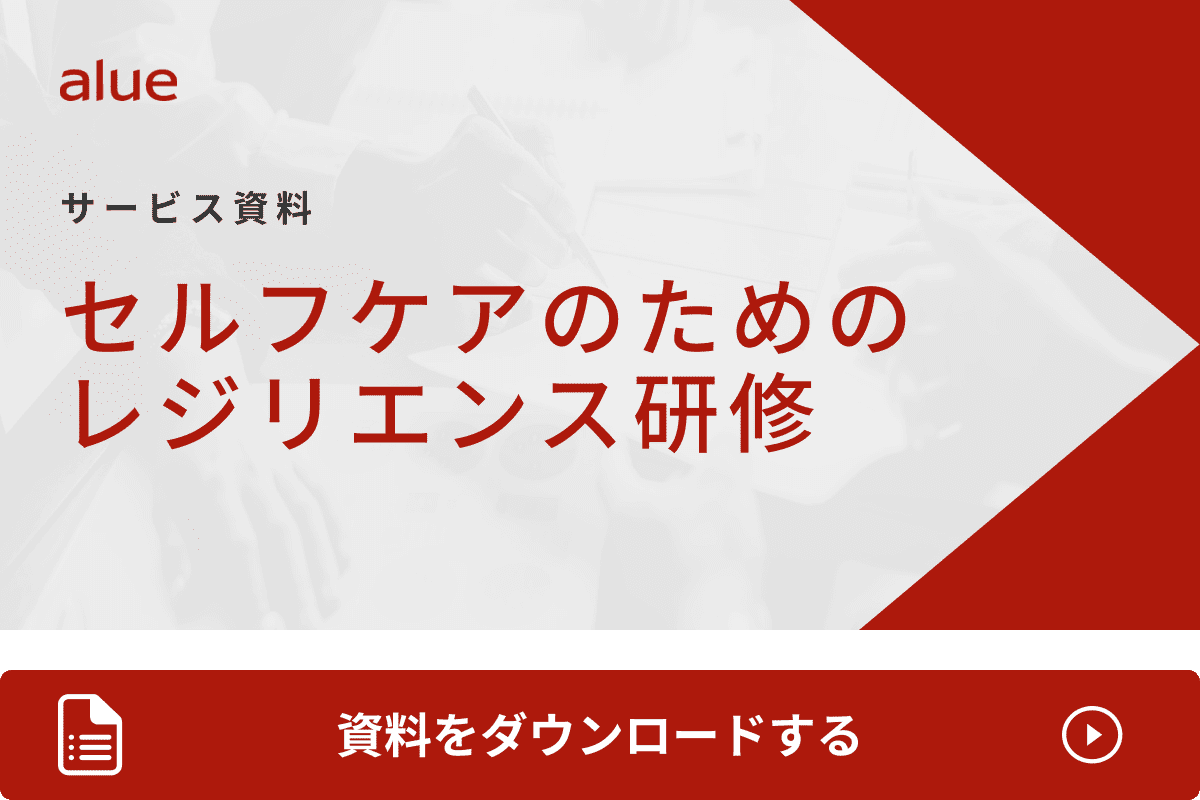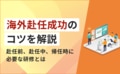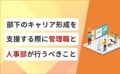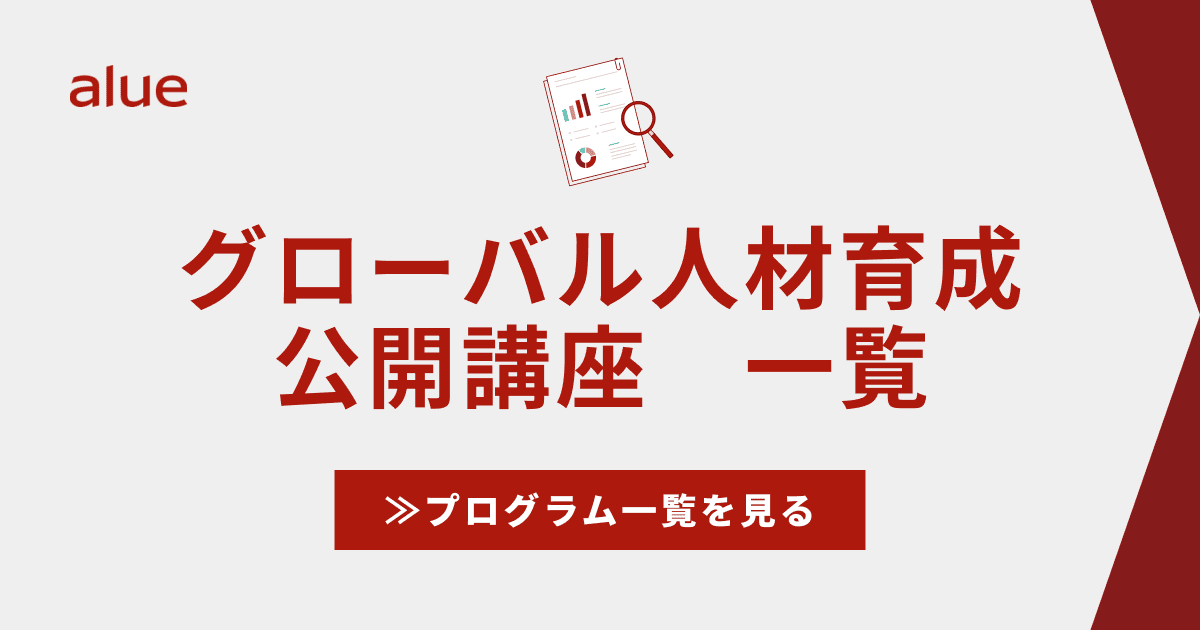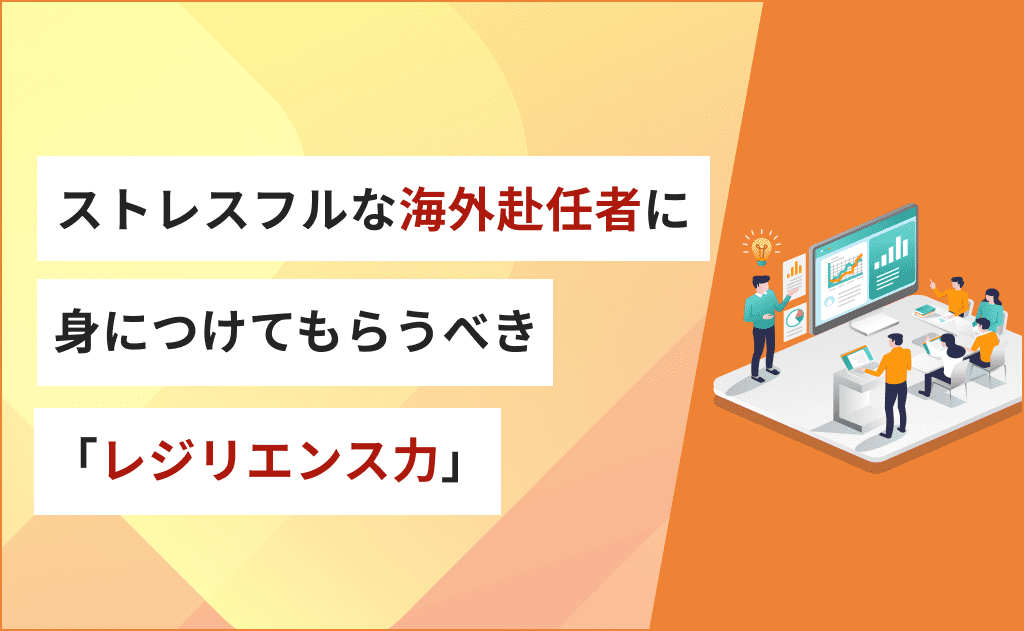
ストレスフルな海外赴任者に身につけてもらうべき「レジリエンス力」
海外赴任は華やかなイメージがある反面、日本と大きく異なる環境での業務にはかなりのストレスと負担が伴うため、赴任者は困難に負けないメンタルを備えておく必要があるのです。この記事では、海外赴任者がストレスに対応するための「レジリエンス力」を身につける方法や、人事から赴任者に対してできるストレス対策などについて解説します。
より深く知るための『オススメ』お役立ち資料
目次[非表示]
駐在員が抱く海外赴任のストレスとは
海外赴任者のストレスは、国内勤務者が抱えるストレスの3倍になるといわれています。日本とは異なる文化や思想の中で、慣れない言語を使いながら同僚とコミュニケーションを取って働くのはストレスが大きいものです。それだけでなく、生活環境が日本と大きくかけ離れていたり、近くに信頼して話ができる人がいなかったりする状況ならば、さらにストレスは重くのしかかってくるでしょう。
駐在員の配偶者への情報やコミュニティを提供するサイト「駐妻cafe」を運営しているグローバルライフデザインでは、過去3年以内に海外駐在員として赴任の経験のある男女131名を対象にアンケートを行いました(2019年3月15日〜4月8日)。その結果を元に、駐在員が抱いている海外赴任のストレスについて解説していきます。
海外赴任前のサポート体制の満足度は低い傾向
海外赴任前から多くの不安を抱える赴任者に対し、企業もさまざまなサポート体制を用意しています。アンケートによれば、企業からのサポートは「引っ越し関連」「渡航先の情報提供」「集合型研修(海外赴任前研修)」などのサポートが多いようです。一方、それに対する赴任者の満足度は低いという結果になりました。
これは、企業側が用意しているサポートの内容や体制が赴任者にとっては不十分だということを示しています。企業側が考えているより海外赴任者のストレスは大きく、日本と海外とのギャップに苦しめられていることがうかがえます。
海外での労働環境におけるストレスとは
海外では、日本と考え方や仕事の方法などが大きく異なるため、ストレスを感じる場面が多くなります。
具体的にストレスを感じる内容としては、「現地スタッフとの人間関係」「時間外労働」「自身のキャリア形成」といったことが挙げられています。
現地の上司と折り合いが悪い、部下とのコミュニケーションがうまくいかないなどの人間関係に悩んだり、日本との時差から生まれる時間外勤務が多い、ローカルスタッフが定時に帰るためその分の業務負担があるなど、日本にいるときより仕事上の負担が大きくなることがストレスになっているようです。
その他にも、海外赴任している日本人同士の人間関係や人事評価などもストレスの理由に挙げられています。
海外赴任のストレスが家族関係にも影響を与えている
海外赴任に家族を帯同している赴任者の約4割が、自身のストレスが家族に何らかの影響を与えていると回答しています。
例えば、海外生活に馴染めず悩む配偶者や子どもに対して、赴任者自身のストレスが多いため、話を聞いて解決策を探すなどの対応をとれずに状況を悪化させてしまうというケースがよくあります。
海外赴任者のストレス対策には「レジリエンス力」が必要
海外赴任者は、このようなストレスフルな環境でも高いパフォーマンスが求められ、結果を出すことを期待されます。そのためには、失敗して落ち込むことや、挑戦へのプレッシャーを克服して成果につなげていく力が必要になります。この力こそ「レジリエンス力」なのです。
レジリエンスとは
レジリエンスとは、ストレスが多い状況に対して、前向きかつしなやかに適応していくことです。これには、自分が対峙している逆境をどのように捉えて対応していくかがポイントになります。
例えば、何か仕事でミスをして落ち込んだとき、レジリエンス力がなければ仕事へのモチベーションは下がり続けてしまいます。
一方で、レジリエンス力が高ければ、落ち込むことで一旦はモチベーションが下がってしまったとしても、状況を冷静に捉え直して次への糧にできるため、モチベーションを再び高めていくことができるのです。
レジリエンス力を高める方法

レジリエンス力は、特別な才能ではありません。誰もが意識し、繰り返し心がけることで高めていけるスキルです。
レジリエンスを高めるには、次のような行程をたどる必要があります。
- 立ち止まる
- 感情を自覚する
- 起こった物事の捉え方を変える
- 成長サイクルを回す
次から、それぞれの項目について詳しく解説していきます。
立ち止まる
ストレスフルなことが起こったとき、つい自分の感情のままに行動したくなりますが、行動する前にまず立ち止まることが大切です。
一旦足を止めることで、動揺を落ち着かせて状況を冷静に見るためのきっかけになります。
感情を自覚する
次に、起こった状況に対して自分がどのような感情を持っているか把握します。例えば、現地社員から理不尽な態度や日本ではあまり見られないような行動を取られて怒りが湧き上がった、上司にミスを厳しく指摘されて自己肯定感が下がり悲しくなったなど、できるだけ客観的に詳しく把握できると良いでしょう。海外では日本では想像つかないような状況を目にすることが多いです。その時に自分はどのような感情を抱いているのか見つめてみてください。
感覚を自覚するのは、ネガティブな感情を把握してコントロールするためです。自分でコントロールできなければ、その感情に支配されて無意識のうちに問題行動をおこしてしまうかもしれません。
また、ネガティブな感情を繰り返し反芻することでさらに落ち込み、パフォーマンスが低下して負のスパイラルに陥ってしまうこともあるのです。
捉え方を変える
人は、出来事の捉え方によって感情や行動が変わります。出来事が起こってすぐに感情や行動が生じるのではなく、出来事を自身の信念や捉え方によって解釈することで感情や行動が生まれるのです。
出来事が起こったときに瞬間的に浮かぶ捉え方のことを、自動思考といいます。この自動思考から、他の捉え方もできるという思考に変えていくことが大切です。
例えば、「上司の返事がそっけない」という出来事が起こった場合、瞬間的に「自分は嫌われているのではないか」と思い浮かぶかもしれません。この考え方が自動思考です。
この自動思考から物事の捉え方を変えられないと悲しい気持ちになり、落ち込んだり、上司に話しかけるのを止めてしまったりという行動をとってしまうでしょう。
この場合に、「上司には何か事情があったのではないか?」という別の捉え方ができれば、上司に同情し、タイミングを変えて話しかけてみよう、という行動に移すことができます。
ネガティブな出来事の捉え方を変えるには、まずは出来事そのものを「ありのままの無色透明な出来事」に近づけていくように捉え直します。具体的には、自分の考えが正しいかを理解するために質問する、自分の考えが思い込みかもしれないと仮定して出来事の原因を特定してみる、などの方法があります。
成長サイクルを回す
ネガティブな出来事を捉え直してモチベーションを回復できたら、自分がどのような状況に対してどんな感情を持つ傾向があるのかを分析することで、成長サイクルを回していきます。
このようにストレスフルな状況を乗り越えていくことで、レジリエンス力は高めていくことができるのです。
海外赴任者のストレスを増加させる10の思考の癖
レジリエンス力を高めるには出来事の捉え直しが大切だということは前述の通りです。実はストレスは、自分の思考の癖による思い込みなどで増加している可能性があります。
ここでは、ストレスを増加させてしまう10の思考の癖を例を挙げながら解説します。
白黒志向
出来事を全て「白」か「黒」かに分けて考える癖が、白黒思考です。例えば、現地社員が挨拶を返してこなかったとき、すぐに自分に悪い感情を持っていると判断してしまうのは白黒思考といえるでしょう。
挨拶を返すのは「白」だけれど、返さないのは理由に関わらず「黒」であるという考えになります。実際には、たまたま現地社員の体調が悪かったなどの「グレー」というどちらでもない状況もあるはずですが、極端な考えで決めつけてしまうのは自分のストレスを増加させる原因になります。
一般化のしすぎ
小さな根拠で過度に一般化をしてしまうことも、ストレスの元となります。
例えば、1人の現地社員の態度が悪かった場合、「いつも○○人は態度が悪い!」「○○人はみんなそうだ」などのように一般化してしまうことが例として挙げられます。
対策としては、矛盾する事実はないか確認することです。「Aさんは態度が悪かったけど、同じ〇〇人のBさんはいつも礼儀正しい」のように、他の例を探すことが大切です。
すべき思考
人間関係にストレスをためやすい人によくあるのが、この「すべき思考」です。「業務報告は欠かさずするべき」「挨拶すべき」など、自分のルールを他人にも求めてしまうと、考え方が異なる海外では特にコミュニケーションが難しくなります。
感情的決めつけ
「感情的決めつけ」は、物事の真偽や価値判断の基準を自分の気分の良いか悪いかにしてしまうことを指します。
例えば、「自分がイライラする相手を無価値と決め付ける」「自分は海外赴任生活が辛いのに、海外赴任は面白いと言っていた上司は嘘をついていたに違いない」という考え方をしてしまう思考です。
対策としては、事実を冷静に確認することです。「失礼な態度を取られたけれど、文化の違いがあるのかもしれない」「自分の話をイライラしながら聞いていたように見えたけれど、彼は今業務が忙しくてそれでイライラしていたのかもしれない」と、冷静になることが大切です。
自己関連付け
自分の行動が相手の行動を引き起こした、と考えるのが自己関連付けです。例えば、上司にいつもどおり声をかけてもそっけない態度や無視されたように感じるのは、自分のタスク処理が遅れているからだと理由付ける場合は、過剰に自己関連付けしているといえます。
上司はそのときたまたま考え事をしていた、あるいはプライベートで心配事があったかもしれません。全ての反応を自分のせいだと考えるのはナンセンスなことです。
拡大解釈と過小評価
拡大解釈は「相手の成功・能力を大きく見積もること」、過小評価は「相手の失敗・悩みを小さく見積もること」を指します。
例えば、
- SNSで充実した生活の様子を投稿している同期を見て、「〇〇は仕事もプライベートも全部うまくいっていてうらやましい」と妬んでしまう。
- 後輩から悩み相談されたとき、「そんな小さいことで悩んでいるの?」とはねつけてしまう。
といったような思考方法です。
対策としては、他者のポジティブに見える面もネガティブに見える面も、一部分が見えているに過ぎないことに気づくことが重要です。
レッテル張り
他人や自分がミスした時に、レッテルを張って決めつけてしまうことも、ストレスをためてしまう思い込みの癖です。
例えば、
- 一度ミスをしただけで、自分は馬鹿だと感じる
- ナショナルスタッフが突然退職したことで、彼のことを根性なしだと思う
などのような思い込みです。
対策として、原因をリストアップすることが挙げられます。
「ミスをした」→「馬鹿だから」という決めつけではなく、
- やり方が分からなかった
- 質問できる人が近くにいなかった
- 相手の説明が不足していた
など、いくつか原因を挙げて思い込みを脱します。
心のフィルター(選択的抽出)
心のフィルター(選択的抽出)とは、自分がこうだと思い込んでる情報ばかり集めて、他に矛盾する情報があっても見ない、無視してしまう癖のことを指します。
例えば、自分には企画力がないと思い込んでいると、企画を評価してくれた多数の声があってもそれを無視してしまったり、ちょっとした批判をより重く受け止めてしまったりしてしまいます。
対策としては、研修などで相手や自分の長所や、肯定できる経験を探すことが必要です。
マイナス化思考
マイナス化思考とは、特にネガティブなことでなくとも、ある事実をマイナスの方向に解釈してしまう思考のことを指します。
マイナス化思考があると、例えば、
- 「TOEICで900点をとった」という事実に対して、900点取れてよかったとは考えず、なぜ満点が取れないのか?とマイナスに考えてしまう
- スタッフが会社を辞めて独立すると聞いた時に、「〇〇さんはこういう良いとことがあるからきっとうまくいくよ」というプラスの思考や言葉が出ず、「きっと失敗するよ」とマイナスの思考・言葉をかけてしまう
というような行動を取りがちです。
対策としては、1回マイナス思考をしてしまったなと思ったら2回プラス思考をしてみるなど、意識的に考え方の癖を直していくことが大切です。
結論への飛躍(心の読みすぎ)
結論への飛躍(心の読みすぎ)は、表情、声、行動から過剰に相手の心意を読み取ろうとして、疲れてしまうことを指します。
結論への飛躍がある場合、例えば、
- 上司がそっけない態度のように見え、「自分は上司に嫌われているのではないか」と感じてつらくなってしまう
- ナショナルスタッフへLINEで連絡をして、既読がついているのに返信がない時に、「自分は嫌われているんだ」と感じてしまう
というような思考になってしまいがちです。
対策としては、そもそも人は自分が思っているほど自分のことに注目していないことに気づくことが大切です。
例でいうと、上司は何気なくいつもよりそっけない態度をとっているだけで、「嫌いだから冷たくしてやろう」と思ってしている可能性は低いことに気づいたり、ナショナルスタッフ側は既読をつけたことが「読んだ」という意思表示だと思っているのだと気付いたりすることが対策として挙げられます。
人事ができる海外赴任者のストレス対策

海外赴任者に高いパフォーマンスを発揮し成果を出してもらうには、人事部のサポートも欠かせません。日本とは違う環境で労働し、さまざまなストレスを抱える赴任者への対策を丁寧に行うことによって、海外拠点の運営はスムーズにすすみます。
ここでは、人事ができる海外赴任者へのストレス対策について説明していきます。
【前提】海外赴任をする人材の選定をしっかりとする
経済のグローバル化に伴って海外拠点をもつ企業が多い中、海外赴任を希望する人も少なくありません。
しかし、ストレス対策の前提として、心身ともに海外赴任に適した人材を選定することは最も重要です。語学力の有無や日本での功績だけでなく、コミュニケーション力の高さや柔軟な視点など希望者の内面までしっかり考慮して選定する必要があります。
国や地域によっては、強い個性や不屈のメンタルを持っていなければやっていけない場所もあります。そのような場所で働くにあたって、心身の健康のバランスが大切になるため、国内以上に適材適所を考えなければなりません。
また、候補者の条件だけでなく赴任先の上司との相性も合わせて考えておく必要があります。
海外赴任をする人材に対する育成方法については、以下の記事を参考にしてください。
『海外で働く「駐在員(海外派遣社員)」。その育成方法と注意点とは?』
赴任前から準備をしておく
赴任の半年以上前から、現地の情報提供や何かあったときの相談窓口の用意など周到な準備をしておくことが重要です。
現地の情報には国についての基本的な情報だけでなく、海外拠点に勤務しているスタッフの人数や勤務状況など労働環境についての詳細も含まれます。あらかじめ現地について詳しく把握しておけば、対応策をシミュレーションしておくなどの用意ができるため、精神的な安心とゆとりにつながります。
赴任前を含め、海外赴任者に必要なサポートをまとめた資料は、以下からご確認いただけます。
早い段階でストレスの対処をする
現地の管理監督者と協力して、赴任者の様子に少しでも変化があれば早い段階で本人と面談を行いましょう。
最初は本人だけでなく周囲も大したことがないと感じるかもしれません。しかし、ストレスをずっとため続けていくと、うつ病など、心身の調子を崩してしまう可能性があります。対処が早ければ早いほど、早い段階で回復が見込めるため、ささいなサインも見逃さないことが大切です。
ストレスを発散できる時間を作る
海外赴任者は、赴任してすぐは引っ越しなどで忙しく、また業務に早く慣れなければという思いで休みを設けず働いてしまう傾向があります。
しかし、赴任してすぐは現地に慣れることを最優先としてもらい、現地の上司とも連携をとってできるだけゆとりのある勤務体系にするように促しましょう。
適度に休みを与えてストレスを発散できる時間を作れば、慣れてきた頃に燃え尽き症候群のように急にやる気を失ってしまうという状況への対策になります。
ストレス要因を整理できるようにしておく
海外で生活しながら業務を行う上で、ストレス要因は数多く存在します。人間関係や食文化などすぐに特定できる要因もあれば、治安や自然環境など意識しなければ気付かないストレス要因もあるでしょう。
赴任者自身がストレス要因になることを整理して把握しておけば、それぞれに人事からも対策を立て解決につなげることができます。
コミュニケーションの場を用意する
赴任者と同じような状況にある人や現地の人々との出会いをサポートするために、積極的にコミュニケーションの場を用意しましょう。
親族や友人など、日本にいる親しい人にすぐ会えない赴任者は孤立感を深めがちです。駐在生活の悩みや喜びを共有できるような支援者を持つのは大切なことです。
海外赴任に合わせた目標設定を行う
海外赴任に向けて、赴任前から適切な目標設定を行うことも重要です。
通常ならば適切な目標設定も、海外赴任することを考慮するとやや設定を下げて達成しやすい目標にしておくべきでしょう。
アルーの駐在員・海外派遣社員育成サービス
海外赴任者の業務上のストレスは、赴任前の研修から現地で想定される場面をよくシミュレーションしておくことや、異文化対応についての知識を深めておくなど入念な準備で軽減できます。
アルーでは、駐在員・海外派遣社員育成に有効な研修をご提供しています。
アルーの研修では、今回ご紹介した海外赴任者のストレス対策やストレスを貯めやすい考え方の癖に対する対処法を解決いたします。
貴社の海外赴任の状況に合わせて内容もカスタマイズも可能です。詳しくは、以下のページをご参考ください。
駐在員・海外派遣社員育成サービス