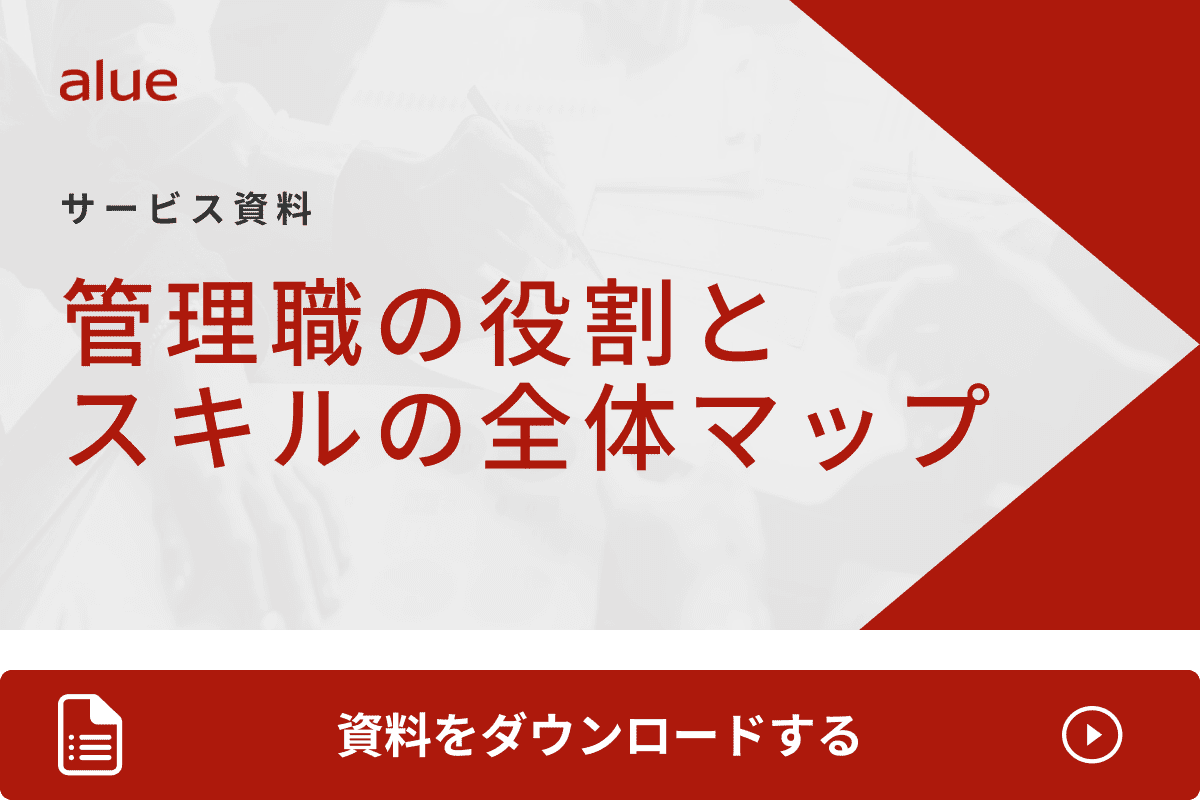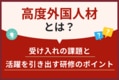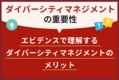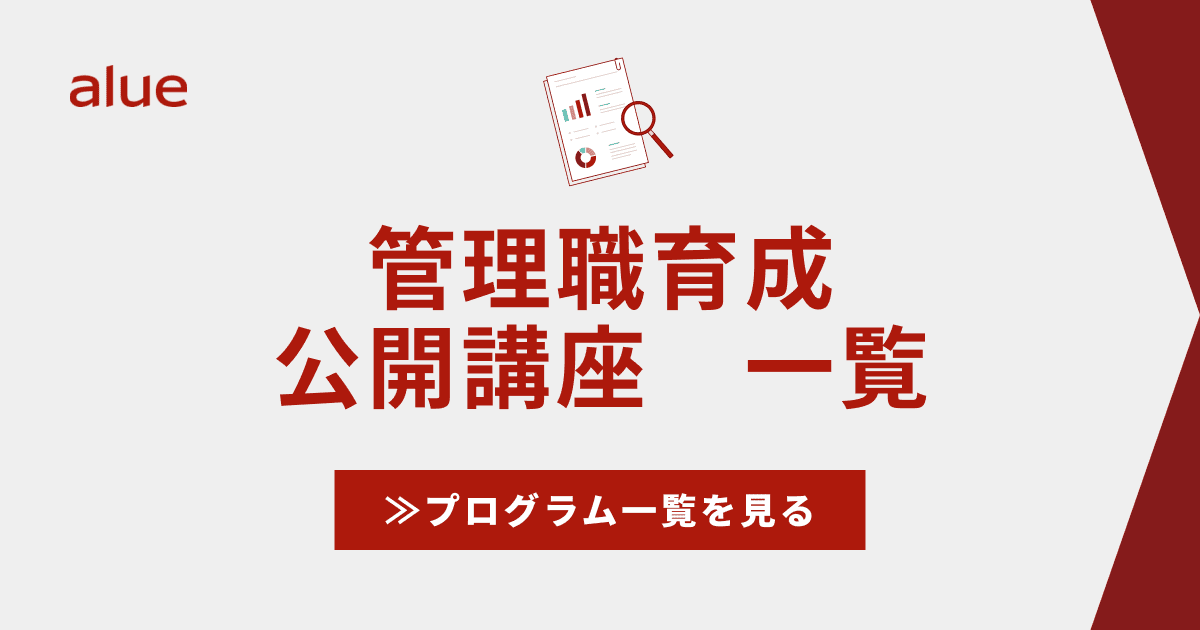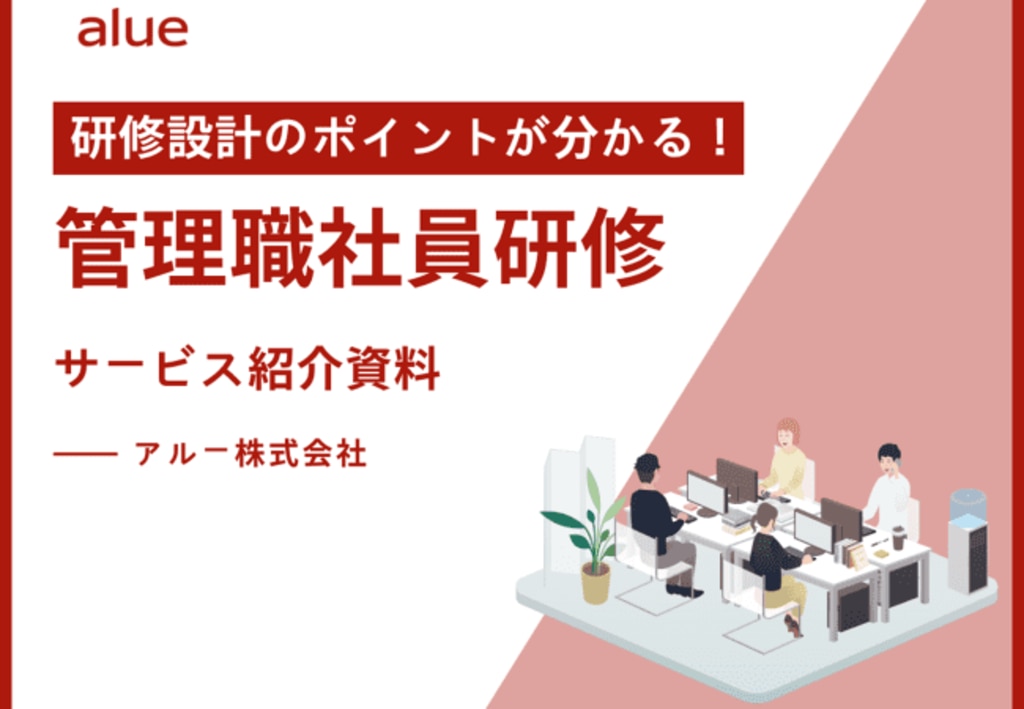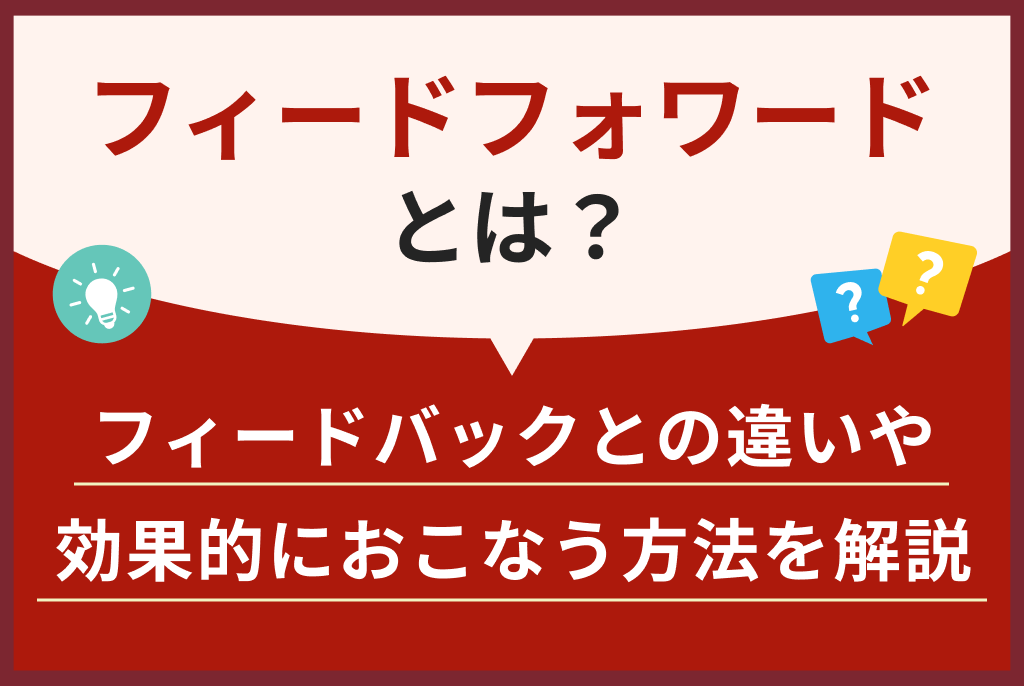
フィードフォワードとは?フィードバックとの違いや効果的におこなう方法を解説
「内向きの意見ばかりで顧客視点のアイデアが出てこない」
「若手が育たず、期待どおりに活躍してくれない」
「会議の場で積極的な意見交換ができない」
こんな状況を改善したいと頭を悩ませている人事・教育担当者も多いのではないでしょうか。
そのようなとき、思考を変え、より良い未来を目指そうとする人材を育成するために、「フィードフォワード」の考え方を取り入れることがおすすめです。フィードフォワードの考え方を身につけることで、若手はもちろん、中堅~管理職の人材の思考が変わり、働くモチベーションの高い組織をつくることができます。
本記事では、フィードフォワードの考え方や目的、メリット、実施方法などを詳しく解説し、最後にフィードフォワードの考え方が身につく研修事例をご紹介します。

目次[非表示]
フィードフォワードとは? 〜未来思考で組織のパフォーマンスを高める〜
フィードフォワードとは、「未来を思い描いたアドバイス」をおこなうことで、「どうやって問題を解決するか」に焦点を当て、過去や現在ではなく未来をみせるアプローチです。
一般社団法人フィードフォワード協会によると、その定義は「過去や現状にとらわれてしまいがちな人に対して、その人が自分の未来に意識を向けて行動することができるように促す技術のこと」とされています。
(参照:一般社団法人フィードフォワード協会「フィードフォワードの定義」 )
フィードフォワードの考え方を身につけることで、メンバーの将来に目を向けた改善点と、目標を達成するためのアイデアを話し合うことができるようになります。
後述しますが、一般的にビジネスの世界では「フィードバック」がおこなわれています。しかし、実際のビジネス現場では、フィードバックのやり方をしっかりと学んだことがない上司も多くいます。特にネガティブフィードバックは難しく、やり方を学んでいないと、やみくもに目に付きやすい欠点や不足点ばかりを伝えたり、成長に向けたフィードバックではなく、過去への指摘ばかりになることも多々あります。そうすると、フィードバックが部下の成長やパフォーマンス向上につながりません。
そんなときにおすすめなのが、未来をイメージさせることに焦点を当てた「フィードフォワード」の考え方です。
フィードフォワードをおこなう目的とは
フィードフォワードをおこなう最大の目的は、人材育成です。フィードフォワードをおこなうことによって、前向きで自発的な社員の育成につながり、パフォーマンスの高い組織づくりにつながることが期待できます。
その背景には、テクノロジーの進歩により事業にスピードが求められるようになったことや、顧客ニーズの多様化により組織の思考に柔軟性が求められるようになったことが挙げられます。また、前述のとおり、上司が正しいフィードバックの方法を学んでいないことが原因で、特にネガティブフィードバックのスキルが不足し、ハラスメントと受け取られてしまうケースもあります。そのような場合には、最悪離職につながることもあります。
フィードフォワードの考え方を身につけ、組織を活性化し、事業を加速、または変革している企業が今、増えています。
フィードフォワードとフィードバックとの違い
先ほどから出ているように、ビジネスの世界ではフィードバックという考え方が広く普及しています。このフィードバックと比較することで、フィードフォワードの考え方を深く理解することができますので、ここからはフィードフォワードとフィードバックの違いについてご紹介します。
フィードバックの目的は、メンバーの実際の言動に対して評価や改善点を伝えて、パフォーマンスを高めて能力開発につなげることです。そのために、フィードバックでは「あなたの行動は周囲に伝わっています or いません」といった視点から、本人に「気づき」を与え、行動を変えることを促します。そして、フィードフォワードとフィードバックの主な違いとして、次の3つが挙げられます。

違い①視点の時間軸が未来か過去か
フィードフォワードは未来の予測をもとに行動をうながします。一方で、フィードバックは過去を振り返って行動を変えていきます。
言い換えると、フィードフォワードでは未来の目標に対し、どのような行動をして、どのような自己成長をすれば達成できるかについて逆算して考え、具体的なステップにつなげます。
それに対し、フィードバックでは、起こった結果をもと過去の行動を振り返り、どう改善すべきかを考え、次の行動につなげるのです。
違い②主に強みをみるか弱みをみるか
フィードフォワードは、前向きな考えを尊重しますので、主に“強み”に注目して問題解決への手段を考えます。一方でフィードバックは、“弱み”を改善するという思考で指摘する場合も多くあります。
ここだけ切り取ると、フィードフォワードが良くてフィードバックが悪いという印象があるかもしれませんが、そういうわけでは決してありません。目的や組織・メンバーの特徴を踏まえて、今どちらがより必要か考えることが重要です。
違い③能動的な姿勢か受け身な姿勢か
フィードフォワードは未来から逆算して、理想の未来に近づけるための具体的な解決策を考えますので、能動的な姿勢につながりやすいといえます。一方でフィードバックは、自分から求められる人もいますが、他の人に指摘してもらうことを待つ人が多く、受け身な姿勢といえます。
フィードフォワードの2つのメリット
フィードフォワードの考え方を取り入れると、次のような効果が期待できます。
個人の成長につながりやすい
フィードフォワードの考え方でメンバーと接すると、単なる「指摘」ではなく、「成長へのアドバイス」となりやすく、個人の成長が加速します。また、フィードフォワードの考え方が根付いている組織では、役職関係なく活発な意見交換が起こります。メンバー間でのコミュニケーションが活発になれば、組織で成果を上げやすくなり、個人の成長が組織の発展にもつながります。
社員が定着しやすい
間違ったやり方で、ネガティブなフィードバックばかりがおこなわれていると、いつも「上司からのダメ出し」されていると感じるようになり、モチベーションが低下していきます。特に最近の新入社員は、自分が認めている人からの意見しか聞こうとしない傾向もあり、尊敬できない上司からのフィードバックをハラスメントと受けとる人もいます。そうすると自然と離職が増え、定着して活躍してくれる社員が減っていきます。
一方で、より良い未来を想像しやすいフィードフォワードでのコミュニケーションは批判的になりにくく、自己肯定感を高めることから受け入れられやすいものとなります。上司と部下間でも率直な意見交流がしやすくなり、成長の加速やモチベーションの向上も期待できます。結果、個人の自律にもつながることが期待されます。
フィードフォワードの3つのステップ
フィードフォワードを実践する際には、どのようなステップを踏むといいのでしょうか。ここでは3つのステップに分けて、フィードフォワードの具体的なやり方をご紹介します。
ステップ1 相手の許可を得る
相手に心構えがないのに、いきなり解決策や改善案を提案したり、指摘しても受け入れられることはありません。そこで、フィードフォワードをおこなう前には「今後の仕事の進め方について話したいんだけど、時間いいかな?」などと相手の許可を得る必要があります。いきなり本題に入らずワンクッション置くことで、相手に話を聞く姿勢をつくってもらうことができます。会議などで意見交換をするときも同様です。「将来目指す姿を達成するためにどんな解決策があるか考えたい」などとフィードフォワードの考え方で意見がほしいことをしっかりと伝えることが重要です。
ステップ2 事実を具体的に伝える
目指す将来像から解決策を考えるためには、正確な現状把握が必要不可欠です。そのために、可能な限り主観は取り除き、事実を具体的に把握しなくてはいけません。主観的な事実を客観的な事実かのように伝えてしまうと、相手が受け入れてくれなくなります。
主観的な事実を伝えるときには、「私にはこう見えた」「私はこう思っている」などと、“I(アイ)メッセージ”で明確に伝えることが大切です。客観的で具体的な事実があることで、意見も同様に具体的になり、それが前向きな解決策について意見を出し合うことにつながります。
ステップ3 未来から逆算した行動と結果に注目する
ステップ2までで現状と目標とのギャップが共有できます。そこでステップ3では「これからどうするか」の視点で、実行する行動を考えていきます。
実現させることを前提として
「目標を達成するためには現状をどう変えたらいいか」
「具体的にどんな解決策が考えられるか」
を深掘りしていき、行動を明確にしていきます。
その際に重要なことは以下の2つです。
- 質問をして相手に答えてもらうよう進めること
- 否定せず問題解決に向けてどうするかを考えてもらうこと
現状は必ず変えることができ、問題も必ず解決することが可能です。そのための解決策を自分の意見として発言することで、主体的な姿勢が生まれ、自律につながります。そしてそれは、強い組織をつくることにつながっていきます。
フィードフォワードができる人材育成ならアルーにお任せください
フィードフォワードができる人材育成ならアルーへご相談ください。人材育成を手掛けているアルーでは、フィードフォワードスキルを向上させるための施策を数多くご用意しています。それぞれの企業のニーズに合わせて、内容を柔軟にカスタマイズすることも可能です。
ここからは、アルーの提供しているフィードフォワードスキル向上施策の一例を紹介します。
フィードフォワードの考え方が身につく研修事例紹介
ここからは、弊社で実際に実施したフィードフォワードの考え方が身につく研修事例をご紹介します。内向きな視点しかもてず、顧客課題に前向きに向き合うことができなくなっている管理職層を対象に実施した2日間の研修です。
ソリューション・フォーカスト・アプローチという、心理療法の考え方を活用し、本人がすでに持ち合わせている能力や資質といったリソースに焦点を当て、より良い未来を目指せるようなスタンスを醸成することを目指した研修です。
▼テーマ
ソリューション・フォーカスト・アプローチ
▼ねらい
・解決志向でお客様の課題と向き合うマインドを醸成する
・最短距離で問題解決するために必要な手法を獲得する
▼内容
① オリエンテーション
研修のねらいと進め方を説明し、自己紹介をします。また、ワークの多い研修を円滑に進めるために、アイスブレイクをおこない、発言しやすい場をつくります。
② 対話ワーク1~3
研修1日目は、ワークを繰り返し、自分や自社のリソースに目を向け、より良い未来が考えられるうにしていきます。最初に、自分の考えを正直にぶっちゃけるワークをおこない、本音を話せる場をつくります。次に、自分の“志”や目指したいことをスケーリングし、未来に目を向けていきます。さらに、事前課題も活用し、自分の強みや、自社や自部署のリソースの良いところを確認し、多様な個性を見える化していきます。自社や自部署のリソースを、“前進のための資源”として考えることがポイントです。最後に、問題が解決した後の理想的な未来の具体的イメージを描き、鮮明にしていくことによって、理想の未来を手に入れるためのスモールアクションを具体化します。
③ ソリューション・フォーカスト・アプローチの基礎理論
ソリューション・フォーカスト・アプローチが、管理職にとって役立つ理由を説明し、解決志向で問題やメンバーに関わることの必要性とその手法を学びます。
④ ソリューション・フォーカスト・アプローチのコミュニケーション
具体的にどのようにメンバーとのコミュニケーションを改善していくか学び、ワークを通じて現場での実践イメージをもちます。
⑤ 多様性の活用と未来日記
組織にいる多様なメンバーを活かして、描いた未来に向けて進んでいくイメージを固めるワークをおこないます。また、未来日記をつくることで、自分の“志”が実現した様子を具体的にイメージし、現場での実践につなげます。研修後は事後課題を通じてスモールアクションが続けられているか確認し、行動の定着をねらいます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
フィードフォワードの考え方が広がることで、人材を前向きに育成することができ、組織のパフォーマンスを上げることにつながります。ぜひフィードフォワードの考え方を取り入れ、前向きで行動力のある組織づくりを目指してください。