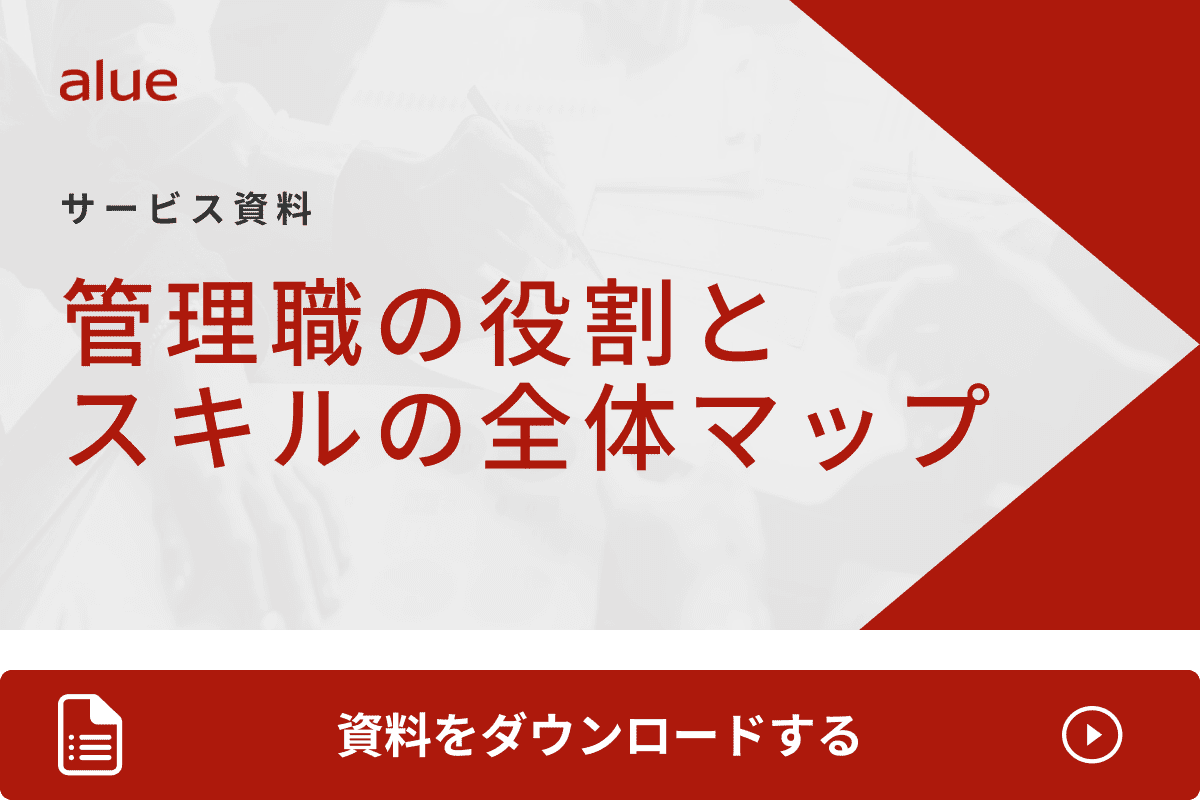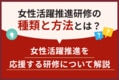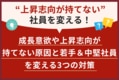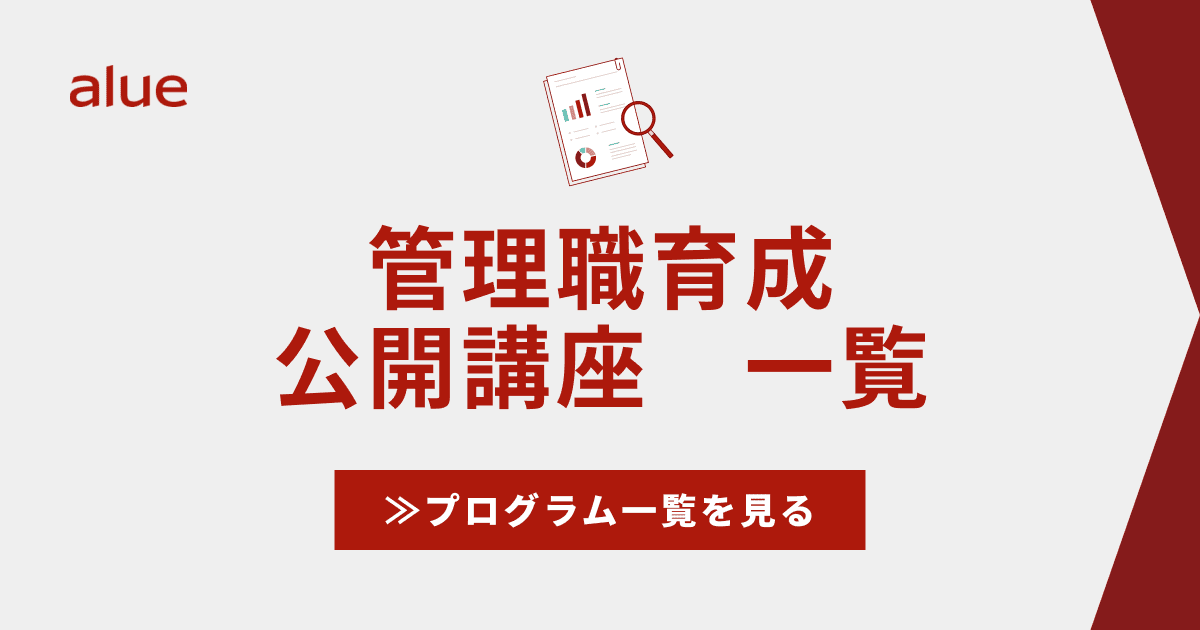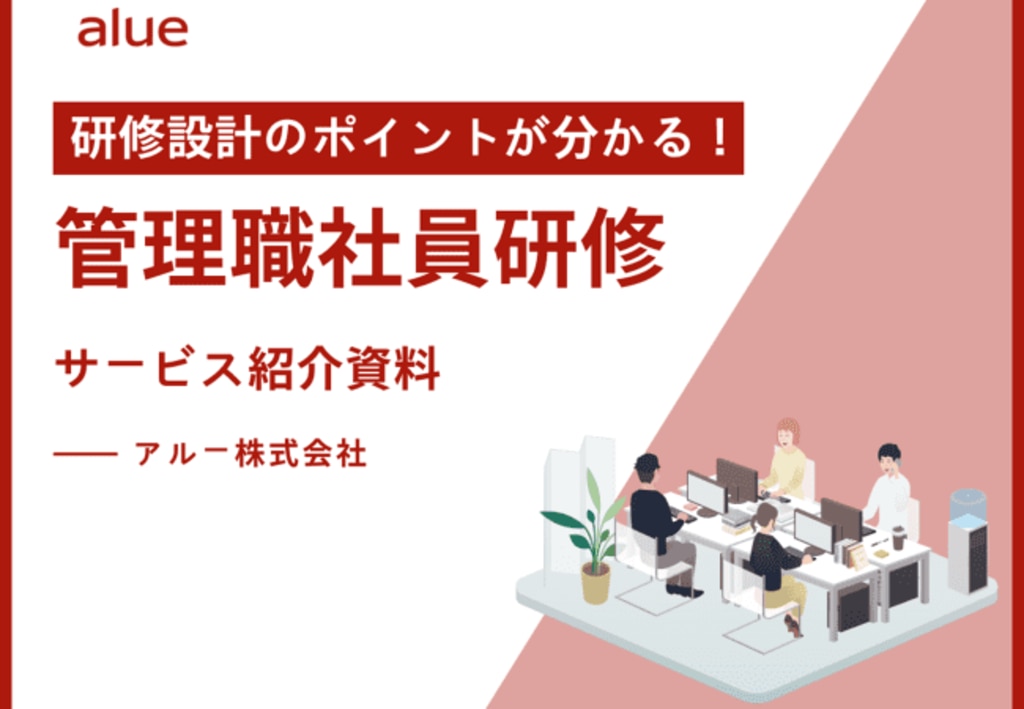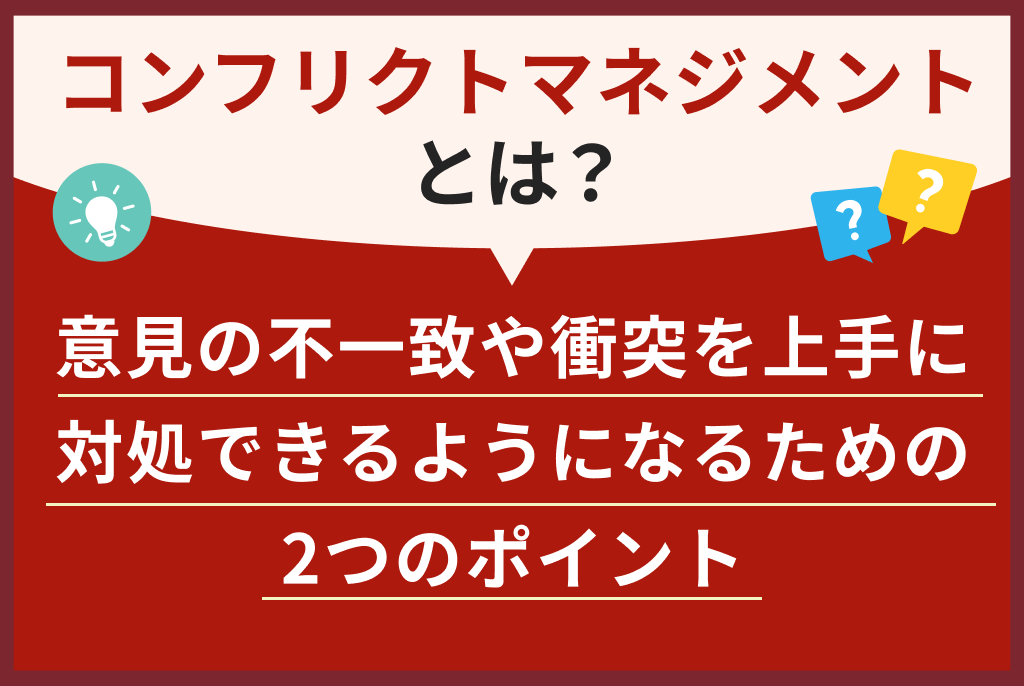
コンフリクトマネジメントとは?意見の不一致や衝突を上手に対処できるようになるための2つのポイント
ダイバーシティ&インクルージョン推進が進み、組織に多様化な人材が所属する企業が当たり前になっています。そんな中、コンフリクトマネジメントに苦手意識を持つリーダー層や管理職が増えています。制度を整備し多様な働き方を認め、実際に多様なメンバーがいる組織にしたのに、逆にコミュニケーションがよそよそしくなり、生産性が下がってしまった、というのは本当によく聞く悩みです。
性別や国籍のように分かりやすい多様性はもちろん、高圧的な上司、ひたすら突っ走るCEO、不機嫌な部下、文句ばかりいう同僚、出世して上司になった元同僚など、様々なメンバーが組織の中にはいます。
ですので、「和をもって尊し」や「空気を読む」ことが得意な日本人にとっては面倒なことに感じるかもしれませんが、多様な組織の中でコンフリクト(対立や軋轢)が発生するは当たり前です。そのコンフリクトを放置してしまうと、業務が滞ってしまったり、職場に緊迫感をもたらすなど、悪い影響が出てしまいます。
一方でコンフリクトによって、競い合うことで意欲が高まったり、活発な意見交換で新たなアイディアが出るなどの良い影響も期待されています。
本記事では、コンフリクトがなぜ発生するのか、コンフリクトに上手に対処できるようになるための2つのポイントを解説します。
より深く知るための『オススメ』お役立ち資料

目次[非表示]
コンフリクトマネジメントとは
コンフリクトは対立や軋轢などを意味しています。相手と自分の利益、主張、信念、感情、価値観、アイディアなどが衝突している状態です。相手との相違点が明らかになり、コンフリクトが発生すると不安や葛藤が生じ、たとえば相手との対立を恐れて避けようとします。
コンフリクトマネジメントとは、このように組織運営においてネガティブに捉えられがちな状況を、組織の活性化や成長の機会と捉え、積極的に受け入れて問題解決を図ろうとする考え方のことをいいます。
コンフリクトは日常の中で自然に起こるもので、悪いことではありません。ただ、コンフリクトが起きた時に、高圧的な態度に出たり、避けたりするなど、対応は人それぞれです。
コンフリクトマネジメントの原理やスキルを習得することで、コンフリクトにうまく対応でき、結果としてメンバーとの絆を深め、組織の生産性を上げることができるようになります。
コンフリクトが発生するのはなぜか
コンフリクトは日常的に発生します。
その要因は多岐にわたりますが、大きく3つに分けることができます。
条件の対立
組織での立場や仕事内容によって、仕事に対しての目標や条件は異なります。
「会社の経営陣の頭が固くて投資をしてくれず、デジタル化が進まない」「あの部下は自分の言うことを聞いてくれないし、強く言うとパワハラと言われそうでどう接していいか分からない」など、上司と部下の権力差や視点の違いによる意見の対立はよく起こります。
他にも組織の横同士の関係では、たとえば営業部門と技術部門との対立などは容易に想像できると思います。
認知の対立
人によって考え方や価値観は様々です。同じ仕事をしていても、同じ話を聞いていても人によって解釈は異なり、対立が発生します。利益を重視する人とホスピタリティを重視する人では、同じ仕事をしていても出す答えは違います。
また、たとえば外国籍人材を採用した時に、「当たり前の報・連・相ができないなんて信じられない」「会議で自分の意見をはっきりと主張されてやりづらい」のように、価値観の違いによるコンフリクトが起こる例もよく聞く話です。
感情の対立
条件の対立や認知の対立が継続すると、感情の対立が発生します。「あの人とは一緒に仕事をしたくない」「一緒にいると気分が悪くなる」のような感情が生じると、解決するのが難しくなってしまいます。
人は感情で判断します。感情のコンフリクトは良く起こりますので、修復不能になるまで発展させないようにすることが重要です。
コンフリクトに対応する5つの技術

コンフリクトに対する反応は、トーマスキルマンモデルに従い、
以下の5つに分けることが一般的です。
競争
相手側を強制的にコントロールしようと、自分の立場や権力を振りかざし、自分の意見を強制するアプローチです。時として管理職が取りがちなアプローチですし、全てを否定することはできませんが、この状態が続くと、部下への監視や規制を強めることにつながり、自分が孤立してしまいます。
服従
強制とは反対のアプローチで、相手のいいなりになります。自分の意見よりも他人の意見を優先しますので、一見コンフリクトが解決したように見えますが、実際には服従した側が強い反発を抱いていることがほとんどです。この状態が長く続くと感情の対立が生まれ、コンフリクトが強くなって解決することが難しい関係になってしまいます。
妥協
コンフリクトに関連する目的を共有し、それぞれの利害を考慮したうえで、両者が納得できる落としどころを探します。日本人の好むアプローチです。しかし、妥協は相手の意見を優先しつつ、お互いに譲り合う行為です。両社が損を引き受けるかたちになるため、不満が残ってしまいます。
回避
対立を避けることで、解決を先送りにするアプローチです。子どもが親と喧嘩して部屋に閉じこもる時のように、単純に時間を空けることも感情を落ち着かせるためには意外と有効です。前向きとはいえないですが、必要な場面はあります。また、ビジネスでは1つの主張だけに縛られず、代替案を用意することで、相手との対立を避けるアプローチを取ることがあります。
協調
双方の意見や利益を尊重し、お互いにとって利益がある解決を目指すアプローチです。5つのアプローチのうち、最も望ましい手段といえます。コンフリクトマネジメントが目指すのもこの方向です。寛容な心で、問題解決のために関係者それぞれが持つリソースを交換してアイディアを創出し、前向きな議論ができるようになります。また、チーム内の相互理解も深まり、人間関係も強固になることが期待されます。
協調のアプローチをするための2つのポイント
コンフリクトが発生した時には、
- コンフリクトによって生じた感情をケアしたいというニーズ
- コンフリクトの原因を解決したいというロジカルなニーズ
の2種類のニーズが発生します。コンフリクトを上手にマネジメントし、協調のアプローチにしていくためには、この2つのニーズを満たすことが必要です。
感情のニーズを満たすことで、人は、相手の言うことを受け入れる準備ができます。自分の言い分を話す前に必ず相手の感情に耳を傾け同調することで、コンフリクトの強度を下げられます。また、情報をできる限りオープンにできる関係性を築くことで、マネジメントがしやすくなります。
そして、相手が自分のことを話してくれ、こちら側の言うことに耳を傾ける準備が整ったら、ロジカルに問題を解決していく努力をします。その時は、特にお互いの目的を明確にすることが重要です。コンフリクトには、それに関連する客観的な目的があります。この目的を共有できればできるほど、話し合いがスムーズになりますし、お互いの合意に達する可能性が高まります。
たとえば、労働生産性を高めて利益を上げることを確保したい経営者と、労災事故や離職率を減らすために働き方改革を推進したい人事の間で意見が対立しているとしても、基本的には残業時間を減らし従業員の健康を守りたいという目的は共通しています。まったく相容れない場合もありますが、コンフリクトが競合的になればなるほど、当事者はより強引に、支配的な態度を示す傾向があり、どんどんコンフリクトが拡大していく悪循環にはまってしまいます。
2つのニーズを意識することでコンフリクトが起きた時に協調のアプローチになりやすく、対立する当事者同士が本音を率直にぶつけあい、相互理解を深め、風通しのいい職場の雰囲気を醸成したり、議論の幅を広げ意思決定の質を高めたりするきっかけになります。
コンフリクトマネジメントに対処できる人材育成ならアルーにお任せください
コンフリクトマネジメントに対処できる人材育成ならアルーへご相談ください。人材育成を手掛けているアルーでは、コンフリクトマネジメントスキルを向上させるための施策を数多くご用意しています。それぞれの企業のニーズに合わせて、内容を柔軟にカスタマイズすることも可能です。
ここからは、アルーの提供しているコンフリクトマネジメントスキル向上施策の一例を紹介します。
コンフリクトマネジメント研修事例紹介
コンフリクトマネジメントを身に付けることのメリットには、
- 不満を出しやすくなり、職場の風通しが良くなる
- 相互理解が促され、チームの結束力があがる
- 「違うこと」に寛容になり、新しいアイディアが生まれやすくなる
- 多様な意見が出ることにより意思決定の質を高められる
- 自分の意見を主張できることで帰属意識が高まり離職が減る
などが挙げられます。
このようにコンフリクトマネジメント研修は、普段ネガティブに捉えられがちな「対立」の状況をポジティブに捉え直し、マネジメントするためのテクニックを学ぶことで、多様なメンバーの「価値観」を見える化し、チームメンバーとの相互理解につなげることができます。
ここからは、弊社で実際に実施したコンフリクトマネジメント研修のカリキュラムをご紹介します。
▼テーマ
コンフリクトマネジメント研修
▼ねらい
メンバー間の意見の不一致、衝突を意味するコンフリクトの結果を、生産性の低下や人間関係の悪化ではなく、より良いビジネスの結果に繋げられるようにマネジメントするスキルを習得する
▼学びのポイント
・コンフリクトをポジティブに捉え直す
・コンフリクトへの対処方法と自分の傾向を認識する
・信頼関係構築と傾聴、解決に向けた話し合いの方法を習得する
▼内容
①コンフリクトについて
コンフリクトについて、原因やネガティブな影響、ポジティブな影響について学び、コンフリクトにはポジティブに捉えられる面もあることを理解してもらい、マインドを変えます。また、ダイバーシティ&インクルージョンが進むなど、コンフリクトが起きやすい状況であることや、放置した時のリスクについて考え、コンフリクトマネジメント習得の重要性を知ります。
②コンフリクトマネジメント~対処方法~
コンフリクトが起きた時の対処方法の種類と、サーベイから自分の行動傾向を知ることで、フィードバックを通じてその人に合ったコンフリクトマネジメントができるようにします。
③コンフリクトマネジメント~2つのニーズ~
本文でご紹介した、
- コンフリクトによって生じた感情をケアしたいというニーズ
- コンフリクトの原因を解決したいというロジカルなニーズ
について学び、ニーズに応えるためのスキルとして、傾聴、ラポール形成、話し合いの3ステップを習得します。
④コンフリクトマネジメント~自分の感情への対処方法~
他者への配慮だけではなく、自分の感情との向き合い方について学び、ケーススタディを通じてコンフリクトに対処できる具体的なイメージを持たせ、現場に送り出します。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
コンフリクトを上手に対処できる人材がいることで、組織の生産性を上げることができます。
この機会に、組織に所属する多様な人材を最大限活かせるようになるためのコンフリクトマネジメントスキル向上研修を企画してみてはいかがでしょうか。