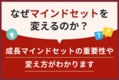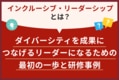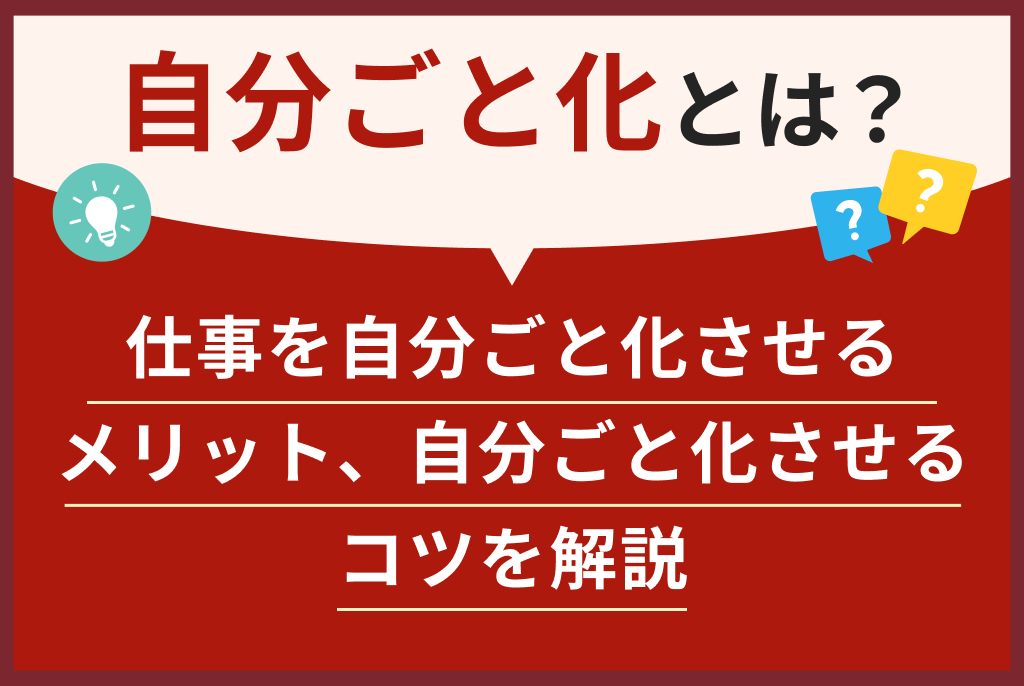
「自分ごと化」とは? 仕事を自分ごと化させるメリット、自分ごと化させるコツを解説 【当事者意識を高める】
仕事を単なる義務や日常のルーチンとして捉えるのではなく、自分の人生の大切な一部として受け止め、情熱を持って取り組むことを考えたことはありますか?
これが「自分ごと化」です。
この記事では、「自分こと化」とは何か、なぜ重要なのか、そして、どのように仕事を「自分ごと化」させるかについて解説いたします。

目次[非表示]
「自分ごと化」とは
「自分ごと化」とは、個人が与えられた仕事やミッションに対して主体性を持って取り組む姿勢やマインドのことを言います。
単なる作業を超えて、情熱を持って仕事に取り組めるようになるので、仕事の質や生産性が上がり、個人の成長や満足感につながります。
また、社員の多くが仕事を「自分ごと化」することで、組織の結束力も高まります。
社員は、何に対して「自分ごと化」するのか
経営課題・事業課題に対する「自分ごと化」
経営課題や事業課題に対して「自分ごと化」するということは、「経営視点」で考えることといえます。特に管理職やチームリーダーなどは、このような意識を持つことが大切です。
経営状況や市場環境を見据えて、売上・利益の向上、市場シェア拡大、事業の持続的拡大、社員のモチベーションや育成、ガバナンス体制などを大局的な観点で考えることがこれに当たります。
仕事の目的に対する「自分ごと化」
仕事の目的に対する「自分ごと化」とは、「この仕事の目的は何か?」という観点で考え、仕事に取り組むことをいいます。
「これまでやってきた業務なのでやっている」や「上司の指示だからやっている」という姿勢ではなく、そもそもの仕事の目的に立ち帰り、「この仕事は本当に必要か?」「今までの仕事のやり方がベストだろうか?」といった観点で、業務を捉えることです。
顧客に対する「自分ごと化」
顧客に対する「自分ごと化」とは、顧客の課題解決に関して、顧客以上に真剣に考え、取り組む姿勢です。このような姿勢で仕事に取り組むことで、顧客から絶大な信頼を得ることができるでしょう。
顧客に対する「自分ごと化」の具体例
顧客に対する「自分ごと化」の例として、あるビール会社の営業担当者のエピソードをご紹介します。
彼の顧客である飲食店は日本酒を提供する際にこだわりのある「特注の錫の器」を使用していました。ある時、その錫の器が入手できなくなったそうです。その話を聞いた営業担当者は、日本酒と全く関係のないビールの営業であるにも関わらず、顧客の一大事であると考え、全国を隈なくあたり、その錫の器の製造元を探し出しました。
あまりの熱意に、その飲食店の経営者は大感激をして、それ以降は、そのお店で扱っている酒類はすべてその営業担当者の会社に注文するようになりました。
社会課題に対する「自分ごと化」
自分が所属する企業の利益を超えて、環境保全、貧困や経済的格差の解消、人権問題などの社会的課題を視野に入れて取り組むことを言います。
SDGsなど企業が公的な役割を果たすことが、これまで以上に求められるようになりました。
今後は、ビジネスパーソンにとって、社会課題といった高次元の視点を持つことが重要になっていくでしょう。
社員が仕事を「自分ごと化」することで得られるメリット
主体性を持った行動ができる
「自分ごと化」することで、上司や先輩の指示を待つだけでなく、「自分は何をするべきか?」と自ら考え、行動することができるようになります。
このような主体的行動のできる社員が増えれば、組織の生産性向上につながります。
意思決定のスピードが上がる
仕事を「自分ごと化」する社員は、自分で判断できる範囲が広がります。
上司の指示を仰がなくても判断できる場面が増えるため、意思決定のスピードが上がります。
モチベーションが高まる
「自分ごと化」することで、仕事へのオーナーシップが高まります。
やらされ感で働くのではなく、自らの意思で仕事の質を上げて、付加価値を高めようとする努力が楽しくなります。
その結果、顧客や同僚から感謝されることが増えるとともに、自分自身の成長を実感できるようになり、仕事へのモチベーションが高まります。
人を動かす原動力になる
仕事を「自分ごと化」している人は、上司や同僚、顧客から信頼されるようになります。このような人が何か提案をしたり、協力を依頼した時には、社内外の人から応援されるようになります。
社員が仕事を「自分ごと化」できないことで起こる問題
受け身、指示待ちになる
仕事を自分ごと化できていないと、自ら考え、主体的に行動することが少なくなります。結果として、「言われたことをやればいい」という受け身、指示待ちの姿勢になりがちです。
責任感が欠如する、責任逃れをする
問題や障害が起きた際に、うまくいかない原因を他人や環境のせいにするようになります。「あの人が悪いから失敗した」、「景気が悪いから商品が売れないのは仕方ない」など責任逃れをしてしまう傾向があります。
危機感がない
仕事に関する問題意識が低くなることや、失敗した際の損害などを考えるとがなくなるため、健全な危機感を持てなくなります。
自己主張しない
「自分ごと化」していないと、仕事に対する問題意意識が薄くなり、周りの意見に流されるようになります。会議の場などで、意見を求められても自己主張ができなくなりがちです。
変化を受け入れられない
環境や行動を変えることには未知の危険が伴います。そのため、人は本能的に変化を恐れるという性質を持っています。仕事を「自分ごと化」できていないと、変化を恐れる、避けるという本能から、変化を受け入れることでできなくなりがちです。
社員が仕事を「自分ごと化」できない原因
仕事の全体像が見えていない
仕事の全体像が見えずに、目の前の仕事をこなすだけだと、どうしても近視眼的なものの見方、考え方になってしまいます。その結果、「指示されたことをやればいい」という指示待ちの状態になりがちです。
仕事の目的、意味を理解していない
自分の仕事が、「組織や会社にとってどんな意味があるのか」、「顧客や社会にどのような貢献ができているのか」、といった仕事の目的、意味を理解していないと、目の前の仕事を淡々とこなすだけとなり、仕事を「自分ごと化」することが難しくなります。
自分のことで精一杯になっている
経験や能力が不足している場合や、あまりにも業務量が多すぎると、人は自分のことで精一杯になってしまいます。このような状態では、心の余裕がなくなるので、仕事を「自分ごと化」することは難しくなります。
責任を負いたくない
仕事をしていく上で、成功もあれば失敗することもあるのが当然です。
失敗した時に「自分が責任を負う面倒は嫌だ」、「恥をかきたくない」という気持ちから、仕事を「自分ごと化」して真剣に取り組むことを避けるケースがあります。
社員の「自分ごと化」を促進する方法
上司・リーダーが行動で見本を示す
上司やリーダーが仕事を「自分ごと化」している姿をメンバーに見せることが大切です。誰もが尻込みするような大きな問題が起きた時に「私の出番だ。任せておきなさい!」と問題解決に前向きに取り組む姿を見せることで、メンバーが上司を尊敬し、憧れるようになります。
部下は、「この人みたいになりたい」という思いを抱くようになるので、「自分ごと化」できる人材が育てることで可能になります。
また、そうした上司やリーダーは、自分の言葉でビジョン・ミッションを語ることができます。上司やリーダー自身の言葉は、メンバーの心を動かし、「自分ごと化」を促進します。
関係の質を高める
上司や先輩、同僚との関係性が良くなると、仲間意識が醸成されて、お互いの仕事の状況に関心が高まります。そうなると、仕事に対して高い視点を持ち、視野が広がるので、仕事を「自分ごと化」しやすくなります。
個人目標が会社目標、組織目標の達成につながることを理解させる
仕事の全体像が見えずに、目の前の仕事をこなすだけでは、「自分ごと化」することが難しいと前述しました。そのため、個人目標を達成することが、目標や組織目標の達成につながると理解させることが大切です。
トヨタ自動車では、「あなたのこの仕事が組織や会社の目標達成にこんな風に貢献しています」という事を、日々部下に伝え続けるよう管理職に教育をおこなっています。
振り返りを習慣づける
自分の仕事の状況や進め方を日々、振り返る習慣を持つことで、新たな気づきを得ることができます。この気づきが、自身の成長につながる大切なヒントとなります。
このような振り返りを習慣化することで、仕事の目的や意味を深く考えるようになり、仕事を「自分ごと化」するようになって行きます。
フィードバックをおこなう
上司や先輩からフィードバックを受けることで、自分では気づくことができなかった成長のヒントを得ることができます。
また、視点が高まることや視野が広がるので、仕事を「自分ごと化」しやすくなります。
「自分ごと化」が成果をあげた企業の事例紹介
アサヒビールグループで初の女性経営者となった千林紀子氏は、入社4年目に営業職から商品企画部に異動になった時、女性だという理由で、庶務の仕事と補佐的な事務作業しか担当させてもらえませんでした。
これは当時の社会的な風潮でしたが、営業で実績を上げてきた千林氏にはショックな出来事でした。しかし、千林さんは腐ることなく、「与えれた業務をしっかりやって、商品開発を任せてもらえる信頼を得よう」と気持ちを切り替えました。そして、与えられた仕事をしっかりとこなすかたわら、「新商品企画書を作って提案してみよう」と考えました。そして、さまざまな困難を乗り越えて、「アサヒ生ビール黒生」という大ヒット商品を生み出すことに成功しました。
千林氏のこのような考え方、姿勢こそ「自分ごと化」の素晴らしいお手本といえるでしょう。
*参考文献:仕事の成果が上がる「自分ごと化」の法則 (千林紀子 著)
仕事を自分ごと化し、社員の主体性を向上させる研修ならアルーにお任せください
仕事を自分ごと化し、社員の主体性を向上させる研修なら、ぜひアルーへお任せください。
人材育成を手掛けているアルーでは、仕事を自分ごと化し、社員の主体性を向上させる育成プログラムを数多くご用意しております。アルーの実施する育成プログラムでは、グループワークや実践を通じて主体性を向上させることが特長です。例えばメンバーの主体性を引き出すため、講師が逐一指示を出さずにメンバー同士の話し合いを重視するワークを繰り返すことで、主体性を向上させることができます。
また、お客様の企業の抱える課題に合わせて、研修内容を柔軟にカスタマイズすることも可能です。例えば、若手社員や中堅社員を幅広く対象とした研修もあれば、女性リーダー層を対象とした研修など、ターゲットを絞った研修を実施することもできます。仕事を自分ごと化し、社員の主体性を向上させるための施策をご検討の際は、ぜひお気軽にアルーまでご相談ください。
仕事を自分ごと化し、社員の主体性を向上させる研修事例
アルーでは、これまでに幅広い企業で仕事を自分ごと化し、社員の主体性を向上させる研修の実施を支援してまいりました。ここではそれらの中から特に参考となる事例を1つ紹介します。
仕事を自分ごと化し、社員の主体性を向上させるための具体的な研修方法について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
【サービス業】若手社員研修
システム会社のB社では、ジョブ型人事制度の導入に向けて、主体的に行動できる社員の育成を目指していました。そこで、若手社員を対象として主体性を伸ばすための研修を実施しています。
本事例は事前課題と4時間の研修当日、事後課題の3つで実施されています。事前課題では1年間の振り返りを行い、主体性を発揮するうえで重要な自分自身のモチベーションを見つめ直してもらいました。研修では主体性を発揮する方法を扱い、事後課題としてアクションプランの実践を行っています。
受講者からは、「新入社員から2年目になることへの不安もあったが、今後自分がどのような行動をしていく必要があるのか、具体的なイメージをもって考えられる機会となった」、「個人ワークやグループワークが沢山あったことで自身の今までの行動を見直したり、新たな目標を考えることができた」などの声があがりました。今後の目標を立て、業務に対して前向きに考えてもらうことに成功しています。
本事例の詳細は、以下のページからご覧ください。
【研修事例】仕事へのオーナーシップを持ち、ひとりだち意識を得る
▼事例資料ダウンロード
まとめ
仕事を「自分ごと化」すると、主体的に考え、行動できるようになります。
社員の「自分ごと化」が進むことで、組織の生産性は高めることや、イノベーションが起きやすくなります。また、社員の自己実現ができるようになり、社員幸福度の向上、定着率の改善に繋がりやすくなります。
ぜひ「自分ごと化」を高める研修や取り組みをできることから取り入れてみましょう。