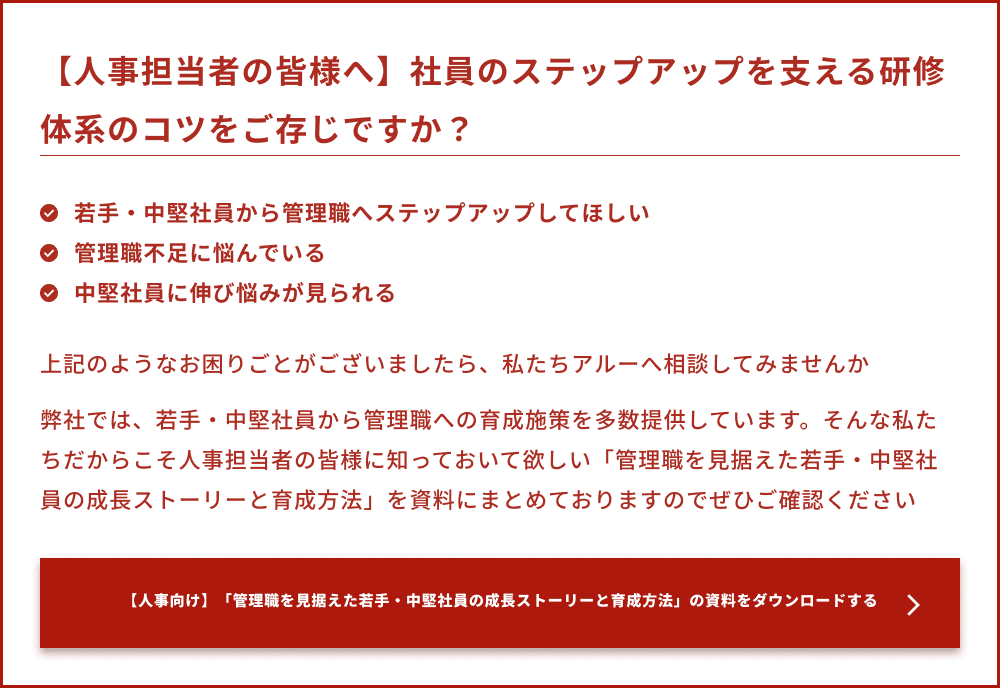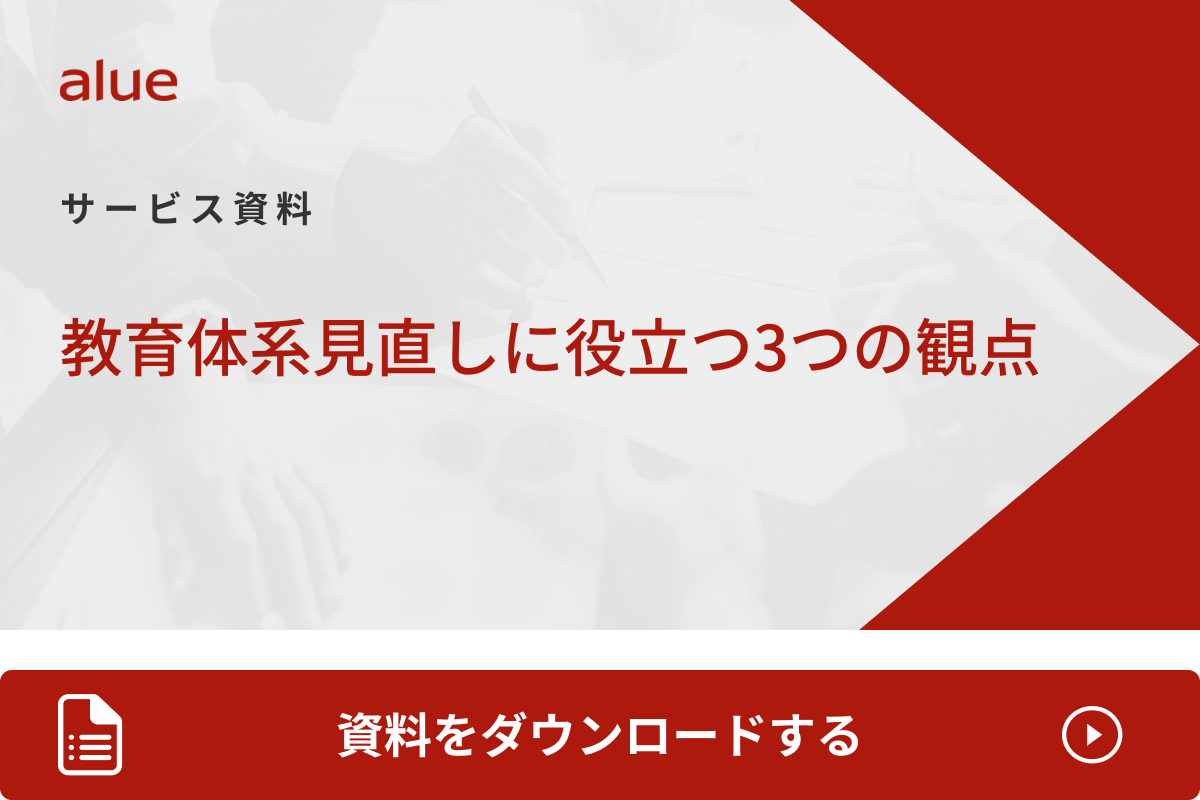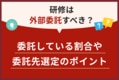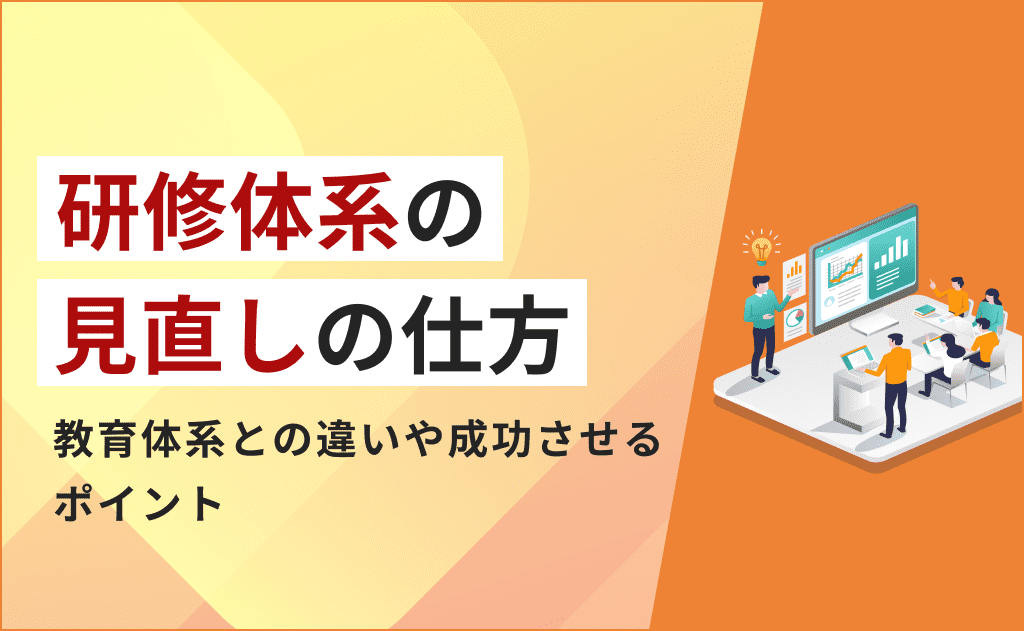
研修体系の見直しの仕方|教育体系との違いや成功させるポイント
新入社員研修や階層別研修など、様々な研修を充実させている企業は少なくありません。しかし、気づけば一度決めた研修内容を毎年使いまわしてしまっている、というケースはないでしょうか?
企業価値の向上につながる人材育成を成功させるためには、研修体系を定期的にブラッシュアップすることが欠かせません。この記事では、研修体系を見直すためのステップや、研修体系の見直しを成功させるために必要なポイントについて徹底的に解説します。
目次[非表示]
研修体系とは
研修体系とは、簡単にいうと、全社の研修を整理したものです。自社で必要とされる技術や知識を向上させるために構成されたプログラムやカリキュラムを全体的に網羅したものです。
例えば、新入社員なら「社会人の基礎を身につける」「業務に必要なスキルを身につける」ことを目標に、「社会人へのマインドセット」「ビジネスマナー」などの研修を行います。このようにどのような研修を行うべきかを階層別・スキル別・業種別などで細分化し、全社でまとめてマップのように図にすることもあります。
研修体系が整っていれば研修の目的や意味を明確にしやすくなり、人材育成を促進させ、企業価値を向上させることができます。
教育体系との違い
研修体系と似た言葉に、「教育体系」があります。
教育体系とは、企業で実施する教育の全体像を示したマップのことです。どの時期にどういった教育を実施するのか、といった内容をひと目で把握できるように作られており、例えば
- 目指す人材像や組織像
- 人材開発方針
- 教育の全体像
- 研修メニュー
といった項目が記載されます。
研修体系は実際に行われるプログラムをまとめたものを指すため、「研修体系は教育体系の一部」と考えるとわかりやすいでしょう。
教育体系・研修体系は共に定期的な見直しが必要
研修を実施する中で、研修を企画する際には、見えてこなかった課題点や問題点が明らかになる場合があります。また変化が激しいVUCAの時代では、変化とともに社員へ求められる能力も変わっていくものです。
効果的な社員教育を実施するためには、研修体系や教育体系を継続的にブラッシュアップすることが欠かせません。気づけば一度決めた研修体系や教育体系を使いまわしてしまっていた、ということがないよう、両者の定期的な見直しが必要です。
研修体系を見直すタイミングとは?
研修体系は定期的に見直すことが必要ですが、実際どのタイミングで見直しを実施すればよいのでしょうか。
基本的に、人事戦略は経営戦略や企業のビジョンと連動しています。したがって、これらが変更になった際には研修体系を見直す必要があるでしょう。
具体的には、
- 経営者が交代したとき
- 大規模な組織体制の変更があったとき
- 中長期経営戦略が策定されたとき
- 企業の統廃合や合併などが実施されたとき
- 評価方法など、人事制度に変更が生じたとき
- 現在の研修体系を策定してから3年以上が経過したとき
などが、研修体系を見直すべきタイミングです。
研修体系を再構築する目的

研修体系を再構築する目的はいくつかありますが、中でも経営戦略と連動した人事戦略を展開するというのは重要な目的です。また、定期的に研修体系を見直せば、中長期的な研修の展開や企業価値の向上にもつながります。
研修体系を再構築する目的について確認していきましょう。
経営戦略の実現を人材育成から支えるため
研修体系を再構築する目的の一つに、経営戦略の実現を人材育成から支えるという点が挙げられます。
市場環境や競合状況などは時々刻々と変化するため、企業の経営戦略は随時アップデートされ続けます。そもそも、社員教育とは企業の経営戦略を実現できるような人材を育成することを目的として行われるものです。経営戦略と連動した人事戦略を展開することが、研修体系を再構築する大きな目的の一つといえます。
経営戦略に合わせて研修体系を再構築すれば、例えばビジネススキルやITスキル、コミュニケーション能力といった、企業の経営戦略に必要なスキルや知識を持つ人材を育成することができるでしょう。
企業価値の向上のため
研修体系を再構築する2つめの目的は、企業価値の向上です。研修によって従業員が専門的なスキルや知識を習得すれば、企業は顧客からの信頼を獲得できるでしょう。例えばITスキルを磨いてもらえば、ITを活用したパフォーマンスの高い仕事ができるようになり、結果的に競合他社との差別化を図ることもできます。
また、従業員の自己啓発を後押しすることで、社員は自分の成長を実感しやすくなり、高いパフォーマンスを発揮することができます。また、社員のモチベーション向上にもつながるので、人材の流出を防ぐこともできます。こういったことから、充実した研修体系は企業価値の向上に直結するのです。
研修の理由・目的を明確にするため
研修体系を再構築する目的の一つに、研修の理由・目的を明確にするという点もあります。
研修体系を事前に作っておけば、「教育の全体像の中でこの研修は〇〇という位置を占める」といったように、それぞれの研修の意義や目的を説明しやすくなります。研修の目的が明確になれば、研修対象者に対してはもちろん、経営者にとっても研修の意義を理解してもらいやすくなるでしょう。
人事制度との一貫性を図るため
せっかく研修を受講してスキルを磨いても、自らの成果が会社から正しく評価されないと、従業員のモチベーションを大きく低下させてしまいます。また、昇進や昇格によってポジションが変動した社員に対しては、新しい階層で求められる能力を改めて育成することが必要です。
研修体系を再構築する目的の一つに、人事制度との一貫性を図ることがあります。研修体系を定期的に見直せば、研修によって習得したスキルや知識を正しく人事制度で評価し、報酬や昇進に反映させることができます。昇進や昇格といった人事処遇と一貫した教育を用意することで、組織力の向上が期待できるのです。
研修を中長期的・継続的に行うため
研修体系を再構築する目的の最後に、研修を中長期的・継続的に行うことがあります。研修は一度行えばそれで終わりというわけではありません。毎年入社・昇進する社員に合わせたプログラムを定期的に提供し、従業員の能力を定点観測することが必要です。
研修体系がしっかりしていれば、「新入社員が組織に馴染むまでに時間がかかっている」「中堅社員のモチベーションに課題がある」といったように、研修プログラムの課題点が浮き彫りになります。研修体系を再構築することで、教育の質を底上げすることが可能です。
研修体系を見直し、再構築するステップ
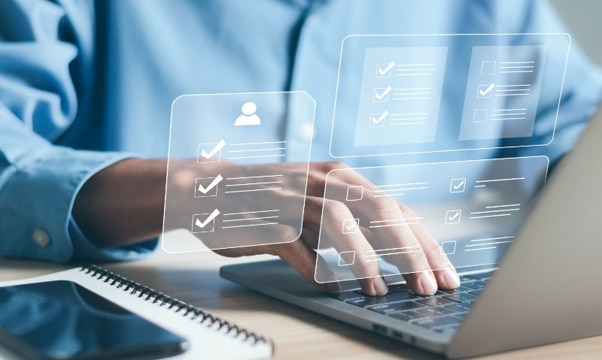
研修体系を見直す時期や、再構築する目的について解説してきました。ここからは、実際に研修体系を見直し、再構築する際の具体的なステップについて解説していきます。それぞれのステップを着実に実施して、研修体系の見直しを効果的に進めましょう。
現状の課題を確認し、状況を把握する
研修体系を再構築する際には、まず状況を把握し、現状の課題を確認するところから始めましょう。
自社の教育における課題を分析するためには、まず「どの従業員が」「いつ」「どこで」「どのような仕事をしているのか」を整理する必要があります。そして、それぞれの仕事について生産性や効率を改善できないかを考えていきましょう。
また、それぞれの仕事に必要な能力育成が十分できているかも確認しておきたいポイントです。「現場で足りていない能力」を正確に把握すれば、教育における改善点も自然と見えてきます。
あるべき人材像の定義
人材育成において重要な概念が、「あるべき人材像」です。あるべき人材像とは人材育成のゴールとも言える存在で、これが揺らいでしまうと結局何を目指して教育しているのかわからなくなってしまいます。
現状の分析が完了したら、次は人材育成におけるゴールである「あるべき人材像」を定義しましょう。あるべき人材像を定義する際には、まず企業全体として掲げている経営戦略や、中長期戦略を参考にする必要があります。企業の経営戦略を実現するためには、どういった人材が求められているのかを明確にしておくことが重要です。
課題をもとに対象者や育成方針を決定する
最初のステップで行った課題の抽出は、「現在地を明確にする」という作業です。そして、次のステップで行ったあるべき人材像の定義は、「ゴールを明確にする」という作業です。
これら2つが終了したら、次は両者のギャップを埋めるために必要な育成方針の決定に進みます。具体的には、まず「誰を対象に育成を実施するのか?」を明らかにするところから始めるとよいでしょう。対象者が決定したら、育成の全体的な方針を定めていきます。
育成方針をもとにコンピテンシーを作成する
どのような方針で育成を進めていくかが定まったら、次は育成方針を具体的なコンピテンシーに落とし込んでいく作業を進めていきましょう。
コンピテンシーには、「目に見える要素」と「目に見えない要素」の2つが存在すると言われています。目に見える要素とは、例えばITスキルや語学力などの知識やスキル、目に見えない要素とは性格や価値観、特性といった要素を指します。コンピテンシーを定める際には、これらの両者にバランスよく着目することが重要です。
作成したコンピテンシーをもとに研修内容を決定する
最後に、作成したコンピテンシーを基に研修内容を決定します。
具体的には、まずどれくらいの研修期間で育成を行うのかといった育成期間から決めていくのがおすすめです。その後、集合型研修で実施するのか、あるいはOJTで実施するのかといった具体的な研修方法について考えていきます。研修で育成したい内容に合わせて、最適な研修方法を採用するのがポイントです。
あるべき人物像(コンピテンシー)を活用した階層別研修の体系図作成は、以下のページで紹介していますので、あわせてご確認ください。
【図例あり】コンピテンシーを用いた階層別研修の体系図作成のススメ
研修体系の見直しならアルーにご相談ください
研修体系を見直しする際は、人材育成を専門として行っているアルーへぜひご相談ください。アルーでは、階層別研修で求められる能力を「8つのレイヤー」と「ジブン・コト・ヒトの3領域」に分けた研修体系図を活用した研修を実施しています。
「アルーコンピテンシーマップ」と名付けられたこの研修体系図を活用すれば、どういったスキルや知識が求められるのかを階層ごとにひと目で把握できるようになり、次に進むために必要な力も一目瞭然で分かります。研修体系を見直す際は、ぜひアルーへお任せください。
コンピテンシーを用いた階層別研修の体系図の作成については、以下の記事をご確認ください。
【図例あり】コンピテンシーを用いた階層別研修の体系図作成のススメ
▼アルーコンピテンシーマップを活用した研修体系見直しの方法はこちらの資料からもご覧いただけます。
まとめ
研修体系と教育体系の違いや、研修体系の再構築を行う目的、さらには再構築する際に必要なステップについて解説しました。経営戦略と連動した人材育成を効果的に行うためには、定期的に研修体系を見直すことが欠かせません。
また、変化の激しい現代では、年を追うごとに求められる能力も刻々と変化するものです。ぜひこの記事で解説した研修体系の見直しに関するノウハウを活用し、自社の研修体系のブラッシュアップに取り組んでみてください。
▼アルーコンピテンシーマップを活用した研修体系見直しの方法はこちらの資料からもご覧いただけます。