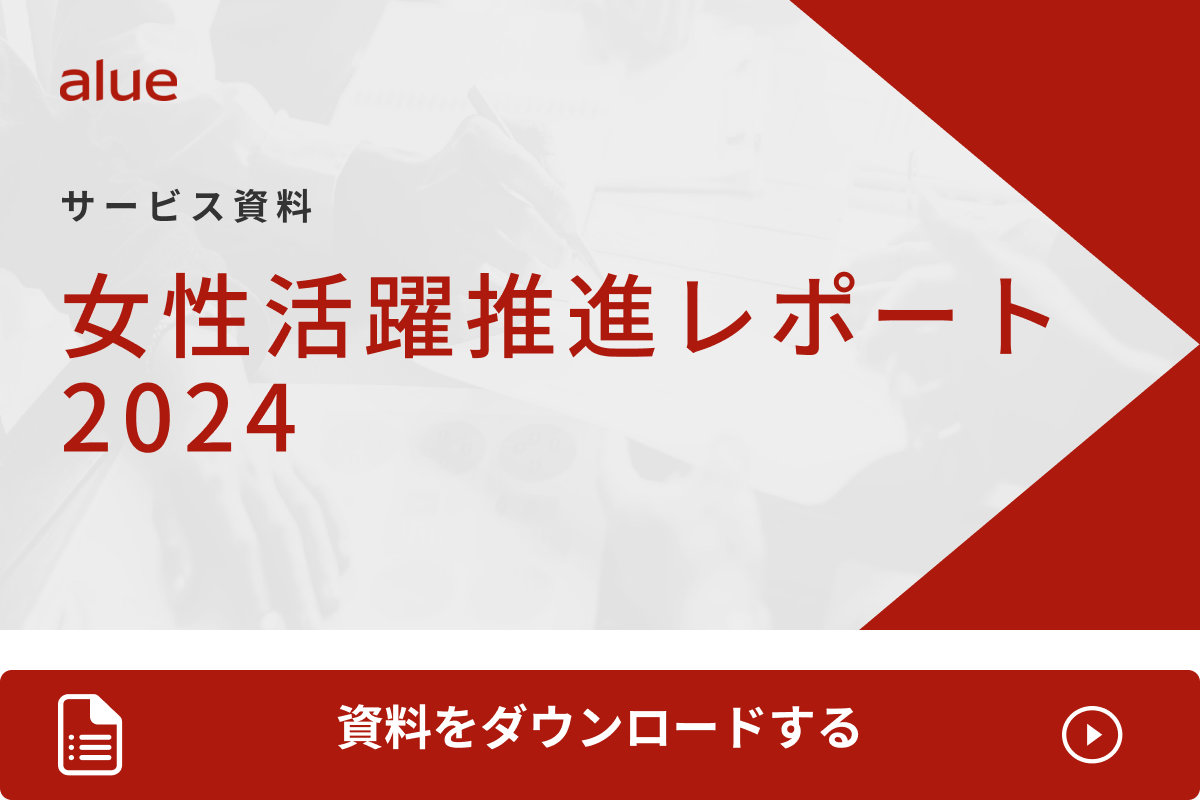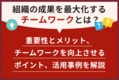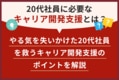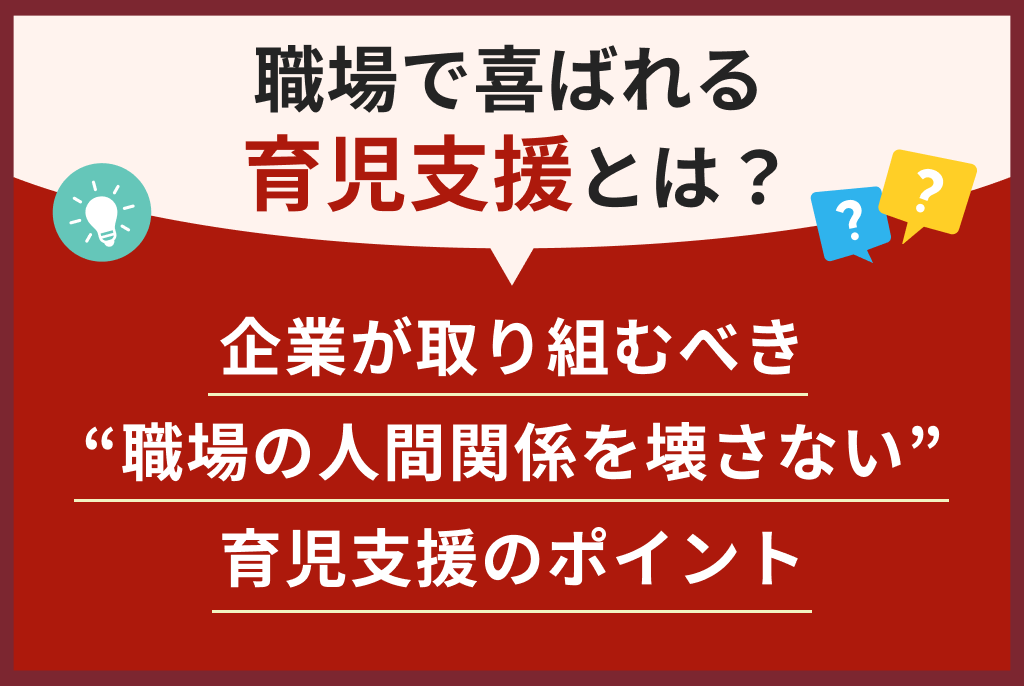
職場で喜ばれる育児支援とは?企業が取り組むべき“職場の人間関係を壊さない”育児支援のポイント
人事労務を担当されている方にとって、特に女性社員の方に対する子育て支援施策をどのように実施していけばよいのかという課題は、常に頭のどこかにあるのではないでしょうか。
子育て支援施策を充実すればするほど、既に子育てを終えた社員からは「私のときはそんなサポートなんてなかった」と不満が出たり、また、出産を希望しない社員からすれば、不公平に感じられるケースもあります。さらに、善意に期待して実施した制度を、時には悪用するかのように利用する社員が現われ、中止を余儀なくされることもあったり・・・。
とはいえ、たとえば平成27年には、「子ども・子育て支援法」が施行されました。この「子ども・子育て支援法」の第4条には、事業主の責務も努力義務として定められており、社員の理解を得ながら子育て中の社員へのサポートをおこなう必要があります。
そこで本記事では、企業が取り組むべき“職場の人間関係を壊さない”育児支援のポイントを解説します。

目次[非表示]
子ども・子育て支援法をチェックする
この「子ども・子育て支援法」ですが、意外とご存じのない人事労務担当の方も多い法律ですので、重要条文だけでもサッと確認しておきましょう。
「子ども・子育て支援法」
(目的)
第一条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他の子どもに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。(基本理念)
第二条 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。
2 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものであり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮されたものでなければならない。
3 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。(事業主の責務)
第四条 事業主は、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。(国民の責務)
第五条 国民は、子ども・子育て支援の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。(子ども・子育て支援法)
職場で喜ばれる子育て支援はまず「雰囲気づくり」
まず、職場で喜ばれる子育て支援を考えたとき、何よりも大事なことがあります。それは「子育てを職場全体でサポートするという雰囲気づくり」です。
子育てサポートの雰囲気づくりはトップの意思表示から
基本的に、子育ては急な遅刻や早退、欠勤がつきものです。
それに対して「またか…」、「いい加減にしてほしいよ…」といった周囲の無言の訴えは、必ず当人のパフォーマンスやエンゲージメントに影響してしまいます。
更にはそういったネガティブな感情を持ってしまった上司や同僚が、子育て中の社員に対して「子育てが大事なのは分かるけれど、周囲に迷惑をかけるなら仕事を続けるかどうか考えて欲しい」、「子どもが心配なら、退職した方がいいのでは?」などと言ってしまうと、いわゆる「子育てハラスメント」や「マタニティハラスメント(マタハラ)」などに該当してしまい、問題がこじれてしまうことも珍しくありません。
そのような「子育てにネガティブな職場の雰囲気」を変えるためにも、「子育てを職場全体でサポートするという強い意志」を企業が示すことがまず大事になります。
言い換えれば、トップが「職場全体の『子育て社員を支えることは、業務の一環である』というトップの意思」を示せるか。それが特に中小企業では最初のステップになります。
職場で喜ばれる子育て支援策3選

社内イントラネットや社内報で、制度の内容や制度を利用した体験談を発信
あなたが人事労務担当者なら、考えて頂きたいことがあります。それは「子育て社員は、本当にすべての育児支援制度を理解していると言えるか」ということです。
大抵の場合、子育て社員は自分や家族が妊娠・出産というライフイベントに直面するまで、子育て支援制度にあまり関心を持っていません。例えば、子どもが1歳になるまで育児休業を取れることについては、ほとんどの子育て社員が知っていると思います。しかし、保育所が見つからない場合に2歳まで延長できるという救済制度についてはどうでしょうか。ここまでは知らなかったという子育て社員もいるはずです。
このように、制度があっても知らなければ使えませんし、あとから「制度があるなら教えて欲しかった」という不満を持たれる可能性も否めません。
そのためにも、SlackやChatwork、LINEWORKSのような社内イントラネットに定期的に情報をアップしたり、社内報でも積極的に取り上げていくという姿勢が重要になってきます。
専門の相談窓口を作る
制度の情報があっても、自分が該当するのかどうか分からない、という子育て社員がいる可能性も考えられます。そういった子育て社員をサポートするために、子育て社員専門の相談窓口を作るというのも一つの方法です。
自社独自の子育て支援制度を検討・実施する
労働基準法をはじめとする、労働関係諸法令は、あくまで「最低限度の基準」を定めたものであり、法律を上回る制度を構築することを妨げるものではありません。中小企業の場合、資金繰りや人手確保の問題が大きいことは重々承知していますが、法律を上回るような、自社独自の子育て支援制度を検討、実施することも、職場の雰囲気を変えていく一つの方法として有効です。
例えば、上述した「専門の相談窓口」制度は、相談の実施日や時間を設定することで、コストを抑えることができるはずです。何より、そういった「子育て支援制度があること」自体が、子育て支援の姿勢を明確にすることに繋がることは言うまでもありません。
その他、「法定の期間に、自社独自の育児休業期間をプラスする」ということも考えてよいかもしれません。もちろん、〇年間プラスする、というのは厳しいことが多いと思いますが、例えば半月や1カ月程度でしたら、実施可能という職場は多いのではないでしょうか。
社員研修を活用して、子育てを応援する雰囲気をつくろう
社員は日々忙しく働いており、どうしても視野が狭くなってしまいがちです。子育て社員を応援しよう、と言われても、目の前の仕事のことを考えてしまい、ポジティブに受け入れられない社員もいます。そうしたときには、忙しい日常を離れられる場、たとえば社員研修参加の機会を提供することも有効な施策のひとつです。
社員研修を実施することは、経営層からの強いメッセージにもなりますし、受講する社員に向けて共通のメッセージを発信することもできます。
「子育てを職場全体でサポートするという雰囲気づくり」の施策のひとつとして、ぜひ社員研修を検討してみてはいかがでしょうか。
アルーの子育て社員を応援する研修事例
人材育成を手掛けているアルーでは、これまでにさまざまな企業で子育て社員を応援するための施策を支援してまいりました。若手女性社員や育休前後の女性社員を対象とした研修から、管理職を対象とした研修まで幅広く対応しています。ここからはアルーがこれまでに支援した中から、男性社員向け『育児と仕事の両立セミナー』 研修事例とワーキングマザー向けキャリア形成支援プログラム事例の2つを厳選して紹介します。
男性社員向け『育児と仕事の両立セミナー』
「子育てを職場全体でサポートするという雰囲気づくり」の一環として、男性社員に向けて実施した研修です。この企業様では、女性管理職比率が伸びない現状の背景に、男性社員や管理職の育児に対する協力意識が弱いという課題がありました。その課題を解決するために、経営層からメッセージを発信し、男性が育児に参加するメリットを理解してもらうことをねらいとして実施しました。
▼テーマ
育児期男性社員向け『育児と仕事の両立セミナー』
▼ねらい
- 男性の立場からも、女性活躍を自分ごととして考えられるようになる
- 男性社員が育児と仕事の両立をしやすい風土を醸成する
▼内容
①オリエンテーション
トップからのメッセージを発信し、会社からの意図を説明してもらいます。また、自己紹介を通じて話しやすい場を醸成します。
②なぜイクボスが必要な戦略なのか
ダイバーシティが必要な理由やイクボス企業のメリットについて解説します。
③自身のダイバーシティ度を自覚する
イクボスやダメなボスの実例を学び、自分のイクボス(ダイバーシティ)度をチェックすることで、自分が育児と仕事の両立について応援できているのかを自覚します。また、ダイバーシティマネジメントに必要なイクボスの要素を学びます。
④ダイバーシティマネジメントを促進する
多様な人材の力を発揮し、成果を出すためのモデルを学びます。また、そのために必要な傾聴や承認のスキル、G-PDCAサイクルを学ぶためのスキルを習得します。
⑤まとめ
研修の内容を振り返り、応援メッセージを出すことで、行動を変えられるよう背中を押します。
ワーキングマザー向けキャリア形成支援プログラム
ワーキングマザーを対象に実施した研修事例です。育児をきっかけに一度職場を離れ、復職した女性社員が、自身のキャリアを描くことを諦めているという課題を解決するために、自律して働くマインドを醸成し、両立のための協力関係を築き自分のキャリアを描けるようにすることをねらいとして実施しました。
▼テーマ
ワーキングマザー向けキャリア形成支援プログラム
▼ねらい
- 仕事と家庭の両立を不安視している状態から脱却する
- 復職後も仕事やキャリアに前向きに取り組めるよう、これからの働き方の軸をつくる
▼内容
①オリエンテーション
研修の狙いと進め方を説明します。また、トレーナーから積極的に自己開示することで、自己紹介を通じて話しやすい場を醸成します。
②自分の基盤を整える
自分が自律するためのルールを考え、自分が快く生きるために大切にすることを明確にします。
③家族を創る
子どもの成長に合わせた家族の在り方を中長期的に考えます。また、家族関係を円滑にするための夫婦間コミュニケーションのやり方と、子どもと接する注意点を学びます。
④職場の関係性を見直す
出産前と出産後のギャップを知り、職場を心地よいものにするための、関係性を構築するコミュニケーションのコツを学びます。そして、自分が大切にするキャリアイメージを描き、理想の自分になるためにできることを考えます。
⑤まとめ
始めること、辞めること、続けることの切り口で、具体的なワンステップを明確にします。そして、その実現のために上司に依頼したことをまとめ、研修後のコミュニケーションにつなげます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
本記事では、職場で喜ばれる育児支援を解説しました。
残念ではありますが、職場によっては「全社員が納得する」ことが、理想論という職場もあり得ると思います。しかし、その場合であっても、「子育て社員以外の不満を子育て社員に向けさせない」ように、努力することは大切です。
本記事を参考に、「子育て社員に優しい職場づくり」について考えていただけましたら幸いです。