
主体的真理を捉えるためには、どうしたらいいのか?①
前回の記事においては、主体的真理の純度を高めていくために、精神的成熟の前段階の願いを大切にして向き合っていくことの重要性についてお話ししました。
主体的真理シリーズもいよいよ大詰めです。主体的真理を捉えるためには、どうすればいいのかについてお話ししたいと思います。
前提として、主体的真理は、言葉で全てを表現できるものではなく、イメージ的なものであり、エネルギーの塊のようなものですから、綺麗に言語化するための方法論ではなく、主体的真理とのつながりを感じることができるための方法として捉えていただければと思います。
主体的真理を捉えるアプローチとして、大きく2つあります。1つは、これまでの経験や現在の活動から、自分が変わらずに大切にしていることの源泉を辿っていく方法。もう1つは、自分の意識の重心を直感的・抽象的に捉えて、その妥当性を検証する方法です。この記事では、前者の具体的経験をもとに主体的真理を捉えるアプローチについて話します。
原体験から主体的真理を捉える
主体的真理は、内なるエネルギーの源泉ですから、これまでの経験において、そのエネルギーが具現化したものが現れている可能性が高いです。これまでの経験を振り返り、それらの経験が主体的真理の体現だったのではないかと捉えてみることによって、主体的真理を捉えてみようとするアプローチです。
これまでの経験において、次のような要素をもつものをなるべくたくさん洗い出してみましょう。全ての要素が当てはまる経験ではなくてもよく、どれか1つの要素でも当てはまれば良いというくらいの気楽なイメージで、たくさん洗い出してみることをお勧めします。
①内なるエネルギーが湧いていた(少なくとも当時は)
②比較的長い時間、前向きに主体的に取り組むことができた(最初は、周囲からきっかけが与えられていたとしてもOK)
③充実感があった(楽しさというよりも、充実した・満たされた感覚。楽しさの要素があってもよいが、必須とは限らない)
④没頭感があった(我を忘れて取り組んだことがある)
⑤インスピレーションが湧いてきた
なぜ、この5つが経験を抽出する基準になるのかについて簡単にご説明します。まず、主体的真理は内なるエネルギーの源泉ですから、①の内容は主体的真理そのものの性質であると言えますし、②については、内なるエネルギーが湧くからこそ、比較的長期間、周囲に何も言われなかったとしても前向き、主体的に取り組めるということになります。
③については、主体的真理につながっているときの感覚で、覚醒度の高い短期の快感情というよりも、覚醒度が低めの安定した快感情という意味で、充実感という言葉を使っています。
④の没頭感については、(主体的真理が属する)直感意識につながっているときに現れるもので、思考意識を介することなく、あるいは、無意識に思考意識を介して、直感意識と身体意識がつながっている状態と捉えることができます。⑤についても、直感意識につながっているときに、起こりやすい現象でです。

どのような経験を思い出すでしょうか?私の場合は、次のような経験がリストアップされました。
▼テニス
・中学1年生から大学院!まで
・エネルギー、充実感、没頭感もあり
・インスピレーションは稀(やる気はあったが、センスはない)
▼物理・数学
・小学校高学年あたりから興味を持ち始めて、大学院まで
・エネルギーあり、たまに没頭感あり
・インスピレーションはたまに湧いていた
▼集団・チーム活動
・大学・大学院時代の6年間は、サークル活動に没頭。また、長男が小学生のときは、6年間ほど地元の野球チームのコーチをしていた
・エネルギー、充実感、没頭感あり
・インスピレーションが湧いてくることもあったが稀
▼教育ビジネスの起業
・2003年から現在に至る
・エネルギー、充実感、没頭感あり
・インスピレーションもたくさん湧いてくる
▼海外旅行・海外出張
・国の数は多くないが、毎月のように出張・旅行をしていた時期あり
・エネルギーは、その当時は湧いていた
・充実感や没頭感は、他に比べると少ない
・インスピレーションは湧いてきやすかった
▼学習
・何か新しいことを身につけることを、長期間やり続けている
・内容にもよるが、一旦やると決めると、エネルギーは持続する
・充実感はあり、没頭感は稀
・インスピレーションは比較的湧きにくい
経験の背景にある願いを捉える
これらの原体験は、具体的な経験ですから、主体的真理につながったものであったとしても、主体的真理そのものではありません。主体的真理を捉えるためには、これらの原体験それぞれの背景にある願いを捉える必要があります。

A. その経験において、内なるエネルギーの源泉には、どのような願いがあるか?
B. その経験において、どのような感覚を繰り返し得たかったか?
C. 似たような経験をしたとしても、何がなければ、内なるエネルギー・充実感・没頭感がなくなってしまうか?
それぞれの経験について、上記の問いのうち、ピンとくるものを選んで、願いを捉えていきます。
なぜ、この3つが願いを捉える問いになるのかについて簡単にご説明します。Aは、主体的真理の定義そのものですので、この問いに答えることができると、主体的真理あるいはそれが一段具体化された願いを捉えることができるかもしれません。
Bについては、主体的真理につながっているときの感覚を直感的・感覚的に捉えるイメージです。主体的真理や願いそのものを捉える問いではありませんが、直感的・感覚的に捉えることで、思考意識を介さずに感じることができやすくなります。
Cについては、いろいろなシミュレーションをしてみると、一番大切にしている要素を見つけやすくなる、面白い問いだと思います。これは、少しわかりにくいかもしれないので、私のテニスの例で具体的にご説明します。
▼仮に、テニスが卓球だったら?(テニスという要素がなかったら)
・・・没頭感・充実感はあまりなさそう。ただし、卓球をずっとやっていたとしたら、卓球でも良かったかもしれない。
▼仮に、スポーツではなく将棋や囲碁だったら?(スポーツという要素がなかったら)
・・・没頭感・充実感はあまりなさそう。仮に、将棋や囲碁をずっとやっていたとしても、スポーツという身体感覚を使う要素は欠かせない気がする。
▼仮に、勝負ごとの要素がなくなったら?
・・・練習をしているだけでも、没頭感・充実感はある。
▼仮に、社交場としてのテニスだったら?
・・・没頭感・充実感はあまりなさそう。テニスそのものに没頭したい。
▼仮に、テニススクールのみで教わるテニスだったら?
・・・充実感はあるかもしれないが、没頭感はなさそう。
▼仮に、相手が自分の実力とかけ離れていたら?
・・・楽しくはあるが、没頭感はなさそう。
このように考えると、「スポーツを同じくらいの実力の相手と、練習だけでもよいので、没頭してやりたい」というのが願いであることがわかります。この中でも同じくらいの実力の相手というのは、没頭するための条件ですので、要は「スポーツを没頭してやりたい」ということになります。スポーツというのは具体的表現ですが、その本質としては「身体感覚を伴った没入感」を求めているというイメージです。
このような形で一つひとつの経験について、願いを捉えていきます。私の場合は、次のようになりました。(自分で書きながら、自分の願いが少しずつ言語化されていくイメージがあります!)
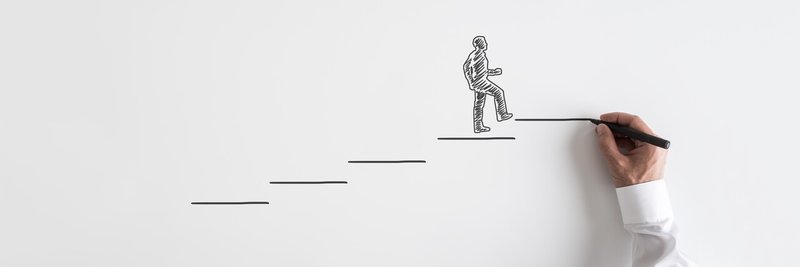
▼テニス
・・・身体感覚を伴った没入感
▼物理・数学
・・・1つの法則で多くのものを説明できる美しさを見たい・感じたい
▼集団・チーム活動
・・・1人ではできない、集団やチームの力が発揮される瞬間を感じたい、見ていたい
▼教育ビジネスの起業
・・・本質を探求して、それが社会の基盤になる姿を実現したい、見てみたい
・・・1人ではできない、集団やチームの力が発揮される瞬間を感じたい
▼海外旅行・海外出張
・・・成長感を感じたい
・・・まだ見ぬ世界に触れてみたい、感じたい
▼学習
・・・成長感を感じたい
・・・新しい世界、新しい感覚に触れてみたい、感じたい
条件付けされたものを仕分ける
このように願いを捉えていくと、いろいろな願いが自分の中にあることがわかります。次にやると良いことは、条件付けされたものを仕分けるということです。
ここでいう条件付けというのは、周囲や外部から、その行動をとることが好ましいこととして条件付けされていることを指します。私たちは、生まれてから親や学校や近所の方から、いろいろな形で条件付けの影響を受けています。
例えば、勉強すると褒められる、あるいは、勉強していい成績を収めると褒められる、という具合で、褒められるという外部からの刺激によって、勉強するという自分の行動が強化されています。このような条件付けは、悪いことではありません。親からの教育や、学校における教育は、条件付けの要素がゼロにはならないでしょう。
条件付けによって、社会適応するための考え方や行動を習得することができます。主体的真理に生きることと、周囲や社会に適応して生きることは両方とも大切なことですから、条件付けは悪いことではありません。
しかし、主体的真理となると話は別です。主体的真理は、その人にとっての真理ですから、外部や周囲からの条件付けとは本質的には異なるものです。ですから、主体的真理と捉えようとするときに、外部や周囲から条件づけされているものをなるべく仕分けるようにする必要があります。
条件付けされたものか、そうではないかを仕分けるために、有効な観点があります。
仮に、それをやらない、意識しないとしたときに、恐れや不安という感情が湧いてくるかどうか?
なぜ、この問いが条件付けされたものを仕分けるのに有効かと言えば、これまでの人生における繰り返しの刺激によって、「それをやること、意識することが良いことだ。逆に言えば、それをやらない、意識しないことは良くないことだ」という具合に、「良いこと、良くないこと」の価値観が形成されているからです。
それをやらない、意識しない
↓
↓←「それをやらないことは、良くないこと」という価値観
↓
良くないことという認識
↓
不安・恐怖
繰り返しになりますが、条件付けがあるからといって、悪いことではありません。むしろ、周囲や社会と調和して生きていくために必要な要素だったからこそ、条件付けとして今も残っているということができますし、いま健全に生活ができているとすれば、それは条件付けされていることのお陰と言っても過言ではないでしょう。
また、条件付けされているかどうかについて、0か100かという白黒はっきりした話ではありません。条件付けの要素が比較的多いか、比較的少ないかと捉えた方が適切かと思います。条件付けの要素が全くないものを見つけようとするよりも、条件付けが比較的少ないものの中で、自分にとって内なるエネルギーが湧いてくるものを探求していく姿勢が良いように思います。
さて、私の例のおいて、条件付けされた要素は「成長感を感じたい」という要素でした。私は、親から「勉強しなさい」と言われたことは殆どないように記憶していますが、幼少期から父や兄の姿を見て、学問の道に自然と向くようになりましたし、勉強をしたら褒められる、成長すると周囲の人から一目置かれるという感覚は、持っていたように思います。

そして、今も成長感をもつことによって、周囲の人から一目置かれるかもしれないという要素は、ゼロとは言い切れません。逆に、成長感を持てないことに対して、「そのままで経営者としてやっていけるのだろうか」というような不安もあります。
このように考えると、私にとって「成長感をもちたい」ということは、条件付けが比較的強いものであると言うことができます。それは、私の主体的真理からくるという部分が0ではないかもしれませんが、どちらかといえば、条件付けによって外部適応するために身につけてきた感覚なのだと捉えています。
ここまで、原体験から主体的真理を捉えていく方法について、お話をしてきました。私自身もこの記事を書きながら、改めて自分の主体的真理と捉えるプロセスをやってみた気づきが多くありました。みなさんも、お時間があるときに、是非ともこのプロセスを試して見ていただき、感想を共有いただけると嬉しく思います。
本日の問いとなります。(よろしければ、コメントにご意見ください)
・これまでの経験で、下記の①から⑤に該当するような経験があるとすれば、それはどのような経験ですか?
①内なるエネルギーが湧いていた(少なくとも当時は)
②比較的長い時間、前向きに主体的に取り組むことができた(最初は、周囲からきっかけが与えられていたとしてもOK)
③充実感があった(楽しさというよりも、充実した・満たされた感覚。楽しさの要素があってもよいが、必須とは限らない)
④没頭感があった(我を忘れて取り組んだことがある)
⑤インスピレーションが湧いてきた
・その経験の背景にある願いはどのようなものですか?(下記の問いの中で、ピンとくるものを選んで考えて見てください)
A. その経験において、内なるエネルギーの源泉には、どのような願いがあるか?
B. その経験において、どのような感覚を繰り返し得たかったか?
C. 似たような経験をしたとしても、何がなければ、内なるエネルギー・充実感・没頭感がなくなってしまうか?
・願いの中で、条件付けの影響が大きいものはどれでしょうか?逆に、条件付けの影響が小さいものはどれでしょうか?
What can we do to perceive the subjective truth? 1)
In my previous article, I talked about the importance of valuing and facing the wishes of those in the former stages of mental maturity in order to increase the purity of subjective truth.
This is the final part of the subjective truth series. I would like to talk about how to perceive the subjective truth.
The premise is that the subjective truth is not something that can be expressed entirely in words, but is imaginary, like a lump of energy, so I hope you will see this as a way to help you feel connected to the subjective truth, rather than a methodology to beautifully verbalize it.
There are two major approaches to perceiving subjective truth: one is to trace the source of what we value as unchanging from our past experiences and current activities. The other is to take an intuitive and abstract view of the tendency of our consciousness and examine its validity. In this article, I will talk about the former approach of perceiving the subjective truth based on concrete experience.
Perceiving Subjective Truth from Original Experience
Since the subjective truth is a source of inner energy, it is highly likely that the embodiment of that energy has appeared in our past experiences. This is an approach that attempts to perceive the subjective truth by looking back on past experiences and wondering if those experiences were the embodiment of the subjective truth.
Let's try to identify as many experiences as we can that have the following elements. It does not have to be an experience in which all of the elements apply, just as long as one of the elements applies to you.
1) I had a lot of inner energy (at least at the time)
2) I was able to work proactively and positively for a relatively long time (even if I was initially given the opportunity to do so by the surroundings)
3) I had a sense of fulfillment.
4) I had a sense of immersion.
5) Inspiration often came to me.
I will briefly explain why these five are the criteria for extracting experience. First of all, since the subjective truth is the source of inner energy, we can say that the content of (1) is the nature of the subjective truth itself, and as for (2), it is because of the inner energy that we are able to work positively and proactively for a relatively long period of time, even if nothing is expected by those around us.
For (3), I use the term fulfillment in the sense of a stable pleasant feeling with low arousal rather than a short-term pleasant feeling with high arousal, which is the feeling we get when we are connected to the subjective truth.
The sense of immersion in (4) appears when we are connected to our intuitive consciousness (to which the subjective truth belongs), and can be regarded as a state in which our intuitive consciousness is connected to our bodily consciousness without or unconsciously through our thinking consciousness. This is a phenomenon that tends to occur when we are connected to our intuitive consciousness.
What experiences do you recall? In my case, the following experiences made the list.
▼ Tennis
・From 1st year junior high school to graduate school
・Energy, contentment, and immersion.
・Inspiration was rare (motivation, but no sense)
▼Physics and Mathematics
・I started to be interested in it in the upper grades of elementary school and went on to graduate school.
・Energetic, sometimes immersed.
・Inspiration comes from time to time.
▼Group and team activities
・During my six years at university and graduate school, I was immersed in club activities. Also, when my oldest son was in elementary school, I coached a local baseball team for about six years.
・Energy, fulfillment, and immersion.
・There were times when inspiration came to me, but they were rare.
▼Entrepreneurship in the education business
・From 2003 to the present
・Energetic, fulfilled and immersed
・Lots of inspiration
▼Overseas travel and business trips
・There was a time when I went on business trips and travels every month, though not to a large number of countries.
・I had a lot of energy at that time.
・I felt less fulfilled and immersed than in other activities.
・Inspiration was easy to come by.
▼Learning
・I have been trying to learn something new for a long time.
・It depends on the content, but once I decide to do it, the energy lasts.
・A sense of fulfillment is present, but immersion is rare.
・Inspiration is relatively hard to come by.
Capture the wish behind the experience
Since these original experiences are concrete, they may have led to subjective truth, but they are not subjective truth itself. In order to understand the subjective truth, we need to understand the wishes behind each of these original experiences.
A. What did you wish for in the source of your inner energy in that experience?
B. What sensations did you wish to have repeatedly in that experience?
C. If you had a similar experience, what, if anything, would have led to the loss of inner energy, fulfillment, and immersion?
For each experience, choose one of the questions above that you feel comfortable with, and capture the wish.
Here is a brief explanation of why these three are the questions that capture our wishes. Since A is the very definition of subjective truth, if we can answer this question, we may be able to perceive the subjective truth or its further embodied wish.
As for B, it is an image of intuitively and sensitively capturing the feeling of being connected to the subjective truth. It is not a question of capturing the subjective truth or the wish itself, but by sensing it intuitively and sensitively, it becomes easier to feel it without involving the thinking consciousness.
As for C, I think it is an interesting question that will help us find the most important factors when we run various simulations. This may be a bit confusing, so I will explain it in detail with my tennis example.
▼What if tennis was table tennis? (If tennis were not an element)
...I don't think I would feel very immersed or fulfilled. However, if I had been playing table tennis all my life, I might have been fine with table tennis.
▼What if it's not a sport, but Shogi or Go? (If there were no sports element)
...I don't think I would feel immersed or fulfilled. Even if I were to play Shogi or Go all the time, I think the element of sports that uses physical senses would be essential.
▼ What if, hypothetically, the element of competition were to disappear?
...There is a sense of immersion and fulfillment in just practicing.
▼What if tennis is just a social event?
...I don't think I'll be able to feel immersed or fulfilled. I want to immerse myself in tennis itself.
▼What if tennis was taught only at tennis schools?
...I might feel a sense of fulfillment, but I don't think I would feel immersed.
▼What if the opponent is not as good as I am?
...It's fun, but it's not going to be immersive.
When I think about it this way, I realize that my wish is to immerse myself in sports, even if it's just for practice, with someone of equal ability. In this case, a partner of the same level of ability is a condition for immersion, so the point is, "I want to immerse myself in sports. Sports is a concrete expression, but in its essence, it is an image of seeking "immersion with physical sensation."
We capture our wishes for each experience in this way. In my case, it went something like this. (I have an image of my wish slowly becoming verbalized as I write it down myself right now!)
▼ Tennis
...Immersion with physical sensation
▼Physics and mathematics
...I want to see and feel the beauty of being able to explain many things with a single law.
▼Group and team activities
...I want to feel and see the moment when the power of a group or team is demonstrated, which cannot be done by one person.
▼Starting a business in education
...I want to explore the essence and realize and see it become the foundation of society.
...I want to feel the moment when the power of a group or team is demonstrated, which cannot be done by one person.
▼Overseas travel and business trips
...I want to feel a sense of growth.
...I want to touch and feel the world that I have not seen yet.
▼ Learning
...I want to feel a sense of growth.
...I want to touch and feel the new world and new senses.
Sorting out conditioned themes
If we capture our wishes in this way, we can see that there are many different wishes within us. The next thing we can do is to sort out what we have been conditioned to do.
Conditioning here refers to the fact that we are conditioned by those around us or outside of us to act in a certain way as being desirable. We are all influenced by conditioning in various ways from birth, from our parents, school, and neighborhood.
For example, if we study hard, we will be praised, or if we study hard and get good grades, we will be praised, and the external stimulus of praise reinforces our behavior of studying. There is nothing wrong with this kind of conditioning, and parental education and schooling will never be free of conditioning.
Conditioning allows us to learn how to think and behave in order to adapt to society. Conditioning is not a bad thing, because living in subjective truth and living in adaptation to one's surroundings and society are both important.
However, when it comes to subjective truth, it is a different story. Since subjective truth is truth for the person, it is essentially different from external or ambient conditioning. Therefore, when we try to understand the subjective truth, we need to try to sort out the things that are conditioned by the outside or the surroundings.
There is a valid point of view to sort out what is conditioned and what is not.
Suppose you don't do it, suppose you are not aware of it, will you feel fear or anxiety?
The reason why this question is effective in sorting out conditioned things is that the repetitive stimuli in our lives have formed a value system of "doing it or being aware of it is good. Conversely, not doing it or not being aware of it is not good."
Not doing it, not being aware of it.
↓
↓ ← Value system that "not doing it is not good"
↓
Awareness that it is not good
↓
Anxiety/fear
Again, it is not a bad thing to have conditioning. Rather, we can say that conditioning remains today because it was a necessary element for us to live in harmony with our surroundings and society. It would not be an exaggeration to say that if we are able to live a healthy life now, it is thanks to the conditioning we have received.
Also, it is not a black-and-white story of whether or not something is conditioned. I think it is more appropriate to think of it as whether there are relatively many or relatively few conditioning factors. Rather than trying to find something that has no conditioning at all, I think it's better to explore something that has relatively little conditioning and that brings up inner energy for us.
In my example, the factor that I was conditioned with was that I wanted to feel a sense of growth. I don't remember my parents ever telling me to study, but from an early age, watching my father and older brother, I naturally gravitated toward the path of learning, and I think I had a sense that I would be praised for my studies and that people around me would take notice of my growth.
And even now, I cannot say that there are zero factors that might make me be recognized by the people around me by having a sense of growth. On the other hand, if I don't have a sense of growth, I may feel anxious about whether I can continue as an executive.
When I think about it this way, I can say that for me, "wanting to have a sense of growth" is a relatively strong conditioning. Although it may not be entirely due to my own subjective truths, I think of it more as a feeling that I have acquired in order to adapt to external conditions through conditioning.
So far, I have talked about how to perceive the subjective truth from the original experience. As I was writing this article, I had many insights into the process of perceiving my own subjective truth. I hope you will try this process when you have time, and share your feelings and thoughts with me.
Here are the quests of the day. (If you'd like, please share your thoughts in the comments.)
・What experiences, if any, have you had that correspond to items (1) through (5) below?
(1) I had a lot of inner energy (at least at the time)
(2) I was able to work proactively and positively for a relatively long time (even if I was initially given the opportunity to do so by the surroundings)
(3) I had a sense of fulfillment.
(4) I had a sense of immersion.
(5) Inspiration often came to me.
・What is the wish behind this experience? (Please choose one of the following questions that you think is appropriate.)
A. What did you wish for in the source of your inner energy in that experience?
B. What sensations did you wish to have repeatedly in that experience?
C. If you had a similar experience, what, if anything, would have led to the loss of inner energy, fulfillment, and immersion?
・Which of the following wishes is more affected by conditioning? On the other hand, which wishes are less affected by conditioning?
Bunshiro Ochiai
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
