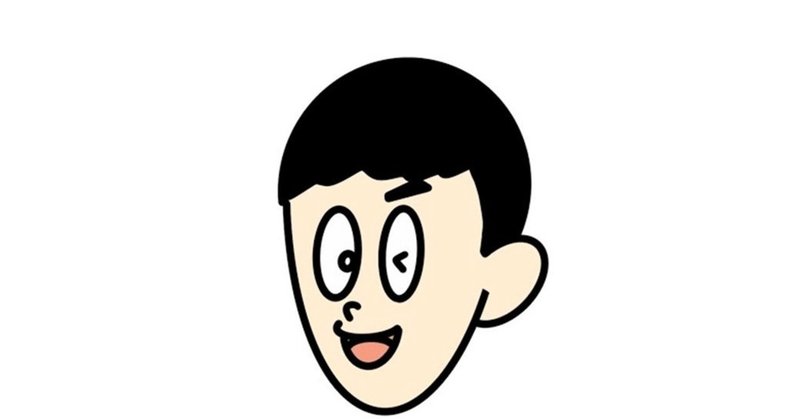
私自身のストーリー① 物理少年が「人の成長の真理」を探究するまで
前回のnoteでは、「経営における矛盾を両立するパラダイムは何か?」について、3+1意識モデル(ミクロ的・微分的視点)や、矛盾を両立する経営の全体像(マクロ的・積分的視点)について述べました。
今回は、私自身のストーリーについてお話させていただくことで、なぜ私が前回のnoteのようなテーマを持っているのかについての背景をご説明できればと思っています。幼少期まで遡った話になりますが、よろしければお付き合いください。
物理との「出会い」と「別れ」
私は両親と4歳年上の兄の4人家族の家庭で育ちました。父は数学の教授で、幼い頃から本棚には数学と物理の本がありました。「時間の進みは速くなったり、遅くなったりする」という相対性理論の記述に、幼いなりにおもしろさを感じたことを記憶しています。私にとっての物理との出会いは、生活の一部に含まれるごく自然なものでした。
学校の勉強に関しても、兄が進学高に通っていたこともあり、自然に取り組むものになっていました。親から勉強を強いられた記憶はなく、無邪気な気持ちで自然と、兄が歩んだ道をそのまま歩いていました。わからないことがあれば、隣で研究の仕事をしている父に聞いて教えてもらうような生活でした。
大学では幼い頃から興味のあった物理を探究し、特に興味のあった素粒子物理の領域で大学院に進みます。このまま父のように学者になるのかもしれない、とぼんやり思っていました。(ちなみに兄も学者をしています)
ところが、物理の世界での研究の環境は非常に厳しく、同世代の同分野の100人で3人のポストを争うような世界。しかも、これまでに出会ってき人の中でも極めて優秀であるだけではなく、寝ても覚めても物理のことを考えている感じの人たちです。そのような人たちと競いながら、100人中3人のポストを争そうことにかける決断をできない自分がいました。
同時に、物理とは違う世界で生きていくことを決断します。私は一度決めるとスパッと動けるタイプなので、特にこだわりもなく、物理の世界を後にします。
そこから就職活動をして、物理の知識が活きる分野として金融トレーダー、または、ビジネスの世界で必要な足腰を最大限鍛えることができそうなコンサルティング業界を中心に面接を受け、トレーダーは不合格、ボストン・コンサルティグ・グループ(以下、BCG)からご縁をいただき、社会人生活をスタートしました。
コンサルティングと物理の決定的な違い
コンサルティング会社での日々は、学びの連続で、成長の手ごたえも想像以上でした。当時のBCGは、コンサルタントで100名前後、新卒同期は6名でみんな個性派揃い。一緒にプロジェクトを行う方々は、大企業や中央省庁出身でMBAホルダーの方も多く、とても刺激的な毎日でした。
個性派揃いの新卒同期とは、一緒にプロジェクトをやることはありませんでしたが、お互い意識し合いながら、いい仲間であり、いいライバルとして共に成長をすることができたと思います。
最初の半年間は、プロジェクトリーダーやシニアコンサルタントの方に教えてもらいながら、リクエストされたアウトプットを出していくことで精一杯という感じでした。半年から1年くらいのタイミングで、自分なりのアウトプットの出し方、付加価値の出し方のコツみたいなものを掴み始めてから、仕事がさらに楽しくなり、あっという間の2年半でした。
2年半が経ち昇進したタイミングで、自分の中でこれまでとは少し違うアンテナが立ち始めていることに気づきます。仕事の楽しさはそれまでと全く変わらないものでしたが、それまでよりは少しエネルギーが停滞しているような感覚になります。いま振り返ると、それは「個別解を出す」というコンサルティングの性質と、自分がもともと持っている指向性とのギャップでした。
コンサルティングは、論点・仮説・検証などのプロセスを経たり、クライアントとの協働によって価値を生み出していくプロセスを経たりするなど、プロジェクトによらずに共通しているものはありますが、基本的にはクライアント企業の状況や文脈に応じて個別解を出していく仕事です。
個別解を出す仕事には、価値もやりがいもあります。しかし、私個人としては、一般解、つまり「普遍的な真理の探究」に心から喜びを感じる人間であることに、ぼんやりと気づき始めたのです。(良し悪しではなく、好みの問題です)。
「普遍的な真理の探究」とは、まさに物理の研究と同じ営みです。様々な現象を説明するシンプルで美しい真理を見つけること。これが私が幼少期から惹かれてきた営みであり、人生を通したテーマになり始めます。
このあたりから、自分で事業を創りたい気持ちがふつふつと沸き上がり、起業するならば、どんなことをやりたいのか、どんなチームを作りたいのかなど想像するようになりました。また、一緒にやる仲間として、大学時代のテニスサークルの友人に声をかけ、週末に起業準備をするようになります。
(余談ですが、学生時代は物理ばかりやっていたわけではなく、同じくらいテニスにも熱中していました)
週末の起業準備を始めてからの半年間、どんな世界を実現したいかを考える日々でした。
それまでの人生を振り返ると、私は人生の岐路のタイミングで、様々な選択肢の中から自分らしいものを選んでここまで来られたと感じました。そして、それは幼い頃から様々な「学び」に自然に触れられる環境で育ったおかげだと思ったのです。よって、人に自分らしい選択肢を持ってもらえるような、教育のインフラ作りに携わりたい気持ちが自然に沸き起こりました。
人の成長の領域でも「普遍的な真理の探求」をしてみたい。そんな想いで積み重ねてきたことが、今の事業につながっています。
主体的真理は「何をやってきたか」ではない
私の中に主体的真理というキーワードがあります。主体的真理についての詳しい話は別の記事でお話したいと思いますが、大雑把に言えば、一人一人が「自分の主観」で大切に考えていること・目指したい姿などを指します。
主体的真理に生きる人がたくさんいる社会に貢献したい、というのが今の私の想い(=主体的真理)です。
ここまで語ってきた私の経験の中にも、主体的真理を読み取ることができます。
私の場合、コンサルティング時代の「個別解」を紡ぎ出していく経験をしたことで、自分は「一般解」を見つけたい人間なのだと気付き、起業に至りました。この「一般解を見つける」が、私の主体的真理の一つだったのです。そして、その原点は幼い頃の物理への興味でした。
ここで重要なのは、主体的真理は、何をやってきたかではなく、やってきたことの「何に共鳴したか」に現れるということです。
もし「自分には物理しかない」と思っていたら、研究者としての厳しい現実を前にして身動きが取れなくなり、本当の心の声に気付くことはできなかったと思います。(素粒子物理の世界が悪いのではありません。あくまで、自分にとっての話です)
しかし現実には、物理そのものにこだわりすぎなかったことが功を奏します。「普遍的な真理の追求」につながるのであれば、ビジネスの世界でもやりがいを持って生きていけると気付くことができました。
起業に至るまでの私の中での意識の変化を整理すると、次のようになります。
「主体的真理=物理学者」 ⇒ 世の中との矛盾に直面
↓
「主体的真理=100年続く真理の追求」 ⇒ 世の中との調和(起業)
起業後のストーリーについては、次の記事でお話したいと思います。
本日の問いとなります。(よろしければ、コメントにご意見ください)
・あなたが、これまで手がけてきたことの共通項があるとすれば、それはどのようなことですか?それは、あなたの主体的真理とのつながりがあるとすれば、どのようなつながりでしょう?
My own story (1) How a physics boy explored the truth of human development
In my last note, "What is the paradigm for integrating contradictions in management?" I discussed the 3+1 consciousness model (micro and differential perspectives) and the overall picture of management that integrates contradictions (macro and integral perspectives).
(English follows in the latter half of the previous article)
In this article, I hope that by sharing my own story, I can provide some background on why I have a theme like the previous note. The story goes back to my childhood, but I hope you'll stay with me.
My "encounter" and "parting" with physics
I grew up in a family of four, my parents and my brother, who is four years older than me. My father was a professor of mathematics, and from an early age there were books on mathematics and physics on the shelves. I remember being fascinated by the theory of relativity, which states that time goes faster and slower, even at a very young age. My introduction to physics was a natural part of my life.
My older brother went to a high-level school and was very diligent, so studying and schoolwork was a natural part of my life. I don't remember my parents forcing me to study; I just naturally and innocently walked the same path that my brother had taken. If there was something I didn't understand, I would ask my father, who worked as a professor and a researcher next to me at home, for help.
At university, I explored physics, which I had been interested in since I was a child, and went on to graduate school in the field of particle physics, which I was particularly interested in. I wondered if I would go on to become an academic like my father. (My brother is also a scholar.)
However, the research environment in the world of physics is extremely tough, with 100 people of the same generation in the same field vying for three posts. Moreover, they are not only the most brilliant people I've ever met, but also people who seem to be thinking about physics day in and day out. I found myself unable to make the decision to compete with such people for the post of 3 out of 100.
At the same time, I make the decision to live in a different world than physics. I'm the type of person who can move quickly once I've made a decision, so I'm leaving the world of physics without any hesitation.
From there, I went on a job search and interviewed for jobs, focusing on financial traders as a field where my knowledge of physics could be used, or in the consulting industry, where I would be able to maximize the ability of legwork and headwork required in the business world. Becoming a trader was unsuccessful, and Boston Consult Group ("BCG") offered me a position, where I started my working life.
The crucial difference between consulting and physics
My days at the consulting company were a constant learning experience, and the realization of growth was beyond my expectations. At BCG at the time, there were about 100 consultants and six new graduates joined at the same time, all of whom were of unique personality. Many of the people I worked with on projects came from large companies and central government agencies and were MBA holders, so every day was very stimulating.
Although I didn't work on any projects with these new graduates of the same age, I think we grew together as good friends and rivals while respecting each other's personalities.
For the first six months, I was just barely able to produce the requested output while being taught by the project leader and senior consultants. After about six months to a year, I started to grasp the knack of creating value-added output in my own way, and that's when I started to enjoy my work even more, and the two and a half years passed very quickly.
After two and a half years, when I was promoted, I realized that my intention had started to come up in a slightly different way. The enjoyment of my work was exactly the same as before, but my energy was a little more stagnant than before. In retrospect, this was a gap between the nature of consulting, which is about coming up with individual solutions for clients, and my original willingness.
Consulting involves a process of setting issues, making hypothesis, and conducting testing, as well as a process of creating value through collaboration with the client, which are common regardless of the project. But basically, consulting work is to come up with individual solutions depending on the situation and context of the client company.
There is both value and rewards in the work of coming up with individual solutions. But for me personally, I have begun to dimly realize that I am a person who truly delights in general solutions, or "the quest for universal truths". (It's not a matter of right or wrong, it's a matter of preference.)
The search for universal truth is exactly the same as the study of physics. Finding simple, beautiful truths that explain various phenomena. This is an activity I have been drawn to since I was a child, and it begins to become a theme throughout my life.
This is when the desire to create my own business began to surge, and I began to imagine what I would want to do and what kind of team I would want to build if I were to start a business. I also approached a friend from my university tennis club as a partner to work with, and we began to spend weekends preparing to start a business.
(As a side note, I wasn't all about physics when I was in university, I was equally passionate about tennis or even more!)
During the first six months of preparing for my weekend entrepreneurship, I spent a lot of time thinking about what kind of social change I wanted to achieve.
Looking back on my life up to that point, I felt that I was able to get to this point in my life by choosing my best way from a variety of options when I was at a crossroads in my life. I believe this is because I was brought up in an environment where I was naturally exposed to a variety of learning experiences from an early age. Therefore, I naturally wanted to be involved in creating an educational infrastructure that would allow people to make their own choices.
I would also like to engage in the "quest for universal truth" in the realm of human development. What I have built up with this in mind has led me to my current business.
The subjective truth is not "what we have done".
There is a key word in my mind, subjective truth. I'd like to talk about the subjective truth in detail in another article, but broadly speaking, it refers to what each of us thinks important and wants to achieve in our own subjective view.
My current passion (i.e. subjective truth) is to contribute to a society where there are many people living in subjective truth.
You can also read the subjective truth in my own experiences.
In my case, I realized that I am a person who wants to find a general solution through the experience of spinning out "individual solutions" when I was in consulting, which led me to start my own business. This "finding a general solution" was one of my subjective truths. And it originated from my childhood interest in physics.
What is important here is that the subjective truth does not appear in what you have done, but in what you resonate with in what you have done.
If I had thought that physics was all I had, I would have been stuck in the face of the harsh realities of being a researcher, and I wouldn't have been able to realize what my true heart was telling me. (It's not that the world of particle physics is bad. It's just a story for me.)
In reality, however, I didn't focus too much on physics itself, and it paid off. I've come to realize that I can live a rewarding life in the business world if it leads to the "quest for universal truth."
If I were to summarize the change in my ISHIKI(consciousness) leading up to my entrepreneurship, it would be as follows.
"Subjective Truth = Physicist"
⇒ Confronted with contradictions in the real world
↓
"Subjective Truth = Quest of universal truth that will last for 100 years"
⇒ Harmony with the world (as an entrepreneur)
I'll talk about the post-startup story in my next post.
Here are the quests of the day. (If you'd like, please share your thoughts in the comments.)
・What are the common, if any, between the things you have done in the past? What kind of connection, if any, would that be to your subjective truth?
Bunshiro Ochiai
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
